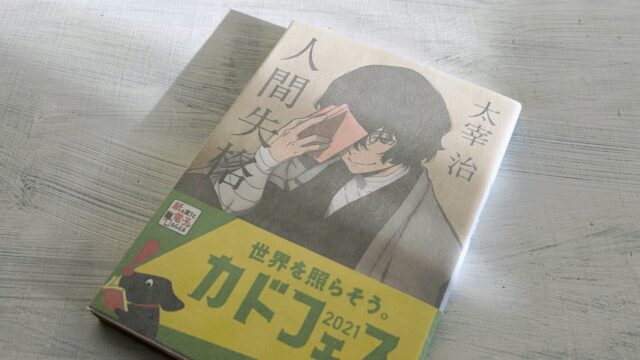小沼丹『銀色の鈴』読了。
本作『銀色の鈴』は、1971年(昭和46年)5月に講談社から刊行された短篇小説集である。
この年、著者は53歳だった。
収録作品及び初出は、次のとおり。
「小径」
・1969年(昭和44年)12月『群像』初出
「猫柳」
・1969年(昭和44年)4月『婦人之友』初出
「山のある風景」
・1969年(昭和44年)6月『群像』
「古い編上靴」
・1967年(昭和42年)9月『群像』初出
「落葉」
・1971年(昭和46年)1月『婦人之友』初出
「昔の仲間」
・1970年(昭和45年)8月『群像』初出
「銀色の鈴」
・1971年(昭和46年)2月『群像』初出
よみがえる小沼文学
小学館「P+D BOOKS」から、小沼丹の『銀色の鈴』が刊行されるらしい(2024年10月10日発売予定)。
今年1月にも「P+D BOOKS」から『緑色のバス』が出ているから、小沼文学の愛読者にとって、今年は少しだけ特別な年になった。
なにしろ『銀色の鈴』は、1971年(昭和46年)刊行の作品集である。
2010年(平成22年)に講談社文芸文庫からも出ているが、文芸文庫は品切れ・入手困難になるのも早い(価格も税別1,400円だった)。
昭和の名作を安価で読むことのできる「P+D BOOKS」に、小沼丹の作品が入ることの意義は大きい。
小沼文学の転換期を示す「大寺さん」ものは、短篇集『懐中時計』(1969)から始まった。
本作『銀色の鈴』では、『懐中時計』に続く、再生初期の小沼文学を読むことができる。
「山のある風景」や「昔の仲間」など、交友関係を素材とした作品にも、良いものが多い。
今年の秋は、小沼丹の秋となりそうだ。
小径 │ 逗子の伯母に捧げるレクイエム
1969年(昭和44年)12月『群像』初出の「小径」は、逗子の山の中に住んでいた伯母の思い出を綴った作品である。
横須賀行きの電車の中で忘れ物の眼鏡を拾ったことや、椎茸採りのこと、伯母の頭に禿を見つけたこと、古いレコードを聴いたこと、耳の悪い小柄な美人の女中(ねえや)がいたことなど、とりとめのないエピソードが、いくつも組み合わされている。
ポイントになっているのは、三味線のお師匠さんだろう。
「──お師匠さんに子供がいたんですよ」と低い声で云った。内緒話でもするような調子だが、どう云うことかよく判らない。「──子供がどうかしたんですか」「──いいえ、伯父さんの子供ですよ」(小沼丹「小径」)
伯父は既に亡くなっており、伯母さん夫婦に子どもはいなかった。
伯母さんの悲しそうな笑顔には、そんな人生の寂しさが反映されたものだったのだろうか。
伯母が死んで間も無く、その家は人出に渡ったと聞いたがその后どうなったのか知らない。三十年も昔の話だから、その辺も悉皆変ってしまったろう。行って見たところで始まらないし、行って見る気にもならない。(小沼丹「小径」)
この作品は、死んだ伯母に送るレクイエムだが、「行って見たところで始まらないし、行って見る気にもならない」という言葉によって、主人公は、思い出の場所と、あえて距離感を取り、感傷に溺れることを拒否している。
そして、この距離感の中に生まれた空白こそが、主人公のほのかな喪失感を、なお浮き彫りにしているのだ。
猫柳 │ 床屋の親爺(モオム氏)の思い出
1969年(昭和44年)4月『婦人之友』初出の「猫柳」は、街道に面した床屋の親爺(モオム氏)の思い出を綴った作品である。
サマセット・モームは、1959年(昭和34年)に来日して、大ブームを巻き起こしているから、「猫柳」が発表された1969年にも、まだ一定の人気を保っていたことだろう。
モオム氏の妹(二十歳ばかり)は、国電のM駅前の通りのお茶屋(吉野園)に嫁いでいたが(主人公も、戦前はそっちの方へ住んでいた)、吉野園の主人(五十過ぎ)と妹との結婚話が、この物語の軸となっている。
「それから間も無く、僕は病気になった」「臥込んで半年以上経った」とあるのは、胸部疾患で一年間の療養生活を送った1950年(昭和25年)頃のことだろう(小沼丹は32歳)だった。
その親爺に久し振りに、ひょっこり、出会わした。四、五年前のことだが、娘と一緒にK町に行って、モオツァルトのレコオドを買って表へ出たら、毛糸の帽子を被った爺さんが立停って此方を見ている。(小沼丹「猫柳」)
「──奥様もお元気で……?」と訊かれた主人公が「女房は死んだよ」と答えると、モオム氏が「そんなの嘘でございますよ」と答える場面が切ない(小沼丹の先妻・和子は、1963年に急死)。
一緒にいた大学生の娘を見て、何やら勘違いしているようだったが、モオム氏のキャラクターが、この物語のポイントと言えるだろう。
山のある風景 │ 横田瑞穂の別荘にて
1969年(昭和44年)6月『群像』初出の「山のある風景」は、早稲田大学の同僚たちと過ごした避暑地の情景を、まるで随筆のように綴った短篇小説である。
浅間山麓の別荘を持つロシア文学者<横井さん>は、横田瑞穂のことらしい。
横井さんは僕と同じ学校に勤めていて、露文科の先生である。僕より大分先輩に当るが、横井さんと同年輩の人のなかには、ロシアに敬意を表してヨコチンスキイと呼ぶ人もいるのである。(小沼丹「山のある風景」)
飲み会中に行方不明になった横井さんを探すと、知らないグループの宴会に紛れ込んで、じゃんけんをしていたというエピソードは、随筆「のんびりした話」にも紹介されていて、「ロシア文学者の横田瑞穂氏」という名前を見ることができる(『小さな手袋』所収)。
ミハイル・ショーロホフ『静かなドン』の翻訳を完成したとき、横田瑞穂は52歳で、まだまだ働き盛りの年齢だった。
物語は、旧い街道に面した横井さんの別荘を舞台に進められていく。
初めて横井さんの別荘を訪ねたのはいつだったか、はっきり憶えていない。この頃、横井さんは胃の調子が怪訝しいとかで酒を節しているが、その頃はまだ盛んに酒場から酒場へと足を運んでいたから、もう十年ぐらい前になるかもしれない。(小沼丹「山のある風景」)
このとき、同じ学校の仏文科の先生(森君)も登場しているが、森君が「うちは母系家族でね」と言ったという話は、「トト」(『小さな手袋』所収)の中にもあって、フランス文学者(室淳介)として登場している。
横井さんの別荘へ一緒に行った友人が白樺の話をするエピソードは、「白樺」という随筆に書かれている(『小さな手袋』所収)。
そのときは、例の動物園に行った友人と一緒に横井さんの別荘を訪ねていたから、その友人も傍に坐っていて、横井さんに、「──そこには白樺もありましたか?」と訊いた。(小沼丹「山のある風景」)
随筆の方を読むと、この友人が天狗太郎(山本亨介)であることが分かる。
横井さんと同年配で英文科の先生(渡部さん)や、渡部さんの大分後輩で、同じ英文科の先生(西田君)も登場するなど、本作を構成しているのは、偉い大学の先生たちの、ちょっとコミカルなエピソードである。
古い編上靴 │ 大寺さんの戦争体験
1967年(昭和42年)9月『群像』初出の「古い編上靴」は、戦争中の体験を書いた、いわゆる戦時譚である。
いよいよ空襲が激しくなってきたため、細君と子どもが信州へ二度目の疎開をしているときに、大寺さん自身が空襲被害に遭った体験が語られている。
大寺さんは睡気も一遍に醒めて、裏の壕に駆込んだ。ラジオのスイッチを入れ、パイプを咥えて編上靴の紐をホックに掛けた。壕の入口を開けて置くとたいへん明るい。覗いて見ると、探照燈の光が幾条も忙しそうに空を撫で廻している。(小沼丹「古い編上靴」)
この日の空襲で仕事場まで失った大寺さんが、妻子のいる信州へ疎開した後は、疎開先の信州で務めた学校の話が中心に綴られていく。
戦時における信州の田舎の日常スケッチは、この物語の大きなポイントとも言えるだろう。
風に吹かれて展望台に立っていると、大寺さんはときにすべてを忘れてしまうような気のすることがあった。「──何故、茲に立っているのだろう?」と不思議に思う。空襲のあったことなど、遠い昔の夢のようにしか思えない。それから、想い出したように、草臥れた編上靴の埃を叩いたりした。(小沼丹「古い編上靴」)
学校の宿直中に、図書室から持って来た地理風俗体系を読みながら、パリの下町やベルリンの並木路、ライン河畔の古城、ロンドンの街の鼻垂小僧、ロシアの農民などが出てきたときにも、大寺さんは、人生のはかなさについて考えている(「──その連中の多くは疾に死んだろう。濃艶な微笑を送る美女も、今は皺だらけの婆さんだろう」)。
殊に、ベルリンの美しい並木路が、戦争で全滅したことを知っているから、大寺さんは、世の中全部が、はかない存在に思えてしまったのかもしれない。
やがて、戦争が終わり、信州の田舎の村にも平時が取り戻される。
「──一体、何があったと云うのだろう?」大寺さんの頭の中に「或る日」があって、その日が余りにも遠く思われたので、大寺さんは殆どその日を見ることは出来ないような気がしていた。それが、突然やって来た。大寺さんは、ぼんやりしてしまった。多分、そんなことだったろう。(小沼丹「古い編上靴」)
前任者が復員してきたところで、大寺さんは学校を辞めて東京へ帰る。
その学校で働いたのは、ざっと三か月ばかりだったが、学校を辞めたときに初めて「戦争は終わった」と、大寺さんは実感していた。
こうした戦争中の体験が、大寺さんの愛用している編上靴を中心に語られていくのだが、もしかすると、古い編上靴こそ、大寺さんにとって、戦争そのものであったのかもしれない。
落葉 │ 植木屋(田口親爺)の思い出
1971年(昭和46年)1月『婦人之友』初出の「落葉」は、植木屋(田口親爺)の思い出を綴った作品である。
荻窪の清水町先生(井伏鱒二)からもらった茶の木を運んでくれたのが、この田口親爺で、せっかく植えた茶の木を、間違って刈ったのも田口親爺である。
何年か前に友人の車で安行に遊びに行ったときことや、清水町先生や吉岡達夫と甲州の波高島へ遊びに行ったときのことは、短篇「凌霄花」に詳しい(『山鳩』所収)。
あれはいつだったか、縁側でぼんやり煙草を喫んでいたら、紅漆の枝下しをしていた田口親爺が降りて来て、「──どうも、たいへんなことだったね」と云った。(小沼丹「落葉」)
「たいへんなことだった」とあるのは、主人公の妻が急死したことを示している。
その田口親爺が、突然に亡くなったというところに、この物語のドラマがある。
そう云われても、何だかその辺から田口親爺の声が聞えて来るような気がしていたら、鵯がどこかで、ぴい・ぴいよと啼いた。あれは何年前のことだったかしらん?(小沼丹「落葉」)
浅間山麓の宿屋で会った友人(森君)は、「山のある風景」にも出てきた、フランス文学者(室淳介)である。
昔の仲間 │ 玉井乾介・伊東保次郎・石川隆士の思い出
1970年(昭和45年)8月『群像』初出「昔の仲間」に登場するのは、学生時代の友人(伊東)と、自ら「竹林亭主人」と称している友人(金井)、池袋方面に住んでいる友人(市川)である。
この物語は、伊東と金井、市川、そして主人公(小沼丹だろう)という四人の若者たちの若き日を描いた、回想の物語である。
酒田の伊東の家には、金井と一緒に一度行ったことがある。大学一年の夏休のとき、金井と佐渡へ旅行することにして、伊東も引張って行こうということで寄ったのである。区劃正しい水田が矢鱈に遠く迄続いているのを見て、金井と二人で感心していたら酒田へ着いたような気がする。(小沼丹「昔の仲間」)
年譜の1940年(昭和15年)のところに「夏に、友人の玉井乾介、伊東保次郎と新潟、酒田、佐渡を旅する」とあるから、作中の<金井>が玉井乾介であることが分かる。
酒田や佐渡を旅した回想は、ちょっとした紀行小説を読むようで楽しい。
伊東と二人で深大寺(東京都調布市)を訪れる場面も印象深い。
深大寺へ行って、帰りに井の頭の池畔でビイルを飲もうと云う話になって、或る日、伊東が三鷹の僕の所にやって来て、一緒に歩いて出掛けたことがあった。麦秋の頃の好く晴れた日で、黄ばんだ麦畑のなかの路を歩いて行くと、練習機が麦畑に影を落して飛んで行ったりした。(小沼丹「昔の仲間」)
この作品を読んだ大学の同僚(上松さん)が、深大寺まで行って、小説のなかの男の真似をして、裸になって滝に打たれてきたという話が、短篇小説「鳥打帽」に出てくる(『木菟燈籠』所収)。
何気ない昔話の中に通底しているのは、今は亡き友人に対する哀惜の情である。
暗い長いトンネルがあって、トンネルを出て見たら、いつの間にか座席のあちらこちらに空席が出来ていて、座席の主は帰って来ない。棚の上に残されたのは、追憶と云うトランクだけである。伊東の座席も空席の儘竟に塞がらない……。雨に濡れる青葉を見ながら、そんなことを考えていたように思う。(小沼丹「昔の仲間」)
伊東は、もちろん、当の昔に死んでしまっているが、「伊東がいつどこで死んだか、忘れてしまった」とあるあたり、必要以上の感傷を拒む小沼スタイルだと思う。
そして、生きている友もまた、あれから年を取った。
久し振りだから二人で乾杯して飲んでいると、金井は想い出したように、市川はどうしたろう? と訊く。娘が嫁に行ったそうだと教えてやったら、ふうん、と天井を見上げて、「──彼奴もいよいよ爺さんか……」と云った。気が附くと、そう云う金井の頭も半分ばかり白くなっている。(小沼丹「昔の仲間」)
ここに登場する<市川>は石川隆士のことで、後に小沼さんは、石川隆士への追悼小説「翡翠(とり)」を書くことになる(『埴輪の馬』所収)。
<金井>こと玉井乾介は、1990年(平成2年)12月17日に亡くなっているが、小沼さんが、玉井乾介への追悼小説を書くことはなかった。
小沼さんが小説を発表するのは、1986年(昭和61年)2月の「トルストイとプリン」が最後だったからだ。
ただし、玉井乾介の思い出は、「筆まめな男」という随筆に綴られていて、『珈琲挽き』で読むことができる。
銀色の鈴 │ 妻を亡くした大寺さんの再婚
1971年(昭和46年)2月『群像』初出の「銀色の鈴」は、六、七年前に妻を亡くした<大寺さん>が主人公の短編小説である。
ベッドの傍の本棚に載せた銀色の鈴から、大寺さんは、亡くなった細君のことを思い出す。
細君が生きていた頃、大寺さんは、目を覚ますと、この銀色の鈴を鳴らして、細君を呼んだものだった。
物語は、そんな死んだ細君の思い出から始まる。
細君が死んだ後、二人の娘とともに遺された大寺さんの再婚が、友人たちの間で話題となった。
淡々とした文章で、前の細君が亡くなってから、現在の細君と再婚するまでのことが綴られていく。
しかし、物語は、あくまでも、死んだ最初の細君に焦点が当てられている。
その翌年の春、大寺さんは細君と一緒に上野の娘の結婚式に出た。ぼんやり花嫁姿の娘を見ていると、いつの間にか時間の歯車が逆に廻転し始めて、春子がだんだん小さくなって行ったかと思うと、その上に母親の顔が重なって見えた。(小沼丹「銀色の鈴」)
春子の母親は、死んだ前の細君である。
前の細君は、大寺さんに何か言ったようだったが、それは声にはならなかった。
「何と云う心算だったのだろう?」と、大寺さんは考えるが、答えは出てこない。
同じような場面が「銀色の鈴」の中に、もう一つある。
それは、片付ける仕事があって、夏の終わりの東北まで出かけたときのことだ。
夕食に酒を飲んで眠り、夜中に目覚めると激しい雨が降っていた。
仕事をする気にもなれなくて、大寺さんは、持参のウイスキイを取出して水で割って飲むことにする。
ウイスキイを飲みながら激しい雨の音を聴いていると、その中からいろんな声が聞えて来るから不思議であった。それに混って、或る旋律を繰返し演奏しているのも聞えた。突然、雨の音が歇むと嘘のように静かになって、それと同時に声も旋律も消えてしまう。──どうだろう?(小沼丹「銀色の鈴」)
激しい雨の音の中、果たして大寺さんはどんな声を聞き、どんな旋律を聞いたのだろうか?
その答えは、どこにも書かれていない。
大寺さんは、ただ、「うん、もう一杯飲もう」と言って、ウイスキイの水割りを飲み続ける。
まるで余白のたっぷりと残されたスケッチブックのように、小沼さんの小説は淡白でさっぱりとしている。
そのくせ、取り残された寂しさの中で、じわじわと何かが胸を濡らしてくる。
この余韻が、小沼文学の最大の魅力なのではないだろうか。
もちろん、この余韻は、本文中で描かれている様々なエピソードの後からやって来るものである。
読者は、春子の結婚式のときに現われた死んだ細君の言葉や、激しい雨の中で大寺さんが聞いた声や旋律を想像することができる。
そして、その想像に共感することができる。
それは、余計なことが一切書かれていない、この小説の中に、余韻を残すだけの物語がしっかりと書かれているからだ。
小沼文学の魅力が、たっぷりと詰まった、おすすめの短編小説である。
日本文学の最終地点・小沼丹の文学
既に書いているとおり、小沼丹の小説は、余白を味わう小説である。
小沼文学の余白は、人生の余白だと読み替えてもいい。
我々の日常生活には、目には見えないところで、様々な感傷や感慨がある。
小沼丹は、消えてなくなりそうな感傷や感慨を巧みにすくい上げ、一篇の短編小説として再構築するスタイルを得意とした。
ストーリーで読ませる小説ではない。
余白と余韻で読ませる小説である。
小沼文学の味わいにハマると、他の文学が物足りなくさえ思えてくるから不思議だ。
この味わいを知らずに文学を語るのはもったいない。
もしかすると、小沼丹の文学は、日本文学の最終地点に近いものかもしれない。
すべての文学好きが、最後に行きつくところがあるとしたら、それは、やはり、小沼丹の文学なのではないだろうか。
書名:銀色の鈴
著者:小沼丹
発行:2010/12/10
出版社:講談社文芸文庫