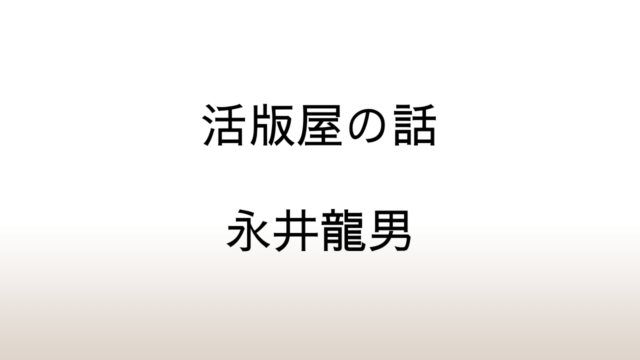後藤明生「ロシアの旅」読了。
本作「ロシアの旅」は、1973年(昭和48年)12月に北洋社から刊行された紀行集である。
この年、著者は41歳だった。
日本文芸家協会とソ連作家同盟の交流使節団
本作「ロシアの旅」は、日本文芸家協会とソ連作家同盟との間で例年行っている交流使節団に参加した際の旅行を綴った記録である。
ロシアへ渡ったメンバーは、古山高麗雄、原卓也、後藤明生の三人で、最年長の古山高麗雄が団長だった(同じロシア訪問記として、古山高麗雄にも『風景のない旅』という紀行集がある)。
一行は、1973年(昭和48年)11月8日に日本を出発するが、際立つのは、著者の無器用な旅行ぶりである。
シベリアの冬の寒さを恐れるあまり、出発前に徹底的な防寒対策を講じて、スキー用の厚い靴下を重ね履きした上で、新しい靴を購入したところまではいいが、その靴が実は革底の革靴だった。
雪が降り、道が凍りつく極寒の地で、革靴は難しい。
北海道の人間としては、ちょっと信じがたい気もするが、なにしろ情報の少ない時代だったから、仕方のない部分もあったのだろう。
ロシアでは、人から借りてきた大切なカメラを置き忘れて、現地の人々の手を煩わせてしまう。
いずれにせよわたしは、そのようにして、ソ連到着二日目にして早くもカメラマンを失格したのである。もちろんわたしは、カメラマンとしてソ連を訪問したわけではない。また失われた「オリンパス35DC」そのものに、カメラ自体として執着するものではない。しかし、わたしが紛失した「オリンパス35DC」は、わたしのカメラではなかった。(後藤明生「ロシアの旅」)
さらに、著者は、現地でロシア風の防寒帽子を購入するが、この帽子も買った直後に、どこかへ置き忘れてしまう。
カメラは無事に見つかったが、帽子は二度と出てこなかった。
現地もロシア人たちも、さぞかし心配したのではないだろうか。
モスクワからレニングラードへ向う日、わたしたちはリヴォヴァさんと、作家同盟のクラブ食堂で、一緒に昼食をとった。挨拶が済んだあと、リヴォヴァさんは、わたしに向ってこういった。「ゴトウさん、あなたはハバロフスクではカメラをなくし、モスクワでは帽子を失ったそうですね! あなたは、また何ということをされたのでしょう!」(後藤明生「ロシアの旅」)
こうした旅の失敗を綴る著者は、まるでロシア文学の主人公のような感じもする。
あるいは、あえてこうした失敗談を交えながら旅を語る姿勢そのものが、ロシア文学にも通じるものだと言えようか。
ゴーゴリの『鼻』の街で
後藤明生は、ゴーゴリに大きな影響を受けた小説家である。
ゴーゴリの墓を訪れたときの感動は大きかった。
できることならば、時間を忘れたかった。そして、いま四十歳であるわたしが、十九歳のときから彼について考えてきたことのすべてを、その場所で一つ一つ思い出してみたかった。ゴーゴリ先生! わたしはあなたのことを十九歳のときから考え続けてきた人間です!(後藤明生「ロシアの旅」)
かつて、ドストエフスキーは「われわれは皆、ゴーゴリの『外套』の中から出てきた」と言った。
時代や国は異なるが、もしかすると、著者もまた、ゴーゴリの『外套』の中から生まれた作家の一人だったのかもしれない。
しかし、よりリアリティがあると感じたのは、墓地ではなく、ゴーゴリの住んでいた家を訪ねる場面である。
雪が激しくなった。わたしは足を早めた。ゴーゴリの家はもうすぐだった。チャイコフスキーがそこで死んだという家が見えたからだ。一八九三年十月二十五日チャイコフスキーはこの家で死んだ、と書かれた記念板が見えた。(後藤明生「ロシアの旅」)
「ゴーゴリの家は、まことに散文的な四階建てだった」とある。
『罪と罰』を書いたドストエフスキーのアパートは、「いかにもラスコーリニコフにふさわしい、汚れた重い木製のドアだった」。
階段もまた同様に、人間の靴によってすり減らされ、いびつに歪んでいて、『罪と罰』らしい「暗い雰囲気」があることに、著者は満足したらしい。
しかし、著者が二度に渡って訪れたところは、「まことに散文的な四階建て」なゴーゴリの家の方だった。
この家でゴーゴリは『肖像画』『ネフスキー大通り』『狂人日記』『鼻』などの名作を綴ったという。
著者は、ゴーゴリは今、ヴォズネセンスキー大通りの床屋へ出かけているのではないかという錯覚を覚え、その錯覚に満足を覚えて安心する。
ヴォズネセンスキー大通りで床屋をしているイワン・ヤーレコヴレヴィチという男は、他ならぬ『鼻』に出てくる床屋の名前だったからだ。
文学作品の舞台を訪ねて、そのまま文学の世界へ入りこんでしまうことは、文学散歩の持つ大きな醍醐味の一つである。
若い頃から敬愛していたゴーゴリの街で、著者は完全にゴーゴリの作品世界に入り込んでしまったのだ。
こういう紀行文を読んでいると、文学旅行というのは、本当に良いものだなと思う。
できれば、この冬、自分もどこか文学の故郷を訪ねてみたいものだ。
いろいろな意味でロシアまで行くことは難しいと思うけれど。
書名:ロシアの旅
著者:後藤明生
発行:1973/12/15
出版社:北洋社