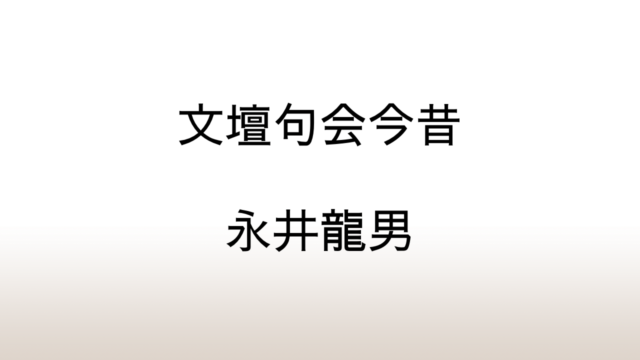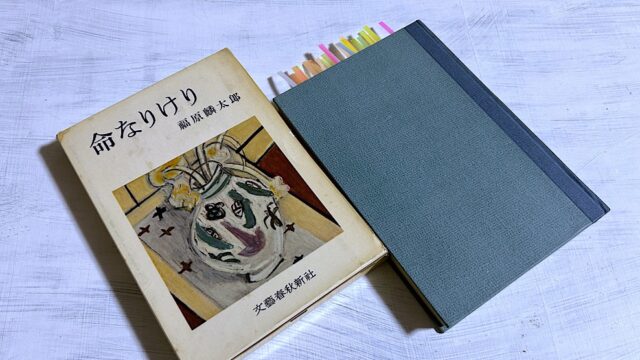夏目漱石「虞美人草」読了。
本作「虞美人草」は、1907年(明治40年)6月23日から10月29日まで『東京朝日新聞』『大阪朝日新聞』に連載された長篇小説である。
この年、著者は40歳だった。
明治時代版「男女6人春物語」
村上春樹『海辺のカフカ』に、夏目漱石の『虞美人草』が登場している。
「ここに来てからどんなものを読んだの?」「今は『虞美人草』、その前は『坑夫』です」(村上春樹「海辺のカフカ」)
外国文学の影響が強い村上春樹にとっても、夏目漱石は特別に意識すべき小説家だった。
漱石の作品を引用するにしても、あえて『虞美人草』というところに、どのような意味が込められていたのだろうか(もっとも『海辺のカフカ』では、『坑夫』の方が重要なメッセージとなっているが)。
https://gentle-land.com/kafka-on-the-shore/
福原麟太郎『夏目漱石』には、庄野潤三との対談が収録されている。
【福原】庄野さんなんかオーステンのほうに近いんだな、それじゃ。【庄野】オーステンのようにいま書きたいと思いますけれども、そのほうがやはり飽きがこないように思います。(略)朝日新聞に入社してからの『虞美人草』なんかになると、やはりオーステンに感心しているのと行き方は別で、人をあっと言わすような装飾で始めるというようなところがありますね。(福原麟太郎「夏目漱石」)
「朝日新聞に入社してから」とあるのは、1907年(明治40年)4月、漱石は教職(東京帝国大学と第一高等学校)を辞めて朝日新聞に入社したことを指しており、本作『虞美人草』が、朝日新聞入社後の最初の作品だった。
夏目漱石初めての新聞小説に対する世間の前評判は高く、三越呉服店の「虞美人草浴衣地」は、大変な売れ行きで、当時の虞美人草ブームを象徴するものとなったらしい。
本作『虞美人草』は、多くの若者たちが登場して、複雑な恋愛模様を見せるが、彼らの中心にいるのは、美貌の女性・甲野藤尾(24)である。
外交官だった藤尾の父は、外地で客死し、現在は、実の母と、哲学者で腹違いの兄・欽吾(27)と三人で暮らしている。
藤尾の父は、まだ存命だった頃、欽吾の親友である宗近一(28)を、藤尾の嫁として考えていたらしい。
「それでね──この時計と藤尾とは縁の深い時計だがこれをお前にやろう。しかし今はやらない。卒業したらやる。しかし藤尾がほしがって繰っついて行くかもしれないが、それでもいいかって、冗談半分に皆の前で一におっしゃったんだよ」(夏目漱石「虞美人草」)
宗近君も、かつての約束を覚えていて、藤尾を結婚相手として意識しているが、藤尾の方では、外交官の試験に合格することのできない男には将来性なしと見ていて、宗近君と結婚する意志はまるでなかった。
藤尾が結婚相手に選んだのは、甲野さんと大学の同期で、将来有望な文学者・小野清三(27)である。
困窮生活から脱することを夢見る小野さんも、また、資産家の娘・藤尾との結婚を目論んでおり、二人は少しずつ距離を詰めつつあるが、小野さんには、孤児だった時代に自分を育ててくれた恩師・井上狐堂の娘である小夜子(20)と結婚の約束があった。
さらに、甲野さんとの結婚を願う宗近君の妹・糸子(21)を加えて、小野さん・宗近君・甲野さんという男性三名と、藤尾・糸子・小夜子の女性三名が、複雑な青春劇を繰り広げるというのが、本作『虞美人草』の簡単なあらすじとなっている。
明治時代版の「男女6人春物語」といったところか。
ヒロインたる藤尾はプライドが高く、気性の激しい女だった。
藤尾は己のために愛を解する。人のためにする愛の、存在しうるやと考えたこともない。詩趣はある。道義はない。(夏目漱石「虞美人草」)
藤尾には、腹違いの兄を追い出して、外交官だった父の遺産を受け継ぎ、将来性のある男と結婚をするという野望があった。
藤尾が、宗近君ではなく小野さんを選んだのは、大学卒業時に恩賜の銀時計をもらった小野さんの将来性を信じたからである。
そして、小野さんもまた、人生の成功者となるため、出世欲に燃える若者の一人だった。
眼鏡は金に変わっている。久留米絣は背広に変わっている。五分刈りは光沢のある毛に変わっている。──髭は一躍して紳士の域に上る。小野さんは、いつのまにやら黒いものを蓄えている。もとの書生ではない。(夏目漱石「虞美人草」)
古いものを捨て、新しいものを追いかける小野さんは、現代風の(トレンディな)若者の象徴であっただろう。
財産と美貌に目がくらんだ小野さんには、藤尾の本性を知ることはできない。
貧しい小夜子と結婚するよりも、資産家の藤尾と結婚して安定した生活を得ることが、恩師である井上狐堂に報いることだと、自分を正当化していた。
「愛」と「金」という永遠のテーマが、そこにはある。
財産の象徴となっているのが、外交官の父が残した金時計である(藤尾が管理している)。
「兄さん」「なんだい」とまた見下ろす。「あの金時計はあなたには渡しません」「おれに渡さなければ誰に渡す」「当分私が預かっておきます」(夏目漱石「虞美人草」)
金時計を手にする者は、藤尾を手に入れる者である。
そして、神経症で心を患う兄の甲野さんには、父の遺産を相続する意思がない。
穏便に兄を追い出して、財産を確保することが、母と藤尾の思惑だったのだ。
彼らの思惑を知った上で、甲野さんは、財産をすべて妹(藤尾)へ譲り、家を出ようと考えている。
「偽の子だとか、ほんとうの子だとか区別しなければいいんです。ひらたくあたりまえにしてくださればいいんです。遠慮なんぞなさらなければいいんです。なんでもないことをむずかしく考えなければいいんです」(夏目漱石「虞美人草」)
財産に目がくらんで、小夜子を裏切ろうとする小野さんの目を覚まさせたのは、直実な宗近君だった。
「真面目とはね、君、真剣勝負の意味だよ。やっつける意味だよ。やっつけなくっちゃいられない意味だよ。人間全体が活動する意味だよ」(夏目漱石「虞美人草」)
結局のところ、金と女に目がくらんだ小野さんが、一度は小夜子を裏切ろうとしたものの、宗近君の説得で正義を取り戻して、藤尾に別れを告げるというところが、『虞美人草』におけるストーリーの主軸になっている、ということだろう。
出世欲に燃えるトレンディな小野さんも、我が良心に勝つことはできなかった(そこに読者の救いがある)。
救われないのは、財産で男を釣りあげようと考えていた、魔性の女・藤尾だ。
虚栄の毒に倒れた魔性の女・藤尾の最期
藤尾は恐ろしい女である。
「藤尾のような女は今の世に有りすぎて困るんですよ。気をつけないと危ない」女は依然として、肉余る瞼を二重に、愛嬌の露を大きな眸の上に滴らしているのみである。危ないという気色は影さえ見せぬ。「藤尾が一人出ると昨夕のような女を五人殺します」(夏目漱石「虞美人草」)
一緒に暮らす甲野さんは、藤尾の本性を見抜いているから、藤尾をうらやましいという糸子(宗近君の妹)に、「藤尾が一人出ると昨夕のような女を五人殺します」と言って聞かせる。
小野さんも宗近君も、藤尾の本性を知らないからこそ、彼女と結婚したいと、簡単に考えていたのだろう。
宗近君は妹・糸子の説得で、また、小野さんは宗近君の説得によって、藤尾と結婚することをあきらめる(外交官になろうとするくらいだから、宗近君は交渉上手だ)。
「藤尾さん、これが小野さんの妻君だ」藤野の表情は忽然として憎悪となった。憎悪はしだいに嫉妬となった。嫉妬の最も深く刻み込まれたとき、ぴたりと化石した。(夏目漱石「虞美人草」)
宗近君から、小野さんのフィアンセである小夜子を紹介された藤尾は、「嘘です。嘘です」「小野さんは私の夫です。私の未来の夫です」と動揺を隠せない。
「ホホホホ」歇私的里(ヒステリ)性の笑は窓外の雨を衝いて高く迸った。同時に握る拳を厚板の奥に差し込む途端にぬらぬらと長い鎖を引き出した。深紅の尾は怪しき光を帯びて、右へ左へ揺く。「じゃ、これはあなたには不用なんですね。ようござんす。――宗近さん、あなたに上げましょう。さあ」(夏目漱石「虞美人草」)
自分の意のままに動く飼い犬のように考えていた小野さんに裏切られた藤尾は、小野さんへの見せしめに宗近君へ金時計をちらつかせるが、宗近君はにべもなく藤尾を払いのける。
呆然として立った藤尾の顔は急に筋肉が働かなくなった。手が硬くなった。足が硬くなった。中心を失った石像のように椅子を蹴返して、床の上に倒れた。(夏目漱石「虞美人草」)
激しい気性の女だった藤尾は、同時に二人の男からフラれて意識を失い、そのまま帰らぬ人となってしまった。
「虚栄の毒」に倒れたのである。
春に誇るものはことごとく亡ぶ。我の女は虚栄の毒を仰いで斃れた。花に相手を失った風は、いたずらに亡き人の部屋に薫り初める。(夏目漱石「虞美人草」)
藤尾の死因は、怒りのあまりの興奮によって、心身に異常をきたした「憤死」だろう。
もともと興奮しやすい性質で、プライドの高い女だった藤尾には、失恋するという事実を受け容れるだけのキャパシティが、心身ともになかったのだ。
藤尾の遺体の横には、虞美人草の絵があった。
色は赤に描いた。紫に描いた。すべてが銀の中から生える。銀の中に咲く。落つるも銀の中と思わせるほどに描いた。――花は虞美人草である。落款は抱一である。(夏目漱石「虞美人草」)
虞美人草はヒナゲシの花のことで、『東京朝日新聞』に掲載された「『虞美人草』予告」に、新連載小説「虞美人草」の由来が紹介されている。
昨夜豊隆と森川町を散歩して草花を二はち買った。植木屋に何という花かと聞いてみたら虞美人草だという。おりから小説の題に窮して、予告の時期におくれるのを気の毒に思っていたので、いいかげんながら、つい花の名を拝借して巻頭に冠らすことにした。(夏目漱石「虞美人草」予告)
「艶とはいえ、一種妖治な感じがある」という虞美人草は、藤尾を象徴する花だったのだろうか。
あるいは、それは、藤尾を中心とする若者集団の、現代的な青春の象徴だったのかもしれない。
青春群像の中で、作者が最も強く投影されている登場人物は、メンタルヘルスに苦しむ哲学者の甲野さんだ(藤尾の兄)。
悲劇は喜劇より偉大である。これを説明して死は万障を封ずるが故に偉大だと云うものがある。取り返しがつかぬ運命の底に陥って、出て来ぬから偉大だと云うのは、流るる水が逝いて帰らぬ故に偉大だと云うと一般である。運命は単に最終結を告ぐるがためにのみ偉大にはならぬ。忽然として生を変じて死となすが故に偉大なのである。(夏目漱石「虞美人草」)
作品の最後に披露される甲野さんの長い日記は、著者・夏目漱石の哲学を示したものだが、ロンドンの宗近君は「ここでは喜劇ばかり流行る」と書いた返事を寄越す。
ここに、魔性の女・藤尾を完全否定することのできない現代の矛盾がある。
男を財産で釣り上げようとした美女・藤尾は、悲劇のヒロインであると同時に、喜劇のヒロインでもあったのだ。
虞美人草については世評はきかず。みんながむずかしいという。すべてわからんものどもはだまっていればよいと思う。それが普通の人間である。(夏目漱石「小宮豊隆あて書簡(明治40年8月3日)」)
『虞美人草』について、作者・夏目漱石は「恋愛事件(ラブ・アッフェアーズ)」そのものを描いたものではないと言っている。
つまりあれはね、ラブというものを唯一のインテレストとして貫いたものじゃないから、恋愛事件の発展として見るとなかなか不安定です。それならどこが完全かといわれるとますます弱るわけだが、つまり二つか三つかのインテレストの関係が互いに消長して、それがしまいには一所に出会って爆発するというところを書いたのです。(夏目漱石「小宮豊隆あて書簡(明治40年8月3日)」)
自己中心的なプライドや資産への固執、そして、急ぎ過ぎた現代性など、藤尾の死には、移り変わる時代への警告的なメッセージがある。
そして、世の中が発展し続ける限り、『虞美人草』に終わりはない。
藤尾は、姿や名前を変えて、いつの時代にも生き続けていくからだ。
『虞美人草』を読み終えた少年カフカは、明治時代の青春小説から、いった何を学んだのだろうか。
書名:虞美人草
著者:夏目漱石
発行:2017/06/25
出版社:角川文庫