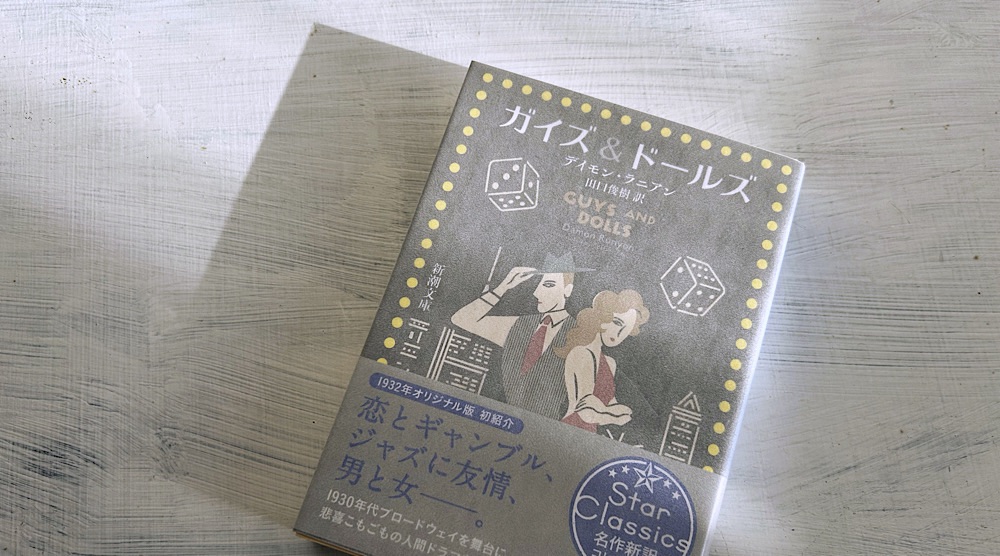デイモン・ラニアン「ガイズ&ドールズ」読了。
本作「ガイズ&ドールズ」は、1932年(昭和7年)に刊行された短篇小説集である。
原題は「Guys and Dolls」。
この年、著者は48歳だった。
新潮文庫版『ブロードウェイの天使』から40年
庄野潤三の随筆集『誕生日のラムケーキ』に「『ブロードウェイの天使』」というエッセイがあって、その中にデイモン・ラニアンが出ている。
『ガイズ&ドールズ』を観た日に、阪田寛夫が銀座の書店の本棚で新潮文庫版の『ブロードウェイの天使』を見つけて買い求めたのは、まことに素早かったといわなければならない。その十二の短篇のなかに『ガイズ&ドールズ』の原作となった「ミス・サラ・ブラウンのロマンス」が入っていた。(庄野潤三「『ブロードウェイの天使』」)
ここにある『ガイズ&ドールズ』とは、1985年(昭和60年)3月3日から31日まで、東京宝塚劇場で宝塚歌劇団月組によって公演されたブロードウェイ・ミュージカルのことである(庄野夫妻は剣幸を応援していた)。
そして、阪田寛夫が買った三日後に、庄野夫人が見つけて買ってきた新潮文庫版『ブロードウェイの天使』は、1984年(昭和59年)に刊行されたもので、デイモン・ラニアンの作品集が文庫化されるのは、これが最初で最後となった(つい最近までは)。
今回、田口俊樹の翻訳によって刊行された『ガイズ&ドールズ』は、前回の『ブロードウェイの天使』から、ちょうど40年ぶりに刊行されたデイモン・ラニアンの作品集ということになる(すごい)。
しかも、前回の『ブロードウェイの天使』は、日本オリジナルの作品集だったが、今回の『ガイズ&ドールズ』は、デイモン・ラニアン最初の短篇小説集の完訳である(おまけとして「ミス・サラ・ブラウンの恋の物語」が収録されているが)。
庄野さんは、このときに読んだ『ブロードウェイの天使』が、よほどお気に入りだったらしく、後に『エイヴォン記』という長篇随筆を連載したとき、デイモン・ラニアン「ブッチの子守唄」を一番最初に取り上げている。
デイモン・ラニアンは、戦後に亡くなった私の父の好きな作家であった。戦争が終った翌年くらいであったか、父が、「デイモン・ラニアンというのは面白い」と何度か私にいった。進駐軍と一しょに入って来たペイパーバック版でラニアンの短篇集を手に入れて読んだらしい。(庄野潤三『ブッチの子守唄』)
今回の『ガイズ&ドールズ』では「ブッチは赤子の世話をする」という題名で収録されている作品が、『エイヴォン記』に登場する「ブッチの子守唄」である。
原題は「BUTCH MINDS THE BABY」だから、意味としては、今回の訳が正しいのだけれど、小説の雰囲気としては「ブッチの子守唄」の方がかっこいい。
昔の翻訳小説は、意味よりも雰囲気を重視したのだろう(『ライ麦畑でつかまえて』みたいに)。
ブッチというのは、金庫破りの名人だった男の名前で、今はもう結婚して引退し、妻が留守の間、赤ん坊(ジョン・イグネイシャス・ジュニア)の世話をしている。
ギャングたちにそそのかされたブッチは、久し振りに昔の仕事に挑戦することになるが、赤ん坊を置いていくわけにはいかないので、ジョン・イグネイシャス・ジュニアを連れて金庫破りに出かける。
ミルクを飲みおえると、ジョン・イグネイシャス・ジュニアがぐずりはじめ、ビッグ・ブッチは遊ばせるのに、金庫破りの道具をジョン・イグネイシャス・ジュニアに渡さなきゃならない。だけど、最後にはその道具が必要になり、ジョン・イグネイシャス・ジュニアから取り上げる。(デイモン・ラニアン「ブッチは赤子の世話をする」田口俊樹・訳)
久し振りの現場復帰に加えて、赤ん坊の世話までしているのだから、仕事がはかどるはずもない。
ブッチに附き添っているリトル・イザドアも、外で見張りをしている馬づらハリーとスパニッシュ・ジョンも、だんだん心配になってくる(この三人がブッチに仕事を依頼した)。
ギャング小説というよりも、ほとんどコメディ小説で、この爽快なユーモアが、デイモン・ラニアンの作品の大きな特徴となっている。
「荒ぶる四十丁目界隈のロマンス」は、ブン屋(新聞記者)ウォルドー・ウィンチェスターとクラブのダンサー、ミス・ビリー・ペリーの恋物語。
めかし屋デイヴは、ミス・ビリー・ペリーを愛しているが、彼女がウォルドー・ウィンチェスターと愛し合っているのを知って、二人の結婚式を企画する。
「だってな、おまえも知ってんだろ、おれが彼女にぞっこんだってのは。そんなおれとしちゃいつも思ってるのよ、彼女には幸せになってほしいってな。それがたとえこんな結婚でもな。で、おれが仕組んだのよ、この結婚式を」(デイモン・ラニアン「荒ぶる四十丁目界隈のロマンス」田口俊樹・訳)
結婚式の会場となったロードハウス<ウッドコック・イン>(ビッグ・ニッグ・スコルスキーが経営している)には、ブロードウェイのすべての店に出入りしている連中が、続々と集まってくる。
グッドタイム・チャーリー、ミス・ミズーリ・マーティン、フィート・サミュエルズ、トニー・ベルタゾーラ、スキーツ・ボリヴァー、ギリシア人のニック、ロチェスター・レッド、ジョニー・マクゴワン(物語の語り手である主人公と一緒にやってきた)。
ところが、主役のウォルドー・ウィンチェスターは、全然楽しそうじゃない。
ここで、ウォルドーには、妻がいるということが明らかになる(つまり、不倫だった)。
盛り上がる会場に乗り込んできたのは、ウォルドーの嫁ローラ・サポラで、曲芸師の一座に加わっている怪力女のサポラは、たちまち結婚式をメチャメチャにしてしまう。
ひどい話になったと思っていると、ウォルドーに騙されていたことを知ったミス・ビリー・ペリーが、めかし屋デイヴに身を寄せて「あんたこそあたしの男よ」なんて、泣きながら訴える。
「おいおいおい!」とめかし屋デイヴは満面に笑みを浮かべて言う。「牧師はどこにいる? 誰かここに連れてきてくれ。ここからはおれたちの結婚式だ!」(デイモン・ラニアン「荒ぶる四十丁目界隈のロマンス」田口俊樹・訳)
めかし屋デイヴとミス・ビリー・ペリーが結ばれてハッピーエンドとなるあたり、爽やかなユーモアがある。
「荒ぶる四十丁目界隈(roaring forties)」は、ブロードウェイ界隈を意味するスラングで、この「荒ぶる四十丁目界隈のロマンス」が、デイモン・ラニアンのブロードウェイものの最初の作品となった(1929年7月号『コスモポリタン』)。
ドタバタの喜劇が、最後に「すごく良い話」になる
『ガイズ&ドールズ』には、とにかくたくさんの男たちと女たちが登場する。
短篇集なのに、ちょい役も含めると、おそらく100人以上の人間の名前が登場しているはずだ(ほとんどの人物がちょい役になるが)。
豊富なキャラクターを、たっぷりと楽しむことができるのが「マダム・ラ・ギンプ」だ。
マダム・ラ・ギンプは、スペイン系の老女の浮浪者で、彼女の娘ユーラリーが、婚約者を連れて、スペインからやって来ることになった。
彼女は、めかし屋デイヴに相談して、スペインからの一行が来る間だけ、自分を金持ちに仕立てあげてもらう(つまり、娘や娘の婚約者や娘の婚約者の家族を騙すわけだ)。
夫役にはヘンリー・G・ブレイク判事が選ばれ(本当の判事ではない)、豪華なアパートメント・ホテル<マーベリー>に住居を構える(オーナーのロドニー・B・エマーソンが協力してくれた)。
スペインからの一行を迎え、めかし屋デイヴは、賑やかな歓迎会を開催するが、そこには、ニューヨークの大物が、続々と詰めかけていた(もちろん、全員が偽物)。
ビッグ・ニッグは大富豪ウィリー・K・ヴァンダービルトで、<チキン・クラブ>のトニー・ベルタゾーラは俳優アル・ジョンソンに、スキーツ・ボリヴァーがパブティストの牧師ローチ・ストラトン猊下で、グッドタイム・チャーリー・バーンスタインはニューヨーク市長ジェームズ・J・ウォーカーとして紹介される。
人気スポーツライターのヘイウッド・ブルーンとして紹介されたギリシア人ニックは「ヘイウッド・ブルーンっていうのは何者なんだ?」なんて、きょとんとしている(ヘイウッド・ブルーンは、本書『ガイズ&ドールズ』に序文を寄せている)。
デスハウス(死刑囚棟)のドネガンはプロレスラーのウィリアム・マルドゥーンとなり、ギニー(イタ公)・マイクなんて、合衆国副大統領チャールズ・カーティス閣下として紹介されてしまった。
本作の語り手である主人公も、大作家ミスター・O・O・マッキンタイアとして紹介されて、スペインの伯爵夫妻とその息子とマダム・ラ・ギンプの娘とマダム・ラ・ギンプの姉さんとヘンリー・G・ブレイク判事と握手することになる。
いろいろな人間が次々と登場して(そして、誰もが人間くさい)、物語を展開させていくところが、デイモン・ラニアンの作品の大きな魅力と言えるだろう。
しかも、本作では、マダム・ラ・ギンプとヘンリー・G・ブレイク判事が、実は、ずっと昔に恋仲だったことが分かる。
「この二日ずっと考えてるんだけど、あんた、私のことを覚えてるかね?」「覚えてる」とマダム・ラ・ギンプは答える。「覚えてるどころか、すごくすごく覚えてるわ、ヘンリー。どうすればあんたのことを忘れられる? でも、あんたも気づくとは思ってなかった。だってもう何年も何年もまえのことなんだから」「二十年だ」と判事は言う。「あの頃のあんたはきれいだった。今でもそうだが」(デイモン・ラニアン「マダム・ラ・ギンプ」田口俊樹・訳)
ドタバタの喜劇が、最後に「すごく良い話」になる。
これは確かにヒューマン・ドラマで、デイモン・ラニアンの作品の特徴を一言で言ってしまえば、ペーソス&ユーモアということになる(あまりにも陳腐な表現だが)。
まるで「浪花節」を思わせるようなラニアンの人情噺は、明らかに日本人の好むところだ。
シカゴの大物ギャングたちの仲裁へ出かけていっためかし屋デイヴ。
<ホット・ボックス>の酒を飲むと、どんなやつでも急に泣きだすことがよくあるんだ。実際の話、<ホット・ボックス>の酒は街で一番人を泣かす酒じゃないかな。(デイモン・ラニアン「ダーク・ドロレス」田口俊樹・訳)
国王を暗殺に行って、国王(実は幼い子どもだった)と仲良くなってしまう3人組(イジー・チーズケーキ、キティ・クウィック、シカゴのジョジョ)。
だけど、おれたちのやったことが子供には大うけで、死ぬほど笑い転げてる。ピーボディ先生も笑ってる。その様子を見ておれは思う、こいつらはこれまで笑う機会にあんまり恵まれなかったんだろうって。(デイモン・ラニアン「紳士のみなさん、国王に乾杯!」田口俊樹・訳)
病気の母親と昔の恋人に会うため、ブロードウェイへ舞い戻ってきた逃亡犯ビッグ・ジュール。
「ああ、ミス・キティ・クランシーにまた会えたらすごく嬉しいよ。おふくろに会えても。自分が住んでた界隈が見れるだけでも」(デイモン・ラニアン「世界で一番ヤバい男」田口俊樹・訳)
妻や愛人よりも、最後に自分を看取ってくれた貧しい女性に遺産を残した、金持ちのブレイン。
萎れたカーネーションにはカードがついてて”親切な旦那さまへ”と書かれてる。それを見ておれは思う、ここには何千ドルもする花もあるかもしれないけど、真心が込められてるのはこの花だけだって。(デイモン・ラニアン「ブレイン、わが家に帰る」田口俊樹・訳)
女豹のような元カノ・リリアンを忘れられない、キャバレー芸人(歌手)ウィルバー・ウィラード。
おれも<ホット・ボックス>には時々出かける。気分がブルーなときに彼が『マイ・メランコリー・ベイビー』とか『ムーンシャイン・ヴァレー』とか淋しい歌を歌うのを聞きに。そういう歌を聞くと、胸が張り裂けそうになる。(デイモン・ラニアン「リリアン」田口俊樹・訳)
最愛の女性を不幸に陥れたルーイに復讐するジャック・オハーツ。
彼女の遺体をサン・ピエールに連れ帰って、ちっちゃな墓地に埋めたよ。あたりには濃い霧が立ち込めててな、遠くじゃ霧笛が悲しく悲しく鳴っててな、ドクター・アルマン・ドルヴァルがおれの耳にこんなことを囁くのさ。「ジャック・オハーツ、あの長い小道の歌(ロング・トレイル)を歌っておくれ」(デイモン・ラニアン「サン・ピエールの百合」田口俊樹・訳)
ブロードウェイの男たちは、みんな、ロマンチストだ。
純情で情熱的で女好きの、気のいいロマンチストたちばかりだ。
そんなブロードウェイの男たちの世界を描いたのが、本作『ガイズ&ドールズ』である。
ただし、序文でヘイウッド・ブルーンは、次のように言っている。
彼はニューヨークのごく一部しか描かなかった。加えてその一部はブロードウェイ全体ですらない。ラニアンの作品で作中起こる出来事は、すべてタイムズ・スクウェアとコロンバス・サークルのあいだにかぎられる。(デイモン・ラニアン『ガイズ&ドールズ』序文・ヘイウッド・ブルーン)
本書には、全部で14篇の短篇小説が収録されているが、登場人物は全作品で共通していて、めかし屋デイヴやビッグ・ニック、グッドタイム・チャーリーなど、街の顔役たちは、いろいろなエピソードの中に登場する。
作品は、すべて、ブロードウェイの住人である主人公(「おれ」)によって語られているが、この主人公には名前がない。
非常に多くの登場人物が出てくる中で名前がないのは、主人公はあくまでも「物語の語り手」としての役割に徹しているためだと思われる(つまり「舞台回し」として)。
しかし、この名前のない主人公も、エピソードを語る中で、自身のキャラクターを語っており、それが、作品に「いい味」を出していることは確かだ。
タフガイばかりの、この街で、主人公は気の弱い小心者だが、なぜか、いつも事件に巻き込まれてしまう。
彼がそばに来たことがおれにわかると同時に、彼の声が聞こえる。「これはこれは。こんなとこで会うとはな!」そう言って、おれの襟をつかむ。こうなったらもう逃げられない。逃げたいのは山々なれど。「やあ、ラスティ」とおれは精一杯陽気に言う。「調子はどうだい?」(デイモン・ラニアン「血圧」田口俊樹・訳)
誘われたら断れない主人公もまた、優しくてセンチメンタルな、ブロードウェイの住人だった。
著者が投影されていると思われる主人公は、1930年代を生きた、ブロードウェイの記録者である。
つまり、本作『ガイズ&ドールズ』は、1930年代のブロードウェイを描いたドキュメンタリーとしても読むことができるのだ(嘘とジョークにまみれたドキュメンタリーとして)。
必死に生きる男たちの姿は、なぜか、ほろ苦い。
それは、この世を生きる、すべての男たちの姿でもあるからだろう。
書名:ガイズ&ドールズ
著者:デイモン・ラニアン
訳者:田口俊樹
発行:2024/06/01
出版社:新潮文庫