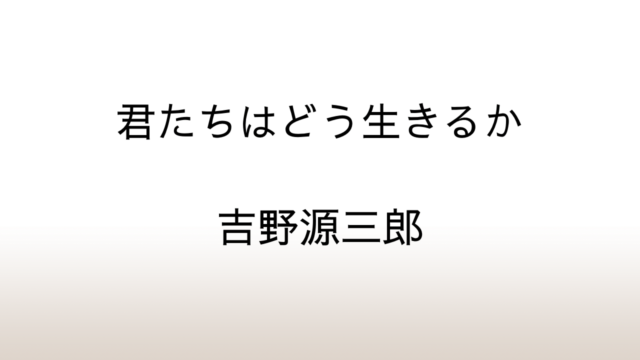石川桂郎「俳人風狂列伝」読了。
本作は、雑誌『俳句とエッセイ』(牧羊社)と『俳句』(角川書店)に連載されたものを書籍化したものである。
俳句の世界における「奇人変人」の評伝
本書は、俳句の世界における「奇人変人」の評伝をまとめたものである。
別に、俳人に狂気の人が多いというわけではないだろう。
だが、本書に登場する俳人たちの奇行は、いかにも尋常ではない。
例えば、最初に出てくる<高橋鏡太郎>は、結核病院から退院したくないがために、再度、結核に罹患しようと考え、夜更けに重病患者の痰コップから血痰を盗み、これを飲みこんだという。
狂っているとしか思われない。
だが、彼にとっては、三食付きの安定した病院の生活は、入院前の破天荒な暮らしに比べれば、まるで天国のような生活だったのだ。
俳人仲間が集まる酒場<ボルガ>で、見知らぬ他人に酒をたかるばかりか、自宅まで付いていって家族に驚かれ、よれよれのボロ服で泊り込んだ挙句、翌朝の朝食を食べ終わったところで「君は会社だろう。ぼくは残って少し仕事をさしてもらうよ」と言いのけた。
うかつに酒を奢った男の悲劇だが、奥さんも驚愕したに違いない。
俳句は、久保田万太郎の『春燈』を拠り所としていたが、師・万太郎の留守宅に上がり込み、泥酔して散々御託を並べて帰ったところが、万太郎や安住敦の激怒を買ったために、出入り禁止の除名処分となってしまった。
晩年は、乞食の婆さんを引き取って、二人で仲良く暮らした。
国電を見下ろす崖っぷちで酔って寝込んでいるうちに、崖下へ転落して死んだときは49歳だった。
次の<伊庭心猿>は、永井荷風の信頼高かったが、荷風の原稿や短冊などの贋物を売りさばき、絶交された俳人である。
荷風の『来訪者』に出てくる<木場>こそ、この心猿だった。
ちなみに、心猿の俳句の師は、両足に障害のあった俳人<富田木歩>である。
<岩田昌寿>は、共産党入党、創価学会入信の後、結核病院に入院した愛人の看病と称して泊まり込んだ病院で共産党活動を始めるが、病院内での女性問題で党関係者から吊し上げを喰らった挙句に発狂、そのまま精神病院へ送られた。
「狂人俳句」こそ、岩田昌寿の文学テーマだった。
「秋夜狂つて図太くなれば生くばかり」や「秋雨の中や睾丸握りしむ」「独房の雪は音楽となり降りそそぐ」「狂ひ女の乾飯すひとる畳つめたし」「町の灯は耶蘇の灯に似て遠し遠し」など、佳作が多い。
晩年は湘南へ移り住み、友人の部屋を転々として、日雇の仕事をしながら「日雇俳句」を作った。
とある友人の家では、妹の結婚話に首をつっこみ、友人を激しく非難した挙句に、結果、この友人を自殺にまで追い込んでしまった。
しかも、自殺した友人に「香取久雄自殺す」の前書きを添えて「石蕗の花死ねざる無援の日雇者」の句を残した。
地元の人々は「もし昌寿が小田原に来なかったら、香取久雄は死ななかったろう」と話し合ったという。
1959年(昭和34年)に句集を出したまでは分かっているが、その後、行方知れずとなり、1966年(昭和41年)、45歳で死んだことは、当時、誰も知らなかったという。
死んだ娘の骨を食いつくした俳人
<岡本癖三酔>は、久保田万太郎が芝居の脚本に書きたいと言った俳人である。
「桂郎さん、あたしはどうしても癖三酔を芝居に書きたい。可愛がっている娘がいてね、十五、六にもなろうか。(略)ところがその子が急死してね、お骨になって帰ると、どうしても寺へ納める気になれない。自分の部屋に骨箱を置いて朝夕お線香をあげるんだけど、そのたびに骨壺の蓋をあけて一つ二つと食べてしまう。とうとう最後に小さな骨の一片を残したという、ね、これは芝居ですよ」(石川桂郎「室咲の葦」)
癖三酔は、金持ちの奇人で、親の遺産で生活して「門外不出十五年」を固く守ったという。
つまり、自宅の門より外には15年間出たことがなかったのだ。
そもそも、自分の部屋から一歩も出ようとしないような、極度の引きこもりだったらしい。
もっとも、問外不出が明けた後は、狂ったように毎夜のカフェ通いを始め、あまりに毎晩大金を使うので、怪しんだ<プランタン>が警察に通報したという逸話も残されている。
その後、癖三酔は、カフェにいた若い女給を自宅に引き取って、一緒に暮らした。
骨壺の骨を食いつくした娘は、癖三酔の実母(娘にとっては祖母)から苛められての自殺だったという。
次の田村得次郎は「バタ屋俳人」である。
蟻の町のマリア北原怜子で有名なバタ屋部落に住み、日本橋の問屋街を主に、籠を背負い棒秤を提げて紙屑や縄の切れ端を拾い廻って、一日の収入がやっと二百円足らず、そんな暮らしの中で久保田万太郎著『残菊帖』五十円を古本屋で見つけ、掘出し物と小踊りする一方では、思わず飲み過ぎた焼酎(ばくだん)の残り金がパンの耳数片にしかならない夕食、そんな毎日だった。(石川桂郎「屑籠と棒秤」)
「夜濯ぎの一夜妻待つ古雑誌」の句は、安住敦所有の「あるバタ屋の日記」に残されていた作品である。
もともと、農協職員だった田村得次郎は、銀行から引き出した職員の給料を、飲み屋の女のために使いこみ、公金横領の罪で指名手配されて逃げ回っているところ、石川桂郎の説得により自首。
横須賀刑務所で獄中生活を送り、「握飯(むすび)白く大きく勤労感謝の日」などの句を作った。
出所後は、放浪生活の末、バタ屋へと転身、「バタ屋日記」を綴ったものと思われる。
最後にもう一人、「乞食俳人」の<相良万吉>を記しておきたい。
目明き千人めくら千人。自選の能力もなくて路傍に俳句──乞食俳句を抱える己の無能力を知らないものでもありません。ただ言はんとするところは。山本健吉君の所謂。発句とは挨拶であり滑稽とは。乞食にとっては自嘲の歌でありました。「鬼は外乞食は内か豆を撒く」(石川桂郎「水に映らぬ影法師」)
相良万吉は数寄屋橋では有名な乞食だったようだが、実は、一高(現在の東京大学)に学んだ秀才だった。
一高中退後は、流浪と労働運動の生活に身を投じ、南太平洋で従軍。
戦後、炭焼きを始めるが、足を怪我して乞食となり、「クリスマス乞食も小さき樅買はん」などの句を詠んだ。
1960年(昭和35年)、「俳句乞食という職業は六法全書にもない」と書き残し、61歳で自殺。
辞世の句は「死を前に破れぶとんの暖かさ」だった。
『俳人風狂列伝』を読み終えて感じたものは、俳句の持つ強靭なエネルギーである。
乞食にしても狂人にしても、逞しいばかりに生きる力となっていたのは俳句だった。
あるいは、彼らは、俳句がなければ、ここまで生き抜くことはできなかったのではないだろうか。
例え最後には自害という結末を迎えていたとしても、彼らの人生は俳句とともに輝いていた。
この本が、中公文庫で今でも入手可能というのは、率直に驚きでしかないが。
書名:俳人風狂列伝
著者:石川桂郎
発行:1973/10/25
出版社:角川書店