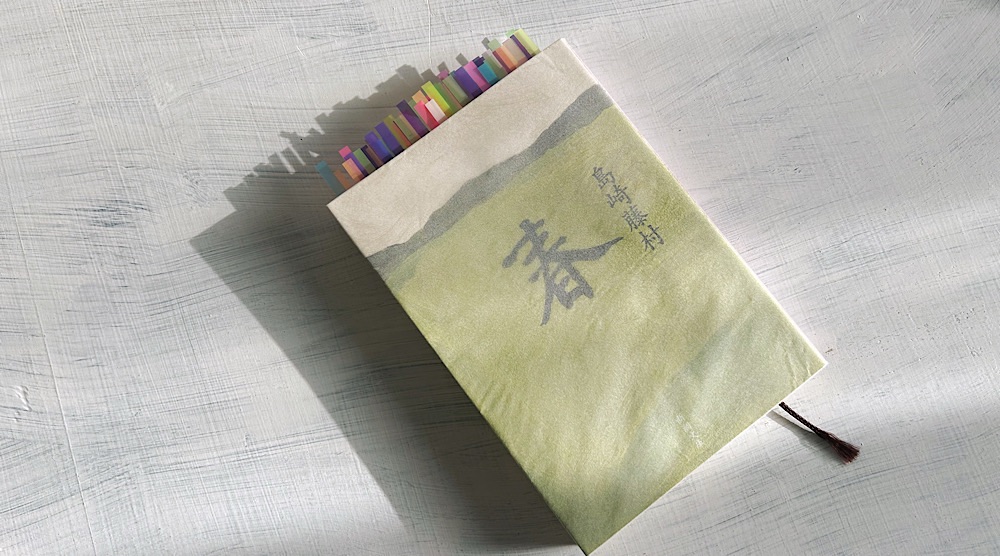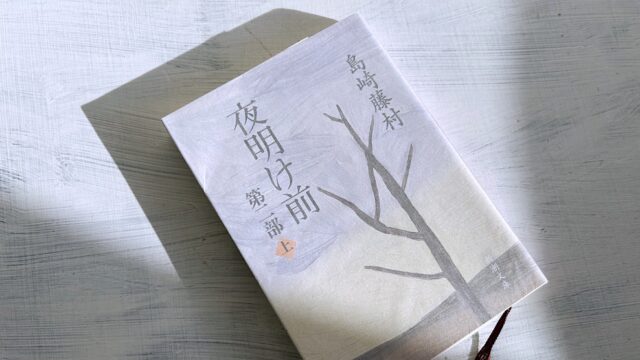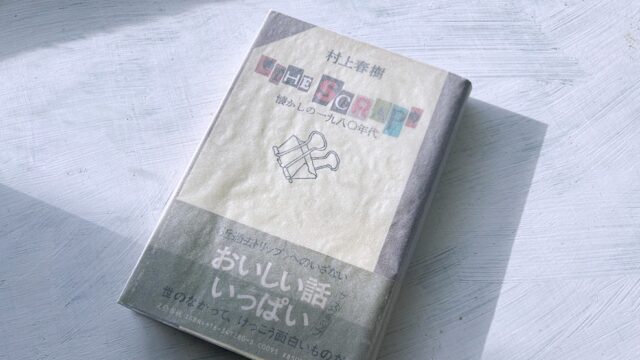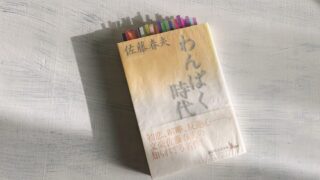島崎藤村「春」読了。
本作「春」は、1908年(明治41年)10月に緑陰叢書第二篇として刊行された長篇小説である。
この年、作者は36歳だった。
初出は、1908年(明治41年)4月~8月『東京朝日新聞』(連載小説)。
死んだ親友(北村透谷)への鎮魂歌
福原麟太郎「変奏曲」という随筆に、島崎藤村の『春』が出てくる。
「春」の年代は明治二十六、七、八年で、私などの生まれたころだが、その初め、島崎藤村は二十二歳であったろう。島崎さんをその歳とすれば、平田禿木は二十一歳である。戸川秋骨は二十四歳、馬場孤蝶は二十五歳であったろう。上田柳村が一ばん若くて二十歳、北村透谷が一ばん年取っていて二十六歳であった。(福原麟太郎「春」)
本作『春』は実在の人物をモデルとしていて、主人公(岸本捨吉)が島崎藤村で、「青木」が北村透谷、「市川」が平田禿木、「菅」が戸川秋骨、「足立」が馬場孤蝶、「福富」が上田敏(柳村)となっている。
英文学者(福原麟太郎)にとって、平田禿木や戸川秋骨らは、英文学を学ぶ上での先生たちであった。
島崎藤村は、平田禿木や戸川秋骨の親友ということで、福原さんにとっても「先生の仲間」的な存在であったに違いない。
私自身にとっては、私がその晩年をよく知っていたといってよい平田先生や戸川先生のお若いころの姿が実在の人のごとく写されているのを、なつかしく思うのである。モデルでも何でもよい。この人が若き禿木であり、若き秋骨であると思って読むのだ。(福原麟太郎「春」)
福原麟太郎は、この『春』という長編小説について、「透谷の狂死を織り込んだ、藤村の煩悶と恋愛と流浪の話」と紹介している。

つまり、本作『春』は、作者(島崎藤村)の若き日を振り返った自伝的青春小説なのだ。
岸本捨吉は、『春』(1908)のほか『桜の実の熟する時』(1919)や『新生』(1919)といった、藤村の自伝的作品の中に、共通して登場する主人公である。
連中が東海道を下った頃は明治二十六年の夏である。大分その日の汽車は込んだ。一行は疲れて吉原の宿に着いた。(島崎藤村「春」)
物語は、主人公(岸本捨吉)の流浪の旅から始まる。
教え子との恋愛問題に疲れた主人公は、勤め先の学校を辞して、流浪の旅へ出た。
「さすがの岸本君も弱って来るだろうなあ」と市川が言った。「行くところまで行ってみなければ承知しないという男だ」(島崎藤村「春」)
青木を筆頭に、岸本、市川、菅の四人は、文学という固い絆で結ばれた仲間だった(「彼と、菅とは同窓の友であった」)。
失意の旅を、青木は「憐むべき巡礼だ」と、心に繰り返している。
岸本に対する仲間たちの共感は、彼らの誰もが、多かれ少なかれ、同じような苦悩を知っていたからだ。
青木に言わせると、ハムレットは最も悲しい夢を見た人間の一人である。この最も悲しい夢を見たという言葉が、妙に岸本の胸に響いた。(島崎藤村「春」)
愛した女性との恋愛の成就や、文学的世界における成功。
若者たちは、いつでも「悲しい夢」を見ていた。
なかでも、既に家族持ちとなっていた青木の夢は悲しい。
連中で細君のあるものは青木一人である。彼は早く結婚した。二歳になる女の児の親でありながら、ようやく二十六にしかならない。(島崎藤村「春」)
主人公(岸本捨吉)が教え子(安井勝子)への恋に苦悩するのと並行して、妻帯者の青木は結婚生活に苦悩している。
彼に言わせると、恋愛は人世の秘鑰である、恋愛あって後に人世がある、恋愛を抽き去った日には人生何の色も味も無い──。不思議なことには、恋愛が造作もなく彼の眼をくらましたように、結婚はまた造作もなく彼の心を失望させた。(島崎藤村「春」)
結婚生活に苦悩する青木の姿は、実は、勝子への恋愛に煩悶する主人公自身の姿でもあることを暗示している。
しばらく青木はぼんやりと三人の友達の様子を眺めたが、旅から帰った岸本がただそこに坐っているとは思わなかった──。彼は眼前に往時の自分を視るような気がした。(島崎藤村「春」)
若者たちの関心は、常に女性へと向いている(「未だラブの話か」)。
「君は女というものをどう思う」こう市川が言出す。「どんな良い家庭に生れて来た人でも、どこかに女郎のような性質を備えているね」(島崎藤村「春」)
男たちに活力を与え得るのも、苦しませるものも、等しく女たちだったと言っていい。
青年たちの「悲しい夢」の先にあるものを知っているのは、青木だけだった。
だからこそ、青木は、もう一人の主人公として、悲しい人生を歩んでいかなければならない。
実際、二人の結婚は世にありふれたようなものではなかった。愛して、愛されて、すべての物を犠牲にして、それでようやく一緒になった仲である。この人のためにはいかなる艱難をも厭うまい。こう決心して操は夫に随ったのである。(島崎藤村「春」)
若い夫婦に、艱難はすぐにやってきた。
長女(鶴子)が生まれて、新婚生活は、ますます困難を極めつつあった。
青木は独りは眠られなかった。こんな調子で押して行ったら、終いにはどうなる。こう彼は考えた。そうして非常な恐怖の念を抱いた。(島崎藤村「春」)
家庭生活が厳しくなっていくのと同じように、青木の精神は加速したように破綻へ向かって進んでいく。
急に青木は耳を澄ました。「あ、誰か僕を呼ぶような声がする」と言いながら、彼は両手を耳のところへあてがって、すこし首を傾げていたが、やがて高い声でこんな歌を歌い出した。(島崎藤村「春」)
かつて、青木は、激しく活動する思想家だった。
新しい社会を切り開くために見せた彼のエネルギーが、年若い後輩のたちにとっての魅力でもあったのだ。
「人間の力には限りがあるネ──。僕は世を破るつもりでいて、返って自分の心を破ってしまった、非常にそれが残念だ」(島崎藤村「春」)
本作『春』は、死んだ親友(北村透谷)への鎮魂歌として機能している。
夢破れて死んでゆく青木の姿は、あまりにも痛々しい。
新婚の当時、新しい洋服姿で、一緒に並んで写真を写した夫の姿に思い比べてみると、今は目も当てられぬ程の変わりかたである。昼夜の懊悩と、不眠の苦痛と、底の知れない畏怖とで、顔色なぞは最早別の人のように蒼ざめている。(島崎藤村「春」)
青木の衰弱ぶりが恐ろしいのは、それが、主人公をはじめとする仲間たちの未来を暗示しているように見えるからだ。
最初の自殺は失敗に終わった。
手が狂った為か、咽喉の傷口は急所を外れた。母や、弟や、それから操は、全力を出して彼を救った。早速医者が駆け付けた。部屋に移され、親切に手当てを施された頃の彼は、ほとんど生きた屍のようであった。(島崎藤村「春」)
しかし、死を決意した者の心が回復することはなかった(「庭の青葉のかげで、彼は縊れて死んだ」)。
「とうとう、宅も亡くなりましたよ」と操は嘆息した。疲労と悲哀とで、彼女の顔色は蒼ざめて見えた。(島崎藤村「春」)
社会に打って出た若者の魂が、夢を叶える間もなく消えてしまったのだ。
「何故青木君は亡くなったんでしょう」と岸本は未亡人にそれを尋ねて見た。「さあ、私にも解りません」こう未亡人が答えた。この「私にも解りません」が一番正直な答えらしく聞えた。(島崎藤村「春」)
ひとつの象徴的存在であった青木の自死は、仲間たちに大きな衝撃を与えた。
青木が奮闘して倒れたということは、連中にとって大きな打撃であった。友達は皆考えた。しかし、仲間中から一人の戦死者を出したということが、返って深い刺激になって、各自志す方へ突き進もうとしたのであった。(島崎藤村「春」)
青木の死をバネに、彼らは精力的な活動を見せたが、それらは決して持続的なものとはならない。
青木は死ぬ、岡見は隠れる、足立は任地を指して出かけてしまう。市川、菅、福富は相継いで学問とか芸術の鑑賞とかいう方へ向いた。連中は共同の事業に疲れて来た。(島崎藤村「春」)
若い彼らにとって、青木という強大な精神的支柱を失ったことは、あまりに大きな痛手だったのだ。
青春の日の夢が、いかに難しいものであるかということを、この長篇小説は物語っている。
そして、それでも前を向いて歩いていかなければならないということも、やはり、青春に与えられた宿命だった。
主人公(岸本)は、勝子への恋愛に苦悩しながらも、青木の死を乗り越えて生きていかなければならない。
本作『春』は、親友の死を乗り越えて生き続ける男の物語だったのだ。
狂人の血と生き続けていくことの苦悩
「死は僕という存在の中に本来的に既に含まれている」と言ったのは、村上春樹『ノルウェイの森』(1987)の主人公(ワタナベ君)だ。
それは今にして思えばたしかに奇妙な日々だった。生のまっただ中で、何もかもが死を中心にして回転していた。(村上春樹「ノルウェイの森」)
死を内包して生きていく若者という意味で、『春』の主人公(岸本捨吉)は、『ノルウェイの森』の主人公(ワタナベ君)と似ている。
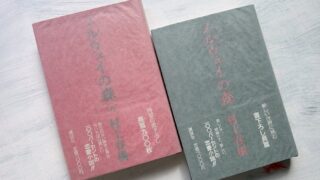
慨然として死に赴いた青木の面影は、岸本の眼前にあった。「我事畢れり」と言った青木の言葉は、岸本の耳にあった。(島崎藤村「春」)
主人公(岸本捨吉)の苦悩の源流は、女(勝子)にあった。
岸本が勝子に逢おうと決心するまでには、どれほど狂人じみた苦痛を嘗めたか知れない。(島崎藤村「春」)
女(勝子)とは相思相愛のはずだった。
この心情の解らない人は、たとえ狂じみてると言おうが、何と言おうが、言ってもかまわない、聞入れもしない、こう書いてある。「ああ、わが身はすでに死せるなり、残るはただ君を慕う心あるのみ」こう書いてある。(島崎藤村「春」)
しかし、女(勝子)は学校時代の教え子であり、まして、彼女には、親の定める許嫁があった。
入口のところには車夫が待っていた。格子戸を出て、勝子は名残惜しそうに岸本の方を見た。二人は無言の思を交換した。その時ばかりは、師弟の礼儀を守ったと言えなかったのである。(島崎藤村「春」)
『ノルウェイの森』だったら、二人はセックスしていたかもしれない。
しかし、時代は明治20年代で、二人は自分自身を厳しく律するしかなかった。
主人公(岸本)の苦悩は、やがて、青木の苦悩へと通じていく。
「とにかく、狂じみたところだけは似ている」と言って、青木はゆすって、「あの男のは自分で知らないでやってる、俺はそれを意識してる──そこが違う」(島崎藤村「春」)
誰もが、青木と岸本は似ていると言った。
「真実に、岸本さんは宅によく似ていらッしゃいますよ」「そうですかなあ。青木君にも僕のような時代が有りましたかなあ」と言って、岸本は自分で自分を嘲るように笑った。(島崎藤村「春」)
苦しみ死んでいく青木の姿は、主人公にとっては、我が身を占う予言のようなものだったかもしれない。
「青木君」と岸本が言った。「僕なぞは、そう長く生きる人間じゃないような気がする。二十五という年齢が来たら、多分死ぬネ」(島崎藤村「春」)
旅の途中で、主人公は死の世界へと導かれていく。
不幸な旅人は、今、自分で自分の希望、自分の恋、自分の若い生命を葬ろうとして、その墳墓の方へ歩いて行くのである。とうとう、彼はその墳墓の前に面と向って立った。暗い波はおそろしい勢いで彼の方へ押し寄せて来た。(島崎藤村「春」)
青木の不幸が、死に至ることだったとしたら、主人公の不幸は、生きていくことにあった。
主人公は、女(勝子)に別れの手紙をしたためて、自分の苦悩と決着をつける。
その夜、彼は初めて自分の心に近い手紙を書いた。しかも、その心は捨てたと書いた。彼は最早勝子を慕っているものではないということを書いた。今までの自分はただ彼女を欺いていたのであると書いた。そして、心の籠った調子で、許嫁の人の許へ行くように、親の心を安んずるように、こう一気に書下した。(島崎藤村「春」)
やがて、二つ目の「死」が、主人公を襲った。
函館へと嫁いでいった最愛の女性(勝子)の死である。
学報には「八月十三日、麻生勝子氏忽然永眠せらる」と記されていた(勝子は函館の麻生家へ嫁いでいた)。
勝子は妊娠していて、ひどい悪阻(つわり)のために心臓病を引き起こしたものらしい。
菅は冗談半分に、「君はあの時分に死んでた方がよかったよ」と笑って、旧からの学校友達を憐むような眼付をした。「あの時分」とは岸本が旅にいた頃のことである。(島崎藤村「春」)
生き続けていくことの苦悩が、そこにはある。
親しい二人の人間の死に加えて、主人公には「狂人の血」という恐怖があった。
国学や神道に凝り過ぎたともいうが、深い山里に埋れて、一生煩悶して、とうとう気が変になった人の手がそれだ。(略)ありあまる程の懐を抱きながら、これという事業も残さず、終いには座敷牢の格子に掴まって、悲壮な辞世の歌を読んだ人の手がそれだ。(島崎藤村「春」)
座敷牢で狂い死にした父親の物語は、やがて、自伝的歴史小説『夜明け前』(1929)として発表されることになる。
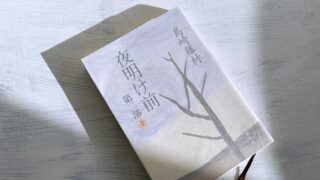
「捨吉も年頃だ。そろそろ阿爺(おやじ)が出て来たんじゃないか」
苦悩する弟(捨吉)を見て、兄は、狂い死にした父親の血の恐怖を語った。
何でも、父が二十の年齢とかに、初めて病気が発って、その時は治るには治ったが、それから中年になって再発した。この事実を民助は思い浮べた。そうして、二十の年齢というから、あるいは弟と同じような動機で。(島崎藤村「春」)
狂人の息子という恐怖は、主人公自身の中にもあった。
鴈が鳴いて屋根の上を通った。その荒い叫び声は怖しく岸本の頭脳へ響けた。「ああ──自分の頭脳の内部の声だ」(島崎藤村「春」)
岸本捨吉という若者の青春は、常に苦しみの中にあった。
苦しみの青春を綴った物語こそ、本作『春』という長篇小説であったと言っていい。
そして、苦しみの中から、主人公は生きることを選んだ。
「ああ、自分のようなものでも、どうかして生きたい」こう思って、深い深い溜息を吐いた。(島崎藤村「春」)
「ああ、自分のようなものでも、どうかして生きたい」という未来への希望をつかんだとことで、物語は幕を閉じる。
もちろん、主人公の人生は、相も変わらず前途多難だ。
人々は雨中の旅に倦んで、多く汽車の中で寝た。復たざアと降って来た。(島崎藤村「春」)
就職のために仙台へと向かう主人公を乗せた汽車は、雨の中にあった。
「復たざアと降って来た」という最後の一行に、主人公の不安が象徴されている。
それでも、主人公(岸本)は生き続けていかねばならない。
そこに、この青春小説のテーマがある。
「岸本君、君はどう思うね。われわれはすこし早く生れて来過ぎたんじゃ有るまいか」こう市川は言出した。(島崎藤村「春」)
あるいは、それが、明治20年代を生きた青年たちの青春というものだったのかもしれない。
新しい時代の向こう側にある期待と不安。
若者たちの未来には、いつでも、希望と恐怖とがあった。
先の知れない時代を、彼らは確かに生きていたのだ。
将来、自殺することになる有島武郎は、青木の自殺に強い共感を寄せている。
五月五日 火曜。『朝日新聞』に連載中の藤村の『春』を読んでいる。青木が自殺しようとしている。青木の気持ちが痛いほどよくわかるので、ほとんど読むのを止めようかとさえ思ったくらいだ。(有島武郎「観想録(第十三巻)」明治41年/『有島武郎全集(第十一巻)』)
ちなみに、安井勝子のモデル(佐藤輔子)の異母兄(佐藤昌介)は、クラーク博士に学んだ札幌農学校一期生で、後に北海道帝国大学初代総長を務めるなど、北海道文学とも縁がある。
札幌農学校の卒業生であり、母校で教鞭も取った有島武郎とも、多少のつながりがあったわけだ(有島の日記にも「佐藤学長」が顔を覗かせている)。
勝子の嫁ぎ先(麻生家)は、佐藤昌介の母方の実家(鹿討家)がモデルで、結婚相手は札幌農学校卒業生(鹿討豊太郎)だった。
書名:春
著者:島崎藤村
発行:1950/11/30
出版社:新潮文庫