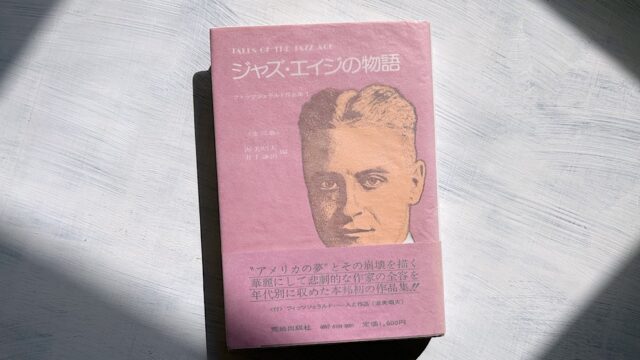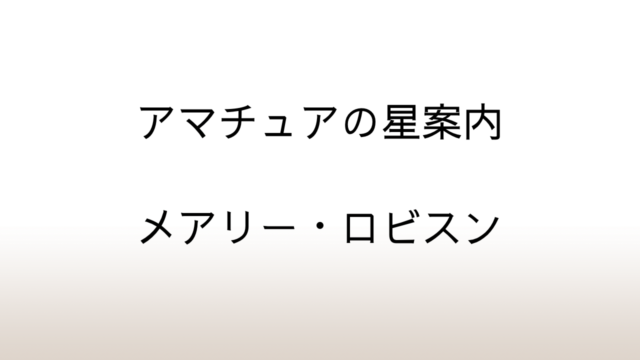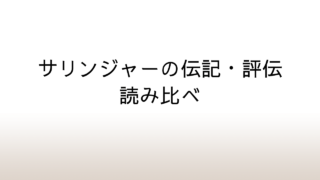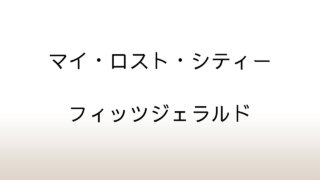橋本福夫「橋本福夫著作集Ⅲ 英米文学論」読了。
本書「橋本福夫著作集Ⅲ 英米文学論」は、1989年(平成元年)に刊行された文芸評論集である。
著者は、1987年(昭和62年)に81歳で逝去している。
戦争の傷痕を描いた戦後小説
橋本福夫は、日本で初めてJ.D.サリンジャーの作品を翻訳紹介した英米文学者である。
その作品は、1952年(昭和27年)にダビッド社から刊行された、サリンジャー初めての長編小説『The Catcher in the Rye』だった。
著者は、作品名の和訳に苦慮した結果、出版社の提案を受けて「危険な年齢」というタイトルとした、としている。
本国アメリカでの出版が1951年(昭和26年)だから、それは、わずか一年後のことだった。
この作品には、映画でやかましく言われたイタリアン・リアリズムに通じるものがあるような気がするし、アメリカの生んだ戦後(アプレゲール)らしい戦後小説だと言えると思う。(橋本福夫『危険な年齢』あとがき)
橋本福夫は、いくつかの文章の中で、『ライ麦畑でつかまえて』を「戦後小説」と表現している。
戦後間もない昭和26年に、この小説を読むということは、現代とは異なる価値観があったのだろう。
彼はまた、「今度戦争が起きたら、自分は原子爆弾を抱いて飛び降りる役に志願する」とも言っている。これらの言葉は戦後の虚無的な、生活の堅実さを見失った、浮草のような生活から生み出された言葉に相違ない。(『時事英語研究』1952)
当時、サリンジャーという作家についての情報は、ほとんど入っていなかったらしい(「主として子供の生活を題材にしてきた作家」として紹介されている)。
ただ、この長編小説を書くのに、サリンジャーが戦前から戦後まで10年の歳月を費やしていることを踏まえて、著者は「戦争の生んだ小説」「戦後小説のひとつ」という表現を使っているのだろう。
短篇小説集『ナイン・ストーリーズ』においても、著者は戦争の傷痕に注目している。
Nine Storiesのうち大半は戦争が若い人達の心に残した傷痕を描いたものである。これらの人達はまた大部分現に頭が狂っているか、狂いかかっている。(『時事英語研究』1954)
ただし、サリンジャーの小説に登場する青年たちは、戦争に痛手を受けているとはいうものの、平和運動に起き上がるような積極性を持ち合わせてはいない。
「このような積極性を持ちえないところに彼等のおちいっている虚無の深さがある」と、著者は指摘している。
東洋思想とシーモアの自殺の謎
別のところでは、著者は『ナイン・ストーリーズ』のエピグラムにも注目している。
『九つの物語』には作者の禅への関心も顔を出している。この短篇集には、「両手の鳴る音は知っている。だが、片手の鳴る音は何か?」─禅の公案─という文句が冒頭にかかげてあり、これらの小説はいわば片手の鳴る小説なのであって、その音の聞きとれる読者でなければわからない難解さがある。(『図書新聞』1962)
この後に続く「主要人物と世間とのあいだには、断絶があり、一方の側の感情だけが音のない音を空間に鳴り響かせているかのようである」というコメントは、『ナイン・ストーリーズ』という作品集をよくとらえているのではないだろうか。
『フラニーとゾーイ』においても、禅や悟りが問題の中心になっていることに着目している。
そこには少年の孤独感があるとともに、ほんのひと突きで精神の均衡が崩れそうな危険も漂っている。それは禅に向う可能性をはらんでいるにしても、流行としての禅にすぎないのではなかろうか。(『図書新聞』1962)
サリンジャーの東洋思想への傾倒について、著者は懐疑的である。
それは、著者にとって「サリンジャーという作家の魅力は、現代の青年男女の純粋でひとりよがりな孤立感を描いているところ」にあったからで、「『フラニーとゾーイ』の傾向は横道にそれている」と感じられたからだ。
もっとも、実際のサリンジャーは、この「横道」こそを我が道として突き進んでいくことになり、その結果、『屋根の梁を高く上げよ、大工たち / シーモア 序章』において、サリンジャーと著者との距離感は、もっと遠いものとなる。
シーモアが自殺した謎(「バナナフィッシュにうってつけの日」)に触れる、これらの作品に、著者はまたしても疑問を投げかけている。
前者(「バナナフィッシュ─」)を書いたころのサリンジャーの頭の中に、シーモア・グラスという人物の明白なイメージが作り上げられていたかどうか疑わしいし、この作品は作中の人物の行動の動機を詮索することを拒否することによって成立っているような小説だからである(作者が愛読しているという日本の俳句のように)。(『時事英語研究』1963)
そういう意味で、著者は「バナナフィッシュ─」については「戦争で神経を傷つけられた帰還兵が社会から孤立した姿を想像に浮べるだけにとどめておいたほうがよさそうである」と、日本の読者に投げかけていると思われる。
それにしても、著者は一貫して「シーモアの自殺の謎を解くゲーム」に参加する意思のないことを強調している。
作中人物の自殺の原因などを、実在の人物に対してのように、詮索していたのでは、きれいに作者の術中におちいることにもなる。なぜなら、小説家は作中人物を現実の人間であるかのように錯覚させるためには、それぞれ独特の魔術を駆使するものだからである。(『時事英語研究』1963)
現に『シーモア─序章』は、「作者が魔術の奥の手をちらとのぞかせている作品」だと、著者は言う。
それを言っちゃあおしまいよ、という感じもするが、文学作品と冷静に向き合う視点を欠いてはならないとの戒めは、確かに、そのとおりかもしれない。
「シーモアの自殺の謎を解くゲーム」は、サリンジャー亡き後、ますます過熱化していくことになるが、謎解きゲームに熱中するばかりでは、文学作品としての鑑賞が疎かになりかねないよ─。
著者のコメントは、そんな未来を予言しているかのように感じられた。
書名:橋本福夫著作集Ⅲ 英米文学論
著者:橋本福夫
発行:1989/04/30
出版社:早川書房