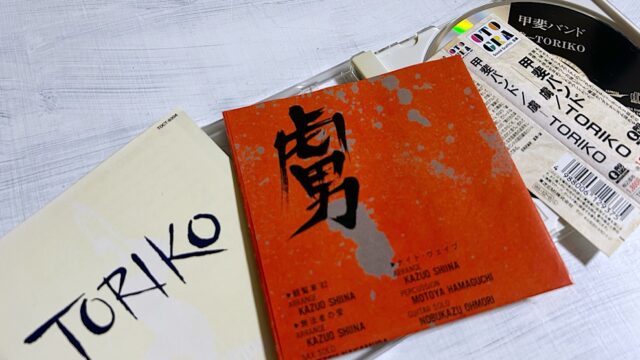ジョゼフ・コンラッド「闇の奥」読了。
本作「闇の奥」は、1899年(明治32年)2月から4月まで『ブラックウッズ・マガジン』に発表された長篇小説(というか中篇小説)である。
この年、著者は42歳だった。
原題は「Heart of Darkness」。
作品集としては、1902年(明治35年)に刊行された『青春、その他二篇の物語』に収録されている。
1979年(昭和54年)、フランシス・フォード・コッポラ監督により、『地獄の黙示録』として映画化された(マーロン・ブランド出演)。
人間の「闇の奥」にあるものを曝け出す
村上春樹『羊をめぐる冒険』に、コンラッドの名前が出てくる。
奥の方の小部屋にだけ、人間の匂いが残っていた。ベッドはきちんとメイクされて、枕はかすかにへこみを残し、青い無地のパジャマが枕もとにたたんであった。サイドテーブルには古い型のスタンドが載っていて、そのわきには本が一冊伏せてあった。コンラッドの小説だった。(村上春樹「羊をめぐる冒険」)
具体的な書名が示されていないにもかかわらず、僕は「コンラッドの小説」というのが『闇の奥』だとばかり思い込んでいた。
大きなプロットという点において『羊をめぐる冒険』と『闇の奥』とは似ていると、僕は感じていたのかもしれない。
二つの小説の共通項は、何かを探し求めて長い旅をする、ということである(『羊をめぐる冒険』では星印のある羊を、『闇の奥』ではクルツを)。
そして、その長い旅は、いずれも都市部から大自然(ウィルダネス)の奥地へと向かっており、旅の過程そのものが、人間の根源的なものを深掘りしようというメタファーとして読み解くことができる。
『羊をめぐる冒険』で、主人公が札幌の街を離れて、旭川を通り過ぎ、やがて十二滝町へと入っていく場面は、読み方によっては、コンラッド『闇の奥』の、アフリカの密林の奥地に向かって川を遡っていく主人公を思い出したとしても、決して不自然ではないだろう。
もちろん、『闇の奥』において旅の目的は、象牙交易で絶大な権力を握りしめたクルツを探し出すことだから、『羊をめぐる冒険』とは設定そのものが異なっている。
しかし、フランシス・フォード・コッポラ監督が、この小説を『地獄の黙示録』というベトナム戦争映画に変換して映画化したように、物語の舞台設定は、もしかすると、さほど重要ではないのかもしれない。
(帝国主義による植民地支配の実体告発という観点からは、もちろん、アフリカの密林であることに意味があるのだけれど)。
この作品のテーマは、人間の中に潜む残虐性の告発だ。
作品名の「闇の奥」は、アフリカにある密林の奥地を意味するものだが、アフリカの密林は、人間の心の奥底にある暗闇を象徴する暗喩でもある。
ひとつの目的を成し遂げるために、人間は、どこまで残虐になることができるのか。
まるで悪魔のようだった。「自分が何をしているかわかってるんですか」と俺が囁くと、彼は「完全に」と、その一語だけを強く答えた。(ジョゼフ・コンラッド「闇の奥」黒原敏行・訳)
恐ろしいのは、こうした残虐性は、あらゆる人間の中に潜んでいるということだ。
(映画『地獄の黙示録』は、この部分が分かりやすく描かれていた)
「彼の闇は見通せない闇だった」という一文があるが、すべての闇は、自分自身には見通すことの難しい闇だ。
すべての人間の中には善と悪とが共存しているから、我々は、相反する二つのものを抱えながら生きていかなければならない。
もちろん、多くの人間は、心の闇の奥底にあるもの(例えば、究極の残虐性)を見ることはできない。
闇の奥にある残虐性は、都市伝説のように神話的な存在であって、普通の生活の中では現出することのないはずのものだからだ。
しかし、極限的な状況の中で、本来は見ることのできなかったはずの「闇の奥」が、心の底から這い出してくることがある。
人間の「闇の奥」にあるものを引っぱりだして、克明に曝け出した作品が、つまり『闇の奥』(あるいは『地獄の黙示録』)ということになるのだろう。
「闇の奥」を見てしまった恐怖
最後の瞬間、クルツは「怖ろしい! 怖ろしい!」という言葉を遺して死んでゆく。
彼はすべてがすっかりわかるというあの死の直前の至高の時、欲望、誘惑、それへの屈服を、細かく憶い出して、自分の人生をもう一度生きたのだろうか。何かの影像、何かの幻覚を見たかのように、二度、囁くような、ほとんど息だけの声で、こう言った──。「怖ろしい! 怖ろしい!」(ジョゼフ・コンラッド「闇の奥」黒原敏行・訳)
「怖ろしい! 怖ろしい!」と二回つぶやく場面は、『闇の奥』では最も有名なもので、かつて中野好夫が訳したときは「地獄だ! 地獄だ!」となっていた。
(映画『地獄の黙示録』でも「地獄だ。地獄だ」とつぶやいている。
原文は “The horror! The horror!” で、個人的には「地獄だ、地獄だ」という訳の方が雰囲気があって良かったと思う。
ただし、物語の意味を理解する上では、「怖いよー、怖いよー」という子どもっぽい言葉の方が感じが伝わるような気がする。
クルツは、本来見てはならない「闇の奥」を見てしまったことに恐怖を覚えているのであり、そこに人生の悔恨がある(「彼が最後に囁いた永遠の断罪」)。
開けてはならないパンドラの箱を開けてしまったと言うべきか。
究極の残虐性を発揮したクルツの中にさえ「恐怖」があったというところに、人間という存在の弱さを感じないではいられない。
身勝手な正論を振り回して我田引水に生きるクルツの姿は、現代社会の象徴としても読める。
彼が「私の象牙」と言うのを君らに聴かせたかったね。ああ、俺は聴いたよ。「私の婚約者、私の象牙、私の出張所、私の河、私の──」何でもかんでも” 私の “なんだ。(ジョゼフ・コンラッド「闇の奥」黒原敏行・訳)
原住民を教化して良質の象牙を集めるという任務は、やがて「獣(けだもの)は皆殺しにせよ!」という指令に脳内変換されて、クルツは、闇の奥をさまようことになる(「象牙がほしいという欲望が(略)物質的でない目標を追求する気持ちを上回ってしまったのだ」)。
「彼には何か欠けているものがあった」「欠けていたものはほんのちょっとしたもの」と主人公(物語の語り手)は述べているが、クルツに欠けていた自制心は、極限状態の中では機能することがなかった。
「たぶん自覚したのは──最後の最後になってからだろう」とあるのは、「怖ろしい! 怖ろしい!」という死に際の言葉へとリンクしていく。
結局のところ、クルツは、闇の奥を見てしまったばかりに、闇に飲み込まれてしまった。
その闇は、ほんのちょっとの自制心で抑制できる程度の闇ではなかったのだ。
おそらく、僕は、僕自身の「闇の奥」を見ることはないだろう(多くの人がそうであるのと同じように)。
ただし、見えようとも見えまいとも「闇の奥」は、誰の中にもしっかりと存在するはずのものだ。
そんな人間理解が、この小説の大きなねらいということなのかもしれない。
書名:闇の奥
著者:ジョゼフ・コンラッド
訳者:黒原敏行
発行:2009/09/20
出版社:光文社古典新訳文庫