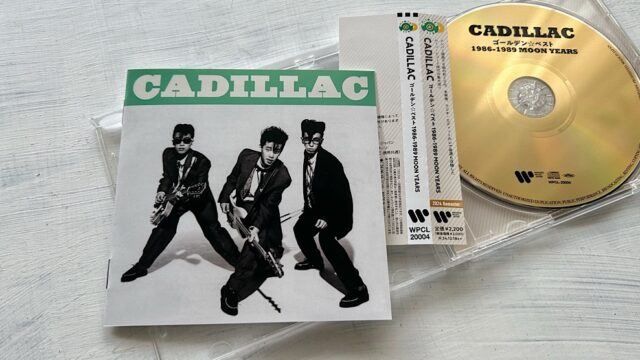志賀直哉「豊年虫」読了。
本作「豊年虫」は、1929年(昭和4年)1月『週刊朝日』に発表された短編小説である。
この年、著者は46歳だった。
作品集としては、1936年(昭和11年)11月に中央公論社から刊行された『万暦赤絵』に収録されている。
庄野潤三が好きだった「豊年虫」
庄野潤三に「豊年虫」という随筆がある(『孫の結婚式』収録)。
志賀直哉の作品でどれがいちばん好きかと訊かれたら、私はためらわずに「豊年虫」と答えるだろう。私はこの短篇を昭和十一年に中央公論社から出た、大きな判の函入りの『萬暦赤絵』の中で読んだ。(庄野潤三「豊年虫」)
庄野さんが、志賀直哉を読むようになったのは、作家として世に立つようになってからで、歳も中年に近づいてからであった。
「志賀直哉が力を入れて書いた作品にはあまり惹かれなかった」「肩に力を入れないで、気楽に一気に書き上げたような小説が好きになった」と、庄野さんは綴っている。
志賀直哉の「豊年虫」は、小説とも随筆とも判別の難しい作品である。
著者である志賀直哉と思しき<私>は、小説を書くために信州戸倉温泉を訪れている。
戸倉で<私>は、小説を書いたり、温泉に入ったり、本を読んだり、散歩をしたりして過ごす。
千曲川の堤を上山田まで歩いていけば、公園敷地の運動場で小学校の教師たちが、ベースボールの試合をしているところを見物したりした。
更級神社では二人の老人が向い合って煙管で煙草をのんでいたり、小学校の門前では三人の女の子がじゃんけんをして遊んでいたりと、<私>はのんびりとした気持ちで、戸倉の町をスケッチしている。
上りの汽車に乗って上田まで出かけたこともある。
<私>は俥で町見物をし、車夫と一緒に蕎麦を食べた後で、停車場まで戻った。
停車場の前にアーク燈があり、それに大きい火取虫が二三間の厚さで渦巻いていた。駅の広い待合室もそれで一杯だった。乗客はそこにいられず、みんな外へ出て避けていた。それは蜉蝣で、縦横十文字に飛び交わす様は風の日の雪と変らなかった。(志賀直哉「豊年虫」)
日が暮れると、街は蜉蝣でいっぱいだった。
戸倉駅から上山田へ向かう乗合自動車の中では、十五六の若い娘が、菊池寛の『真珠夫人』の活動写真の話をしていた。
『真珠夫人』は1920年(大正9年)の流行小説。1927年(昭和2年)には栗島すみ子主演で映画化されている。
自動車が千曲川の長い橋にかかったとき、今まで黙っていた運転手が「えらい豊年虫だぜ。まるで雪のようだ」と言った。
誰もいない暗い夜、此処を先途と夢中に渦巻く虫の群を眺めるのは一種不思議な感じがした。虫は川の真中に近づくほど多かった。そしてその電燈の下には二三寸の厚さにそれが積っていた。自動車の通ったあとを見ると雪と変らぬ轍の跡が残っていた。(志賀直哉「豊年虫」)
翌晩、<私>は宿の座敷で、一匹の蜉蝣を見つける。
蜉蝣はすっかりと死にかけていて、<私>は「なるほど生きているうちからこの虫の身体は腐れて行くのかもしれぬ」などと考えていた──。
賑やかな人間の営みと小さな蜉蝣の死
のんびりとした信州スケッチだった物語が、上田の町で日が暮れた後からは、蜉蝣(豊年虫)が主役になっていく。
豊年虫の溢れる街並みは、まるで異界のようで、神秘的な霊界をさえ思わせる謎めいた雰囲気がある。
この物語の大きなテーマは、もちろん、前半ののんびりとしたスケッチと、後半に登場する豊年虫の精緻な描写との対比にある。
人々が生き生きと活動する前半部に比べて、蜉蝣が死にかけている最終場面は、あまりにも切ない。
それは、人間の営みのはかなさをも感じさせる展開だ。
著者の志賀直哉が戸倉温泉に滞在したのは、1927年(昭和2年)のことで、旅行中に芥川龍之介の訃報を受け取ったという。
芥川龍之介が自殺したのは、1927年(昭和2年)7月。享年35歳だった。
賑やかな人間の営みと小さな蜉蝣の死とを対比させて描くことで、著者は何を伝えたかったのだろうか。
派手なストーリー展開はないが、何気ない物語の中に人生の光と影とが描かれている。
庄野潤三が、この小説が一番好きだと言った理由が分かるような気がした。
作品名:豊年虫
著者:志賀直哉
書名:ふるさと文学館(第二十四巻)【長野】
発行:1993/10/15
出版社:ぎょうせい