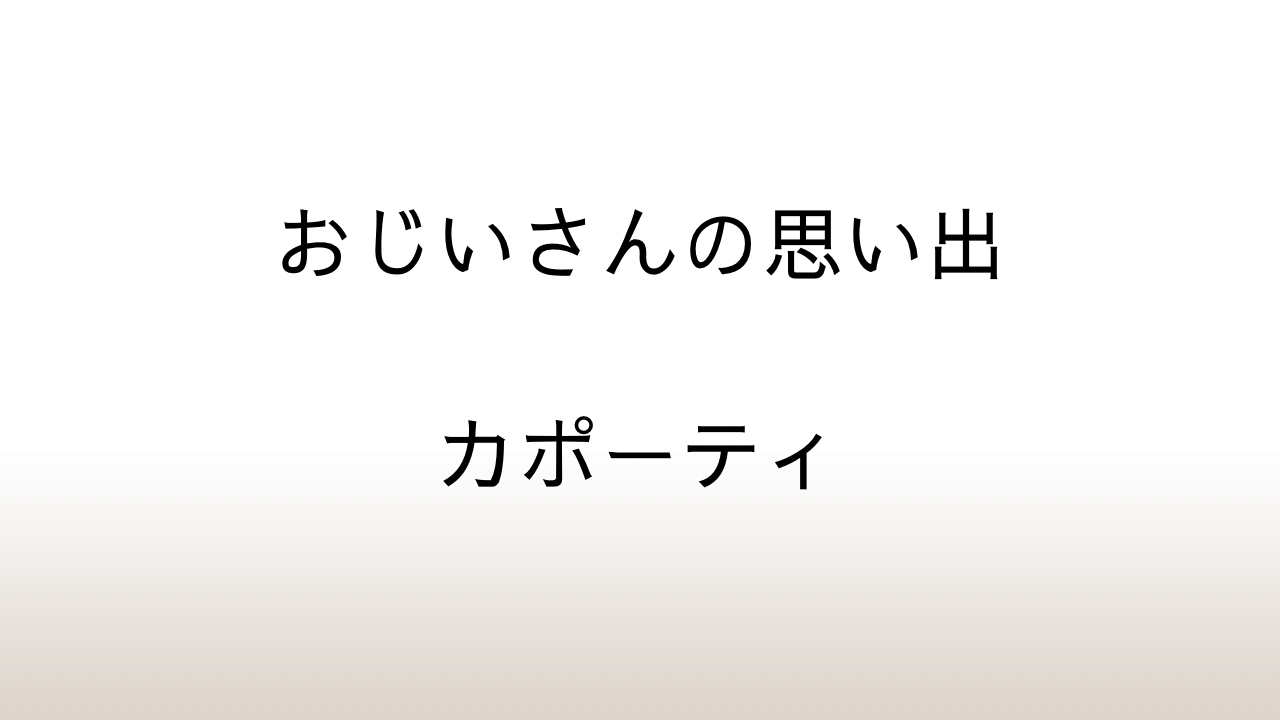トルーマン・カポーティ「おじいさんの思い出」読了。
本作「おじいさんの思い出」は、トルーマン・カポーティの死後に発見され、1986年(昭和61年)に発表された短篇小説である(カポーティは1984年に59歳で死亡)。
原題は「I Remember Grandpa」。
この作品を執筆したとき、著者は22歳だった。
日本では、1988年(昭和63年)、村上春樹の翻訳により『Switch』に発表された。
人生で初めて知った「家族との別れ」
雑誌『Switch』1988年2月号(Vol.6)には、トルーマン・カポーティの特集が掲載されている。
その中のメイン作品が、村上春樹翻訳による「おじいさんの思い出」の本邦初公開だった。
このとき、原タイトルは「I Remember my Grandpa」として紹介されている。
本作「おじいさんの思い出」は、幼い頃に負った心の傷について描かれた少年物語である。
そのとき、少年は人生で初めて「家族との別れ」というものの辛さを知った。
故郷の実家で祖父母と一緒に暮らしてきた少年一家は、少年が学校へ上がるのを機に、実家を離れることになったのだ。
「なあ、坊や」とおじいさんは話を始めた。「この五年というもの、お前の父さんは一人で土地を耕してきた。代々七〇年だか八〇年だが、家はそうやってきたんだよ、ずっと。そのあとはお前に継いで欲しいと思ってたんだがね。今他所者が入って来ようとしているし、この先どうなるかわかったもんじゃない。わしには見当もつかんのだよ、坊や。お前の父さんというのはまったく頑固な男だ。突然わしらを残して行っちまうなんてな。いけないことだよ。ひどいじゃないか」(トルーマン・カポーティ「おじいさんの思い出」訳・村上春樹)
そこは、ウエスト・ヴァージニア州アレゲーニー山脈の麓にある小さな村で、おじいさんは、たまに出かける街の向こう側に、どんな世界があるのかということさえ、まったく知らなかった。
少年にとっても、おじいさんにとっても、そこはそこだけで完結された、自分たちだけの独立した世界だったのだ。
しかし、少年の父さんは、そんな閉鎖的な世界で小作農として生きる人生に満足していない。
「俺はこれまでずっとなんだかよくわからんものに縛りつけられて生きてきた。そして相も変わらん貧乏暮しだ。今、ボビーがそれと同じ道を辿ろうとしている。いいか、俺の目が黒くて働けるうちは、あの子に俺の人生よりましな人生を与えるために何でもしてやる。あの子がどうなるかその結果を見届けることはできんかもしれんが、まともなスタートを切らせてやることはできる」(トルーマン・カポーティ「おじいさんの思い出」訳・村上春樹)
自分たちを置き去りにして出ていくという一家の計画を聞いて、おじいさんもおばあさんも大きなショックを受ける。
そして、もちろん少年自身も。
この物語は、五歳にして初めて大好きな家族との別れを経験した少年による、回想の物語である。
家族を愛することの大切さ
この小説を読んでいると、確かに自分にも少年時代に、そんな経験があったと思えるような気がしてくるから不思議だ。
大切な家族との別れというのは、あるいは多くの大人たちにとって、原体験みたいなものなのかもしれない(その別れが、どのような形のものであれ)。
そして、少年時代、あれほど泣いたおじいさんとの別れさえも、成長とともに少年の中では遠い記憶となっていく。
高校生になった少年が、久しぶりにおじいさんのことを思い出したのは、「おじいさんが死んだ」という故郷からの手紙を、彼が受け取ったからである。
やがて、おじいさんの遺品だという写真の入った額が、少年のもとに送られてくる。
荷物の箱は翌日着いた。とても脆くて壊れやすそうなものに見えたので、僕は丁寧にその箱を開けた。中に入っていたのは、長い間おじいさんの寝室のたんすの上に置かれていた写真の入った大きな額だった。(トルーマン・カポーティ「おじいさんの思い出」訳・村上春樹)
子どもたちと別れた後、すぐに(なんと翌日に)おばあさんは死んでしまい、一人残されたおじいさんにとって、かつて家族と過ごした時間は、何よりの宝物だったのだろう。
額の中には、家族みんなの写真が飾られていたが、どうしてか、少年の写真だけが、そこからは外されていた。
おじいさんと過ごした日々を思い出して泣きながら、少年はこんなことを考える。
「これは遺産なのだ。これは僕の過去なのだ。これは僕の人生の一部なのだ」(トルーマン・カポーティ「おじいさんの思い出」訳・村上春樹)
かつて、おじいさんが教えてくれた、おじいさんの秘密。
それは、「父さんと母さんを愛するんだよ」ということであり、「毎週日曜日には父さんと母さんと一緒に教会へ行きなさい。大きくなったらお前が二人を教会に連れていってあげなさい」ということだった。
家族を愛することの大切さこそが、おじいさんの人生にとっての、何よりの秘密だったのだろう。
街の向こう側にある世界さえ知らないおじいさんだったけれど、家族を愛することの大切さは、誰よりも深く知っていた。
額の中に、少年の写真だけが飾られていなかったのは、おじいさんが誰よりも少年を愛していたことの表れだ。
おそらく、おじいさんは、少年の写真を肌身離さず持ち歩いていたに違いない。
おじいさんにとって少年と過ごした日々は、自分が亡くなる瞬間まで、生涯で最も大切な思い出の時間だったから。
少年は、おじいさんの言葉を大切にして、未来を生きていこうと誓う。
目に見えないものの大切さを、久しぶりに、この物語は思い出させてくれた。
作品名:おじいさんの思い出
著者:トルーマン・カポーティ
訳者:村上春樹
書名:Switch 1988/02(Vol.6 No.1)
出版社:扶桑社