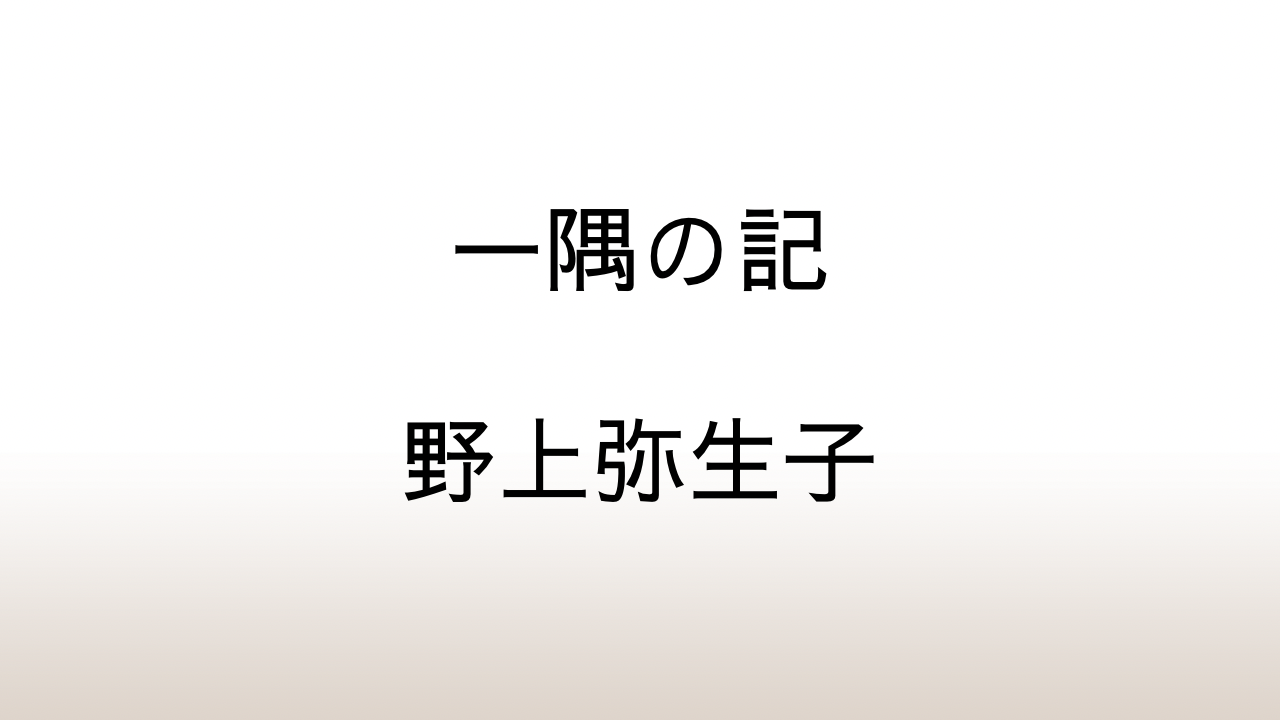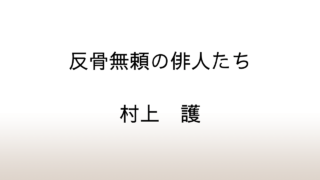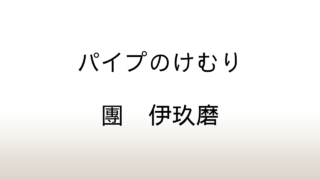野上弥生子「一隅の記」読了。
本書は、1968年(昭和43年)に刊行された随筆集である。
この年、著者は83歳だった。
病院の個室に生まれた書斎の一隅
本書の眼目は、タイトルにもなっている「一隅の記」である。
人間ドックで経験した三か月の入院生活を綴ったエッセイだが、東大病院を自由に抜け出して、近隣散歩を楽しんだりしている。
入院日記と言いながらも話題は豊富で、思いつくことを思いつくままに綴っていたらしい。
例えば、第二次大戦が始まったとき、著者はフランスのパリに滞在していた。
地元市民に交じってボルドーへ避難したときの回想などは、まるで古い映画を観るようでもある。
ボルドーの街では、戦地へ出兵する男たちを見送った。
駅で召集されて行く男たちに出逢うのはほとんど毎日であった。肉親らしいほんの数人に見送られ、ひとりひとりをかき抱いて別れを惜しみ、しおしお汽車の中へ消える。日本の出征風景のばんざい、ばんざいで表面勇ましげで、かえって底にうつろな淋しさを漂わせるより正直で、真情にあふれ、見るものの心を打った。(野上弥生子「一隅の記」)
百貨店の売り子の中でも、とりわけ器量よしの娘が赤く泣きはらした眼で、高い陳列棚のかげに隠れて、なおもしゃくりあげているのを見ると、多分そうやって若い夫か恋人を送り出した一人なのだろうと考えたりした。
女性作家だけあって、兵士を送り出した女性への強い共感が感じられる。
百貨店から駅へ出る路上での葡萄売りの女は、灰青いくるっとした眼の可愛い顔立ちながら、ぼうぼう髪にまるで腕まくりしているような短袖のよれよれワンピースで、旬の葡萄を売りさばいている。
「亭主が同じく出征したにしろ泣いている暇はないのだ」という言葉に、女性の生命力と戦争への強い憎悪が感じられた。
「一隅の記」の中で、フランスの思い出話はごく一部にすぎないが、この中篇エッセイの中で、最も心に残った場面である。
どこの国でも、市民は戦争に翻弄されていたのだ。
ちなみに、タイトルにある「一隅」とは、三か月の入院生活で、すっかりと自分の書斎のようになってしまった、病院の個室の一隅を指している。
「茶三昧」であり「お菓子三昧」だった朝飯自慢
本書には「一隅の記」の他にも、夏目漱石に関する回想記などが収録されているが、その中でも、小品と言える「私の茶三昧」が特に面白かった。
「私の茶三昧」は、著者と抹茶との付き合いを綴った作品である。
野上弥栄子は、朝食に重い米飯を好まず、抹茶を朝食としていた。
朝起きて冷たい牛乳を飲み、「書斎にはいって書くか、読むかして」、一時間から二時間経って頭の疲れてきたときが「お抹茶の朝食」である。
私は隅の小卓に盆にのせていつでも用意してある茶道具を机の上に移し、ほどよく暖めた茶碗でおもいきり大服にたてた茶をかならず二杯飲む。またいっしょにお菓子をたくさん食べるが、それにはちょっと贅沢をする。空也のものは絶やされない。重過ぎるようかんよりカステラで、それも店がきまっており、最後にうす焼きの塩せんべいをかりかり噛んでさっぱりした味を愉しむ。(野上弥栄子「私の茶三昧」)
「空也」といえば、<空也もなか>で有名な銀座の和菓子店のことだろう。
カステラのブランドが明示されていないのは、ちょっと残念だが、朝から抹茶とお菓子というのは、なかなかオシャレな食習慣である。
しかも、朝のうちにお菓子をたくさん食べるので「私はもう久しいあいだ間食というものを欲しいとおもったことがない」とまで書いてある。
本書に限らないが、朝ごはんに関するエッセイというのは、読んでいて楽しいものである。
「茶三昧」であり「お菓子三昧」であった野上弥栄子の朝食を、ちょっとうらやましく思った。
自分は影響を受けやすい人間なので注意しなければ(笑)
書名:随筆 一隅の記
著者:野上弥栄子
発行:1968/8/30
出版社:新潮社