山口瞳「行きつけの店」読了。
本書「行きつけの店」は、1993年(平成5年)に刊行されたエッセイ集である。
そこで生きて働く人々を描いたエッセイ集
「銀座鉢巻岡田の鮟鱇鍋を食べないと冬が来ない」
「鉢巻岡田の鰹の中落ちを食べないと夏が来ない」
「鉢巻岡田の土瓶蒸しを食べないと、私の秋にならない」
「九段下寿司政のシンコを食べないと、私の夏が終らない」
本書『行きつけの店』は、そんな山口瞳流の生き方を知ることができる、人生の教科書だ。
登場する店は、「鉢巻岡田(銀座)」や「寿司政(九段下)」のほか、「ホテル・ニューグランド(横浜)」「八十八(横浜)」「つる幸(金沢)」「皆美館(松江)」「千里十里庵(倉敷)」「亀の井別荘(湯布院)」「とら寿司(長崎)」「冨茂登(函館)」「海陽亭(小樽)」などなど全国に及ぶ。
その後、私は松江にかぎらず、山陰地方へ行けば、少し無理をしてでも皆美館へ寄るようになった。そうして必ず神魂神社へ参拝する。昼食は皆美館の近くの蕎麦の古曽志と決めている。こういうのを、すなわち「行きつけの店」と言うのだと私は思っている。(山口瞳「行きつけの店」)
そんな感じだから、行きつけの店は全国にある。
そして、当地に滞在中は、それが何泊であっても、昼食・夕食ともに、必ず「行きつけの店」で食べる。
その生き方が徹底している。
横浜山下町のホテル・ニューグランドに滞在したときは、「八十八(鰻)」で食事をして、関内の「倫敦(酒場)」で飲むというのを一週間続けたという。
そのくせ、著者は特別に鰻を好きだというわけでない。
むしろ、脂に弱くて、鰻は苦手な方になるというから驚く。
私にとって大事なのは、それが料亭であるとすると、そこの料理が美味い不味いよりも、店の雰囲気や従業員の気ばたらきのほうである。それと縁というものを大切にしたいと思っている。そうして従業員の気ばたらきのいい店の料理は、これはもう間違いなく美味なのである。(山口瞳「行きつけの店」)
だから、おかしなグルメ・エッセイのように、素材がどうの調理技術がこうのといった、小うるさい能書きは登場しない。
「行きつけの店」というのは、そこで生きて働く人々を描いたエッセイ集なのだ。
酒場で出会う人々との交流が短篇小説のように描かれる
「行きつけの店」では、きっと様々なドラマを体験しているに違いない。
「鉢巻岡田(銀座)」の鮟鱇鍋で飲んでいるとき、随筆家の戸板康二が現れて、奥の小間へと入っていった。
大きな病気をした後のことだったので、著者の山口瞳は、戸板先生の近況を伺うような俳句を書いて、メモ用紙を女中に届けさせた。
戸板先生からも返信が来て、というようなやり取りを三度ばかりやった。
それだけで、もう、私の胸は一杯になっていた。よくぞ、まあ、御無事でという思いがあった。やがて、戸板先生から、最後の俳句が返ってきた。寒燈や生きて今年の誕生日──私は目の前の鮟鱇鍋が見えなくなった。(山口瞳「行きつけの店」)
酒場で出会う人々との交流が、まるで短篇小説のように描かれている。
こんな人情噺ならいくらでもある。
山口文学の源流が、こうした「行きつけの店」にあるということが理解できる、そんなエピソードが、いくつも出てくるのだ。
カッコいい大人になりたいと思うなら、こういうエッセイを読まなければならない。
最後に、管理人の好きな場面をひとつ。
並木の薮へ行くと、それが冬時分であったら、まず、鴨なんばんのソバ抜きを注文する。これを鴨ヌキという。春とか秋とかには、天ぷらそばのソバ抜き、つまり天ヌキを頼む。黙っていても酒が出てくる。「蕎麦屋の酒が一番うまい」のだから仕方ない。並木の薮は菊正宗の樽酒だ。ツキダシは固く練ったミソ。鴨ヌキで飲む酒がいい。スープで酒を飲むのもっともうまいし、体にもいいと私は信じている。ちょっと酔ったなというあたりで、もりそばを注文する。一枚か二枚。二枚という時が多い。(山口瞳「行きつけの店」)
人生を謳歌するって、きっと、こういうことなんだろうな。
書名:行きつけの店
著者:山口瞳
発行:2000/1/1
出版社:新潮文庫
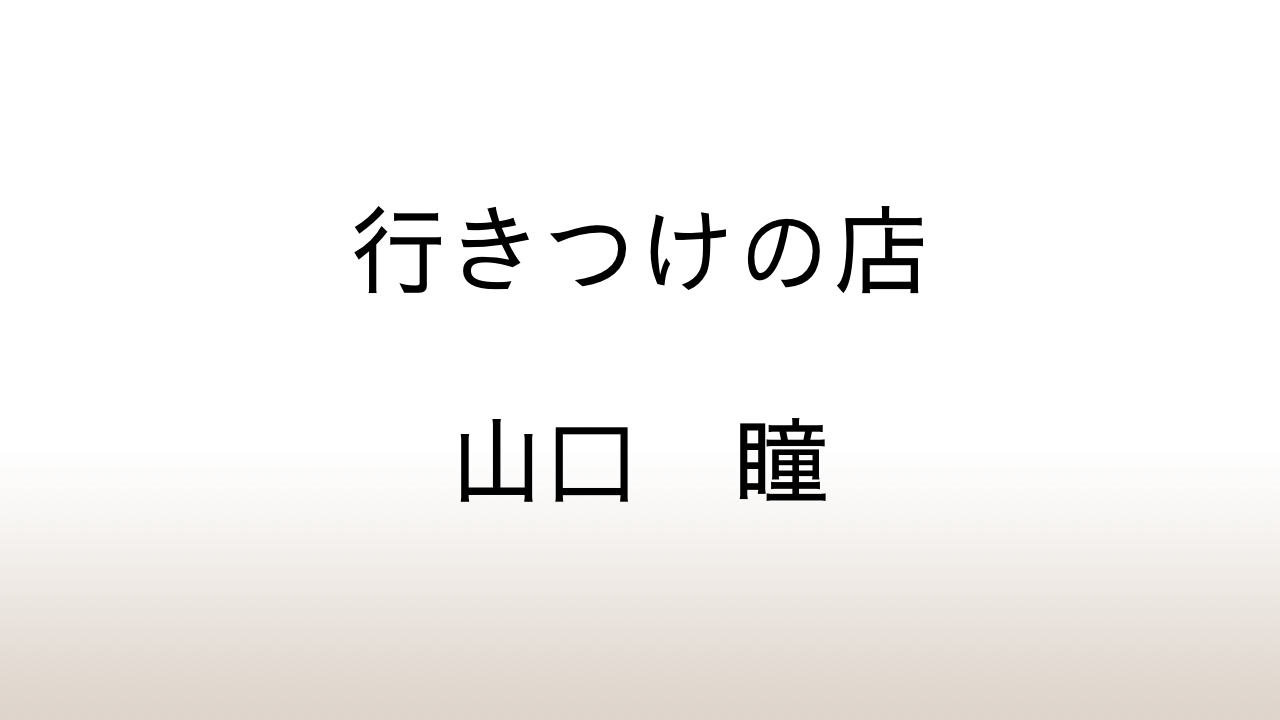



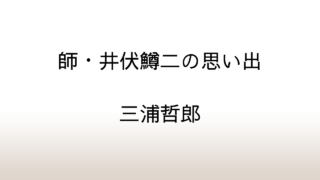
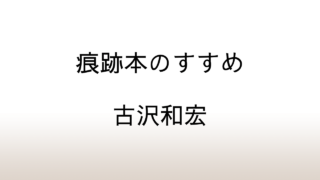
-150x150.jpg)









