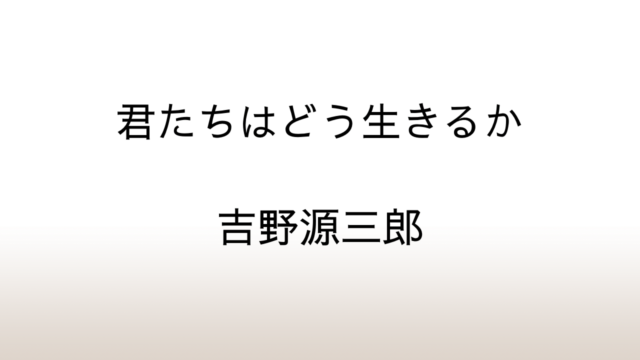庄野潤三「インド綿の服」読了。
本作「インド綿の服」は、1988年(昭和63年)2月に講談社から刊行された短篇小説集である。
この年、著者は67歳だった。
初出は、1981年(昭和56年)~1987年(昭和62年)『群像』。
長女の手紙を素材とした短篇小説「足柄山シリーズ」
最初に整理をしておく。
1965年(昭和40年)に『夕べの雲』で、生田の山の上で暮らす五人家族の物語を書いた庄野潤三は、1972年(昭和47年)の『明夫と良二』まで、五人家族をモチーフとした作品を発表し続ける。
『明夫と良二』で、長女が結婚して家を出てしまった後は、近所に暮らす長女を登場させながら、『野鴨』(1973)、『おもちゃ屋』(1974)、『鍛冶屋の馬』(1976)といった作品を発表。
ところが、1980年(昭和55年)3月、長女一家が南足柄市へ引っ越してしまったため、これまでのように長女を作品の中に登場させることが難しくなった。
一方で、1970年代の後半から、庄野文学のモチーフは、『引潮』『水の都』『シェリー酒と楓の葉』『ガンボアの春』『早春』など、五人家族を離れたものが中心となっていく。
そんな中、1981年(昭和56年)10月『群像』に発表された作品が、「インド綿の服」という短篇小説である。
去年の三月に南足柄市に引越した長女の一家は、天気のいい日には遠くに相模湾が見える山の、雑木林の中の家で二度目の夏を迎えて息災に暮しているが、先日、長女から八月六日に行われた市の水泳大会の二十五メートルに小学四年生の上の男の子が出場したと知らせて来た。(庄野潤三「インド綿の服」)
いつもは「足柄山からこんにちは」で始まる手紙を送ることの多かった長女は、このとき、「暑中お祝い申し上げます(我ら亜熱帯民族の言葉)」という謎の書き出しの手紙を送ってきた。
あるいは、この長女の手紙が、新しいシリーズのヒントを与えたのかもしれない。
去年の夏(1980年の夏)は、夏好きの庄野一族にとって、甚だ意気消沈させる夏だった。
なにしろ、庄野一族の人々には、夏の日差しが強ければ強いほど喜ぶという性質があり、海の水につかる時、何とも言えずに心が安らぐという傾向を持っている。
「いまでは私は海水浴場の浜べに群がる人の中で自分よりも年長の人を見つけるのが難しくなりつつある」と、主人公(庄野さんだろう)は綴っている(ちなみに、この作品が発表された1981年、庄野さんは60歳だった)。
長女からインド綿の服が届いたのは、そんな1980年の涼しい夏が終わった、九月も二週間が経ってからのことだった。
ハ月半ば過ぎの妻の誕生日までに、贈り物の洋服を仕上げるつもりだった夏は、金時が産湯をつかったという夕日の滝まで「朝飯前のドライブ」で行って来られる山に家を新築したおかげで、多くの来客を迎える。
もとの家のお隣の「たか子ちゃん一家」も登場して、民宿「あしがら」は大盛況だったため、洋裁の作業は大幅に遅れてしまった。
今年(1981年)の夏は一転して夏らしい夏となり、長女の「暑中お祝い申し上げます(我ら亜熱帯民族の言葉)」という挨拶から始まる手紙へと繋がっていくのである。
それにしても、「ニワトリはこの頃、ソトトリと呼びたいほど、遠くまで遊びに行ってしまいます」とか、長女の手紙はかなり独創的で楽しい。
そんな手紙があったからこそ、足柄山から届く手紙を素材とした短篇小説はシリーズ化されて、1987年(昭和62年)まで毎年一篇の割合で発表され続けたのだろう。
1981年10月『群像』インド綿の服
1983年 1月『文藝』大きな古時計
1984年 1月『群像』楽しき農婦
1984年11月『群像』雪のなかのゆりね
1985年11月『群像』誕生日の祝い
1987年10月『群像』足柄山の春
1981年(昭和56年)の「インド綿の服」から1987年(昭和62年)の「足柄山の春」まで足掛け6年、何とも息の長いシリーズとなった。
長女の手紙を素材とした短篇小説「足柄山シリーズ」は「足柄山の春」で終了となるが、1988年に闘病記『世をへだてて』を発表した庄野さんは、その後、『エイヴォン記』(1989年)から続く一連の家族物語を書き始める。
つまり、1970年代後半から途絶えていた五人家族の長篇小説が、1980年代の後半から、子どもたちの家族までを含めた大きな家族物語として復活するのだ。
連作短編小説とも言える「足柄山シリーズ」は、庄野一族の1980年代を繋ぐ家族物語だったと言えるだろう。
些細な日常生活の中にある文学
長女が引っ越した後、妻と長男(たっさん)の嫁(あっちゃん)の三人は、三月に一度くらい顔を合わせて昼食を食べる「ウーマンズ・ミーティング」を始めた。
最初のミーティングは、小田原にある「長女が高校二年の時に家族全部で夕食を食べに行ったことのあるお濠の近くの古い鰻屋」で行われたとあるが、この古い鰻屋「柏又」は、その後も登場する。
一族全員で行こうねと話したという古い鰻屋は私たちがいまの長女の一家と丁度同じように多摩丘陵のひとつに家を建てて越して来た年から数えて三年目、空気の澄んだ秋晴れの祭日にみんなで小田原へ出かけた折に食事をした思い出のある店だ。(庄野潤三「楽しき農婦」)
長女の手紙によると、この日、庄野親子は、トマトサラダと鰻の蒲焼きを食べたらしい。
昨年の夏、小田原にある庄野さんのお墓参りへ出かけたときは、思っていた以上に時間がかかって、予定していた「柏又」での食事が叶わなかった。
今年はぜひ、柏又の蒲焼きとトマトサラダを食べてみたい。
長男の転職の話題も気になる。
「わが弟がヒルトンマンとして一生頑張ってやって行ってくれることになり、これで万々歳です。九月、目も眩い建物が完成の暁には、また皆で出かけて行って、大いに賑やかにお祝いしたいですね」これには八年間、赤坂にあるホテルに勤務していた長男が、いったん解散して新宿副都心の三十八階の建物で営業を始める新会社の方へ移るについて、当人の気持が定まるまでに多少の時間を必要とした事情から説明しなくてはいけないが、省略させて頂く。(庄野潤三「雪の中のゆりね」)
1963年(昭和38年)に日本初の外資系ホテルとしてオープンした「東京ヒルトンホテル」は、当初の契約に従い、1984年(昭和59年)から「キャピトル東急ホテル」へと営業譲渡される一方で、ヒルトンホテルは、1984年(昭和59年)、西新宿に「東京ヒルトン インターナショナル」を開業する。
運営者の分裂に伴って、従業員は、「東京ヒルトン インターナショナル」へ転籍する者と「キャピトル東急」に残留する者とに分かれたというから、庄野さんの長男(たっさん)も、このとき難しい選択を迫られたのだろう。
夏子なのに10月生まれの長女の誕生日に、本を贈る習慣になっているのは、長女が結婚した年の秋に「クリスマス・キャロル」を贈ったのが始まりだった。
長女が中学の頃には『ウェークフィールドの牧師』や『トム・ブラウンの学校生活』など、あまり女の子が興味を示さないような本を読ませたことがある。だが、年とともに、悲しいかな、「良書推薦」も種切れになりつつある。(庄野潤三「楽しき農婦」)
この年(1983年10月)は、「上下二冊の文庫本のイギリス十九世紀の女流作家の小説」を贈ったらしいが、作品名は記されていない。
ただし、長女の手紙に「これは昔、うちにあった世界文学全集に入っていて、挿絵の中に暗い廊下の向うから気の狂った女の人がじろりと覗いているのがあって、そこで背筋がぞっとしたけれど、面白くて最後まで引きずり込まれて読んだのを思い出しました」とある。
この少年少女向けの世界文学全集は、長女が「大家さんの家作」にいる時分にそっくり譲り渡して、現在は足柄山の子どもたちの部屋にある。
庄野さんの著作が出てくるのは「雪のなかのゆりね」で、1984年(昭和59年)2月に文芸春秋から刊行された『陽気なクラウン・オフィス・ロウ』の話が紹介されている。
「毎晩、ラムを読んでいます。ストランドの宿でお父さんのしゃっくりが止まらなくなったり、お母さんが毎日、エムバンクメントの屋台のおじいさんの店へ果物を買いに行ったり(勇気ある行動、すごい!)、身近な日常の話が出て来て、とても楽しいです。そして初めて知ったラム姉弟の生涯に感動しています」(庄野潤三「雪のなかのゆりね」)
『陽気なクラウン・オフィス・ロウ』は、「四年前の五月(長女の一家が南足柄市へ引越して行ったその二月あとである)、妻と二人ではじめてロンドンを訪問した折の十日間の日記と、テムズに面した法学院テムプルで生れ育ったチャールズ・ラムと姉メアリイの生涯を重ね合せるかたちで書いた、紀行とも評伝ともつかないもの」とある。
「細々としたことが出て来るから、読むのも楽ではなかった筈だ。申し訳ない気がする」とあるのも楽しい。
短篇小説としては、長女の妊娠と、留学生の受け入れが中心となる「誕生日の祝い」がいい。
昼食が始まるまでに私は著書の一冊に署名をして贈った。英訳された作品ならともかく、貰っても読めない本を上げても仕方ないが、長女の話では閑があれば本を読むか、家族に手紙を書いているジャッキーは私の本を持って帰りたいらしく、どこの本屋へ行けばお父さんの本が買えるかと訊く。長女が、父の本は少ししか出版されないので、普通、本屋では見つからないのと話したところ、がっかりしていたという。(庄野潤三「誕生日の祝い」)
ニュージャージーからやってきた17歳の女子高生ジャクリーン・パスカスは、庄野さんの小説としては、かなり異質な登場人物だろう。
ジャッキーがアメリカへ帰る日、空港で「さようなら」を言ったときに、長女もジャッキーも涙を流したという場面では、思わず貰い泣きしそうになった。
庄野さんの小説では、時々そういう不思議なことが起きる。
些細な日常生活の中にも文学がある、ということなのではないだろうか。
「夫婦の晩年シリーズ」の萌芽
最後の「足柄山の春」は、長篇闘病記『世をへだてて』の姉妹編みたいな作品で、足柄山の飼い猫タマの死と、一命を取り留めた庄野さんの回復とが、対照的に綴られている。
特筆すべきこととしては、未婚だった次男(カズヤどん)が、1986年(昭和61年)10月に「みさをちゃん」と結婚したことだろう。
長女の家のすぐ下に染織工芸家の宗近拓三さんのお宅があり、全国各地から染織の勉強に来た研究生の若い娘さんが何人かいる。その中の一人で栃木県から来ていた娘さんが仕事の合間にときどき長女のところへ遊びに来ていた。のんびりした、大らかな気質の娘さんで、この人ならカズヤどん(と長女は下の弟のことを呼んでいる)と合いそうだと考えた長女が、研究生のみんなで写した写真を借りて、生田へ送って来た。(庄野潤三「足柄山の春」)
翌1987年(つまり今年だ)7月に赤ん坊が生まれることになっていて、保健所の検診日と重なった「みさをちゃん」は「ウーマンズ・ミーティング」を欠席する。
この「七月に生まれることになっている赤ん坊」というのが、晩年の庄野文学でヒロイン役を務めることになる初めての孫娘「文子(フーちゃん)」だった。
だから、晩年の長いシリーズ作品の萌芽は、この短篇小説にあったということができるのかもしれない。
短篇小説集『インド綿の服』は、後の「夫婦の晩年シリーズ」を知らなくても、本作だけで楽しめる内容となっているし、「夫婦の晩年シリーズ」を好きな人だったら、ぜひ読んでおくべき作品集ということになる。
何より明るくて楽しい家族の物語がいい。
小説の中でまで、嫌なことを蒸し返さなくてもいいだろうという、作者の人生観に激しく共感したい。
書名:インド綿の服
著者:庄野潤三
発行:2002/04/10
出版社:講談社文芸文庫