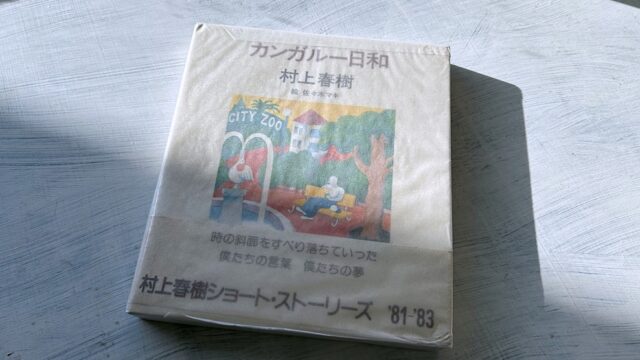竹野雅人『純愛映画・山田さん日記』は、1989年(平成元年)1月に福武書店から刊行された短篇小説集である。
この年、著者は23歳だった。
竹野雅人最初の作品集で、収録作品及び初出は次のとおり。
「純愛映画」
1988年(昭和63年)11月『海燕』
「山田さん日記」
1988年(昭和63年)2月『海燕』
「正方形の食卓」
1986年(昭和61年)11月『海燕』
1986年(昭和61年)、第五回海燕新人文学賞受賞作
純愛映画 │ 本当の自分とは何か?
1988年(昭和63年)11月『海燕』初出。
高校の映画研究会に所属する男女の恋愛ストーリー。
主人公(本多由喜男)は、元カノ(加来美也子)への未練を断ち切れないでいる。
ところが、八ミリの自主映画撮影班・浦野監督の指示で、二人は、元・恋人同士という役で共演することになった。
しかも、主人公は、元カノへの思いを断ち切ることができないでいる男の子の役である。
実生活では、美也子と普通の友だち関係を築こうと努力している主人公だけに、撮影の中で、うまく演技をこなすことができない。
彼女と映画の撮影を通して再会してから、由喜男はずっと無理をしていた。映画という演技の上で成り立っている世界と、現実とがごちゃごちゃになり混乱し続けたままだった。彼女と別れてから半年、ずっと自分は演技をしていた、ということを、映画の中での演技を通して、じわじわと意識し始めていた。(竹野雅人「純愛映画」)
演技の中の自分が本当で、現実の中の自分が虚構(演技)であることに、主人公は、映画の撮影を通じて気づく。
この作品のポイントは、映画の撮影を通じて、主人公がメタ認知を得る過程が描かれている、ということだ。
単行本の帯には「無重力世代の表現を予兆する 22歳の新鋭の優しいメタ・ノベル」とある。
映画の撮影は、箱庭療法によるカウンセリングみたいなもので、演技を通じて、主人公が自分を取り戻していく過程は興味深い。
八ミリの自主映画というのも、学生らしくていい。
「ビデオ全盛期のこの時代に、こうしてあと数年でしぼんで消えていってしまうという八ミリ映画に固執してシコシコ撮り続けていることに時間を費やす俺たちってのは、時代やら何やらから全く取り残されてしまっている、存在なんだろうなあ」(竹野雅人「純愛映画」)
細野不二彦『あどりぶシネ倶楽部』(1986)にでも出てきそうなセリフだ。
とりわけ、元カノとの復縁を描いた作品としては、吉田拓郎「たえこ MY LOVE」にインスパイアされたと思われる「舞子・MY・LOVE」とイメージが重なるかもしれない。
もっとも、本作「純愛」は、やはりバブル全盛期の作品であって、登場人物たちは、浜田省吾や松任谷由実、渡辺美里などのJ.POPに親しんでいる。
由喜男は加来美也子と別れたあと、雄一から『悲しい本多くんに捧げるバラード全集』というテープを貰った。別れの曲ばかり集めて雄一自身が編集した特別テープだった。それは、清水健太郎の『失恋レストラン』ではじまり浜田省吾の『悲しみの岸辺』を経て松任谷由実の『Destiny』で締めくくられていた。(竹野雅人「純愛映画」)
1988年(昭和63年)に清水健太郎もないだろうが、浜田省吾「悲しみの岸辺」は、1986年(昭和61年)発売の2枚組アルバム『J.Boy』収録曲だから、まあ、リアルタイムと言っていい(♪愛が片翼の旅なら~)。
ちなみに、ユーミン「Destiny」は、1979年(昭和54年)発売『悲しいほどお天気』収録曲だから、厳密に言うと70年代だが、1984年(昭和59年)に富士フイルム「ビデオテープスーパーHG」のCMソングとして起用されたほか、1988年(昭和63年)には、片岡鶴太郎主演テレビドラマ『季節のなかの海岸物語』の主題歌にも使われているくらいだから、当時の高校生にもお馴染みだったのだろう(♪安いサンダルをはいてた~)。
本当の自分とは何か?ということを考えさせてくれる作品。
夏を実感できないでいる主人公が、元カノへの愛を確かめたとき夏を実感できるというエンディングもいい。
爽やかな青春ラブストーリーとして楽しみたい。
山田さん日記 │ 日常からの脱出願望
1988年(昭和63年)2月『海燕』初出。
この作品のポイントは、主人公の現実生活と、『山田さん日記』なるロールプレイングゲームの主人公とが、完全にシンクロしているということだろう。
いわゆる「メタ小説」だが、ファミコンのキャラクターに、主人公像を投影するという設定は、いかにも80年代後半的だ。
本間洋平『家族ゲーム』(1981)で将棋の駒だった「ゲーム」が、「山田さん日記」ではファミリーコンピューターになっている。
史上初! あなたの日常をシミュレートする画期的なロールプレイングゲーム。ゲームの終わりがないネバーエンディングのストーリー展開ゲームついに登場!!(竹野雅人「山田さん日記」)
本作「山田さん日記」でも、主人公は『山田さん日記』というロールプレイングゲームを通して、本当の自分とは何かというメタ認知を得ることになる。
「純愛映画」では八ミリ映画だった(箱庭)が、ここではファミコンゲームになっているわけだ。
その根底にあるのは、繰り返される日常からの脱出願望である。
主人公は、やがて、現実世界とゲーム内世界との区別に混乱を来すようになり、どれが、本物の自分なのか分からなくなってしまう。
さらに、主人公の夢には、いつでも「ぼく自身」が二人登場した(「こいつがいわゆる潜在意識っていうやつだね」)。
つまり、本作「山田さん日記」では、ゲームのキャラクターと、夢の中の自分自身という、二つのオルターエゴが登場しているのだ。
もちろん、ゲームの中のキャラクターは、主人公自身が操作しているから、半ば意識的な無意識ということになる。
村上春樹の言葉を借りると、一階(意識下)と地下一階(潜在意識)と地下二階(深層心理)とが、ごっちゃまぜになっている、ということになる(ここがおもしろい)。
高橋源一郎は、この作品を、非常に高く評価していた。
やりたくなるようなゲームを書いた竹野くんには降参するっきゃない。それは竹野くんが「ゲーム」について少なくとも一つはなにかを掴んでいるからだ。「少なくとも一つはなにかを掴む」ということはすっごく大事なことだ。それはちゃんとした小説になっているということなんだから。(高橋源一郎『文学がこんなにわかっていいかしら』所収「「たけの」くんのゲーム」)
実際に自分でプレイしてみたくなるゲームを書いた、というところが、高く評価されたらしい。
『山田さん日記』はメタ認知ゲームだから、このゲームをプレイしたくなる人というのは、あるいは、自分を掘り下げてみたいという願望にくるまれているのかもしれない。
自分だったら、こんなゲームは怖ろしすぎて近づきたくないが(本当の自分をさらけ出すなんて怖ろしすぎる)。
ちなみに、初めてのロールプレイングゲームとして社会的にも注目された『ドラゴンクエスト』の発売は1986年(昭和61年)(「今、新しい伝説が生まれようとしている」)。
ゲームの中で行き詰まる山田さんの姿は、日常生活に行き詰まる主人公の姿だ。
大切なことは、我々の日常生活に「GAME OVER」はない、ということではないだろうか。
本書の中で、最も注目すべき作品である。
正方形の食卓 │ 日常生活の死守
1986年(昭和61年)11月『海燕』初出。
1986年(昭和61年)に第五回海燕新人文学賞を受賞したとき、著者は20歳だった(法政大学経営学科)。
作品タイトル「正方形の食卓」は、主人公はじめとする四人家族の象徴である。
真っ白なテーブルに、煙草の焦げ跡をつけたとき、父も母も激しく狼狽して、この焦げ跡を何とか修復しようと試みた。
二人が守ろうとしていたものは、ささやかな四人家族という絆だったのだ。
ささやかな四人家族という退屈な日常からの脱出を願った姉(女子高生)は、年上の男性と同棲するために家出をした。
そして、退屈な日常生活が、いかに平穏なものであるかという事実に気が付いて、家庭に戻ってくる。
この物語は、退屈な日常生活からの脱出を願う中学生の物語だ。
力をこめて振りおろす。その木製バットからは激しい音がした。同時に手がしびれた。その音はあまりに瞬間的であった。(竹野雅人「正方形の食卓」)
単調な生活からの脱出を願う主人公は、真夜中、退屈な日常生活の象徴たる「正方形の食卓」を叩き壊す。
しかし、日常の象徴たる食卓テーブルは強固で、脚が一本折れただけだった。
父は、ひと晩かけて、食卓テーブルを修復し、一家はいつもと変わらぬ日常の朝を迎える。
必死にテーブルを修復する父の姿は、ささやかな家庭を死守する家長の姿でもあったのだろう。
一本だけ壊れた脚は、もちろん、主人公の象徴だが、不格好ながらもテーブルは、元の形を取り戻した。
繰り返される単調な日常生活への苛立ちは、後の「山田さん日記」でも描かれているものだが、主人公の不満は、家族生活にフォーカスされている。
注目されるのは、主人公の焦燥が「単調に繰り返される日常生活」にあったというところではないだろうか。
日常生活が「安定的に繰り返される」ことを保障されたとき、その日常生活は「単調で退屈なもの」となる。
平穏な生活こそ、若者たちの苛立ちの理由となったのだ。
あのあと、真夜中に父が丁寧にまた慎重にあの折れた脚を直したのであろう。テーブルの裏側に手をあててみると、ベニヤ板が何枚も重ねて打ちつけてあった。ベニヤ板はしつこいぐらいの厚さになっていた。(竹野雅人「正方形の食卓」)
世の中の大人たちは、単調で退屈な日常生活を手に入れるために、あくせく働いていた。
両親は、おそらく戦争を体験した世代か、少なくとも、戦後の混乱を経験した世代である。
単調な日常生活こそ、彼らの祈りではなかっただろうか。
そこに、親と子の間に生じる、世代的な価値観のズレがある(ジェネレーション・ギャップ)。
単調で退屈な日常生活の有難味は、家庭から出たときに初めて分かるはずだ(家出をした姉は、そのことを知っている)。
この物語は、平穏な家族生活を死守しようとする父と母の姿を、少年の視点から描いた家族小説である。
そして、少年の不満は、父や母が死守しようとしているものにこそあったというところに、現代社会の闇が潜んでいる。
80年代アメリカのミニマリズム小説を、日本風に解釈した作品として読めるかもしれない。
まとめ │ 日常生活からの逃避
本書で描かれているのは、繰り返される日常生活への疑問と、単調な生活の中で生きる自分自身への疑問である。
主人公を十代の少年として設定することで、日常生活への疑問は、家庭生活や学校生活への疑問として置き換えることができる。
その根底にあるのは、社会の中での居場所を探し始めた少年の焦りと恐怖である。
あまりにも日常が安定しているからこそ、主人公は、自分に自信を持てなくなっていくのだ。
「5対0」でリードしている試合を任されたリリーフ・ピッチャーのように。
「勝って当たり前」というプレッシャーの中で蓄積されたストレスを抱えて、彼らは生きていかなければならない。
日常生活からの脱出は、つまり、日常生活からの逃避でもあった。
それは、そうでもしなければ生きてはいけないと思わせるような、そんな時代だったのだ。
書名:純愛映画・山田さん日記
著者:竹野雅人
発行:1989/01/14
出版社:福武書店