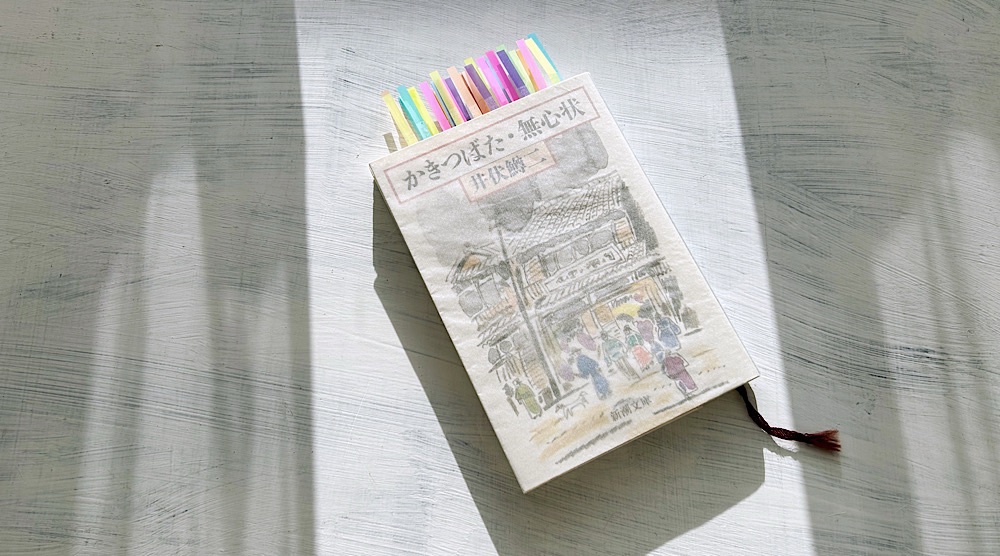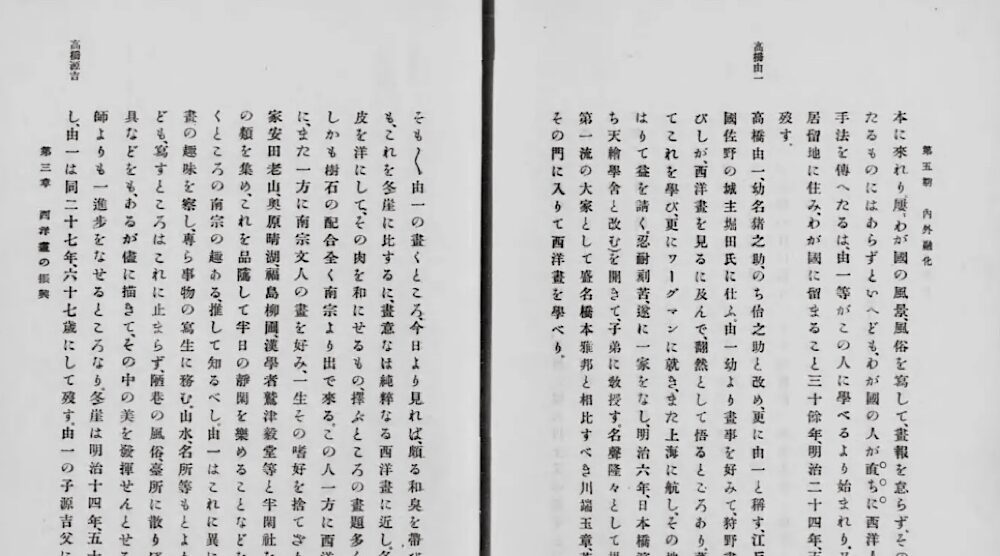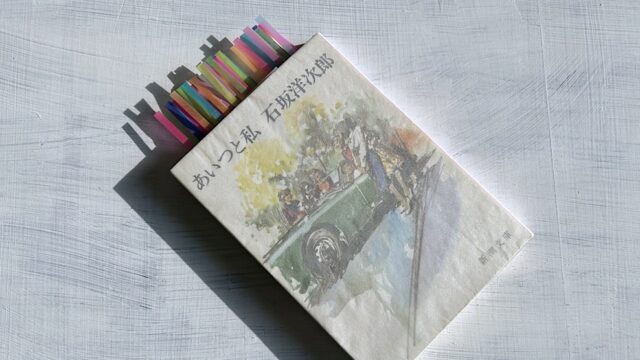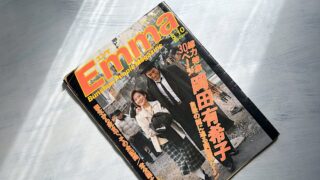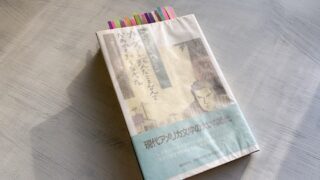井伏鱒二『かきつばた・無心状』読了。
本作『かきつばた・無心状』は、1994年(平成6年)7月に新潮文庫から刊行された短篇小説集である(新潮文庫オリジナル)。
井伏鱒二は、1993年(平成5年)7月10日に他界している(95歳だった)。
収録作品及び初出は、次のとおり。
「普門院さん」
・1949年(昭和24年)5月『改造文芸』
「爺さん婆さん」
・1949年(昭和24年)10月『群像』
「おんなごころ」
・1950年(昭和25年)12月『小説新潮』
・初出時のタイトルは「をんなごころ」
「かきつばた」
・1951年(昭和26年)『中央公論文芸特集』
・初出時のタイトルは「カキツバタ」
「犠牲」
・1951年(昭和26年)8月『世界』
「ワサビ盗人」
・1952年(昭和27年)12月『オール読物』
「乗合自動車」
・1952年(昭和27年)4月『別冊文芸春秋』
「野辺地の睦五郎略伝」
・1953年(昭和28年)4月『文芸春秋』
「河童騒動」
・1955年(昭和30年)2月『週刊朝日別冊』
・初出時のタイトルは「河童の騒ぎ」
「手水鉢」
・1955年(昭和30年)7月『文芸』
「御隠居(安中町の土屋さん)」
・1958年(昭和33年)1月『新潮』
・初出時のタイトルは「御隠居さん」
「リンドウの花」
・1958年(昭和33年)秋号『声』
・のち「リンダウの花」と改題
「野犬」
・1961年(昭和36年)7月『新潮』
「無心状」
・1961年(昭和36年)9月『小説新潮』
「表札」
・1962年(昭和37年)10月『小説新潮』
解説(小沼丹)
小説とも随筆とも区別の難しい短編作品群
本作『かきつばた・無心状』は、新潮文庫オリジナルの作品集である。
戦後に発表された作品が、ほぼ年代順に収録されている。
最初の「普門院さん」(1949)が、作者51歳の年で、最後の「表札」(1962)が、作者64歳の年の作品。
つまり、円熟期の井伏鱒二作品が、ここに並んでいると言っていい。
収録作品数は計15作品。
小説とも随筆とも区別の難しい短編作品は、井伏文学の真骨頂とさえ言える。
文章に味わいがあるし、どの作品も、物語の始まりと終わりがいい。
「普門院さん」の終わり方など、ある意味で象徴的だ。
かよ女は昭和十五年頃には八十歳すぎになっていました。老齢のため呆けたようになっていましたが、何かの拍子に小栗上野介──御殿様の話を持ちだすと、身を引きしめたようにしゃんとして見せる。少女の頃、御殿様によほど心酔していたのだろうと思われました。(井伏鱒二「普門院さん」)
江戸幕府の外国奉行(小栗上野介)の評伝なのに、最後は、ほとんど関係のないかよ女のエピソードで締めているところがいい。
「爺さん婆さん」(1949)は冒頭に注目してみる。
今年の春、友人の倅が医院を開業したのでお祝に梅の盆栽を持って行った。「寒代眼科医院」という看板だけは見事だが、診察室はバラック建で、廻転椅子や薬戸棚などセコハンの古物であった。(井伏鱒二「爺さん婆さん」)
戦後の庶民の暮らしが、そこにはある。
医者から高血圧を指摘された主人公(井伏鱒二だろう)は、甲州S寺の温泉へ行った。
今年の夏は、なるべく私は旅行に出るように心がけた。からだを遠近に運んで、瘠せようとするためと、瘠せることによって死神のことを忘れようとするためである。(井伏鱒二「爺さん婆さん」)
何気ない文章の中に、いかにも読者を惹きつけずにはいられない、巧みな話術がある。
研ぎ澄まされた文章という感じではなく、むしろ、作者の人間性によって読ませる文章という感じがする。
「おんなごころ」(1950)は、作品集『太宰治』(1989)にも収録された。
「昨日の晩から、僕は一睡もしないんです。とんでもない迷惑でした。寄ってたかって、みんなで僕をいじめやがるんだ。井伏さんを恨みます」(井伏鱒二「太宰治」)
太宰治のことは、井伏鱒二以上に上手に書ける人はいない(特に話し方や仕草など)。
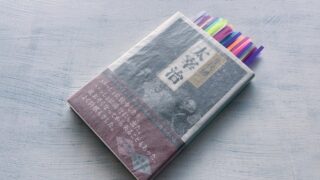
名作「かきつばた」(1951)も、冒頭から読ませる作品だ。
広島の町が爆撃されて間もないころ、私は福山市近郊の知人のうちでカキツバタの花の狂い咲きを見た。たった一輪、紫色に咲いていた。折から停戦命令が出た直後、八月中旬すぎのことであった。(井伏鱒二「かきつばた」)
原爆直後の広島近郊の町を舞台にする「かきつばた」は、名作長篇『黒い雨』の姉妹編として読むことができる。
福山市から広島市まで約四十里の距離である。広島が爆撃された当日のお昼ごろ、私は福山の町に出かけて行き、この町もこれが見おさめだろうという感慨で街を歩きまわっていた。(井伏鱒二「かきつばた」)
駅前の小林旅館で、主人公は水甕を譲ってくれるよう交渉する(「あの水甕、僕の村に疎開させないか」)。
「水甕なんか、疎開させなくっても結構ですよ」と、おかみさんが云った。「空襲なんか、あるもんですか。うちじゃあ、ただ疎開命令が出たから、人間だけ疎開するつもりです」(井伏鱒二「かきつばた」)
福山が空襲を受けたのは、広島が焼けた翌々日のことだった。
主人公の村にも、広島の爆撃被害を受けた怪我人が避難してきていた。
当初は謎の病気だった原爆症を、村の医者(田和さん)は、「義勇兵の病気」「不思議な苦しみをする病気」「治療法のない病気」などと呼んでいる。
原爆被害に戸惑う日本人の姿が、地方で暮らす庶民の視点から描かれている。
お城から降りて、駅前の小林旅館の焼趾に行って見ると、立札に立退先が書いてあった。中庭の植木は跡かたもなくなって、伊部の水甕が真二つに割れて、もとのままの美しい長春色であった。(井伏鱒二「かきつばた」)
割れた水甕は、戦災によって損なわれた主人公自身の心を象徴したものとして、読むことができる。
あるいは、それは、史上初の被爆国となった日本国そのものであったかもしれない。
カキツバタの花は、被災した女の遺体の近くで咲いていた。
夜明けごろ目がさめて、窓から見ると目の下の池に異様なものが見えた。電燈をつけ、コードを伸ばしてその光を池の水面に向けた。思わず私は目をそらして電燈の明りを消した。(井伏鱒二「かきつばた」)
狂った女の隣で咲いている狂い咲きのカキツバタは、狂った時代の象徴だ。
本作品集『かきつばた・無心状』の中で、最も読み応えのある作品と言っていい。
「犠牲」(1951)も戦争物で、徴用中の犠牲者たちを振り返っている。
長篇『徴用中のこと』(1996)の系譜に属する作品。

決して一枚岩とは言えなかった日本軍の現実が、そこにはある。
ことに意地わるい若い船員が一人いた。この船員を、十八師の兵隊の一人が擲りつけた。隊長がその兵隊を呼びつけて「貴様は船員が生意気だと云って、擲ったそうじゃないか。たしかに擲ったか」と云った。「はい、自分は船員を擲りました」「なぜ斬らんのだ。今度からは斬れ」「はい、今度から斬ります」「斬れ。作戦の邪魔だったから斬ったのだ、と報告する」(井伏鱒二「犠牲」)
「ワサビ盗人」(1952)は、井伏鱒二らしい庶民物語。
「兵法は密なるを要す」と幸平さんは心に念じました。「あいつ、どうするだろうか。おどかしてやろうか。いやいや、兵は国の大事なり、みだりにすべからず」(井伏鱒二「ワサビ盗人」)
渓流釣りの途中で、わさび泥棒の痕跡を発見した主人公(幸平さん)は、村人と連携して、わさび泥棒を捕まえる(「やあ、あいつだ。あの男だ。みんな抜かるな」)。
狸を利用したわさび泥棒というのも、いかにも、のんびりしていていい。
「乗合自動車」(1952)も、本作品中では注目したい戦後庶民譚である。
「おい、そこの図々しい客」と運転手が、くわえ煙草で云った。「いま、そとのお客が云うのを聞いたろう。あれは民衆の声じゃと思え。世論を聞いとけ。よい加減にして、お前も降りて押せ」(井伏鱒二「乗合自動車」)
乱暴なバス運転手と都会から来たカップルとのいさかいに、他の乗客たちが巻き込まれてしまう。
エンジンが止まるたびに、乗客全員が降りてバスを押さなくてはならない、という設定もすごいが、いかにもありそうで楽しい。
「野辺地の睦五郎略伝」(1953)は歴史物語で、奥州八戸藩の武家(野村軍記)の家来(野辺地の睦五郎)の生涯を紹介している。
「在所でなら、恥かしくないので御座いましょうか」「おぬし、どうせ在所でなら、恥のかきついでじゃろう。早う行って、在所で身を固めさっしゃれ」(井伏鱒二「野辺地の睦五郎略伝」)
名もない歴史上の人物に光を当てているが、どのような庶民にも、人生のドラマがあるということを、改めて教えてくれる。
「河童騒動」(1955)も、歴史もののひとつで、河童の出没で村中が大騒ぎになる様子が描かれている。
江戸時代、明和六年のことであった。この年の七月から八月にかけて、夜ごとに東南の空に彗星(ほうきぼし)が現われた。すると九州から山陰山陽方面に、この二箇月間、そこかしこに河童が出て人畜を害するという噂が立った。(井伏鱒二「河童騒動」)
明和6年は、西暦で1769年。
この年、フランスの天文学者(メシエ)が大彗星を発見していて、日本国内にも観測記録が残されている。
河童は、馬や牛を川の淵に引きこんで溺死させるばかりか、人妻や若い女性をレイプするらしい。
意外と、凶暴な動物として認知されていたのだろうか。
そのなかに佐野の好きな俳句の茶掛があった。<朝づとめ妻帯寺のかねの声 良> その句を佐野は幾度も黙読して、「ちょっと弱い句じゃ。しかし、悪くない句じゃ」と半ば讃めた。(井伏鱒二「河童騒動」)
河童の物語の中に、俳句のエピソードが混じる。
こういう寄り道が、井伏さんは得意だった。
作者の生活を中心とする広大な井伏文学の世界
「手水鉢」(1955)は、井伏家の庭にあった手水鉢の由来を綴った作品。
あの手水鉢は、僕がこの家に世帯を持った翌年、五円七十銭で買った。未だに値段を覚えている。昭和二年十月末に僕がここに引越して、それから満一年の十月末日に買ったことも覚えている。(井伏鱒二「手水鉢」)
名作長篇『荻窪風土記』の落穂拾い的な作品と言っていいだろうか。
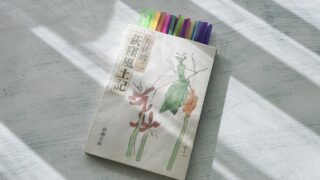
「御隠居(安中町の土屋さん)」は、庶民評伝とも言うべき歴史物語の小篇である。
土屋金太郎さんは、今年八十歳になる。上州安中町の生れで、現在、安中城址に建てた自宅に住んでいる。場所は、太鼓櫓のあった跡地で、昔、その櫓太鼓の音が遠く熊谷の町まで聞えたという。(井伏鱒二「御隠居(安中町の土屋さん)」)
一人の庶民が見た日露戦争史である(「あれは三月九日で、蒙古風の吹く日でした。息もつけないほどの風でした」)。
「リンドウの花」(1958)は、御坂峠シリーズの作品。
「ええ、そうですわ。私、御坂峠に行きたいんです。崖のはなに、リンドウの花が咲いておりました。私はリンドウの花が好きです」(井伏鱒二「リンドウの花」)
夫に逃げられた聾美女の苦悩が、リンドウの花をモチーフに描かれている。
「野犬」(1961)は、須々木村(現在の静岡県牧之原市)に現れる野犬の群れについて書かれた作品。
「うちのおとっつあんは、大陸におるときには、二度も三度も銀色の虹を見たちゅうこってすが」と、おかみさんが云った。「銀色の虹が出ると、大陸の現地人でも不吉の前兆じゃと云うとるちゅうこってすわ。人間の心の暗い影や土地の異変などが、天に映って虹になるちゅうこってすわ」(井伏鱒二「野犬」)
野犬を描きながら、庶民(農谷本多吉)の生き様を描いている。
中年の洋画家(菰田君)の手紙によって構成された物語は新鮮。
書名にも登場している「無心状」(1961)は、作者の初恋物語として読むことができる。
私は大正六年に上京して早稲田の文科に入学した。そのころ早稲田では各学部とも本科と予科に分れ、文科部の予科はEクラスとDクラスに分れていた。私が入ったのはDクラスだが、入学第一日目の第一時間目に、英文講読の授業があった。テキストはアーサー・シモンズの「アルルの町」である。教師は吉田源次郎先生であった。(井伏鱒二「無心状」)
吉田源次郎(筆名・吉田絃二郎)は、当時、小説「島の秋」を発表して、文壇の新進作家と呼ばれていた。
後年は、旅行記や随想を主として、『小鳥の来る日』『花梨の花の散る頃』などの代表作を残している。
主人公(井伏鱒二だろう)は、吉田先生へ提出するレポートと間違って、兄に宛てて書いた手紙(無心状)を提出してしまったので、吉田先生の自宅まで出かける(「そのころ吉田先生の自宅は、大塚駅から郊外電車で行ける庚申塚というところにあった」)。
その帰り、庚申塚から大塚まで引き返して、市電で本郷三丁目に下車したところ、主人公が片思いしている女性が停留所に立っていた。
そこは、「かねやす」という小間物屋のある停留所である(江戸川柳にも「本郷もかねやすまでは江戸のうち」と云ってある)。
電車の中で、主人公は吉田先生の言葉を真似したりしながら、女学生と親しくなる。
「あらいやあだ」と相手は、他の乗客に視線を向けさせるほどの声を出した。「高橋源吉さんは、日本美術史に出ている画家ですって。あたしのおばあさまのお兄さまの、絵の先生してらっしゃったんですって。日本に来ていたイタリア人の、フォンタネジーという人の、お弟子さんだったんですって」(井伏鱒二「無心状」)
二人は古本屋で『近世絵画史』という本を一緒に読むが、この出来事が、主人公にとって忘れがたい出来事になった。
あの日、吉田先生のところからレポートと引換に返してもらって来た私の無心状は、古本屋を出て、一人になってから、歩きながら二つにさいてまたポケットに入れた。それを取出し幾つにもさいて、またポケットに入れた。(井伏鱒二「無心状」)
ズタズタに引き裂かれた無心状は、主人公自身でもある。
藤岡作太郎『近世絵画史』(金港堂、初版1903)の訂正版は、1914年(大正3年)に刊行された。
実らなかった初恋を、無心状を舞台回しに語っている構成もいい。
最後の「表札」(1962)は、井伏家に暮らすお手伝いの女の子の話で、荻窪シリーズの作品である。
ふと私は「葉山の雨」という小説を思い出した。作者は木村庄三郎である。(井伏鱒二「表札」)
木村庄三郎は、フランス文学の翻訳者として知られているが、戦前は、同人誌『山繭』などに小説を発表していた。
他愛ない世間話のような事件こそ、井伏さんにとっての小説というものだったのだろう。
巻末の「解説」を、井伏鱒二の愛弟子(小沼丹)が書いているところも、本書のポイントである。
昔、あれはいつ頃のことだったかしらん? はっきりした記憶はないが、同行した吉岡達夫が、「──二十年ぐらい前だよ……」と云うから、二十年ぐらい前だと思うことにする。(小沼丹『かきつばた・無心状』解説)
井伏鱒二の自宅を訪れた二人(小沼丹と吉岡達夫)は、太宰治が井伏鱒二に宛てて書いた手紙を譲り受ける。
小沼さんの解説は、井伏さんからもらった太宰治の手紙の紹介になっていて、既に、ひとつの完成された随筆として読むことができる(というか、読むしかない)。

いずれも短い作品ばかりだが、どの作品にも、井伏鱒二らしい、井伏文学のきらめきがある。
文学を読んでいるという負担感がないので、初心者にもおすすめ。
書名:かきつばた・無心状
著者:井伏鱒二
発行:1994/07/01
出版社:新潮文庫