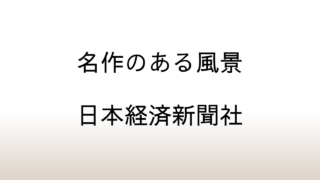大佛次郎「帰郷」読了。
本作「帰郷」は、1948年(昭和23年)5月から11月にかけて毎日新聞に連載された、戦後直後の日本を代表する大衆文学の名作である。
戦前・戦中の価値観を失った日本人が戸惑う時代
物語は、太平洋戦争末期のマラッカ(シンガポール)から始まる。
元・軍人の<守屋恭吾>は、仲間たちと海軍の金を遣いこんだ責任を負って、妻子を棄てて日本を出国したという、秘密の過去を持つ。
ヨーロッパを放浪した後、彼はマラッカに滞在していた。
そのマラッカで、海軍相手の水商売をしていた華族の<高野左衛子>は、恭吾に惹かれて肉体関係を持つようになるが、彼女の発言が元となって、恭吾は憲兵に捕らえられてしまう。
やがて、戦争が終わり、戦後の日本は、高野左衛子と、彼女を取り巻く男たちによって描かれていく。
例えば、左衛子と一緒にマラッカを訪れたことのある画家<小野崎公平>は、敗戦・日本の荒廃した姿に嘆いてみせる。
「人間が生きるって、大変なことだ」と、嘆息しそうに、画家は云った。「もともと、そうなのに、何もかも戦争でぶち毀してしまったんだからね。第一、敗けた経験のない国民が惨めに敗けたのだから、処置なしに、おっこちてしまった。一度に、ぼろが出たのだ」(大佛次郎「帰郷」)
「日本は大好きだが、個々の日本人は嫌いだな」とつぶやく画家に対して、復員兵の大学生<岡部雄吉>は、また違った感情を持っている。
「僕なんか、もっと、ひどい生活をして来たから、今でも夜、寝ようとして床の上に転がって電燈を消すと、現在の幸福だけ算えて、ひとりで楽しくなって来るんです。自分は内地に帰って来ているぞ。蒲団の上で寝ているんだぞ。この家には屋根があるから雨が降っても起きる心配ないぞ。そんなことが嬉しいんですよ」(大佛次郎「帰郷」)
さらに、新しい時代を象徴するのが、アプレゲールの<岡村俊樹>である。
「では、手を組んで行きましょう。あすこに来るアメリカ人がしているように」驚いて「厭!」と思わず首を振って云い切った。ゆたかな髪が、強く揺れた。「極りが悪いんですか。古いなあ」と、俊樹は子供のような顔で笑った。「若いものの特権じゃないですか。みんなが、そうしている」(大佛次郎「帰郷」)
新しい時代の波に乗って自信に満ちた俊樹の態度は、画家や雄吉など、古い時代の感覚を持つ大人たちからは、強い反発を受ける。
こうした新旧世代対立の中間に位置しているのが、長く日本を離れていて、すっかりと外国人的な感覚を身に付けて帰郷してきた、主人公の守屋恭吾だった。
「みんな、てんでに、奇妙な生き方をしている」と、恭吾は云った。「牛木も俺もだ。お前にはまだ判らんだろうが、この提灯のようなものだ。ぶらりとこの人生にぶら下がって、それでいて、どこかに悲しいところがある。しかし、誰がそうさせたというのでもない。自分、自分なのだね。まことに」(大佛次郎「帰郷」)
本作「帰郷」は、戦前や戦中の価値観を失った日本人が戸惑う時代を描いた物語である。
同じ日本を見ていながら、誰もが別々の日本を見ていた。
それが、戦後という時代だったのだ。
自分さえ確かならば、余計なものはない方がよい
この物語の名場面の一つとして知られているのが、京都の金閣寺で、久しぶりに再会した娘の伴子を、京都駅までタクシーで送るシーンだろう。
父親が急に手を出して、「お見せ」と、云った。何のことか、判らなかったが、伴子が膝に置いているハンドバッグのことであった。「どんなものを、お前のような若い娘が持って歩いているのか、見当がつかないのでね。よかったら、お見せ」うちとけた様子なので、伴子も無邪気に笑顔を誘われた。(大佛次郎「帰郷」)
このとき、伴子のハンドバッグの中から、恭吾はダイヤモンドの粒を発見する。
それは、旧華族の高野左衛子から贈られたものだったが、伴子は、それを返すつもりだと言う。
「だって、こんなに、どなたも困っていらっしゃる世の中に、伴子だけがよければいいということはないんですわ。あたし、自分で働いています。よその方から、こういうもの頂かなくてもいいし、ダイヤモンドなんか、この世界になくてもいいものじゃないでしょうか。こういうものを持つようになると、もっと他のものも欲しくなるでしょう」(大佛次郎「帰郷」)
伴子の言葉を聞いて、恭吾は「そうだ、自分さえ確かならば、余計なものはない方がよいのだ」と、娘に説いてみせる。
この場面こそが「帰郷」という物語のクライマックスであり、著者がすべての日本人に伝えたかったことだろう。
さまよう日本人の中で、明るい希望の光を、恭吾は自分の娘の中に見つけたのだ。
板坂元は『紳士の小道具』(1993)の中で、恭吾が伴子のハンドバッグの中を見せてもらう場面について注目している。
その最後に、娘の伴子と京都を訪れる。金閣寺の場面が美しい。そして、いよいよ別れのタクシーの中で伴子にバッグの中を見せてくれと頼む。若い娘のハンドバッグの中を見る場面は妙に切なくて、そこはかとないエロティシズムを漂わせる。(板坂元「紳士の小道具」)
男にとっても女にとっても、バッグは秘かに守っている自分だけの領域である(聖域)。
バッグ中を見せてもらう行為は、他者の聖域に踏み込む行為であり、そこに離別する父と娘の思いが描かれていると、板坂さんは考えていたのだろう。
『帰郷』の主人公が、娘との別れ際にバッグの中を見せてもらう場面の、胸をしめつけられるような思いは、バッグの持つ神秘的な力によるものだ。(板坂元「紳士の小道具」)
ハンドバッグに託された親子の別れ。
それは、敗戦直後の日本を生きる、多くの人々の思いでもあったのだ。
書名:帰郷
著者:大佛次郎
発行:1999/3/10
出版社:毎日新聞社