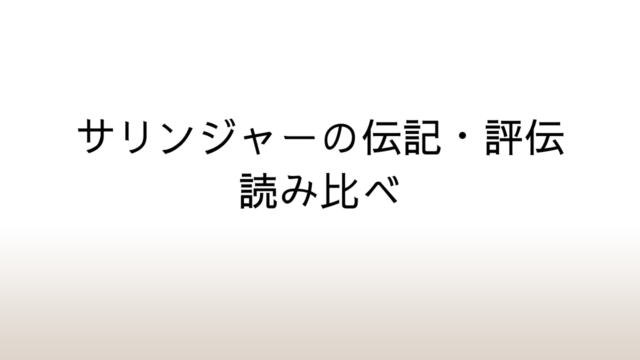映画『桐島、部活やめるんだって』のラストシーン。
バレー部のエリート「菊池宏樹(東出昌大)」が見せた涙の理由は、単なる「敗北感」ではない。
なぜ彼は泣いたのか?
映画では描ききれなかった原作小説の心理描写を補助線に、カースト最上位の宏樹が、最底辺で生きる映画部「前田涼也(神木隆之介)」に自分を重ねた「同じ高校生」としての正体を深く考察してみた。
映画と原作の違いから見える、救いの正体とは。
屋上の沈黙を破る、あの「涙」の違和感
映画『桐島、部活やめるんだって』最大の謎は、クライマックスとなる最後の場面で、菊池宏樹はなぜ泣いたのか?ということだ。
「なぜ泣いた?」映画ファンが抱き続ける最大の謎
2012年の公開から10年以上が経過してもなお、検索窓には「桐島 宏樹 なぜ泣いた」という言葉が打ち込まれ続けている。
端正な容姿、高い身体能力、そして「野崎沙奈(松岡茉優)」という美しい彼女。
スクールカーストの頂点に君臨し、全てを手にしているはずの彼が、最底辺で生きる映画部員・前田涼也の前で見せた涙。
その理由は、「持てる者」が「持たざる者の熱量」に当てられた敗北感のようにも思える。
しかし、本当にそれだけだったのだろうか。
その答えは、朝井リョウの書いた「原作小説」に隠されていた。
映画と原作の違いから見える、二人の「共通点」
映画版は、「空間」や「視線」によって、スクールカーストの残酷な断絶を可視化した。
一方で、原作小説は、それぞれの生徒の独白という手法によって、彼らの内面を丁寧に描き出している。
そこから見えてくるのは、スクールカーストという階級社会の、「上位」と「下位」という記号的な格差ではなかった。
「何者でもない自分」への焦燥を抱え、同じ地平であがいているという意味では、菊池宏樹も前田涼也も、どちらも同じ高校生である。
映画の演出を原作の言葉で補完したとき、あの涙の真の正体が浮かび上がってくるのではないだろうか。
映画が突きつけた「スクールカースト」という名の絶望
映画版『桐島』は、スクールカーストの中で生きる高校生の姿をリアルに描き出している。
空間演出で見せる、上位層と映画部の「越えられない壁」
吉田大八監督による映画版は、学校という閉鎖空間を「音」と「高低差」で鮮やかに階層化してみせた。
校庭から響く野球部の爽やかな声や、校舎の窓から重なり合う吹奏楽部の音色は、「リア充」と呼ばれる上位層の輝かしい背景音として機能している。
一方で、映画部が潜む放課後の暗がりや、吹き溜まりのような屋上には、特有の「静寂」が流れている。
こうした物理的な隔離は、彼らの間に存在する「越えられない壁」を視覚的に、そして聴覚的に観客へ突きつけたものだ。
記号化された菊池宏樹と、異物としての前田涼也
その階層構造の頂点に立つ菊池宏樹は、もはや一人の高校生というより「完璧なエリート」という記号として描かれている。
何をやっても器用で、周囲の期待に応え続ける彼の姿は、どこか空虚で実体がない。
一方、カースト最下層に位置する前田涼也は、周囲の嘲笑を浴びながらも8ミリカメラを回し続ける、現代社会の「異物」だ。
スマートに「役割」を演じる宏樹と、不格好でも「好きなこと」に全振りする前田。この両極端な二人のコントラストが、物語の緊張感を極限まで高めていく。
【原作視点】上位も下位も、地続きの空虚を抱えていた
一方、朝井リョウの原作小説は、一人一人の生徒の心理描写から「スクールカースト」という虚構の実体に迫っている。
「何者でもない自分」への焦燥。桐島の不在が可視化したもの
原作小説が暴き出すのは、映画のように鮮やかな階層ではなく、そこで生きる生徒たちの生々しい「焦り」だ。
桐島はスクールカーストを支える重要なポイントであり(カリスマとまでは言わないが)、桐島が欠けた瞬間、彼らの階級社会は途端にバランスを崩してしまう。
「上位層」という不安定な共同体の歪みが明らかとなったとき、そこに残るのは「自分は何者でもない」という、下位層の生徒たちと何ら変わらない空虚な自分自身の姿だった。
「同じ高校生」として、彼らは等しく未来に怯えている
原作小説『桐島』は、カーストの上下を問わず、彼らが等しく「放課後の終わり」を恐れていることを浮き彫りにしていく(つまり、いずれは社会へと出ていかなければならないことを)。
桐島の代役として試合に出場するリベロの小泉風介も、映画に執念を見せる前田涼也も、そして、野球部の練習から逃げて、何もしないことを選んだ菊池宏樹も、彼らは、一歩校門を出れば「何者かにならなければならない」という不透明な未来に直面していたのだ。
スクールカーストという階級社会によって、一見、彼らの不安は隠されているかもしれない。
しかし、彼らは間違いなく、同じ「高校生」という名の、もろくて壊れやすい青春を共有していた。
【考察】菊池宏樹はなぜ泣いたのか?レンズが暴いた「敗北」と「共鳴」の真実
それでは、映画のラストシーンで、上位層の菊池宏樹は、なぜ涙を見せたのだろうか?
ファインダーの魔法。宏樹が「ただの被写体」に戻った瞬間
映画のラストシーン。映画部の監督・前田涼也が菊池宏樹にカメラを向けた瞬間、大きな変化が現れる。
それまで菊池宏樹は、常に「他人からどう見られるか」というスクールカーストの視線に縛られながら「完璧な自分」を演じ続けてきた。
しかし、前田涼也の構えたレンズは、彼の社会的地位を一切評価しない。ただ一人の「被写体」として、彼の内面に潜む揺らぎや空虚さを、客観的に写し出していく。
レンズというフィルターによって宏樹は、自らの「虚像」を捨て去ることができたのだ。
前田の中に見た「かっこ悪いけど、確かな自分」
宏樹に衝撃を与えたものは、「自分たちは映画監督になれるわけじゃない」と語った前田涼也の「残酷な自覚」である。
将来へ繋がるわけでもなく、まして、学校内では「カースト最底辺の人間」として蔑視され、嘲笑を浴び続けてきた。それでも、自分の好きな映画に情熱を傾けている前田の姿は、あまりにも不格好でありながら、確かに「生きている」高校生の姿だった。
だけど、そのレンズを覗く映画部ふたりの横顔は、ひかりだった。ひかりそのもののようだった。(朝井リョウ「桐島、部活やめるんだって」)
本気で傷つくことから逃げてきたスマートな宏樹にとって、彼の「ダサさ」こそが、自分がずっと求めていた「確かな手応え」だったのかもしれない(桐島の代役・風介は、その伏線として読むことができる)。
涙の正体。それは「同じ地平」に立つ者を見つけた救い
菊池宏樹の涙は、決して「自分より格下だ」と思っていた相手に負けた「敗北」の涙ではない。
それは、学校生活という暗闇の中で「何者でもない自分」に怯え、それでもなお一歩を踏み出そうとしている「仲間」を見つけた、共鳴の涙である。
宏樹は「カーストの頂点」という孤独な場所から降りて、前田涼也という「同じ高校生」が立つ地平へと降りた。
前田の回し続ける8ミリカメラの中で、菊池宏樹もまた、本当の自分を見つけていたのだ。
青春という名の「不平等で平等な」季節
そして、大人になった今も、我々は『桐島、部活やめるんだって』に共鳴を受け続けている。
今もあの「放課後」の中で生き続けている
我々が今なお『桐島、部活やめるんだって』を語り継ぎ、検索し続けるのは、あの夕焼けの屋上で撮影された「ゾンビ映画」の中に、自分自身の姿を見つけていたからだ。
前田涼也の撮影する「ゾンビ映画」は、現代社会という名のディストピアを映像化している。
あのとき、自分は「ゾンビ」だったのか、それとも、ゾンビに食い殺される「無様な人間」の方だったのか。
スクールカーストという空虚な序列の中で、「何者かにならなければならない」と焦る高校生たち。それは、特定の時代や場所を超えた、普遍的な青春の痛みだ。
もしかすると、我々は、今もあの夕焼けの中で生き続けているのかもしれない。
まとめ:カーストを超え、ひとりの人間に立ち返る一冊
映画版『桐島』が提示した鮮烈な「現象」を、原作小説に描かれた「内面」という補助線によって読み解くことで、菊池宏樹の「涙」は意味付けされた。
スクールカーストは絶対的な境界線ではなく、その中には、等しく不安を抱え、あがき続けている高校生たちの姿があるはずだ。
階層という記号から抜け出して、一人の人間として向き合うことの尊さ。
本作『桐島、部活やめるんだって』が与えてくれたものは、自分自身を再発見するための「きっかけ」だった。
書名:桐島、部活やめるんだって
著者:朝井リョウ
発行:2012/04/25
出版社:集英社文庫