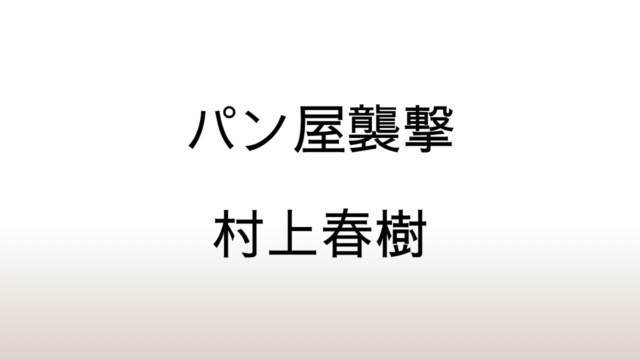井伏鱒二「鯉」読了。
「鯉」は、講談社文芸文庫『私小説名作選(上)』(中村光男選)に収録されている短篇小説である。
初出は『三田文学』1928年(昭和3年)2月号。
元は『桂月』1926年(昭和元年)9月号に発表した『鯉(随筆)』だった。
井伏さんの作品集では『夜ふけと梅の花』(1930、新潮社)に収録されている。
私は釣竿を逆さにして枇杷の実をたたき落した。
学生時代のこと。
「私」(井伏さんのことだろう)は、親友の青木南八から白い鯉をもらった。
鯉は下宿の池で飼っていたが、素人下宿へ引っ越したのを機に、青木の愛人の邸宅にある池で預かってもらうこととした。
井伏さんは、愛人の池に放ったとしても、鯉は必ず自分のものであると力説する。
白い鯉は、二人の友情の証であったのだ。
それから六年目の初夏に、青木が急逝した。
井伏さんは、青木の愛人に頼み込んで、池の鯉を返してもらうのだが、死んだ親友の愛人宅の池で鯉釣りをする場面は、この短篇小説の前半の山場と言えるだろう。
枇杷の実はすでに黄色に熟していて、新鮮な食欲をそそった。のみならず池畔の種々なる草木はまったく深く繁って、二階の窓からも露台の上からも私の姿を見えなくしていることに気がついたので、私は釣竿を逆さにして枇杷の実をたたき落した。ところが鯉は夕暮れ近くなって釣ることができたので、つまり私はずいぶん多くの枇杷の実を無断で食べてしまったわけである。(井伏鱒二「鯉」)
井伏さんは、釣った鯉を早稲田大学のプールに放った。
夏が来て、学生たちはプールで泳ぎ始めたが、井伏さんの白い鯉は姿を見せなかった。
あるいは、もう死んでしまっているのかもしれない。
ところが、ある蒸し暑い夜が明ける頃、清々しい空気を吸おうと散歩に出かけた井伏さんは、白い鯉がプールの水面近くを泳ぎ回っているところを発見する。
私の鯉は、与えられただけのプールの広さを巧みにひろびろと扱いわけて、ここにあってはあたかも王者のごとく泳ぎまわっていたのである。のみならず私の鯉の後には、いくひきもの鮒と幾十ぴきもの鮠と目高とが遅れまいとつき纏っていて、私の所有にかかる鯉をどんなに偉く見せたかもしれなかったのだ。(井伏鱒二「鯉」)
やがて、冷たい季節が来て、プールの水面には木の葉が散った。
それから氷が張った。
もはや、井伏さんは、鯉の姿を探すことをあきらめた。
ある朝、氷の上に薄雪が降った。
井伏さんは、長い竹竿を拾ってきて、氷の面に大きな絵を描いた。
それは、亡くなった親友・青木南八にもらった、あの白い鯉の絵であった。
亡き友に贈る鎮魂歌
「鯉」は、亡くなった親友・青木南八を悼むために綴られた作品だろう。
白い鯉は二人の友情の証左であり、青木が死んだ後、白い鯉の存在は、井伏さんの中でますます大きくなっていった。
死んだかもしれないと思っていた鯉が泳ぎ回っているのを見つけた朝、井伏さんは「このすばらしい光景に感動のあまり涙を流し」ているが、この涙は、亡友に捧げられた涙であったに違いない。
雪の上に鯉の絵を描いた後で、井伏さんは「鯉の鼻先に「……」何か書きつけたいと思ったがそれは止して」と綴っている。
このとき、井伏さんが書こうと思った言葉は、果たしてどんな言葉であっただろうか。
それは、きっと死んだ友へ捧げる追悼の言葉だったに違いないが、ここで亡き友の話を持ちだしてしまえば、作品は陳腐になる。
早稲田のプールに鯉を放してしまった後は、もうどこにも青木南八という名前は出てこないからだ。
井伏さんにとっては、白い鯉そのものが、もはや青木南八自身であったのだろう。
懐かしい友情を、ここまでさらりと美しく書くことができる。
真の友情というものを知っていなければ書けない小説だと思った。
書名:私小説名作選(上)
編者:中村光夫
発行:2012/5/10
出版社:講談社文芸文庫