中村白葉「ここまで生きてきて 私の八十年」読了。
本書は、ロシア文学者として著名な中村白葉の自伝的エッセイ集である。
あとがきには「年代的には二十歳前後から八十を越す今日まで、わが身に起こったこと、考えたことその他、悲喜こもごもの自分の生態を土台に、自分という人間を掘りさげ、突き崩して、日記でもつけるつもりで、機会あるごとに書きためたもの」とある。
『チェーホフ全集』と『チェーホフ著作集』
冒頭の「一平凡人の半生」は、昭和27年の「新潮」に掲載されたもので、次の「私の履歴書」は、昭和42年の「日本経済新聞」に掲載されたものである。
「私の履歴書」は、喜寿(七十七歳)のお祝いをしたところで終わっているから、ほぼ自伝と言っていい内容となっている。
中村白葉といえば、野尻抱影の随筆に、近所で暮らしている中村白葉を介して、志賀直哉と交流を持った話がある。
私は、武者さん(武者小路実篤氏)は古くから知っていたが、志賀さん(直哉氏)と知り合ったのは、昭和十二、三年ごろ、志賀さんがこの世田谷新町へ越してこられてからであった。新町にはそのころ、お互いに歩いて五分とかからぬ近くに、野尻さん(抱影氏)、若山さん(為三氏—春陽会員)、それに志賀さんと私の四人がひとかたまりに住んでいた。そして戦争中は、ほとんど毎日のように往来してすごした。(中村白葉「私の履歴書」)
また、戦後間もない頃の庄野潤三が、集中的に読んだチェーホフ作品を翻訳したのも、この中村白葉で、庄野さんの小説や随筆ではおなじみのロシア文学者となっている。
その中村白葉が「チェーホフ全集」を個人訳で完成させたのは、昭和11年のことだ。
昭和八年の後半から企画を立て、前に私の創作長編『蜜蜂の如く』をだしてくれた古い知友の金星堂主福岡益雄君と相談して、その秋十一月ごろから隔月配本の予定で発行にかかったのが、「チェーホフ全集」十八巻の個人訳であった。この全集はちょうど私が四十四歳の秋、原著者チェーホフの没した年齢からはじめてまる三年、三十六ヵ月で一応完結したのである。(中村白葉「私の履歴書」)
このとき金星堂には、まだ二十代の伊藤整がいて、『チェーホフ全集』の刊行に尽力していたそうである。
ところで、庄野潤三が読んでいたチェーホフは、この金星堂の『チェーホフ全集』ではなく、戦争中に三学書房から刊行された『チェーホフ著作集』だった。
庄野さんの随筆「文学を志す人々へ」(『自分の羽根』)によると、この『チェーホフ著作集』は、「昭和十八年の春から全十九巻の予定で刊行されたのだが、戦争がひどくなって来たので、十九年九月に六冊目の配本を終って中止された」ということであるが、中村白葉の「私の履歴書」には、この『チェーホフ著作集』は登場しない。
そもそも、戦時中のことは、ほとんど書かれていないので、著者としては、あまり触れたくない部分だったのかもしれない。
宮原晃一郎との別れ
ロシア文学者として歴史に名を残す中村白葉だが、翻訳家としての暮らしは、決して簡単なものではなかったらしい。
本書では、酒も煙草も女遊びもやらなかった著者が、金銭面では随分苦労した話が何度も出てくる。
有島武郎の友人であり、北欧文学の翻訳家として知られる宮原晃一郎は、終戦の年の初夏、北海道へ疎開する旅の途中、青森に近い野辺地付近で、汽車に腰かけたまま亡くなった。
宮原晃一郎にとって中村白葉は、有島武郎に次ぐ古い文学仲間だったらしいが、文筆生活は苦しいもので、北海道へ疎開する直前、宮原は「どうにもやりきれないから、やきいも屋でも始めようかと思う」と言った。
ちょうど壺焼きというもののはやりかけた頃のことで、それをやろうというわけだが、その商売道具—素焼きの大きな壺を買う十五円が手もとにない。困ったという話である。宮原は私の苦しい内証も知っていたので、むきつけに私に貸せとは言わなかった。が、用立てれば喜ぶことは知れていたし、多少はそれを期待していたかもしれなかった。しかも、その時私の金入れには、十円札が一枚きりあった。(中村白葉「一平凡人の半生」)
結局、中村白葉は金を貸すこともなく、宮原晃一郎は病躯を引きずるようにして北海道へ疎開する途中で死んでしまったという。
最後に別れるときの言葉は、涙のたまった目で言った「君にだけはもう一度会って行きたいと思ってね」だった。
書名:ここまで生きてきて—私の八十年
著者:中村白葉
発行:1971/12/5
出版社:河出書房


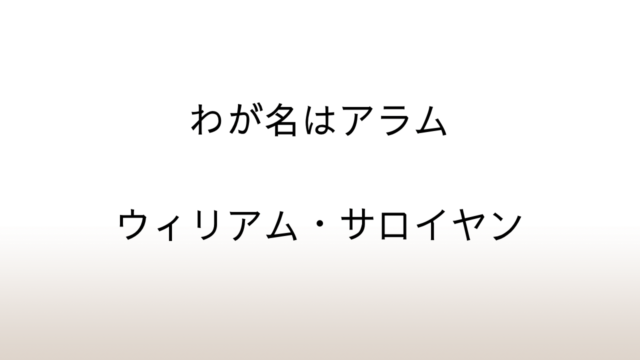
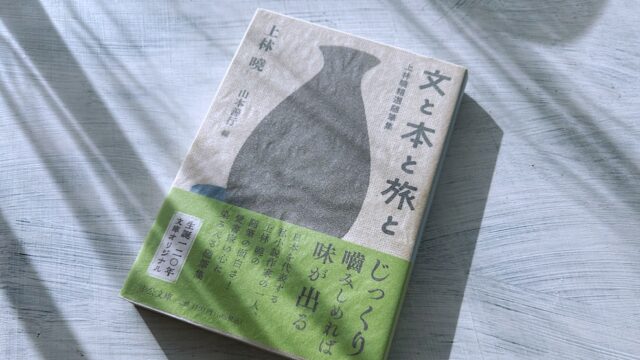
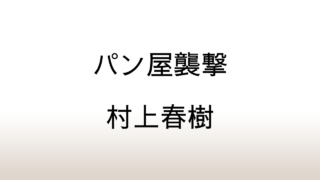

-150x150.jpg)









