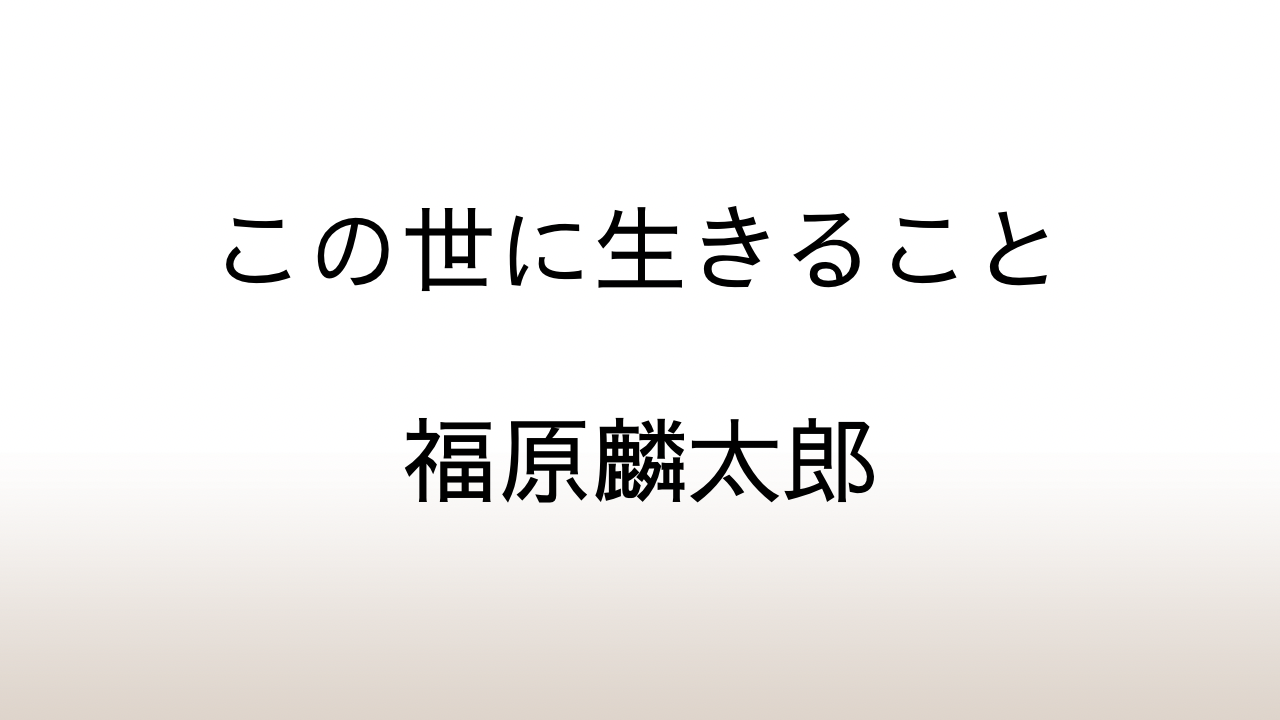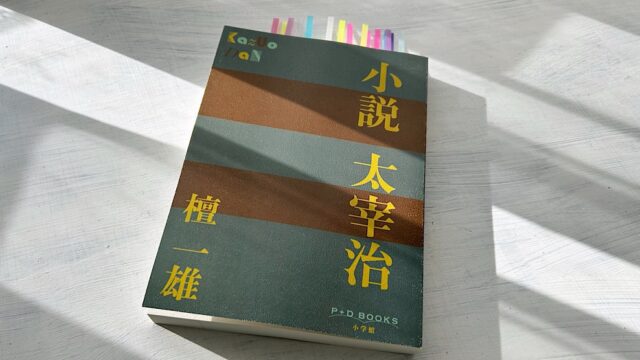福原麟太郎「この世に生きること」読了。
本作「この世に生きること」は、1954年(昭和29年)に刊行された随筆集である。
この年、著者は60歳だった。
しみじみと心の話の出来る随筆家だった福原麟太郎
庄野潤三の作品を読んでいると、福原麟太郎の名前が出てくる。
そうすると、自分自身でも福原麟太郎の作品を読んでみたくなって、何か著作を一つ探してきて夢中になって読みふける。
そういうことが、これまでに何度もあった。
そして、今回もまた、庄野潤三の『サヴォイ・オペラ』の中に、福原麟太郎の名前が登場しているのを見つけた僕は、福原麟太郎の作品を読みたくなり、久しぶりに古い随筆集を取り出してきた。
それが、本作『この世に生きること』である。
福原麟太郎という人は、本職は英語の先生で、英文学の紹介などでも有名だったが、戦後は随筆を書く人ということでも人気だったらしい。
もっとも、本書『この世に生きること』を読んでいると、1952年(昭和27年)の時点で、エッセイ集としては『新しい家』『猫』『われ愚人を愛す』くらいしかないと書いてある。
他に英文学についての著作もあるが、それは知識を書こうとしているものであって随筆ではない、と福原さんは考えていたのだ。
そういう、知識を主としないもので、この世に生きる話を、ぽそぽそと語り、人間というものは、おかしいものですな、とか、悲しいものですなという類のことを、沢山書いてみたいと思う。それがエッセイであり、随筆であると思うのだが、なかなかそれは出来ないものだし、たまに新聞雑誌からたのまれると、新制大学についてとか、パチンコの流行についてとか、題を指定されて、一言居士みたいなものになってしまった。それでエッセイ集が少ないのである。(福原麟太郎『この世に生きること』)
イギリスのエッセイスト、チャールズ・ラムを敬愛する福原さんにとって、随筆というのは、人間の笑いや悲しみに、しみじみと触れるものでなければならなかった。
昭和28年に書かれた「随筆について」という作品は、「ちかごろは、随筆がはやるというのだが、なるほど、随筆集がたくさん出るようである」という文章から始まっている。
世相批判、身辺雑記、思い出、社会批評、芸能界の話、科学随筆、女と酒、政界裏表など、各種入り乱れる状況を見て、一体随筆というのは何だろう?と考えるのが、この随筆のテーマである。
だが随筆というものは、そう思われているよりは、もっと文学作品のはずだと思う。古今の名作といわれるようなものは、何だか、ぴたっと貼りついたら、もう離れないような、芸術性を持っているようである。専門の文筆家の作であろうがなかろうが、出来上がったものはまごうかたなき文学だ、ということがあっても、差支えない。私はそのようなものを読みたい。(福原麟太郎『この世に生きること』)
戦後、気軽な随筆というものが流行しているのを見て、福原さんは苦々しく感じていたのかもしれない。
「私はユーモア随筆などというものの価値を信じない」とまで言い切っている。
「何か人間や自然や社会の話で、何かそこに一つの心の世界を書いてみせるといったもの」こそが、福原さんにとって、真の随筆であり、エッセイであった。
「私は、しみじみと心の話の出来る随筆家に出くわしたいのである」という一文が、この随筆を締めくくっているが、やがて、福原さんは「しみじみと心の話の出来る随筆家」として、歴史に名前を残すことになる。
異国情緒と旅の高揚感が伝わってくる旅行記
正面から人生と向き合うような文章もいいが、「思い出の記」(昭和29年)のような回想文もいい。
特に、かつて留学した思い出の地・ロンドン再訪記は、優れた紀行文となっている。
今は夏である。しかも好天気だ。街路樹も、家々を囲んで立っている木立も、みなこんもりと茂って、ロンドンを森の町にしていた。板塀が立って映画や芝居の広告が大きくはりつけてある中に、プロムナード・コンサートの番組が見える。これが夏の景物なのだ。──私はいく本も煙草をくゆらし、だんだん賑やかな市街になり、家が櫛比してくるのを眺めながら、凡そ一時間もかかったろうと思うほどバスの二階を堪能して、ハイド・パークを通り越して、ヴィクトリアの終点まで来た。(福原麟太郎『この世に生きること』)
別のところでは「紀行なら、のんきに書けるから書きたい。楽しいものだ。紀行文集などというものがあったら、うれしいだろうと思う」(「静かなる勝利を」)を書いているから、福原さんは、実際に紀行文が好きだったのだろう。
肩肘の張らない旅行記は、異国情緒と旅の高揚感が伝わってきて、実に楽しいものである。
こうした思いが、後に『諸国の旅』(1962)という形で結晶することになるのだ。
書名:この世に生きること
著者:福原麟太郎
発行:1954/9/20
出版社:文藝春秋新社