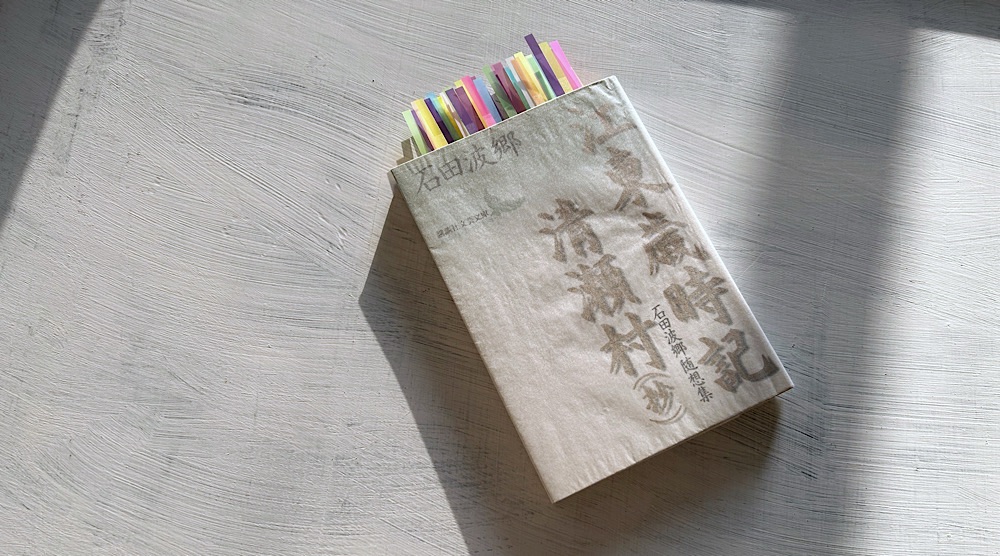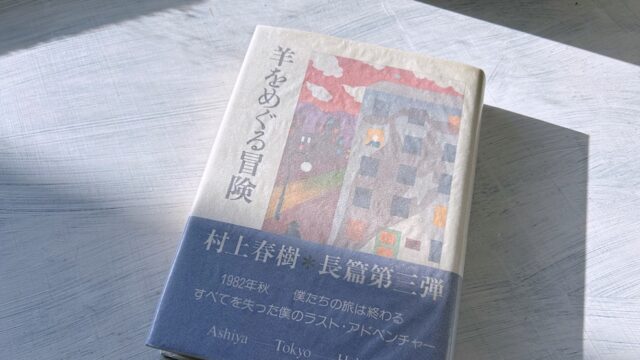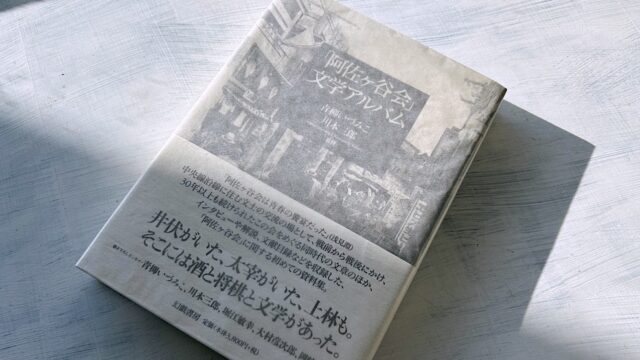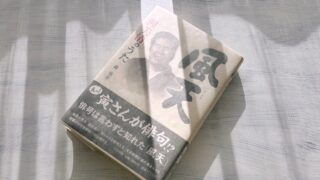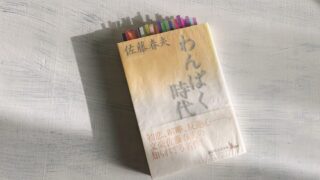石田波郷『江東歳時記・清瀬村(抄)』読了。
本作『江東歳時記・清瀬村(抄)』は、2000年(平成12年)10月に講談社文芸文庫から刊行された随想集である。
オリジナルは次のとおり。
「清瀬村」
・1952年(昭和27年)11月 四季社
「江東歳時記」
・1966年(昭和41年)7月 東京美術
・初出は、1957年(昭和32年)読売新聞江東版(連載)
オリジナル『江東歳時記』(1966)には、スナップ写真も収録されている。
下町情緒あふれる俳句散歩
ラズウェル細木『酒のほそ道』の主人公(岩間宗達)は、俳句と下町情緒が好きなサラリーマンで、粋な風流人に憧れている。
本作『江東歳時記・清瀬村(抄)』には、そんな岩間宗達が喜びそうな話が、たっぷりと収録されている。
例えば、「両国橋畔ももんじやで」(「猪(しし)吊れば夜風川風吹きさらし」)。
両国橋を渡ってくる自動車群のヘッドライトのはげしい流れがやや左へ曲がり気味に奔流する。この勢いに削りとられてしまう位置の右岸に、享保三年創業猪料理ももんじ屋がある。(石田波郷「江東歳時記」/『江東歳時記・清瀬村(抄)』)
『江東歳時記』には、江東区を実際に歩いたスケッチと俳句が収録されている。
猪料理「ももんじ屋」店主(八代吉田実)とのやり取りが加わるなど、俳句随想というよりもルポルタージュに近い側面もある。
吾妻橋では「神谷酒造」に立ち寄っている(「秋深み合へり巨樽通ひ樽」)。
吾妻橋の町並をゆくと、何か浅草の香が流れているようである。橋一つ隔てただけだからだろう。神谷バーの名と共にオールドファンにはなつかしいカクテル酒「電気ブラン」の製造元神谷酒造がここにあるのも不思議ではない。(石田波郷「江東歳時記」/『江東歳時記・清瀬村(抄)』)
酒と俳句と下町だから、これは、いかにも『酒のほそ道』の世界だ。
隅田公園にはビヤガーデンがあった(「葉ざくらの夜をまつごとビール園」)。
隅田ビヤガーデンは隅田公園の南端、東武電車の鉄橋のたもとにあり、すぐとなりはビール会社だ。(石田波郷「江東歳時記」/『江東歳時記・清瀬村(抄)』)
隅田公園といえば「言問団子」と「さくら餅」(「風あそぶ母子の髪やさくら餅」)。
隅田公園の北隅に、言問団子と長明寺のさくら餅が対峙している。花見客は、花など目に入らないような酔払いばかりではない。(略)酒を飲む人も飲まない人も、言問団子かさくら餅のいずれかを食べて帰るようである。(石田波郷「江東歳時記」/『江東歳時記・清瀬村(抄)』)
若き日の正岡子規が、このさくら餅屋の二階に下宿をして、娘(お六さん)と恋愛をしたと伝えられているのは、明治21年の夏のこと。
深川には、どじょう鍋の「伊せ喜」がある(「灯入れて葭戸透くなりどぜう鍋」)。
勤め帰りの男女や、近くの浴衣がけの家族ずれの客が多い。マルの鰌はどうもねというような食わずぎらいは土地ッ子にはいない。子供の時から食いなれているからだ。(石田波郷「江東歳時記」/『江東歳時記・清瀬村(抄)』)
同じく、深川森下町には馬肉専門の鍋屋があった(「暖簾割る夜寒の肩をつらねけり」)。
森下町の交差点を菊川町の方へ曲がると、すぐ左側に紺のれんに赤いサクラのマークに「なべ」の二字を白抜きにした「みのや」がある。(略)先代が美濃の国から出て、はじめは呉服屋をやっていたが、日露戦争後から此処に始めたという馬肉鍋専門の店である。(石田波郷「江東歳時記」/『江東歳時記・清瀬村(抄)』)
鍋物ばかりではない。
向島須崎町にはお好み焼き屋がある(「時雨るゝやよせやき冷ゆるさざめ言」)。
都鳥なく向島の三業地にも、百四十軒の料亭にまじって、戦前は二軒しかなかったお好み焼が、現在は七軒ある。時雨模様の夕景、その一軒「田川」を訪う。(石田波郷「江東歳時記」/『江東歳時記・清瀬村(抄)』)
お好み焼きは、路地の入口などにやってくる「どんどんやき」が、大人用に発展したものと書かれている。
江戸川尻では、鰻とりを見る(「葭原に梅雨あがるらし鰻筒」)。
ベカ舟の胴底には青藻にまじって鰻と鯊(はぜ)がひしめいていた。見ていると、三本に一本の鰻があがる。豊漁だ。(石田波郷「江東歳時記」/『江東歳時記・清瀬村(抄)』)
「ベカ舟」というと、山本周五郎『青べか物語』(1961)を思い出す。
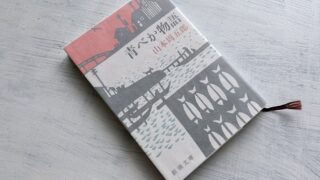
東京の川も、まだ、豊かな時代だったのだ。
葛西には、牡蠣を採る家があった(「牡蠣剥くやかげろふばかり海苔干場」)。
葛西には十軒ほど牡蠣を採る家があって、もちろ海苔のかたわら仕事。砂町の沖に夢の島という埋立地がある。戦争中は飛行場にでもする気だったのだろう。戦後はここに夢のような娯楽センターを作る計画もあったが、今は有名な鯊の釣り場になり、くずれた石垣に牡蠣がついている。(石田波郷「江東歳時記」/『江東歳時記・清瀬村(抄)』)
葛西には有名な襤褸市がある(「襤褸市や羽影すぎゆく春の鳶」)。
縞か絣、モンペ姿のおかみさんのはんらんだ。海苔がとれなければ蓮、白魚、田んぼなどで一年中商売になる土地だそうだ。が何といっても海苔の盛りの冬場がよい。(石田波郷「江東歳時記」/『江東歳時記・清瀬村(抄)』)
海岸には漁村があり、内陸部には農村があった。
溝川一つ越すと埼玉県という足立も外れの舎人町は「東京のチベット」とさえ呼ばれ「辺境視」されているが、すべて東京の目で見るからのこと、武州足立郡内一万石、関東群代伊奈氏の赤山陣屋から江戸への街道、赤山街道に沿う一農村とすれば、さして驚くにあたらない。(石田波郷「江東歳時記」/『江東歳時記・清瀬村(抄)』)
当時(高度経済成長期)の江東区には、まだ、農村が点在していたのだ(「足もとに暮るる牛蒡や牛蒡市」)。
足立区舎人町は、なにかと気になる存在である(「移動図書館穂草の風のあそぶなり」)。
舎人町は江東の極北である。江戸川、葛飾区の農地地帯とはちがった、東京の置き忘れられたところといった感じがあるが、それだけに心ものびのびとする清澄な空気だ。「きぼう号」はにわかに音楽を流しはじめた。(石田波郷「江東歳時記」/『江東歳時記・清瀬村(抄)』)
東京都内にも、移動図書館(きぼう号)があった。
葛飾区青戸四丁目には、ウサギの毛皮のなめし屋まである(「行く年やしづかに乾く兎皮」)。
晴れつづいて紺のふかい空に何百羽あろうか。大部分が白兎で、普通のザツというチンチラ、クロ、ゴマ、ブチの毛皮、それに緬羊が二頭。板塀の門に町内で立てたらしい竹が兎の前景になって風に吹かれていた。(石田波郷「江東歳時記」/『江東歳時記・清瀬村(抄)』)
映画『男はつらいよ』の舞台となった柴又も出てくる(「木洩れ日にきらめく獅子や秋祭」)。
十月十五日、秋晴の京成柴又駅は大変な降車客だ。これらの人々も八幡様の獅子舞を見にゆくのかなと思いながら歩いてゆくと、人の流れはそのまま帝釈天の参道へとつづいていた。庚申の日だったのだ。(石田波郷「江東歳時記」/『江東歳時記・清瀬村(抄)』)
柴又帝釈天の参道には団子屋が並んでいた(「草餅やをぐらき方の煙草の火」)。
一昨年(昭和三十年)帝釈天こと経栄山題経寺は大鐘楼堂を建立した。しかし江戸末期の庚申待の信仰が次第に失われてきた今日、かつての宵庚申の殷賑は懐古趣味の夢であろう。(略)かわらないのは草団子の素朴な匂いと味である。(石田波郷「江東歳時記」/『江東歳時記・清瀬村(抄)』)
『男はつらいよ』とくれば、「矢切の渡し」を忘れることはできない(「用もなく乗る渡舟なり猫柳」)。
犬を抱いた若妻、自転車を押した娘、臨月も近いような腹を風呂敷包でかくすように抱いた女、それぞれカメラをさげた青年群、そういう人々のわきから飛びうつる子供達。(略)上は葛飾橋、下は市川橋までの長い間隔は、この渡舟の利用価値を失わしめない。(石田波郷「江東歳時記」/『江東歳時記・清瀬村(抄)』)
秋元治『こち亀』にも登場する「お化け煙突」を詠んだ句もある(「お化け煙突隠れつ現(あ)れつヨツトの帆」)。
対岸の火力発電所の有名な四本煙突が二本に見えて、銀灰色の胴を西日にかがやかしている。二キロほど下流の日之出町先の常磐線わきの堤下では、今日武装警官まで出動してバタ屋部落の取りこわしがあった。(石田波郷「江東歳時記」/『江東歳時記・清瀬村(抄)』)
北原怜子『蟻の町のマリア』(1963)の世界が、ここにもあったのだ。
戦後と高度成長が混在する街
戦後は、まだ、至るところに傷痕を残していた。
特に「江東区」は、東京大空襲による戦災が著しく、戦後復興のために生まれた新しい区域だった。
亀戸普門院にある伊藤左千夫の墓も例外ではない(「墓の間に彼岸の猫のやつれけり」)。
戦火を浴びた左千夫の墓は剥落もはなはだしいが、中村不折の六朝風の「伊藤左千夫之墓」の文字は、すでに実となった大八ツ手に囲まれながら、はっきり残っている。(石田波郷「江東歳時記」/『江東歳時記・清瀬村(抄)』)
深川白河小学校は、春の種痘で賑わっていた(「種痘の児讃歌(ほめうた)のごと泣きはじむ」)。
高橋を渡りながら、十一年前満目荒涼たる焦土の中に行列を作って種痘をうけた日を思い起こした。「焼跡の植疱瘡の列あはれ(波郷)」貧しい飢えた民の群であった。(石田波郷「江東歳時記」/『江東歳時記・清瀬村(抄)』)
「江東歳時記」の連載が始まった1957年(昭和32年)といえば、まだ、終戦から12年しか経っていないのだ。
それは、決して「遠い記憶」ではなかったに違いない。
戦後、東京は凄まじい勢いで変貌を遂げた。
深川清澄庭園には、労働者の姿があった(「木瓜褪せて庭園春をふかめけり」)。
泉池の周りを、椿や木瓜の紅い花を混えた木立がくれにゆくと、東京都の失業対策事業の女人工達が十二、三人ほおかむり姿で道路清掃をしていた。亀戸職安深川分室から回されきた人々で、まだ三十過ぎの若い女もまじっている。(石田波郷「江東歳時記」/『江東歳時記・清瀬村(抄)』)
コントラストの激しい街、それが、高度経済成長期の東京という街だったのかもしれない。
太平町には精工舎の工場があった(「時計工いつせいに退けて梅雨上る」)。
精工舎は服部時計店の工場で、明治二十五年服部金太郎の創設、七馬力の蒸気動力を用い、掛時計と懐中時計側を製造したという。(石田波郷「江東歳時記」/『江東歳時記・清瀬村(抄)』)
砂町小学校は工場街にある(「夜を集ひ来てコーラスや返り梅雨」)。
新しく出来た、都電錦糸堀車庫砂町出張所のすじ向いに砂町小学校がある。雨つづきのぬかるみの道を学校横に入るとうすぐらく、工場街とも思えぬ静けさだ。そこだけ明るい小学校の一室からロシア民謡「ロマンス」の混声合唱がきこえてくる。(石田波郷「江東歳時記」/『江東歳時記・清瀬村(抄)』)
勤労青年の集いが、各地で賑やかな時代だった。
大島小学校の裏にはマネキン工場がある(「蠅とめてマヌカンの胸その腕(かひな)」)。
梅雨のうす日のさす大島小学校裏、中央工芸社では、工場の庭も狭しとバラバラのマネキン人形を干している。糊の乾く異臭がし蠅が群れとんではいるが、天日の下の裸女像はやはり異様に目を圧する。(石田波郷「江東歳時記」/『江東歳時記・清瀬村(抄)』)
下町といえば、やはり、工場街だったのだろう。
水上バスから見る隅田川は汚れていた(「炎天の筏はかなし隅田川」)。
隅田川の水は今は真黒で悪臭を放つが、炎天下でも船上の川風は快い。いつもくぐる橋の脚台に鳩が並んで涼をとっていた。汚い首都東京を批判しているのかもしれない。(石田波郷「江東歳時記」/『江東歳時記・清瀬村(抄)』)
急激な経済成長に、街も戸惑っていたのだ。
1960年代の東京には、過去と未来が微妙に混在していた。
千住三丁目では大八車を見かけることもある(「秋風や火床(ほど)やすめたる車鍛冶」)。
トラック、バス、乗用車を問わず自動車はおびただしく増えて、人間専用道路でも欲しい位だ。そういう中でまれに荷馬車や大八車を見かけると立止ってながめる程珍しい。(石田波郷「江東歳時記」/『江東歳時記・清瀬村(抄)』)
戦後の焼け跡と高度成長の未来が近在していた、昭和30年代の江東歳時記。
現代からは失われてしまった下町風景が、そこには残されている。
戦災については、『清瀬村』にも綴られている。
三月十日の朝の大空襲で城東区内の家は焼け、妻の母、二人の妹が死んで了った。同家に預けてあった僕の家のものも全部、応接間に置いてあったという二つの本棚も無くなった。(石田波郷「一冊の芭蕉全集」/『清瀬村』)
1945年(昭和20年)3月10日、東京大空襲の記憶が、ここにもある。
私は昭和二十一年三月十日、北砂町一丁目の現在のところに、北埼玉の利根川べりの疎開先から移ってきた。戦争は終っていた。満目焦土のただ中である。(石田波郷「砂町ずまい」/『清瀬村』)
その後、間もなく、作者(石田波郷)は、結核に倒れる。
昭和二十二年八月三十一日のことである。(略)たしかその日のひるすぎ吉祥寺の成蹊高校(今は大学になったが)に中村草田男氏を訪ねた。(石田波郷「蜩」/『清瀬村』)
それから4年。
作者は、清瀬村にて長い闘病生活を送る。
「波郷君よかったな。早く元気になって大いに飲み、またいっしょに旅に出ようじゃないか」(略)私はもう一度思うまま酒を飲みたいとは考えていない。しかし旅はしてみたい。(石田波郷「蜩」/『清瀬村』)
「木曽路」は、島崎藤村の『夜明け前』の舞台を訪ねた、戦前の紀行随筆である。
石ころの多い、実り薄い、狭い田がそこらに広がっていた。屋根石を置いた家。定紋をつけた白壁の土蔵。恵那山をみはるかす街道に沿って、すべては「夜明け前」の通りに在った。(石田波郷「木曽路」/『清瀬村』)
本作『清瀬村』は、戦後の復興と作者の病気からの回復が重ね合わせて描かれている、復活の文学として読むことができる。
戦後という時代、東京も、病気の俳人も、必死で生きていたのだ。
書名:江東歳時記・清瀬村(抄)
著者:石田波郷
発行:2000/10/10
出版社:講談社文芸文庫