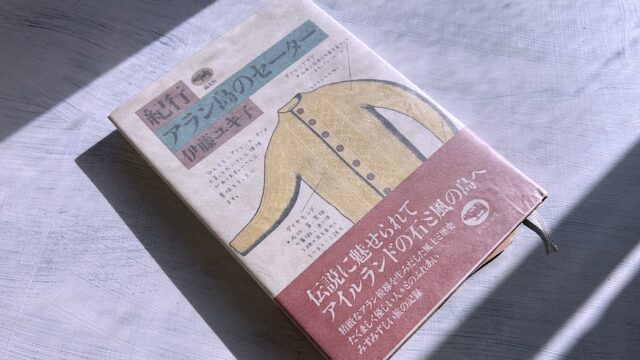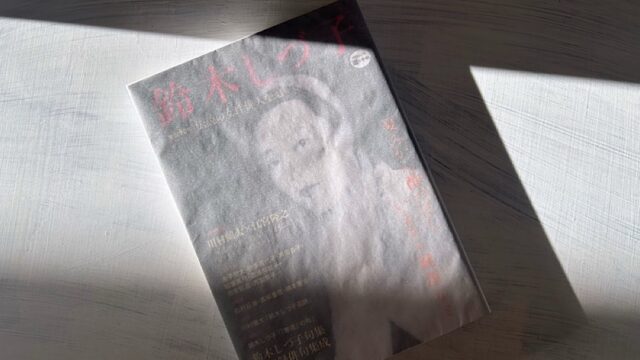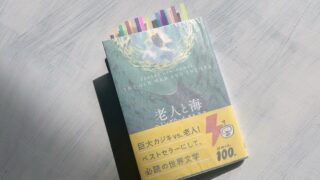小沼丹『黒いハンカチ』読了。
本作『黒いハンカチ』は、1958年(昭和33年)8月に三笠書房から刊行された連作短篇小説集である。
この年、著者は40歳だった。
初出は、1957年(昭和32年)4月~1958年(昭和33年)3月『新婦人』(連載小説)。
収録作品は、次のとおり。
・指輪
・眼鏡
・黒いハンカチ
・蛇
・十二号
・靴
・スクェア・ダンス
・赤い自転車
・手袋
・シルク・ハット
・時計
・犬
イギリス文学の影響
小沼丹は英文学者である。
ミステリー小説の中にも、イギリス文学の匂いがする。
例えば、主人公(ニシ・アズマ)の勤めるA女学院の院長(タナカ女史)には「有名な文人の警句なぞを引用する癖」があった。
或るとき、女性にとって良き料理人たることが如何に大切か、を強調するの余り、彼女はイギリスの文人ジョンソン博士の言を引用した。曰く、「男は概して、細君がギリシャ語なんか喋るより、食卓に美味い料理が並ぶ方が嬉しいものなのだ」と。(小沼丹「眼鏡」)
ジョンソン博士については、福原麟太郎『ヂョンソン大博士』(1969)に詳しい。

イギリス人は話をするときに、ジョンソン大博士の言葉を引用することを好んだというから、A女学院のタナカ女史もイギリス流だったのかもしれない。
タナカ女史は、イギリスの作家(ジョージ・エリオット)の言葉も引用している。
彼女は先ず、ジョオジ・エリオットの言葉を引用して先生連中を煙に巻いた。曰く、「私(これはエリオットである)は女が莫迦であることを否定しません。全能の神様は女を男に似つかわしく造られたのです」と。(小沼丹「眼鏡」)
ジョージ・エリオットの『サイラス・マーナー』(1861)は、イギリス帰りの夏目漱石が、東京帝国大学の授業で紹介したことで有名な作品である。
イギリス贔屓らしいタナカ女史の引用は、スイフトにも及んでいる。
すると、タナカ女史は日頃の癖を出してこう云った。「スイフトが云っているわ、いい手が来る迄はカアドの切り方が悪いと文句を云わねばならない、って」「誰?」とナカダ女史が訊いた。「スイフトって?」「ガリバア旅行記の作者よ」「ああ、あのお伽話書いたひと?」「お伽話じゃありませんよ。あれは……あら」(小沼丹「眼鏡」)
小沼丹は、1951年(昭和26年)3月に小峰書店から『ガリヴア旅行記』(少年少女のための世界文学選4)を出版している。

日本では児童文学として知られている『ガリヴァー旅行記』だが、本来は、現代社会をシニカルに描いた風刺文学である。
「お伽話じゃありませんよ。あれは」というタナカ女史の言葉には、しっかりとした作者の主張があるのだ。
タナカ女史が引用する英文学は、そのまま、小沼丹自身のものだったかもしれない。
アメリカ文学の引用もある。
最后に、のっぽ自身はニシ・アズマと一緒に女子大学を出た友人で、スミスと呼ばれていた。と云っても彼女が純粋の日本人じゃないと云う訳では無い。それは専ら「蚊トンボ・スミス」に由来するらしかった。(小沼丹「蛇」)
アメリカの女流作家(ジーン・ウェブスター)の代表作『あしながおじさん』(1912)を『滑稽小説 蚊とんぼスミス』(1919)と訳して日本へ紹介したのは、東健而(ひがし・けんじ)である。
小沼丹は、この「蚊トンボ」がお気に入りだったらしく、『青の季節』(1956)にも「蚊トンボ」と呼ばれる少女が登場している(『お下げ髪の詩人(小沼丹未刊行少年少女小説集 青春篇)』所収)。
https://gentle-land.com/osage-gami-no-shijin/
山で亡くなった恋人を思って、ニシ・アズマがつぶやく詩は、ドイツの詩人(オイゲン・クロアサン)の『秋』だった。
いま、デック・チェアに凭れて、遠い連邦を見ていると、その頃読んだ詩の一節が甦って来たりした。──今日つくづくと眺むれば、悲しみの色口にあり。(小沼丹「十二号」)
オイゲン・クロアサンの「秋」を訳して『海潮音』(1905)に収録したのは、東京大学の講師(上田敏)である。
上田敏の詩集『海潮音』は、ドイツの詩人(カール・ブッセ)の『山のあなた』(山のあなたの空遠く「幸(さいわい)」住むと人のいう、が有名)や、フランスの詩人(ポール・ヴェルレーヌ)の『落葉』(秋の日のヰ゛オロンのためいきの身にしみて、で有名)などで知られている。
そもそも、上田敏も英文学者なので、小沼丹の源流的な存在の一人と言えなくもない。
島崎藤村の自伝的青春小説『春』(1909)にも、上田敏は「福富」として登場している。
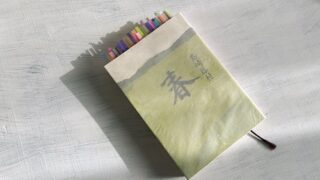
登山の遭難事故で死んだ恋人を思い出す「十二号」では、ドイツの詩人(ハイネ)の詩が重要な役割を担っている。
ニシ・アズマは遠い連峰を眺めて云った。「ね、こんな詩知ってる? 今日つくづくと眺むれば、悲しみの色口にあり、って云うの」「知らない。誰の詩?」「誰だったかな? 忘れちゃった」(小沼丹「十二号」)
もちろん、彼女は、その死の作者を忘れたわけではなかっただろう。
彼女は、ただ、死んだ恋人の記憶を忘れたくなかっただけなのだ。
主人公の女教師(ニシ・アズマ)は、表題作「黒いハンカチ」でも、ハイネの詩に触れている。
開け拡げた窓からは五月の爽やかな風が流れ込んだ。(略)「ね、美しき五月になれば、とかって云う詩が無かった?」(小沼丹「黒いハンカチ」)
ハイネの「美しき五月」は、林房雄の小説『美しき五月となれば』(1938)にも引用されていた。
美しき五月となれば
花々の蕾ほころび
ほのぼのとわが胸のうち
恋の花ほころびそめぬ。
美しき五月となれば
野辺に鳴く小鳥のごとく
われもまた胸の思いを
かの人に告げて歌いぬ
(林房雄「美しき五月となれば」)
林房雄は、小沼丹の短編小説「四十雀」(『木菟灯籠』所収)の主役でもあるから、小沼丹ワールドは、至るところで繋がっているとも読める。

ニシ・アズマが、ハイネの詩を愛誦しているのは、当時の女性読者を意識していたということもあるのだろう。
イギリス・ミステリーの古典といえば、コナン・ドイル『シャーロック・ホームズ』である。
彼女に云わせると、その街の地図は他でもない、ロンドンはベエカア街を示すものに他ならなかった。ベエカア街、に加うるにパイプ、短刀、拡大鏡と来ると、S・H氏は余人ならぬシャアロック・ホオムズ先生を指すことになる筈であった。(小沼丹「靴」)
本作『黒いハンカチ』には、連載時、「ある女教師の探偵記録」というキャッチコピーが添えられていたという。
小柄でかわいらしい女教師(ニシ・アズマ)の活躍ぶりは、そのまま、この『黒いハンカチ』の魅力となっている。
ジャンルを越えた小沼丹ワールド
本作『黒いハンカチ』はミステリー小説だが、随所に小沼丹らしい文章が挿入されている。
それは小さな時計屋であった。と云うよりは、みすぼらしい時計屋と云った方が良かった。彼女は黙ってその店の奥にいる主人を見た。片眼に覗眼鏡を嵌込んで時計を覗込んでいる猫背の男を。店の前には五つぐらいの女の子がしょんぼり立っていた。(小沼丹「指輪」)
女探偵として活躍する主人公の女教師(ニシ・アズマ)は、軽いフットワークで事件を解決していくが、彼女が見ているものは、実は犯罪ではない。
彼女の目は、犯罪に踏み切らねばならなかった人々の方へと向いている。
推理マニアの主人公が、トリックにばかり注目する探偵小説とは、その点、趣きが異なっている。
山の中腹を上り列車が通っていた。ニシ・アズマは何度か列車の窓からこの入江を見降したことがある。列車は忽ちの裡に、この入江を見捨ててしまう。そしてニシ・アズマ自身、この入江に自分がボオトを浮べるなんて夢にも思わなかった。いま、誰かあの汽車からこの入江を、このボオトを見ている筈だけれども、その人は何を考えているのだろう?(小沼丹「蛇」)
小沼丹の小説の登場人物たちは、時々ふと人生を振り返ってみる。
なぜなら、作家が小説を書く意味というのは、案外そんなところにあるかもしれないからだ。
いつだったか、雨の降る夜、この道を二人の若い男が歩いていたことがある。二人は、一本の傘に肩を並べて、街燈の灯の濡れる甃の道を歩きながら、「何だか、如何にも秋と云う感じじゃないか」「うん、全く秋らしい道だね」なんて話していた。(小沼丹「スクェア・ダンス」)
まるで、小沼丹の随筆を読んでいるかのような味わいが、この物語にはある。
おそらくは、作者自身の体験が、そのまま小説の中へ投入されていて、ひとつ筋の通った小沼丹ワールドを展開しているのだろう。
いい傘には違いなかった。何しろ、ワダの伯父さんなる人物がイギリスはロンドンで買い求めた代物だったから。尤も、買い求めたのは既に三十年も昔の話である。(小沼丹「赤い自転車」)
細部を読みこんでいくと、エンターテインメントではない小沼丹の小説を読んでいるのと違和感がない。
そういう意味では、小沼文学の世界で、純文学とかエンタメとかミステリーとか、ジャンル分けをすることに、あまり意味はないような気がしてくる。
小沼丹の小説は、つまり、小沼丹の小説でしかないのだから。
小沼丹のミステリー小説『黒いハンカチ』が長く愛されているのも、結局のところ、それが、小沼文学であるということに尽きるのではないだろうか。
英文学に影響を受けた小沼丹の小説は、ユーモアとペーソスを重要な価値観としている。
軸がしっかりとしているから、どんなジャンルの小説を書いても、それは、小沼丹の小説として読むことができる。
「黒いハンカチよ」とニシ・アズマは云った。「それだけよ」「黒いハンカチですって?」「ええ、黒いハンカチ。あたし、教場にいたとき、あの女が廊下を通るのを見たの」(小沼丹「黒いハンカチ」)
石原裕次郎『赤いハンカチ』を思わせる表題作は、1957年(昭和32年)6月『新婦人』に発表された作品である。
石原裕次郎のシングル『赤いハンカチ』は、1962年(昭和37年)に発売されているから、『黒いハンカチ』の方が5年も早い。
謎を呼ぶタイトルは、女性読者の興味を、さぞかしそそったことだろう。
書名:黒いハンカチ
著者:小沼丹
発行:2003/07/11
出版社:創元推理文庫