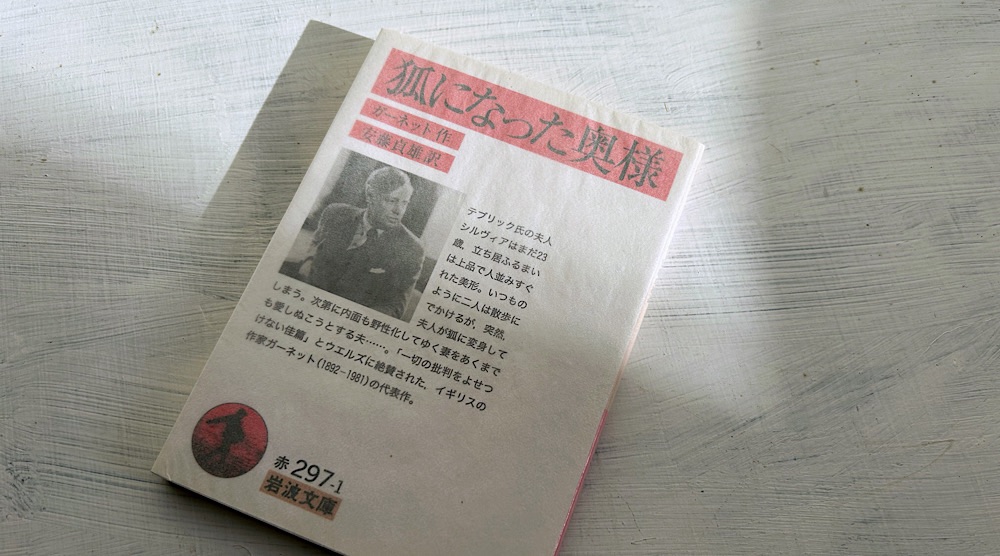デイヴィッド・ガーネット「狐になった奥様」読了。
本作「狐になった奥様」は、1922年(大正11年)に刊行された長篇小説である(デビュー作だった)。
この年、著者は30歳だった。
ジェイムズ・テイト・ブラック記念賞及びホーソンデン賞受賞。
庄野潤三も好きだった『狐になった奥様』
庄野潤三の文章には、何度か、この『狐になった奥様』が登場している。
私が大阪で放送会社に勤めていたころ、文学好きの同僚に『狐になった奥さま』の話をしたことがある。そのとき、この夫の朗読と鳥かごの鳥に注がれる妻の視線のことを身ぶりを入れて、つまり、夫と狐になった奥さまの一人二役を演じて、話して聞かせたのを覚えている。(庄野潤三「ピアノの音」)
庄野さんの本を読んだとき、『狐になった奥様』というのは、きっとほのぼのした楽しい小説なんだろうなと思ったような気がするが、実際に読み終えてみて、これはとても重い小説だということが分かった。
しかも、シャレにならないくらい、重い小説。
解説の言葉を引用すると、本作『狐になった奥様』は、「雑木林を散歩中に不意に一匹の狐に変身した若い妻を愛し抜こうとする男の物語」である。
二人が雑木林のはずれにたどりつかないうちに、シルヴィアは、いきなり、夫の手をとても激しく振りほどいて、ギャッと叫んだ。それで、テブリック氏は、すぐさま振り返った。ついさっきまで妻がいたところに、燃えるような赤毛の小さな狐がいた。(デイヴィッド・ガーネット「狐になった奥様」訳・安藤貞雄)
愛妻シルヴィアが狐になってしまった原因は、まったく分からない。
とにかく、ただ突然に、彼女は狐へと変身してしまったのだ。
「あらゆる国、あらゆる時代に、あらゆる人種のあいだで、欺瞞と奸智と狡猾さで知られる狐」になってしまった妻を、テブリック氏は愛し抜くことができるのだろうか
それが、本作『狐になった奥様』のテーマである。
そして、この難題は、夫婦間の永遠の愛が試されているものとして読むことができる。
何があっても、夫は妻を愛し続け、妻は夫を愛し続けることができるのか。
狐になった妻は、夫婦間に起きるかもしれないすべての変化の、最も大きなメタファーなのだ。
人間であることを捨ててまで、一匹の雌狐を愛し続ける
テブリック氏は、狐になった妻を愛し続ける。
「よしんば、きみが狐であっても、ほかのどの女性よりもきみといっしょに暮したいんだ。誓って言う、きみが何に姿を変えたとしても、わたしの気持ちは変わらないよ」(デイヴィッド・ガーネット「狐になった奥様」訳・安藤貞雄)
しかし、テブリック氏に与えられた人生の試練は厳しい。
狐となったシルヴィアは、次第に人間らしさを失っていき、ついにはまるきり獣の姿となって、テブリック氏を失望させる。
さらに、森の中へ逃げ込んだシルヴィアが、やがて子狐を連れて戻ってきたときの驚愕。
野生の狐に最愛の妻を寝取られてしまった男の絶望。
このあたりは、他の男と不倫関係に陥り、その男の子どもを産んでしまった妻を愛することができるかという、人間世界でよくあるような問題が提示されているようにも思われる。
嫉妬や苦悩に苛まれつつも、テブリック氏は人間という存在を乗り越えて、純粋に狐を愛することを決意する。
一匹の雌狐を愛し、狐の子どもたちを愛するテブリック氏の献身的な姿は、もはや悲劇を越えて感動的でさえある。
そして訪れる最悪のラストシーン。
その瞬間、絶望の悲鳴が、駆けつけた狩猟隊員全員の耳にとどいた。かれらは、あとから、その声は男性の声というよりも、女性の声に似ていた、と断言した。とはいえ、それが果たしてテブリック氏だったのか、それとも、突然声をとりもどしたかれの妻だったのか、はっきりした証拠はひとつもなかった。(デイヴィッド・ガーネット「狐になった奥様」訳・安藤貞雄)
妻が人間に戻るのを待つより先に、狐の生活へと同化していったテブリック氏の変化には、考えさせられるものがある。
なぜなら、テブリック氏は、人間であることを捨ててまで、一匹の雌狐と生活を共にしようと考えていたのだから。
最初のイメージとは違ったけれど、庄野さんが好きだった理由も分かるような気がした。
書名:狐になった奥様
著者:デイヴィッド・ガーネット
発行:2007/6/12
出版社:岩波文庫