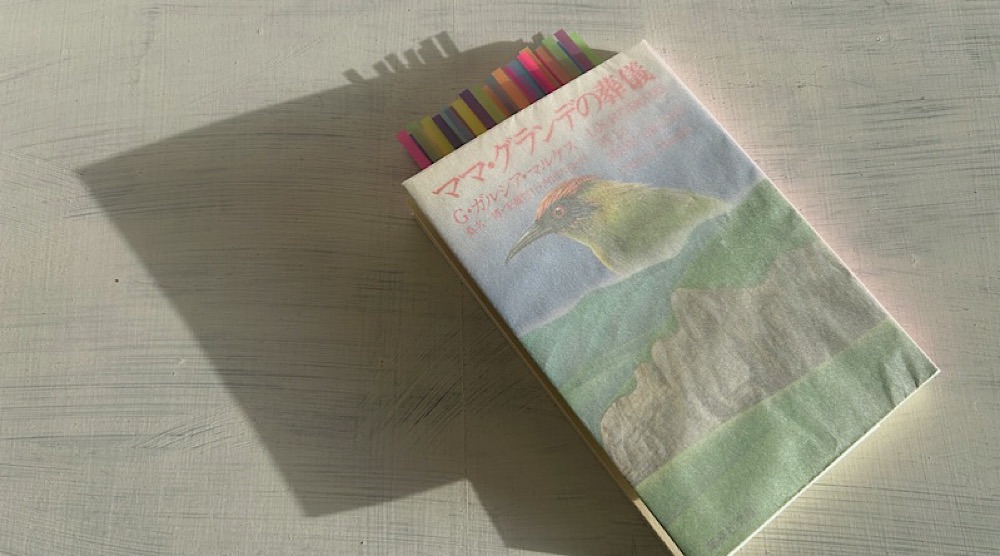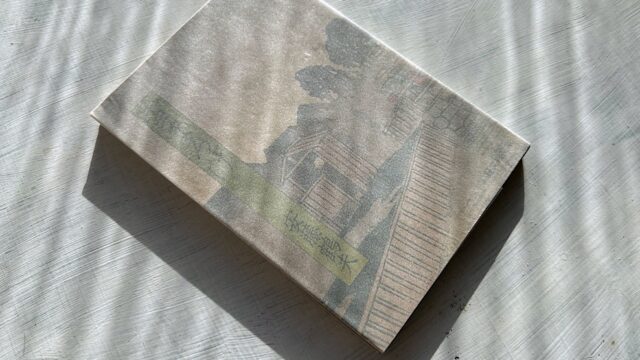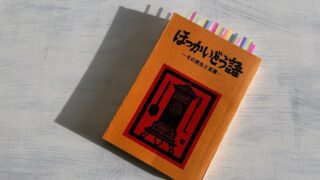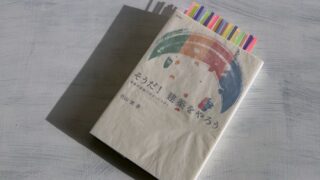ガブリエル・ガルシア=マルケス『ママ・グランデの葬儀』読了。
本作『ママ・グランデの葬儀』は、1982年(昭和57年)12月に集英社文庫から刊行された短篇小説集である。
この年、著者は54歳だった。
収録作品は次のとおり。
・大佐に手紙は来ない
・火曜日の昼寝
・最近のある日
・この村に泥棒はいない
・バルタサルの素敵な午後
・モンティエルの未亡人
・土曜日の次の日
・造花のバラ
・ママ・グランデの葬儀
・解説(桑名一博)
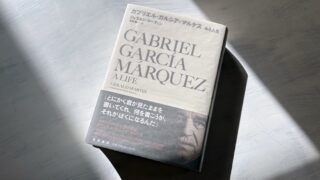
孤独を乗り越えた男の再起
ガルシア=マルケスの短篇小説集は、次のとおりである。
①青い犬の目(1962)
②ママ・グランデの葬儀(1962)
③純真なエレンディラと邪悪な祖母の信じがたくも痛ましい物語(1978)
④十二の遍歴の物語(1992)
集英社文庫版『ママ・グランデの葬儀』には、ガルシア=マルケス二作目の短編小説集『ママ・グランデの葬儀』に加え、初期の中編小説『大佐に手紙は来ない』(1961)を加えた構成となっている。
代表作『百年の孤独』の刊行が1967年(昭和42年)だから、『ママ・グランデの葬儀』には『百年の孤独』以前のガルシア=マルケスが収録されている、ということになる。
ガルシア=マルケスと言えば、現実世界ではあり得ないことが当たり前のように描かれる「マジック・リアリズム」が有名だが、『ママ・グランデの葬儀』は「マジック」の付かない「リアリズム小説」である。
マジック・リアリズムを取得する以前のガルシア=マルケスの小説が、ここにはある。
最も読みごたえのあるのは、中篇小説『大佐に手紙は来ない』だ。
荒廃した社会で、政府からの軍人恩給を待ち続ける老夫婦の暮らしが、この作品では描かれている。
「みんなそうしたものですよ」と、彼女はつぶやいた。「あたしたちだって生きながら腐っていくようなもんですから」(ガブリエル・ガルシア=マルケス「大佐に手紙は来ない」)
彼らの息子(アグスティン)は、反政府的な行為の疑いによって、政府軍に銃殺されていた。
「選挙のためにあなたに約束してくれたことを二十年も待ちつづけ、その結果あたしたちにのこされたのは死んだ息子がひとり」彼女はつづけた。「死んだ息子がひとりだけよ」(ガブリエル・ガルシア=マルケス「大佐に手紙は来ない」)
彼らに残されたものは、息子が大切にしていた軍鶏だけだった。
貧しい彼らは、軍鶏を売り飛ばそうと何度も考えるが、死んだ息子を象徴する軍鶏を手放すことができない。
「革命」という高い志を持ちながら、大佐の暮らしはどんどん行き詰まっていく。
「大佐にはなにもきてませんか?」大佐ははっとした。局長は袋を肩にかつぐと、台を降り、むこうを向いたまま答えた。「大佐に手紙はきませんよ」(ガブリエル・ガルシア=マルケス「大佐に手紙は来ない」)
届くことのない軍人恩給は、大佐にとって、(来るはずのない)新しい時代そのものだったかもしれない(「これは物乞いじゃない」「われわれは国を救うために骨を折ったんだ」)。
革命に破れた男たちの孤独が、この物語からは浮き上がってくる。
「わしの場合はそうじゃなかった」と大佐は言った。彼は自分が孤立していることにはじめて気がついた。「わしの仲間たちは郵便を待ちながら死んでいきましたよ」(ガブリエル・ガルシア=マルケス「大佐に手紙は来ない」)
「マコンド地区」の革命軍の出納責任者だった大佐は、内戦の資金を入れたトランクを背負って、苦しい旅をしたことがある。
「マコンドの会議で、われわれがアウレリアーノ・ブエンディーア大佐に降伏を思いとどまるよう進言したとき、たしかにわれわれが正しかったと考えていたんだ。なにもかもだめになりはじめたのはあれがきっかけだからな」(ガブリエル・ガルシア=マルケス「大佐に手紙は来ない」)
やがて、長篇『百年の孤独』となるパーツを、この物語でも読むことができる。
『百年の孤独』のようにマジック・リアリズムではないが、ガルシア=マルケスらしい表現力が、この中篇小説の魅力となっている。
「あの靴は孤児がはいてる靴みたいだからな」と文句を言った。「あれをはくといつも孤児院から逃げ出してきたような気になるんだ」「あたしたちは息子に死なれた孤児みたいなものですよ」と夫人が言った。(ガブリエル・ガルシア=マルケス「大佐に手紙は来ない」)
希望を待ち続けるだけでは、新しい未来を手にすることはできない。
そのことを誰よりも知っているのが、主人公の大佐だった。
「間違いなく今日着くはずだったんだ」と大佐は言った。郵便局長は肩をすぼめた。「間違いなく来るのは死だけですよ、大佐」(ガブリエル・ガルシア=マルケス「大佐に手紙は来ない」)
失敗した革命に対する後悔は、人生にやり残したことを、そのまま意味している。
それでも、大佐は人生を放棄することはない。
「言ってちょうだい、あたしたちはなにを食べればいいの?」大佐は七十五年の歳月──その七十五年の人生の一分、一分──を要して、この瞬間に到達したのであった。「糞でも食うさ」(ガブリエル・ガルシア=マルケス「大佐に手紙は来ない」)
「糞でも食うさ」という言葉には、軍人恩給にすがりついて生きる人生を放り投げて、自ら、新しい人生を自ら獲得しようという開き直りが見える。
だからこそ、「そう答えたとき、彼はすっきりとした、すなおな、ゆるぎない気持ちであった」という最後の一文が、大きな意味を持ってくるのだ。
降伏によって得られるはずだった軍人恩給への希望を捨てて、今、大佐は、新しい希望を手に入れようとしている。
おそらく、ここから始まる新しい物語があったはずだ(それは、おそらく革命という名前の)。
そう考えたとき、革命がどのようにして生まれてくるのかという「革命前史」こそが、この物語の隠されたテーマだったことに気付く。
さらに、眠っていた意識が目覚め、抵抗と反逆の感情が生まれてくる。ガルシア=マルケスにとって、つねに何よりも大切な人間の尊厳が、ここにおいて回復されるのである。(ジェラルド・マーティン「ガブリエル・ガルシア=マルケス ある人生」木村榮一・訳)
終わりを書いているように見せながら、実は、始まりを書いているのだというところに、この物語の秘密がある。
抑圧された社会で生きる男の孤独は、そのまま、革命という戦いへとつながっていくものだったのだ。

腐敗した社会で生きる貧しい人々
短篇小説集『ママ・グランデの葬儀』にも良い作品が多い。
彼はサウス・ケンジントンにあるホテルの狭い一室で六週間ほど過ごした。その間に書いていたのは『悪い時』ではなく、そこから派生したいくつかの短篇で、のちに短篇集『ママ・グランデの葬儀』に収められて読者から愛されることになる。(ジェラルド・マーティン「ガブリエル・ガルシア=マルケス ある人生」木村榮一・訳)
泥棒に入ったために殺された息子の墓を訪ねる母親の物語『火曜日の昼寝』もいい。
『火曜日の昼寝』は、作者自身による評価も高い作品だった。
彼は何度も、この作品は自分の最高の短篇であると同時に、「もっとも個人的な」作品だと思うと言っている。(ジェラルド・マーティン「ガブリエル・ガルシア=マルケス ある人生」木村榮一・訳)
この物語は、少年時代の記憶と体験の中から生まれてきた作品だったかもしれない。
「先週ここで殺された泥棒です」と女は同じ調子で言った。「私は母親なんです」(ガブリエル・ガルシア=マルケス「火曜日の昼寝」)
町の人々は「泥棒は殺されて当然だ」と考えている。
一方で、母親は、息子を泥棒へと追いやった社会の誤りについて考えている。
その後で彼女は、コンクリートの歩道で金属的な衝撃音がするのと、たいへん低くて穏やかだが、恐ろしいほど疲れ切った声が、「ああ、お母さん」と叫ぶのを聞いた。(ガブリエル・ガルシア=マルケス「火曜日の昼寝」)
貧しい生活を強いられていた息子は、生きるために、やむなく泥棒に入りこんだのだ。
母親の毅然とした姿勢は、間違った社会に対する挑戦として読んでいい。
この短篇は、記憶に残っている少年時代のある出来事をもとにして生まれた。ある時、誰かが「あの盗人の母親が来たぞ」と叫ぶ声を耳にし、気の毒な女性がアラカタカの大佐の家の前を通りかかるのを子供だった彼は目にした。(ジェラルド・マーティン「ガブリエル・ガルシア=マルケス ある人生」木村榮一・訳)
『最近のある日』は、貧しい歯医者と村長の物語。
「中尉、あんたはこの歯でわが方の二十名の死者の償いをするんだな」(ガブリエル・ガルシア=マルケス「最近のある日」)
村長は内戦の勝者であり、歯医者は内戦の敗者である。
「勘定をまわしてくれ」と彼は言った。「あんたにですか、それとも役場の方に?」村長は彼の方を見なかった。村長はドアを閉めると金網越しに言った。「どっちだって同じさ」(ガブリエル・ガルシア=マルケス「最近のある日」)
「どっちだって同じさ」という村長の台詞は、腐敗した行政を象徴する言葉だっただろう。
『この村に泥棒はいない』も、貧しい人々の暮らしを描いた作品だ。
「村から村へと渡り歩くんだ」とダマソは続けた。「ひとつの村で玉突きの球を盗んで、別の村でそれを売るんだ。どの村にも玉突き場はあるからな」(ガブリエル・ガルシア=マルケス「この村に泥棒はいない」)
ビリヤードは、南米の貧しい街で生きる人々の、ささやかな憩いだった。
盗んだ球を返したダマソは、盗んでいないお金の罪まで背負わされてしまう。
「分ってるんだろ、何もなかったってこと」ドン・ローケはあいかわらず笑みを浮かべていた。「二百ペソ、あったんだよ」(ガブリエル・ガルシア=マルケス「この村に泥棒はいない」)
ありもしない現金のことを主張するドン・ローケは、人々の心の貧しさまで象徴している。
そして、人々の心をこんなにも卑屈なものにしてしまったのは、間違った政治なのだという強い信念が、この物語からは感じられる。
『バルタサルの素敵な午後』でも、貧しい人々と豊かな人々との暮らしぶりが、対照的に描かれている。
主人公(バルタサル)は、ペペ少年に依頼された立派な鳥籠を完成させて、ホセ・モンティエルの家へ持っていくが、金持ちのドン・ホセ・モンティエルに追い帰されてしまう。
「金持ちどもが死んでしまう前にたくさん作ってみんな売りつけてやるんだ」彼は酔払って前後不覚になって喋っていた。(ガブリエル・ガルシア=マルケス「バルタサルの素敵な午後」)
金持ちの愚かさと、貧しい人々の愚かさが、同時に描かれているところが、この短篇小説のポイントだろう。
『モンティエルの未亡人』では、その金持ちのドン・ホセ・モンティエルが死んだ後に遺された未亡人が主人公となっている。
「あなたにいつも言ってたでしょう、ホセ」と彼女はひとりごとを言った。「この町の人たちは恩知らずなんだって。まだ、あなたのお墓が建つか建たぬかの間に、もう世間の人たちは背中を向けてしまったんだからね」(ガブリエル・ガルシア=マルケス「モンティエルの未亡人」)
金持ちの独りよがりな孤独は、むしろ、ユーモラスでさえある。
「私はいつ死ぬのでしょうか?」ママ・グランデが頭を上げた。「おまえの腕がだるくなったときだよ」(ガブリエル・ガルシア=マルケス「モンティエルの未亡人」)
ロザリオを持つ未亡人の腕は、実際のところ、信心に耐えられるようなものではない。
彼女の腕は、とっくに「だるくなっていた」のだ。
『土曜日の次の日』も、長篇『百年の孤独』へと連なる短篇小説だ。
アントニオ・イサベル神父が毎日駅へ来るという習慣は、たぶんその頃に始まったのだろうが、その習慣は、労働者たちが機関銃で掃射され、バナナ園が廃止され、それと共に百四十輛の貨車も無くなり、誰も乗せてこなければ、また誰も乗せて行かない、黄色い埃っぽい列車だけになった今日まで、相変わらず続いていたのである。(ガブリエル・ガルシア=マルケス「土曜日の次の日」)
バナナ農園労働者の虐殺事件が、この物語でも語られている。
「そうに違いない」と、彼女は内臓から上がってくるような声で言った。「なぜ鳥が死ぬのかこれで分ったわ」(ガブリエル・ガルシア=マルケス「土曜日の次の日」)
『造花のバラ』は、盲目の祖母と暮らす女の子(ミナ)の物語である。
「ミナ」と盲目のおばあさんが言った。「幸せになりたかったら、よそ者とはつきあわないことだよ」(ガブリエル・ガルシア=マルケス「造花のバラ」)
ミナの傷心を見抜く盲目のおばあさんは、不思議な存在だ。
現実を超越したものに対する強い関心が、この物語からは感じられる。
表題作『ママ・グランデの葬儀』は、本作品集の中では異色の作品と言っていい。
全世界の不信心な者たちよ、これは、九十二年間にわたって統治者として生き、去る九月のある火曜日、徳望を謳われて他界し、その葬儀には法王が参列したというマコンド王国の絶対君主、ママ・グランデにまつわる真実の物語である。(ガブリエル・ガルシア=マルケス「ママ・グランデの葬儀」)
この物語は、絶対的な独裁者の死と葬儀を神秘的に描きつつ、その愚かさを浮き彫りにさせていくという、逆説的な物語である(いわば「ほめ殺し」に近い)。
その中世的な光景は当時、一家の過去の思い出であったばかりでなく、国の過去のそれでもあった。(ガブリエル・ガルシア=マルケス「ママ・グランデの葬儀」)
独裁者の思い出は、国家の歴史でもある。
同時に、それは、独裁者を支える愚かな国民の歴史でもあったかもしれない。
モデルとなっているのは、作者の祖国コロンビアだった。
キューバ革命後のガルシア=マルケスの作品「ママ・グランデの葬儀」のテーマは、コロンビアに限定されていた。(ジェラルド・マーティン「ガブリエル・ガルシア=マルケス ある人生」木村榮一・訳)
華々しいママ・グランデの葬儀は、民衆の愚かさの象徴でもある。
絶対君主も、独裁政権という国家も、盲従する大衆たちも、すべては互いに支え合って維持されているものだ。
そこに、作者(ガルシア=マルケス)の苛立ちがある。
明日水曜日には掃除夫たちが来て、ママ・グランデの葬儀で出たゴミを、未来永劫にわたり掃き去ってしまうであろう。(ガブリエル・ガルシア=マルケス「ママ・グランデの葬儀」)
絶対君主が歴史に残すものなど何もない。
残るのは民衆の虚しさだが、盲従する民衆には虚しささえ感じられなかっただろう。
「ママ・グランデの葬儀」は、ガルシア=マルケスの自国の状況に対する憤りと、四年間外国で暮らしたあと帰国して感じた失望から生まれてきた。(ジェラルド・マーティン「ガブリエル・ガルシア=マルケス ある人生」木村榮一・訳)
スケールの大きな表題作『ママ・グランデの葬儀』は、確かに、他の作品群とは次元を異にする物語である。
これはガルシア=マルケスの文学的、政治的軌跡の中で鍵になるテキストのひとつ、つまり彼の──「写実的」と「魔術的」な──二つの文学様式がはじめて結びついたテキストなのである。同時に、以後半世紀以上にわたる円熟期の作品全体、とりわけ『百年の孤独』と『族長の秋』という決定的な二大傑作につながっていく道筋をつけた作品でもある。(ジェラルド・マーティン「ガブリエル・ガルシア=マルケス ある人生」木村榮一・訳)
あるいは、『百年の孤独』を読み終えた後、次に読むべき作品が『ママ・グランデの葬儀』という短篇集だったのかもしれない(順序は逆になるとしても)。
なぜなら、『ママ・グランデの葬儀』には、『百年の孤独』へと続くだろう「マコンド」の物語が、いくつも収録されているからだ。
『百年の孤独』を深く理解したいと考える人に、本作『ママ・グランデの葬儀』を避けて通ることはできない。
『大佐に手紙は来ない』を同時に読むことができるというところも、集英社文庫版のポイントになっている。
マジック・リアリズムの世界を堪能したいという人には、次作『純真なエレンディラと邪悪な祖母の信じがたくも痛ましい物語(1978)』がおすすめ。
書名:ママ・グランデの葬儀
著者:ガブリエル・ガルシア=マルケス
訳者:桑名一博、安藤哲行、内田吉彦
発行:1982/12/25
出版社:集英社文庫