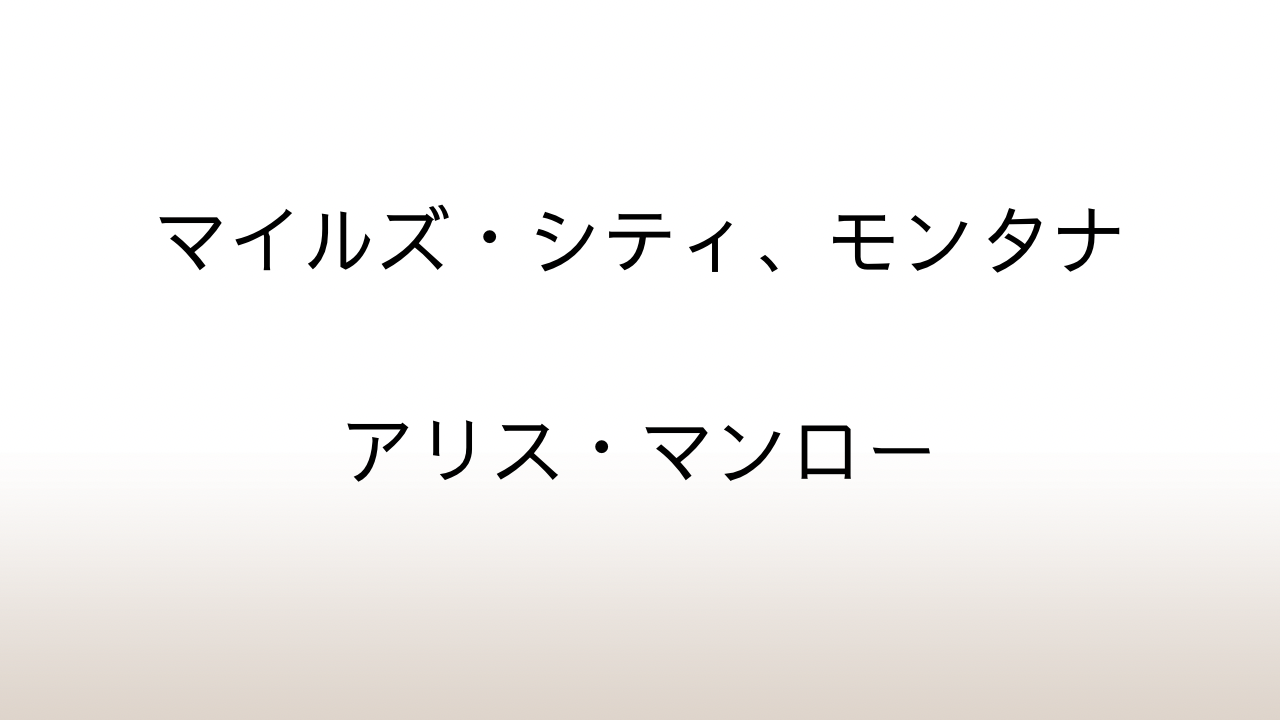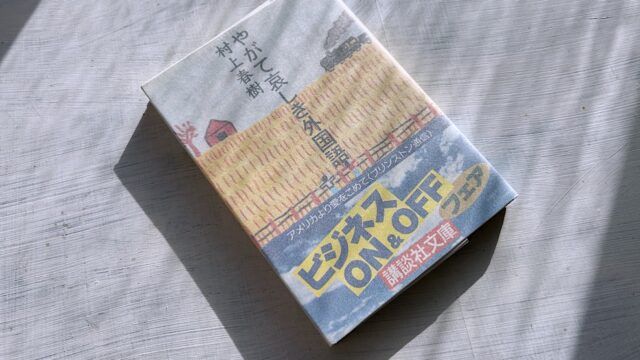アリス・マンロー「マイルズ・シティ、モンタナ」読了。
本作「マイルズ・シティ、モンタナ」は、1986年(昭和61年)に本国カナダで刊行された作品集『The Progress of Love』に収録されている短篇小説である。
この年、著者は55歳だった。
原題は「Miles City, Montana」。
日本では、1989年(平成元年)にスイッチ・コーポレイション書籍出版部から刊行されたアンソロジー『American wives「描かれた女性たち」現代女性作家の短篇小説集』(Switch編集部)に、川本三郎の翻訳により収録されている。
なお、作品集『The Progress of Love』は、2014年(平成26年)11月に栩木玲子の翻訳により、彩流社から『愛の深まり』の邦題で刊行された(2013年のノーベル文学賞受賞を受けてのもの)。
娘であり、妻であり、母親である「女性」という存在
今月は、1980年代のアメリカ文学を集中的に読んでいるんだけれど、目立つのは女性作家の作品である。
実際に女性作家の作品が多いし、女性作家にフォーカスしたアンソロジーも多い。
当時の日本ではアメリカ文学が注目されていたから、必然的にアメリカの女性作家に関する企画が多い、ということになる。
今読んでいる『描かれた女性たち』も、80年代らしい、そんなアンソロジーのひとつだ。
当時のアリス・マンローは、日本ではまだあまり有名な作家ではなかったらしく、編集部あとがきでは「この編纂の機会を利用して、未知の作家の紹介にも務めたい、と思った」「殊に、マーガレット・アトウッド及びアリス・マンローといった、アメリカの文学界に多大な影響を与えているカナダの実力派作家をここで紹介できることは、この短篇集じたいにある方向性を与えてくれていると思う」と記されている。
アリス・マンローの作品が、日本で刊行されるようになるのは、1990年代後半以降、主に2000年代から2010年代のことなので、1980年代の日本では、やはりまだ「新しい小説家」ということだったのだろう。
本作「マイルズ・シティ、モンタナ」は、1986年(昭和61年)に刊行された作品集『The Progress of Love』(邦題:愛の深まり)に収録されている短篇小説である。
舞台は1960年代のアメリカで、ある夏、物語の語り手である<私>は、夫<アンドリュー>や二人の幼い子どもたちとともに、久しぶりに実家のある故郷へ帰省する。
物語は、ヴァンクーバーからアメリカを経由してオンタリオへと向かう、夏のドライブ旅行が主軸となっているが、そこで語られているのは、夫と妻の関係であり、母親と子どもたちとの関係であり、そして、自分たちと両親との関係である。
娘であり、妻であり、母親である女性の役割と、それぞれの世代間で埋めることのできない断絶が、この作品のテーマなのだ。
私たちはなぜこんなことをしているのだろうと私は思った。答はすぐにわかった──親に顔を見せに行くのだ。アンドリューの母と私の父に孫の顔を見る喜びを味わわせに行くのだ。それは私たちの義務だった。しかしそれだけではなく私たちは親に自分たちのいいところを見せたかったのだ。(アリス・マンロー「マイルズ・シティ、モンタナ」訳・川本三郎)
実家へ帰省することは、明確に「私たちの義務だった」と記されている。
それだけでなく「私たちは親に自分たちのいいところを見せたかった」ともある。
「親に会いたいから帰る」とは書かれていないところに、親と子の断絶がある。
そして、その断絶は、将来の娘たちとの関係性をも暗示している。
実は、この短篇小説は、まさしく、自分と娘たちとの将来の断絶にフォーカスした、予言のような物語なのである。
彼らは私たちを頼り切っていた。そうする他なかったからだ。しかし私には彼らが生まれて初めて親に不信を抱いたこと、私たちを非難したいと思ったことがわかっていた。(アリス・マンロー「マイルズ・シティ、モンタナ」訳・川本三郎)
読んでいて楽しくはないけれど、それは、身につまされる話だからだろう。
子どもたちも親になればきっと分かってくれる──
そう思えるのは、それは彼女自身が歩んできた道だからに他ならない。
親子三世代の舞台設定が、本当に見事だと思った。
1960年代を生きる一人の女性の物語
親子の関係とともに、どちらかというと脇役的に描かれているのが、夫アンドリューとの関係である。
この物語を書いている時点で、物語の語り手である<私>は、「私はアンドリューにはもう何年も会っていない」と綴っている。
二人が離婚したことは明確には書かれていないが、それを暗示するエピソードは、いくつもある。
「僕にはわかっているよ。君には根本的にわがままで、信頼できないところがあるんだ」とアンドリューが言ったことがある。「僕にはずっとわかっていた。だから僕は君が好きになったんだけれどね」(アリス・マンロー「マイルズ・シティ、モンタナ」訳・川本三郎)
「あなたなしで暮らしたほうが幸せになれるって私にはわかっているの」と、主人公は答える。
そして「あなたも私がいないほうがずっと幸福になれるわ」とも。
<妻>であることに疑問を抱きながら、<私>は<妻>であり続けていた。
そんな彼女にとって、帰省のための旅行は「日常生活から脱出できたというだけで幸せだった」と思える程度のものだったのだ。
最後に、母親と娘たちとの関係。
私はあるタイプの母親になるのを恐れていた──身体がたるんで締まりがなくなり、子どもの服の匂いやミルクの匂いが身体にしみつくようになる。こまかいことを口うるさく子どもにいう。そんな母親にはなりたくなかった。(アリス・マンロー「マイルズ・シティ、モンタナ」訳・川本三郎)
親との関係・夫との関係・娘たちとの関係というエピソードを通して、<私>という一人の女性の姿が描き出されている。
結局のところ、この物語は、1960年代を生きる一人の女性の物語だったのだ。
親子の断絶は、その一つのモチーフでしかない。
重いなあと感じたけれど、読み終わった後の満足感は、確かにあった。
ミニマリズムの文学では味わうことのできない、「食い応え」のある作品だった。
作品名:マイルズ・シティ、モンタナ
著者:アリス・マンロー
訳者:川本三郎
書名:American wives「描かれた女性たち」現代女性作家の短篇小説集
編者:Switch編集部
発行:1989/6/30
出版社:スイッチ・コーポレイション書籍出版部