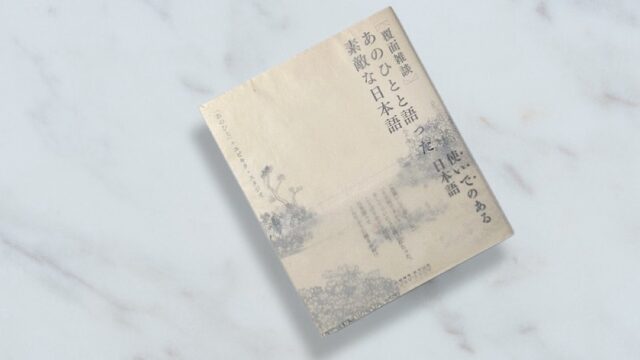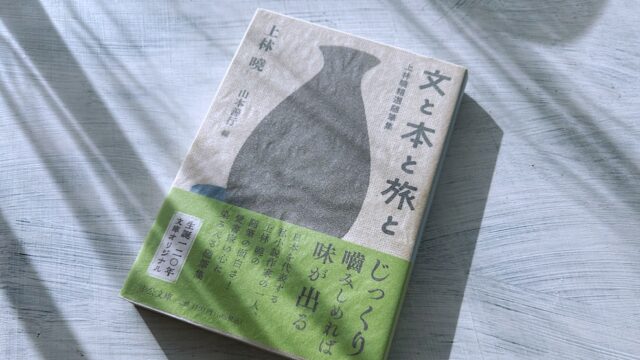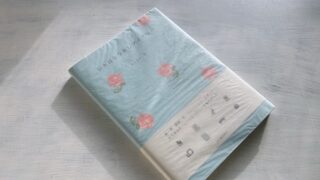福原麟太郎『昔の町にて』読了。
本作『昔の町にて』は、1957年(昭和32年)6月に垂水書房から刊行された随筆集である。
この年、著者は63歳だった。
人生を綴り続けたエッセイ文学
福原麟太郎の随筆を読むと、懐かしい気持ちになる。
古い話が書かれているからではない。
我々の祖父母世代の人たちと会話をしているような気がするからだ。
まるで、遠い田舎の祖父母の家へ遊びに出かけたときのような懐かしさが、ここにはある。
私どもは、戦争中とにかく東京にいて戦火と戦ったことを誇としている。私は決して逃げなかった。逃げることは私の学校の勤めが許さなかった。然し危険は確かに危険であった。私はいつでも死ぬ覚悟をしていた。(福原麟太郎「猫」)
大学で英語を教え続けるために疎開をしなかったという、その生き方は、明治生まれの不器用な生き方そのものだ。
自分の損得を考える以前に、世の中の正義ということを考えた。
正義を重んじる人だからこそ、戦後の不秩序が許されなかった。
書留だっていくらでも盗まれるんだ、小為替位仕方ない、このごろは、盗難は災難だというつもりでいるに相違ない。みんなが、世間の混乱を是認している。信義を破ることを、大して罪だと思っていない。日本もあはれな国になった。(福原麟太郎「信義」)
日本人が信義を重んじる国民であることを信じていたからこそ、戦後の混乱が悲しかったのだ。
誰も彼もが信義を守らなくなれば、社会機構は止ってしまう。共産主義も文化国家もなくなる。とにかく、自分の守るべき信義だけは、損をしても守ることにしようではないか。(福原麟太郎「信義」)
本作『昔の町にて』は、自選選集の随筆集である。
厳選された作品の中に「とにかく、自分の守るべき信義だけは、損をしても守ることにしようではないか」という生き方が通底している。
明治生まれの祖父が、そんな男だった。
福原麟太郎の懐かしさは、遠い記憶の中の祖父の懐かしさでもあったかもしれない。
もとより、祖父は炭鉱町の大工であり、大学で英語を教えるインテリジェンスな福原麟太郎とは、まったく異なる生き方をしてきた。
四十歳の歌は秋の歌である。蕭條として心が澄んでくる。あきらめのすがすがしさを身にしみて覚える。自分にどれだけの事が出来るかという見通しがすっかりつく。どんなことは出来ないか、ということも解る。そして先ず、天の定め給うたおのれの職分と、それに対する配分とは、これだけだったのかという見極めがつく、なにしろそれで落ち着いてくる。(福原麟太郎「四十歳の歌」)
福原麟太郎の随筆は、人生を描いた。
イギリスのエッセイ文学である。
業界のゴシップや美味しいお店の情報を書くために、随筆はあるのではない。
実際、人一人は、人一人、一いろの生活をして何十年かを過して来て死んでしまうのである。おそらく入学試験を受けたり、恋をしたり、新しい背広を着たりして、それも他人様と同様に而も銘々で銘々流の為方で、そして一ぺんしかそれを経験しないで、やがて死んでゆくのである。そうか人生はこれだったのか、ここまで来るのが俺の切符だったのか、では一つ落着いて青空を眺めようという気になる。(福原麟太郎「四十歳の歌」)
つまり、祖父には「炭鉱町の大工」という切符があり、その切符を持って90年の生涯を全うしたということなのだろう。
福原麟太郎の随筆は、(人生について)いろいろなことを教えてくれる。
貧乏な僕は、本箱を買う金がなかった。家を持ってから二三年たった。本はどんどん増えていった。細君が冬になると溜る蜜柑箱をせっせと丸善の包紙──鳶色のハトロン紙で貼ってくれた。それへ十四五冊づつ本をつめては積み重ねていた。(福原麟太郎「書籍と職業」)
本箱を買うお金がないから、蜜柑箱に本を入れた。
福原夫人が丸善の包装紙を貼ってくれたとあるところもいい。
福原麟太郎の100分の1も本を読まないような我々が、大きな本棚を並べた書斎を持つなんて、どうにも時代が間違っているような気がする。
我々だって、蜜柑箱から始めるべきなのだ。
私は本棚を見る。そうすると一昨年買って置いた書物が一ぺんも読まれずに埃をかむっているのが目に付く。あああれをゆっくり読みたいなあと思う。(福原麟太郎「気を紛らされること」
読みたい本があるのに、本を読むだけの時間がない。
愛書家にとって、これほど辛い日々はないだろう。
我々は暇つぶしをするために本を読むのではない。
自分のまだ知らない世界に触れて、自分にない教養を身に付けるために本を読むのである。
人生は、後になってやり直すことはできない。
然しそれを悔いるには四十歳の男は餘りにもものを知りすぎている。それが自分の成行であったにすぎない。これをもう一度やりなおすわけにはいかない。スタートをしなおすには遠くへ来過ぎている。(福原麟太郎「気を紛らされること」)
逆説的に言うと、五十歳や六十歳、七十歳になったときに後悔しないために、四十歳の人は四十歳の今を生きるということだ。
昔へ戻ることはできないが、今日の自分を変えることはできる。
ロレンス先生がなくなった年に夏目漱石が死に、その翌年にプレイフェア先生も箱根で急死して、我々の学生時代も終るのだが、思えば遠い遠い昔である。(福原麟太郎「あの頃のこと」)
昔を懐かしむのは、充実した人生の裏返しでもあったかもしれない。
人生に遊ぶということがともかくも先生の生活のキー・ノートであった。だから先生は自然とか理念とかの世界よりも人間の世界を愛した。(福原麟太郎「人間に遊ぶこと」)
福原麟太郎が「先生」と呼ぶのは、英文学の師である岡倉由三郎のことである(昭和11年に没)。
岡倉由三郎の生き方は、福原麟太郎の生き方に、大きな影響を与えていたに違いない。
そういうわけで先生は只管、人生を味わうということを努められた。少しでも先生にわからない価値がこの世に存在するということは、もう人生に敗けていることであったから、先生は、がむしゃらになってそれに食いついた。(福原麟太郎「人間に遊ぶこと」)
学問の世界にも「征服欲」というものがあった。
自分の知らない世界を征服するために、「先生」は必死だったと、福原麟太郎は回想している。
つくづく、昔の人たちは、真面目で頑固だったのだろうかと思わずにいられない。
いつから、我々は、こんなにもあきらめの良い民族になってしまったのだろうか。
英文学とロンドンの思い出
表題作「昔の町にて」は、かつて留学で暮らしていたロンドンを訪れたときの話である。
とうとう、トッテナムコート・ロードの町角を曲がって大英博物館まで来てしまった。通いなれたる土手八丁。昔二年間、通いつづけた図書館のあるところだ。その入口に昔ながらの獅子の口から落ちている水を、昔ながらに重い大きな水呑みで、二杯のんで、やっと眠気がさめた。以来、二十何年。そのころ私は三十四歳であった。(福原麟太郎「昔の町にて」)
昔の学生の日に帰った気分で、作者はロンドンの町を歩いていく。
「そのころ私は三十四歳であった」という最後の一文に、流れた時間の大きさがある。
短い随筆にも巧みな技が仕組まれていて、まさに「随筆の名手」らしい逸品である。
「男ありけり」も、かつて夢に見た住宅を回想する話だ(「要するに私は小塔や柱などのある西洋風建築の古めかしい家に住みたかったのである」)。
とはいうものの、小さいながら、どうにか、ついの住家をこしらえて、一いき安心する気持もあった。その生け垣の外には麦畑が青々と眺められて小石川の谷の小官舎よりもすがすがしかった。昔男ありけり、「武蔵野は今日はな焼きそ若草のつまもこもれりわれもこもれり」という気持にもなったのである。(福原麟太郎「男ありけり」)
短い随筆の中に時間が流れがあって、それが、つまりは人生というものを表現している。
イギリス流のエッセイとは、「人生とは」ということを大上段に構えることではない。
私の夢は二塁手であった。非常に優秀な二塁手になりたい。(略)──私は多分に派手性であった、のかも知れない。そういう夢を抱いているうちに、老人になってしまった。そして二塁手などちっとも興味を持たないようになった。(福原麟太郎「二塁手」)
若い頃の実現しなかった夢を思い出しながら、どこか清々しい風が吹いている。
二塁手ではない人生を、作者なりに生きたことに対する充実感が、その根底にはあるのかもしれない。
自選選集だけあって、良い作品ばかりが並んでいる。
いまに、亡くなった父の忌日も、秋の終りになるとやってくる。娘も祖母も、私たち夫婦も、せめてそういう折には、一つところに集まって法事をして、もう火鉢のほしい夜、家族の団欒を楽しみたいと、しきりに思うこともある。(福原麟太郎「秋の空は澄んで」)
家族ものも良いが、英文学者だった福原麟太郎には、やはり、英文学に関係した随筆に興味深いものが多い。
イギリスでは、日本の友人に頼まれた名刺をテムズ川へと落とした。
ある日の午後、お茶の前に、そのさきまで歩いていって、議事堂の建物を仰ぎ、ウェストミンスター橋の欄干によって、しばらくテムズの川波を見ていた。私は東京を出るとき、たのまれた用事が一つあった。それは、テムズ河に名刺を流してくれという依頼であった。(福原麟太郎「英京七日」)
名刺をテムズ河へ流すように依頼したのは、作家の十和田操であることが、庄野潤三『陽気なクラウン・オフィス・ロウ』に書かれている。
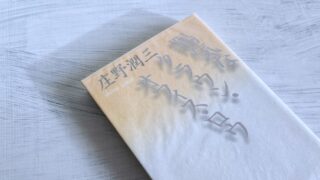
留学生として暮らしていたロンドンは、特別の思い入れのある街だった。
ぎらぎら光る広告の照明もややいぶされて、遠くなってゆくバスはぼんやりと、濁れた牛乳の色の幕のかなたに消えて行った。然し、あとからあとからくる赤いバス、自動車、自動車、荷車、バス、バス。町はごった返している。(福原麟太郎「クリスマス風景」)
遠い異国で迎えるクリスマスは、特別のクリスマスだったに違いない。
この老人に或る朝、今日は「クロニクル」が欲しいんだと変更を申し出たことがあった。すると彼は「クロニクル」は売りませんよと言うのである。何故だ、と私は訊ねてみた。あっしゃ保守党なんで、他党の新聞は持っていないんです、と彼は答えた。(福原麟太郎「イギリス気質」)
『タイムス』を売っている新聞売りの老人はロンドン訛りだったのだろう。
「あっしゃ保守党なんで、」という東京弁のような訳し方がいい。
又或る時、「あっしはね、これから古い古い友達に会いに行きますよ、あっし達はあなたがたの行かないコーヒー店で会うのですよ。昔なじみの店でね」と言ったのを聞いて、息子が「どこだえ、お父つあん」と訊ねる。「誰にも言わないんだ、おれ達の昔の話のためてあるところさ」と彼は答えた。(福原麟太郎「ロンドンの宿」)
過ぎてきた人生を楽しんでいる様子が、下宿屋の主人の言葉から伝わってくる。
「生きていてよかった」と思うのは、あるいは、こういう瞬間なのかもしれない。
イギリス流のティータイムも、印象に残る慣習だった。
我々はイギリス人の持っているティーの習慣、四時半になると、誰も彼も仕事から離れて紅茶をのむ、スコーンだのブレッドンバターなどを食べながら、何杯でも茶をのんで世間話をしている、ああいう習慣を何だかイギリスらしく感じる。(福原麟太郎「イギリス気質」)
英文学者だから、イギリスでも古本屋を訪ねて回った。
一番愉快であったのはロンドンを離れて二時間ばかりの南、タムブリッヂ・ウェルズという隠居町、これは平田禿木氏がひいきの浴泉地で、私なども二度か遊びに行ったが、その町はずれにちょっとした古本屋があって、そこへ入ると、すばらしく色々の良い本が列んでいる。(福原麟太郎「ロンドンの古本屋」)
有名なチャリング・クロス・ロードは、さして良い本屋があるわけではなくて、「ただたくさん並んでいるだけのことだ」と、作者は回想している。
「このあらむ命」は、平田禿木の回想記である。
平田禿木先生に始めて御目にかかったのは、大正八年か九年であったろうと思う。東京・田端一〇八番地というところであった。上野の山つづきで、今は家が立てこめているが、その頃は、郊外に近い市内で、先生の御宅は、藁屋根であった。(福原麟太郎「このあらむ命」)
最近では、平田禿木の作品を読むことも難しくなってしまった(「平田先生は、このごろの若い読者などには、恐らく知られていないだろうと思う」)。
文学というものは「古いから忘れられていい」というものではない。
文学というのは、付け焼刃ではないのだということを、その時、悟った。人間そのものなのだ。(福原麟太郎「このあらむ命」)
古本屋で無理をしながら探して買うだけの値打ちのある文学が、昔の人たちの作品の中にもある。
現代を生きる我々は、ただそのことを知らないだけなのだ。
イギリス滞在中には、フランスも出かけた。
パリのバスは、専ら裏町を通るように出来ているらしかった。名も無い町、貧民の町、せま苦しい横町、そういうところばかり選んで、バスは、ごとごと私を運んで行ったが、それが実はとても楽しかった。今から考えると、私の半日見て通った町々は、あの「パリの屋根の下」に出てくるような場面なのであった。(福原麟太郎「フランスの思い出」)
福原麟太郎の随筆は、人生の記憶そのものである。
生きてきたことの記憶が、飾らない文章で綴られてゆく。
これは、遠い昔を生きた人生の先輩の記憶なのだ。
ワシントン会議から乱闘までの日本を、私は教師として見て来たが、私が疲れたように日本も疲れたろうか。私が、教師としてはなはだ不完全であったように、日本も不完全らしい。しかし、日本よ。その年月に得た知慧をもって、ふたたび永久に、よき国となれ。(福原麟太郎「日本よ、よき国となれ──一停年教授の思い出一一」)
1953年(昭和28年)3月、東京教育大学を定年退官したとき、福原麟太郎は59歳だった。
そして、大学教授を退官した後に、福原麟太郎の大きな仕事は待っていた。
『トマス・グレイ研究抄』と『チャールズ・ラム傳』で二度の読売文学賞を受賞するのは、いずれも1960年代に入ってからのことである。
書名:昔の町にて
著者:福原麟太郎
発行:1957/06/20
出版社:垂水書房