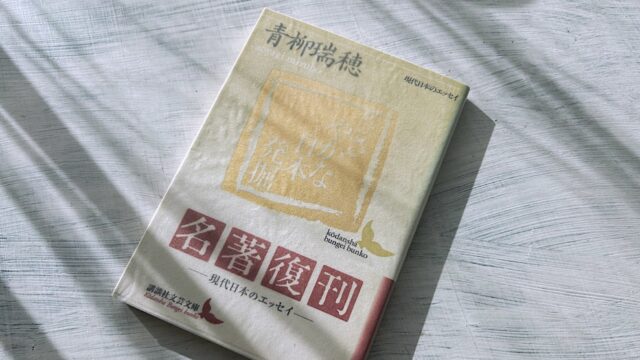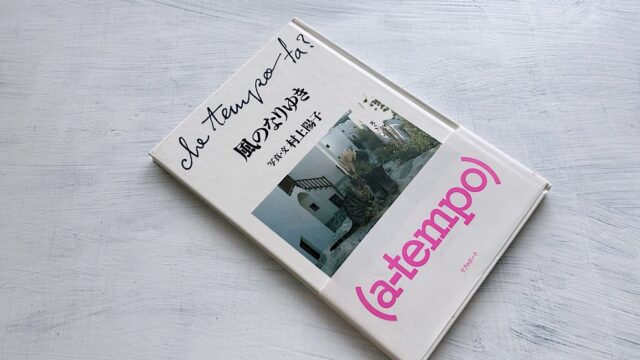小沼丹「椋鳥日記」読了。
本作「椋鳥日記」は、1974年(昭和49年)6月に河出書房新社から刊行された長篇小説である。
初出は、1974年(昭和49年)4月『文藝』。
この年、著者は56歳だった。
1975年(昭和50年)5月、第三回「平林たい子文学賞(小説部門)」受賞。
森鷗外『椋鳥通信』へのオマージュ
庄野潤三『山田さんの鈴虫』に、『椋鳥日記』の話が出ている。
昔、荻窪の井伏さんのお宅で小沼丹と一緒になった。丁度、小沼の半年間のロンドン留学の思い出話の第一回が「文芸」に載ったばかりで、そのことが話題になった。題は「椋鳥日記」。井伏さんはこの題がお気に召さないらしい。「椋鳥じゃあねえ」といわれる。(庄野潤三「山田さんの鈴虫」)
『文藝』発表時、「椋鳥日記」は「三○○枚一挙掲載」だったから、「ロンドン留学の思い出話の第一回が~」とあるのは、庄野さんの記憶誤りだとして、「椋鳥日記」という題名を、井伏さんがお気に召さなかったことは確からしい。
この作品、「椋鳥日記」と言いながらも、ムクドリは一切登場しない(ロンドンの雀や鳩は登場しているが)。
おそらく、この作品タイトルは、森鷗外が1909年(明治42年)から『スバル』に連載した「椋鳥通信」のパロディ(というかオマージュ)ではないかと思われる。
椋鳥がギャーギャーとやかましく鳴く鳥であることから、江戸の昔、東京の人々は、地方から上京してくる騒がしい田舎者を「椋鳥(むくどり)」と呼んで馬鹿にした。
鷗外は、こうしたいわれを踏まえて、世界の中の田舎者に過ぎなかった日本を「椋鳥」に喩えたものらしい。
もちろん、小沼さんに、そこまで深い意図があったかどうかは分からないが、「椋鳥通信」の作者が森鷗外であったことも、井伏さんとしては引っかかるところがあったのではないだろうか。
なにしろ、若い頃の井伏さんには、森鷗外宛てに、偽名を用いた批判的な手紙を送りつけたという経歴があったのだから。
まあ、「椋鳥日記」という思わせぶりな作品名だけでも、なかなか楽しませてくれる作品であることに間違いはない。
本作「椋鳥日記」は、著者・小沼丹のロンドン滞在の記録である。
年譜の1972年(昭和47年)4月のところには「早稲田大学の在外研究員としてイギリスに渡り、約半年間、次女李花子とともにロンドンに滞在」とある(この年、小沼さんは54歳だった)。
もっとも、この「椋鳥日記」、一見して普通の旅行記ではない。
旧仮名遣いで漢字を多用するビジュアルは、いかにも古風で厳めしい。
イギリスのパブを「酒場」と書き、女主人を「お上さん」、ウエイトレスを「給仕」と書く。
赤煉瓦のアパートメントは「四階建ての長屋」で、テーブルは「卓子」、ベッドは「寝台」、カトリックは「加特力」。
国名に至っては「英吉利(イギリス)」「愛蘭(アイルランド)」「蘇格蘭(スコットランド)」「丁抹(デンマーク)」「埃及(エジプト)」という具合だから、一体ここはいつの時代のロンドンだろうと、不思議な気持ちになる(もちろん、1972年のロンドンだ)。
さらに、主人公は、極めてぶっきらぼうな中年男性で、なかなか気難しい様子を呈している。
「閉口した」「煩わしい」「頗る迷惑する」みたいな言葉がしばしば並び、「音楽会と云うと億劫で出掛ける気にならない」「国立美術館のような大きな美術館は草臥れるから、序だからちょっと覗いて見ようと云う気は起らない」といった態度だから、当然、一般に期待されるようなイギリス観光案内などはあるはずもない。
此方は倫敦に来たからと云って、別に特別のことはしたくない。郷に入っては郷に従えと云うから、郷に従ってのんびり暮せたらいいと思っている。半年間も修学旅行の気分でいては草臥れてやり切れないから、のんびり過して気が向いたらどこかへ行こうと思う。(小沼丹「椋鳥日記」)
そもそも、主人公には、観光旅行など最初から眼中になかったのだろう(25歳の次女や若い友人に引っ張られて、あちこち見て歩くことにはなるが)。
そんな無愛想な中年男性の旅行記がおもしろいのかというと、すごくおもしろい。
これは、やはり、小沼丹でなければ、書くことのできなかったイギリス滞在記なのだ。
とりとめのないこの作品を、書評家の斎藤美奈子は「散歩文学」と呼んだ。
英文学者でもある小沼丹は、ほんとは非常なインテリなのだ。が、どんな話題が出てきても、親戚の小父さんの書斎に上がり込んで雑談を聞いているような気分。読みながら、私の頭の中では『ぼくの伯父さん』という仏蘭西映画のテーマ曲がなっていたのだが、もしかしたら別の映画の音楽だったかもしれない。(斎藤美奈子「本の本」)
「けっして派手じゃないけれど、この文章は癖になるってもんだわ」というコメントが、小沼文学の特徴を言い表しているのではないだろうか。
はかない人生への畏敬
地下鉄駅では、きれいな売店ではなくて、建物の陰で汚い恰好をしている爺さんから新聞を買う。
新聞を並べた台の傍に、古ぼけた鳥打帽を被った爺さんが背中を丸めて坐っているのを見ると、何となく昔の倫敦がぽつんとそこに残っているような気がする。一つには、それで買う気になったのかもしれない。(小沼丹「椋鳥日記」)
往来では騎馬警官の姿を見かけることがある。
いつだったか小雨の降る日騎馬警官を見たが、馬上に長い外套の裾を翻して颯爽とした姿に見えた。若い警官自身、自分の姿を意識して馬を走らせていたように思われる。往来に蹄の音を聞くと、失ったものが甦る気がして懐しかった。(小沼丹「椋鳥日記」)
ダウテイ通にあるディケンズの家で夕立に降られたときは、ジョンソンの家を見に行ったときのことを思い出す。
ジョンソンの家に行ったのは倫敦に来たばかりの五月初旬で、雷鳴を伴った激しい驟雨が前の小さな広場を白く染めたのを想い出す。驟雨の通り過ぎた后、雨上りの濡れたフリイト街の歩道を物珍しく歩いたことも想い出した。想い出したら、遠い昔のような気がする。(小沼丹「椋鳥日記」)
ぶっきらぼうな男が、不意に感傷的な言葉を口にする。
そのアンバランスなところに、読者は引っかかってしまうのだ。
好い天気だが、冷やかな風が吹いて歩道に落葉が乾いた音を立てる。いつの間に木の葉の散る季節になったのかと思う。昔、こんな具合に歩いたことがある、と思ったのは追憶をそそる風の悪戯だったのかもしれない。(小沼丹「椋鳥日記」)
初めてのロンドンを歩いているはずなのに、主人公は随所で懐かしい気持ちを抱く。
この懐かしさこそ、本作『椋鳥日記』に流れている最大の主旋律だろう。
そして、その懐かしさを生み出しているものは、はかない人生への畏敬と、滲み出るような自身の記憶である。
映画館で「アラビアのロレンス」を観ているとき、ぶつぶつと独り言を言っている爺さんを発見する。
「――どうだい、お前。あれは砂漠だ。広いではないか。あそこを歩いて行くのは一苦労というものではないか……」爺さんは亡くなった細君と一緒に観ているつもりで、そんなことを話掛けているのではないかと思う。(小沼丹「椋鳥日記」)
若い友人の春野君からは、同じ下宿屋で暮らす独居老人の話を聞く。
部屋のなかは乱雑で埃だらけで、普段はろくろく掃除もしなかったと見える。保健所の係が掃除している間、春野君は何となくあちこち見ていたら、棚の上に、死んだ奥さんのものらしい日傘や手提袋が埃を被って載っていたそうである。(小沼丹「椋鳥日記」)
老人の家から脱走した爺さんを見送った後では、懐かしいメロディを思い出している。
一体、爺さんはどこへ行ったのかしらん? 何となく老人の家を見たら、窓に黄色い灯が映っていて何事も無かったようである。どこからか「ホオム・スヰイト・ホオム」の旋律が聞えて来たが、あるいは空耳だったかもしれない。(小沼丹「椋鳥日記」)
日本とかイギリスとかの国境を越えて、小沼丹の小説には、生きている人間なり、死んだ人間なりへの共感がある。
『椋鳥日記』を呼んだときに、単なる旅行記ではないと感じられるのは、国家や文化を越えたところにある人間への畏敬の念が影響しているからだろう。
そして、主人公の持つ古い記憶が重ねられたとき、深みのある文学作品が姿を見せるのだ。
英文学とはかない人生への慈しみ
老人の家の前にあるバスの停留所に並ぶ子どもたちを見て思い出したものは、古い散文詩だ。
ある詩人は遠い窓のなかの貧しい老婆の姿を見て、その老婆の架空の物語を作り上げ、涙を流しながらその物語を自分に語り聞かせた。昔、そんな散文詩を読んだことがある。老人の家の窓を見ていると、ひょっこり、忘れていたそんな散文詩が甦って来たりする。(小沼丹「椋鳥日記」)
「忘れていたそんな散文詩」とあるのは、19世紀に生きたフランスの詩人、ボードレールの「窓」だ。
波のように起伏した屋根の向うに一人の女が見える。盛りをすぎて既に皺のよった、貧しい女である。いつも何かに寄りかかっていて、決して外へ出掛けることがない。私は此の女の顔から、衣物から、挙動(ものごし)から、いや殆んど何からということはなく、此の女の身の上話を――というよりは、むしろ伝説を造り上げてしまつた、そして私は時々涙を流しながら、この話を自分に話して聞かせるのである。(シャルル・ボードレール「窓」富永太郎・訳)
ロンドンの停留所でバスを待ちながら、主人公は、かつて『巴里の憂鬱』で読んだ古い散文詩を思い出している。
「老人の家の窓」が、主人公の中に潜む懐かしい記憶を呼び起こしたのだ。
ダニエル・デフォーの墓を訪れたときは、代表作『ロビンソン・クルーソー』が登場している。
如何にも「ロビンソン・クルウソオ」の作者らしいと話していると、甃の上に落ちた陽差しが揺れて黄ばんだ葉がひらひらと落ちて来た。何だか遠い場末の淋しい墓地に来たような気がする。茲は倫敦のどの辺になるのだろう? と春野君に訊くと、「――シティです」と笑っている。(小沼丹「椋鳥日記」)
デフォー『ロビンソン・クルーソー』は、イギリス近代小説の始まりと呼ばれる作品だ。

主人公にとっては、英文学そのものが懐かしさを覚えるフィルターの一つであって、1972年のロンドンも、小沼丹という作家の眼を通して見ることによって、たちまち郷愁に満ちた風景となる。
もちろん、郷愁を誘うフィルターは、英文学だけに留まらない。
ベルトルト・ブレヒト原作の映画『三文オペラ』が登場するのは、ニューゲート監獄を訪ねたときだ。
「ニユウゲイト跡」のプラアクを入れた写真を秋山君に撮って貰っていたら、昔観た映画「三文オペラ」の懐かしい主題歌が甦って来て、ルドルフ・フォォスタァ扮するメツキ・メツサが見えるような気がした。(小沼丹「椋鳥日記」)
ディケンズではなく、『三文オペラ』というところに、主人公の青春時代が感じられるのではないだろうか(ルドルフ・フォルスター主演の『三文オペラ』は1931年公開)。
グリニッジパークでは、ヘンリー八世と踊ったというアン・ブリンへの思いが綴られている。
眼隠しされたアン・プリンが跪いて両手を合わせている傍に、仮面を着けた首斬人が立って剣を振上げている絵を見たことがある。アン・ブリンの希望で、熟練した首斬人が海の向うのカレエから連れて来られた。妻の首が落ちるころ、夫のヘンリ八世はリッチモンドで猟を愉しんでいた。二人がこの木の周囲を廻って踊ってから、何年と経っていない。蔦に被われた枯木の前でそんなことを想い出したら、異国の遠い昔が身近に甦るような気がしたから不思議である。(小沼丹「椋鳥日記」)
グリニッジパークでは、帆船カティ・サークの船内も見学している。
小さな船室の寝床を見て、誰がそこで眠ったのだろうと思っていると、通路にこつこつと松葉杖の音が響いて来るような気がする。狭い昇降口の急な梯子段を降ると広い部屋があって、その壁に古い船首飾が沢山並べてある、それを眺めていると、……ラム酒が一本、と云う唄の文句がひょっこり甦った。その前に文句があるが、それが想い出せない。(小沼丹「椋鳥日記」)
帆船の中で思いだしたのは、スティーブンソンの『宝島』だったのだろう。

そう言えば、小沼丹には、スティーブンソン『旅は驢馬をつれて』の邦訳があった。

「……ラム酒が一本」とあるのは、『宝島』の中で海賊が歌ったものだ。
当たり前だけれど、英文学に精通しているからこそ、見える風景というものもある(うらやましいし、ちょっと反省)。
テムズの川下りで思い出したものも、古い歌だった。
昔憶えた輪唱用の短い唄に、静かに愉しく流を漕ぎ下ろうと云うのがあった。どこだったか忘れたが、静かな流がゆったり石の橋の下を潜ると、その先の深い樹立のなかに消えて行くのを見て、矢張りこの唄を想い出したことがある。しかし、小舟に乗らなくても構わない。現にこの船の上でも、この世は夢だ、何だかそんな気分になる。(小沼丹「椋鳥日記」)
「楽しく流れを下っていこう、人生は夢のようなものさ」は、イギリス民謡「Row,Row,Row,Your Boat(漕げ漕げボート)」で、もちろん、主人公は、この歌のタイトルも歌詞も、鮮明に覚えていたはずだ。
なぜなら、この曲は、小沼丹の盟友・庄野潤三が酔うたびに歌っていた(しかも、みんなで輪唱していた)愛唱歌の一つだったのだから。
もしかすると、「人生は夢のようなものさ」というフレーズは、『椋鳥日記』全体を通奏低音のように流れている旋律なのではないだろうか。
いや、それを言い始めると、小沼文学全体の、そもそものテーマが「人生は夢のようなものさ」ではなかったか。
はかない人生への慈しみ。
この『椋鳥日記』、ただの旅行記だと思って読み始めると、思わぬ怪我をするかもしれない。
そんな身構えを起こさせるくらいに、エッジの効いた紀行文学なのだ。
ちなみに、庄野潤三は『陽気なクラウン・オフィス・ロウ』の中で、小沼丹『椋鳥日記』の世界を追体験している。
同じ経営の魚屋が隣りにあり、そこから魚を運んで来るので、ヴィクトリア駅の傍の魚屋レストランと呼んでいる。今度ロンドンへ来る前に小沼に店の名前を尋ねたら、手帳に Overton と書いてくれた。(庄野潤三「陽気なクラウン・オフィス・ロウ」)
『椋鳥日記』を読んでから『陽気なクラウン・オフィス・ロウ』を読む。

読書は、いつだって繋がっているのだ。
駅蕎麦に促された帰国
駅のプラットホームで「立ち食い蕎麦でも食べようかな」と思ったときから、主人公は「そろそろ引揚げる汐時を考えないと不可ない」と考え始める。
プラットフォォムに軽食堂があるのを見て、何となく、「――蕎麦を食おう……」と思ったのは、どう云う料簡だったか判らない。茲は英吉利だと気が附いたのと、娘が珈琲でも飲みましょうかと云ったのと、どっちが先だったか忘れたが、途端に蕎麦は消えてしまって何だかたいへん淋しかった。これはそろそろ引揚げる汐時を考えないと不可ない、そう考え始めたのはこのときからである。(小沼丹「椋鳥日記」)
自然体で駅蕎麦を食べようと思うくらい、ロンドンの街に体が馴染んでいたということもあるだろうし、無意識のうちに日本を懐かしく求めていたということもあるだろう。
いずれにしても、「途端に蕎麦は消えてしまって何だかたいへん淋しかった」とあるのは、紛れもない郷愁である。
慣れ親しんだイギリス文学の舞台を訪れ、懐かしい英文学をリアルに追体験し、庶民の暮らしに垣間見た人生のはかなさに共感する。
どこまでも充実したロンドン生活に見えて、最後はやはり「蕎麦」を求めてしまった。
自分の中にある日本を感じたとき、主人公は、森鷗外の『椋鳥通信』を思い出していたのではないだろうか。
まだまだ、世界の中の田舎者を自称しなければならなかった、明治時代の日本へ向けて書かれた海外便り。
『椋鳥日記』という題名は、意外とそんなところから生まれてきたのかもしれない。
あまりに深すぎて、一回や二回読んだくらいでは、この紀行小説を充分に味わったとは言えないみたいだ。
書名:椋鳥日記
著者:小沼丹
発行:2000/09/10
出版社:講談社文芸文庫