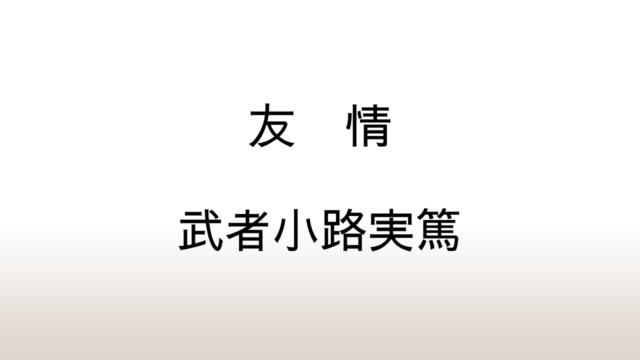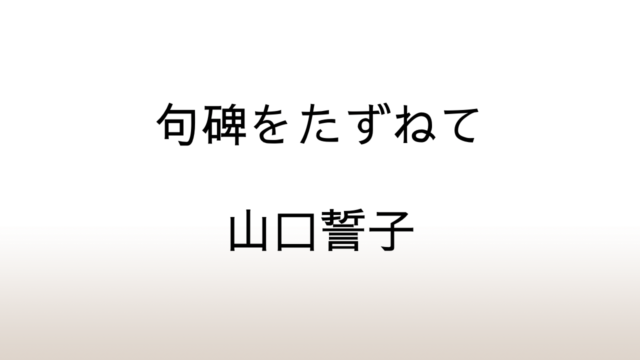村上春樹「村上朝日堂」読了。
本作「村上朝日堂」は、1984年(昭和59年)7月に若林出版企画から刊行されたエッセイ集である。
この年、著者は35歳だった。
結婚願望が強かった村上春樹
本書『村上朝日堂』の多くを占めているのは、1982年(昭和57年)8月から1984年(昭和59年)5月まで『日刊アルバイトニュース』に連載されたコラム「シティ・ウォーキン」だが、その他にも、1984年(昭和59年)2月から3月まで『ビックリハウス』に発表された「千倉における朝食のあり方」「千倉における夕食のあり方」、1984年(昭和59年)2月『GORO』発表の「男にとって ”早い結婚” はソンかトクか」が収録されている。
簡単に言うと、昭和50年代後半に書かれた雑文で構成されたエッセイ集ということになる。
大きな特徴は、いずれの作品も、イラストレーター安西水丸と一緒の仕事になっているということで、付録の「カレーライスの話」「東京の街から都電のなくなるちょっと前の話」なんて、水丸さんが文章を書いて、村上さんが挿絵を描いている。
そのためか、全体にかなり緩やかで自由な雰囲気があって楽しい。
『日刊アルバイトニュース』連載の「シティ・ウォーキン」なんて、飲み屋で隣に座ったおじさんの無駄話を延々と聴かされているのに近い非生産性がある。
頭を使わないで暇つぶしをしたいときにはぴったりなんじゃないだろうか(もしも、ヒマな時間というものがあるのだとしたなら)。
だけど、本書『村上朝日堂』でいちばん注目すべきは、村上さんと水丸さんとの対談「男にとって ”早い結婚” はソンかトクか」だ。
二人とも学生結婚だったということで、若いうちに結婚したことは良かったか否かということを、割と真面目に語り合っている。
村上さんが奥さんと知り合ったのは、18歳か19歳の頃で、結婚したのは22歳だった。
ただし、7年間も大学にいたという村上さんは、結婚当時まだ大学生で、しかも、結婚と同時に商売(国分寺のジャズ喫茶)を始めたというから、さぞかし忙しい新婚生活だったのではないかと思う。
ちなみに、結婚して、商売を始めた頃のことは「国分寺の巻」に詳しい(昭和49年開業だった)。
【村上春樹】ぼくもいまの結婚で十分におもしろかったと思っている。べつに後悔する気もないですね。このぐらいおもしろい人生はなかったから。(村上春樹・安西水丸「男にとって”早い結婚”はソンかトクか」)
当時、村上さんは35歳で、結婚から10年以上が経過している。
借金をしてお店を出したりとか、苦労からスタートしている分、夫婦の連帯感みたいなものも強かったのかもしれない。
意外だったのは、村上さんは結婚願望が強かったという話だろう。
【村上春樹】ぼくは早く結婚したいという気持が強かった。というのは、ぼくはひとりっ子なんですね。家にはいつも親とか、そういう人しかいなくて、つねに従属的でしょう。早く自分の世界を持ちたいと思っていた。(村上春樹・安西水丸「男にとって”早い結婚”はソンかトクか」)
村上春樹の小説というと、やたらと、離婚したり、奥さんが突然に失踪したりするような話が多いけれど、もしかすると、あれは、「嫁に逃げられたらどうしよう」という恐怖心が生み出しているものなのだろうか。
こういうのは、著者と作品世界のイメージとがズレていたりして楽しい。
逆に、作品世界のイメージと一致しているのは、夫婦間でも(家庭内でも)互いにきちんとしているということ。
【村上春樹】ぼくらの若いころはアイビー全盛でVANジャケットの時代ですよね。格好つけてるわけでしょう。結婚しても、やはりある程度、格好つけなきゃいけないという感じがあるんですね。ジョギングするときも、家に入る前にきちんと呼吸をととのえる。汗もふいてね(笑い)。(村上春樹・安西水丸「男にとって”早い結婚”はソンかトクか」)
村上春樹の小説の主人公というのは、大抵の場合、きちんとしているから、こういうのは、著者の生活が反映されているのかもしれない。
いちばん感心したのは、現代の若い人たち(1984年当時)の生き方についての検証の部分だ。
【村上春樹】いまはある種の閉塞状況があるでしょ。ぼくらのころは高度成長があって、とりあえずお金がなくてもがんばればもっと金持ちになれるとか、有名になれるとか。いまはそれがない。いまの男のコは先を見てめげちゃう部分があるね。女のコはそういうのを敏感に感じているから、それだったら金があるとか、才能があるとか、頭がいいとか、学歴があるほうにいっちゃう。(村上春樹・安西水丸「男にとって”早い結婚”はソンかトクか」)
1980年代というと「バブル景気」のイメージが強いけれど、実際にバブルが始まるのは1986年からで、1984年頃というのは、オイルショック(第二次)とインフレという最悪の経済状況から、どうにか抜け出しつつあるという時代だった(ちなみに、当時の最低賃金は、時給400円前後)。
80年代と言っても、前半と後半とでは、世界がかなり違っていたような気がする(その意味で、1980年代というのは「激動の時代」だった)。
村上さんの「いまの男のコは先を見てめげちゃう部分があるね」などというコメントを読んでいると、こうした社会観が、いずれ小説に反映されていくことになるんだろうなと思う。
すごくおもしろい対談だったけれど、村上さんは嘘を言う人なので、全部を正直に受け止めることは危険かもしれないけれど。
村上春樹の署名本の価値
さて、『日刊アルバイトニュース』に連載された「シティ・ウォーキン」の方は、かなりくだらない四方山話で構成されている。
30代前半のおじさんが大学生を相手に「よぉー、そこの若いの、、、」なんて話しかけているような雰囲気に近い。
例えば「辞書の話(2)」は、「英語の辞書に、よくイラスト付いてるでしょ? オレ、あれ大好きなんだよね~」みたいなエッセイ。
もっとすごいのは318ページの「ナイトクラブ」編で、このイラストはどうみても湯村輝彦風である。それから今brassiereをとったばかりのStripperを食い入るように眺めているスケベそうな顔つきの客はどうみても糸井重里である。嘘だと思う人は書店で立ち読みして確かめて下さい。(村上春樹「辞書の話(2)」)
何の生産性もないと思うけれど、ここで紹介されているオックスフォード・ドゥーデンの『図解英和辞典』(福武書店、現在のベネッセ)は、村上さんのエッセイの影響で、もしかすると売り上げを伸ばしたかもしれない。
辞書の話は他にもある。
僕は翻訳の仕事をする時は大・中・小の三種類の英和辞典と二種類の英英辞典を机に並べて場合場合で使いわけているが、そのうちのひとつに研究社の「新簡約英和」というのがある。これは高校に入学した時に買ったもので、以来二十年近く使っていて、とてもよく手になじんでいる。(村上春樹「辞書の話(1)」)
辞書というのは、暇つぶしに読んでも楽しいものだけれど、大人になると、潰さなければいけない閑な時間というのが、意外と少なくて悲しい。
知識とか教養というのは、退屈な時間にこそ培われるのかもしれない。
村上さんは作家だけあって、本についてのエッセイが多く、子どもの頃に読んでいた文学全集の話なども興味深い。
当時(一九六〇年代前半)僕の家は毎月河出書房の「世界文学全集」と中央公論社の「世界の歴史」を一冊ずつ書店に配達してもらっていて、僕はそれを一冊一冊読みあげながら十代を送った。おかげで僕の読書範囲は今に至るまで外国文学一本槍である。(村上春樹「本の話(3)つけで本を買うことについて」)
大人になってから(社会人になってから)外国文学の世界を制覇しようというのは、意外と困難を伴うものである。
昭和時代に流行した文学全集のように、定期的に届く本を、定期的に一冊ずつ読破していく方法というのは、ある意味で正しいのかもしれない(系統的な読書をすることができるし)。
ちなみに、1960年代前半に刊行されていた河出書房の「世界文学全集」というと、1959(昭和34年)年から1966年(昭和41年)まで刊行された『世界文学全集グリーン版』(全100巻)ということになる。
7年間かけて100冊の文学全集を読むというのは、すごいエネルギーを要するような気がするけれど、世界の文学を網羅するというのは、つまり、そういうことなんだろうな。
いちばん腹が立つのは原書で新刊ハードカバーを買ったのに読まないうちに翻訳がもう出ちゃったという例で、翻訳書があるのにわざわざ英語で本を読む気なんてしないし、英語の本なんて売っても安いもんだし、こういうのは泣くに泣けない。(村上春樹「本の話(1)「日刊アルバイトニュース」の優れた点について」)
村上さんのような翻訳家は、翻訳よりも原文で読むことを好むのかと思っていたので、「翻訳書があるのにわざわざ英語で本を読む気なんてしないし」とあるのは、ちょっと意外な気がする。
サイン会が嫌いだという話もおもしろい。
古本屋にたとえば僕のサイン本を持っていくと高く取ってくれるかというと、そんなことはない。古本屋のおじさんに聞いた話だとサインがあって高くなるのはせいぜい遠藤周作・開高健といった世代までで、あとの若い作家の署名なんて汚れみたいなものだそうである。(村上春樹「本の話(4)サイン会雑感」)
現代の話をすると、村上春樹の署名本は、かなり数が少ないらしくて(サイン会が嫌いだったためか)、たまに市場へ出ると、ものすごい高額がついていたりする。
署名本に関して、僕は、庄野潤三と小沼丹の本だけ、細々と集めている。
値段がそれほど高額ではないからで、二人と関係の深い作家仲間へ献呈した署名本を見つけると、うれしくてつい手を出してしまう。
関係ないけど、作家仲間へ献呈した署名本というのは、献呈先の作家の蔵書が一斉処分されたときに市場へ出る場合が多いらしくて、市場に出るときにはまとまって出てくる。
高名な作家でも、亡くなってしまえば、蔵書は遺族によって処分されてしまうわけで、こういう献呈本というのは何とも切ない。
本以外の話では、地元・北海道の話に注目しなければならない。
札幌で何をしたかというと、まずビヤホールに入って生ビールを三杯飲んで昼食をとり(北海道で飲むビールはなぜあんなにうまいんだろう?)、それから「ランボー」と「少林寺」の二本立てを見た。(村上春樹「旅行先で映画を見ることについて」)
なんだか『羊をめぐる冒険』みたいな話で楽しい。
ただし、「札幌には十軒の映画館がまとまって入ったビルがあって、これは凄いね」とある札幌スガイビルは、既にない。
村上春樹のエッセイにも、札幌の歴史的光景が描かれているのだ。
ちなみに、『羊をめぐる冒険』と『ダンス・ダンス・ダンス』は、北海道が重要な舞台として登場するので、北海道文学マニアにもおすすめ(そんな人がいれば、だけれど)。
それにしても、函館から札幌へ向かう特急列車に食堂車があったなんて、まるで夢みたいだ(「食堂車のビール」)。
我々の生活は、本当に豊かになっているのだろうか。
少なくとも、JR北海道(もと国鉄)に関しては、1980年代の方がずっと充実していたような気がするんだけれど(「冬こそJR」とかドヤ顔で言っていたというブラックジョークみたいな話もある)。
その他「ダッフル・コートについて」とか「報酬について」とか「夏について」とか、あまり生産性が高いとは思えないエッセイにも、意外と好きなものが多い。

小説とのギャップが大きいことも、アーリー村上春樹エッセイの大きな魅力だったのではないだろうか。
村上春樹のエッセイ集を一冊だけ残すとしたら、今でも『村上朝日堂』を選んでしまうかもしれない。
ちなみに、単行本の表紙裏には、猫を抱いた村上春樹の写真が掲載されている。
書名:村上朝日堂
著者:村上春樹・安西水丸
発行:1988/02/25
出版社:新潮文庫