村上春樹「村上朝日堂の逆襲」読了。
本作「村上朝日堂の逆襲」は、1985年(昭和60年)4月から1986年(昭和61年)4月にかけて『週刊朝日』に連載されたエッセイ集である。
連載開始の年、著者は36歳だった。
単行本は、1986年(昭和61年)6月に朝日新聞社から刊行されている。
群像新人賞の授賞式に出席した頃
この本の中に、すごく好きな作品がある。
「ダークブルー・スーツ」というエッセイである。
村上春樹には珍しく大人のファッションに関するエッセイだ。
僕が生まれてはじめてスーツを着たのは十八の年だった。今でもよく覚えているけれど、VAN・JACKETのグレーのヘリンボーン・スーツである。シャツは白のボタンダウンで、タイは黒のニット。アイヴィー全盛の頃の話である。(村上春樹「ダークブルー・スーツ」)
ヘリンボーンのスーツは、かなり渋いので、十八歳の少年には、あまり似合わなかったらしい。
二着目のスーツは、二十二歳で結婚したときに作った、渋いオリーブグリーンのブリティッシュ・スタイルのスリーピース。
当時の写真を見ると、髪が長く、今より(36歳のときのこと)痩せていて、わりによく似合っていたそうである。
興味深いのは、三着目に作ったスーツの話だ。
二十九の歳にたまたま応募した『群像』という文芸誌の新人賞に当選(というのかな)して、その授賞式に出るためにわざわざサマー・スーツを買ったのである。(略)当時は僕もつっぱっていて、文芸誌の新人賞受賞式ごときに出るためにちゃらちゃらと高いスーツなんか買えるかと思っていたのである。(村上春樹「ダークブルー・スーツ」)
結局、村上さんは、倒産バーゲンをやっていたVANで、オリーブグリーンのコットンスーツを、一万四千円で購入したという。
授賞式には、古いテニスシューズを履いて出席した。
このエピソードは、村上春樹の文壇に対する反骨精神を現わしているのだろう。
でも、最近は、個性的な作家志望者が多いので、古いテニスシューズを履いて授賞式に出席したくらいでは、異端とも呼ばれないのかもしれない。
東京から千葉へ引っ越しした頃
スーツの話に限らず、エッセイというのは、作家の人間性や生き方が反映されている。
書いてある内容が、事実か否かはともかく(嘘や誇張も多いんだろうな)、文章には書く人の本性みたいなものが、どこかに現われているものだ。
良いとか悪いとかの話ではなくて、だからエッセイは面白いのだろう。
藤沢から東京へ引越しをする「バビロン再訪」も興味深い作品だ。
以前に東京で生活していたときは、店をやりながら『風の歌を聴け』と『一九七三年のピンボール』という小説を書き、身も心もくたくたになって移った千葉では『羊をめぐる冒険』という長篇小説を書いた。
東京を棄てたのは「そのまま東京に住んでいると、じっくり腰を据えて小説が書けなくなってしまうような気がしたから」。
だから東京を離れるにあたって僕には僕なりの思いがあったし、その当時は「もう東京になんか戻るもんか」と思っていた。その騒がしさとテンションの高さとうわっつらのけばけばしさにかなりうんざりしていたのである。(村上春樹「バビロン再訪」)
久しぶりに暮らす東京は、大きく変貌してしまっていた。
今にして思うと、このとき、東京は(というか日本は)、あのモンスターみたいなバブル景気時代に突入しつつあったのだろう。
大きく変貌を遂げた東京は、やがて『ダンス・ダンス・ダンス』という長篇小説の中で、克明に描かれることになる。
たしかクレイグ・トーマスだったと思うけれど(『ファイア・フォックス』を書いた作家)、彼がある小説のあとがきの中で「多くの処女作は夜中に台所のテーブルで書かれる」といったようなことを書いていた。(村上春樹「バビロン再訪」)
ジャズ喫茶のオーナーだった村上春樹も、最初の二冊の小説を書いたのは、アパートの台所のテーブルだった。
小説の構成がぶつぶつに分断されているのは、一日に二、三時間しか書く時間がなかったから。
村上さん曰く「都会でサーバイブする人間の時間制のすきまからしぼり出された小説」ということになるらしい。
本人は満足していないようだけれど、少なくともデビュー作の『風の歌を聴け』は、今も僕は好きな作品の一つになっている。
ちなみに、本書は、巻末の対談(村上春樹と安西水丸)が本編以上に面白い。
書名:村上朝日堂の逆襲
著者:村上春樹
発行:1989/10/25
出版社:新潮文庫



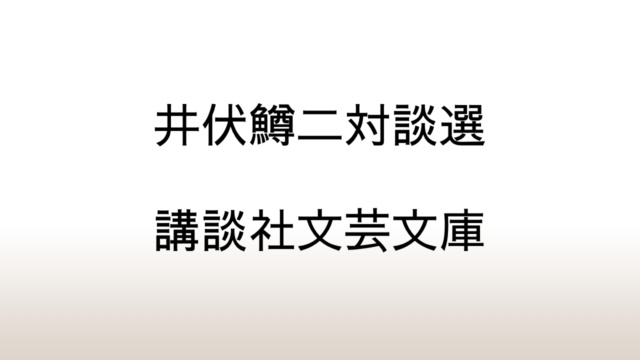


-150x150.jpg)









