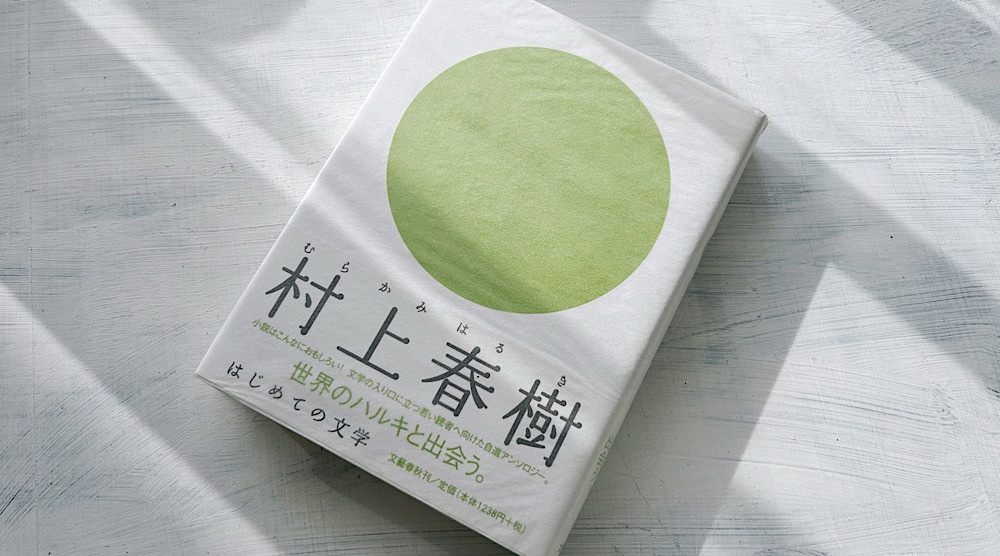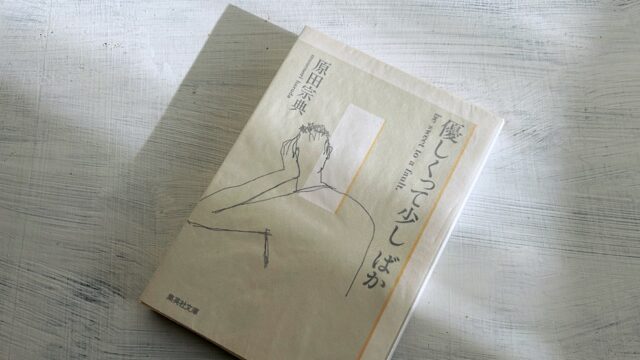村上春樹「鏡」読了。
本作「鏡」は、1983年(昭和58年)2月『トレフル』に発表された短篇小説である。
この年、著者は34歳だった。
作品集としては、1983年(昭和58年)9月に平凡社から刊行された『カンガルー日和』に収録された。
『はじめての文学・村上春樹』(2006)にも収録されている(村上春樹初心者にはおすすめ)。
本当の自分自身と向き合うことの恐ろしさ
本作「鏡」は、自分自身と向き合うことの怖さを伝えている短篇小説である。
主人公の<僕>は、若い頃、大学進学を拒否して、肉体労働をしながら日本中を旅して回った。
放浪二年目の秋、中学校の夜警として働いていたときに、<僕>は鏡の中の自分自身と向き合ってしまう。
そこには僕がいた。つまり──鏡さ。なんてことはない、そこに僕の姿が映っていただけなんだ。昨日の夜まではそんなところに鏡なんてなかったのに、いつの間にか新しくとりつけられていたんだな。(村上春樹「鏡」)
しかし、その「鏡」は、単なる鏡ではなかった。
なぜなら、鏡の中の<自分>は、激しく<僕>を憎んでいたからだ。
でもその時ただひとつ僕に理解できたことは、相手が心の底から僕を憎んでいるってことだった。まるでまっ暗な海に浮かんだ固い氷山のような憎しみだった。誰にも癒すことのできない憎しみだった。(村上春樹「鏡」)
結局、<僕>は鏡を壊して、その場から逃れるが、もちろん、そこには本物の鏡なんてなかった。
<僕>は、ただ「僕自身の内面」と向き合っていただけなのだ。
この物語から伝わってくるのは、本当の自分と向き合うことの恐ろしさである。
村上春樹の小説ではよくあることだけれど、人は誰も、今見えている自分のほかに、もう一人の自分を内面に持っている。
有名な「眠り(ねむり)」も、「もう一人の自分」を主人公とした短篇小説だ。
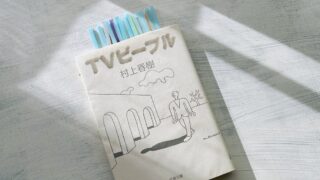
小説の中で、それは「森の中」だったり「壁の中」だったりするけれど、この物語では、それが「鏡の中」だった。
つまり、「鏡」は、自分自身の内面を映し出す道具として、この物語では用いられているのである。
いや、外見はすっかり僕なんだよ。それはまちがいないんだ。でも、正確には僕じゃないんだ。僕にはそれが本能的にわかったんだ。いや、違うな、それはもちろん僕なんだ。でもそれは僕以外の僕なんだ。それは僕がそうあるべきではない形での僕なんだ。(村上春樹「鏡」)
「本当の自分」と向き合った<僕>は、恐怖のあまり、鏡を破壊して、その場から逃げ去ってしまう。
本当の自分自身と向き合うということは、そのくらい恐ろしいことだったのだ。
今も、主人公の家には、ひとつの鏡もないという。
あの日以来、主人公は、鏡と向き合うことを(つまり本当の自分自身と向き合うことを)拒絶し続けているのだ。
自分の人生を憎んでいるのは自分自身だ
それでは、なぜ、鏡の中の自分は(つまり本当の自分自身は)、<僕>を憎んでいるのだろうか。
そのヒントは、作品の冒頭でしっかりと書かれている。
僕が高校を出たのは六〇年代末の例の一連の紛争の頃でね。なにかといえば体制打破という時代だった。僕もまあそんな波に吞みこまれた一人で、大学に進むことを拒否して、何年間か肉体労働をしながら日本中をさまよってたんだ。
そういうのが正しい生き方だと思ってた。ま、若気のいたりというかね。でも今から考えてみれば楽しい生活だったよ。それが正しかったとか間違っていたとかじゃなくて、もう一度人生をやりなおすとしても、たぶん同じことをやっているだろうね。(村上春樹「鏡」)
そして、放浪の旅に出た主人公は、二年目の秋に、「鏡」の中の自分自身と出会う。
つまり、大学に進むことを拒否して、肉体労働しながら日本中をさまよっている「自分自身」の内面と。
本人は「そういうのが正しい生き方だと思ってた」「今から考えてみれば楽しい生活だったよ」「もう一度人生をやりなおすとしても、たぶん同じことをやっているだろうね」と語っているけれど、それは本当だろうか?
その答えが、おそらく「鏡の中の自分」だ。
大学進学を拒否して、放浪の道を選んだ人生に、主人公は「満足している」と思いこもうとしているけれど、内面の中の彼は違ったのかもしれない。
大学に進まなかったことを後悔している自分、放浪の旅になんか出たことを後悔している自分、自分自身をごまかし続けている自分。
そんな自分自身の欺瞞に憎しみを突き付けているのが、「鏡の中の自分」だった。
それは「抑圧された自分」である。
プールの仕切り戸は頭のたがが外れた人間のように、不規則に否定と肯定を繰り返していた。うん、うん、いや、うん、いや、いや、いや……っていった具合にね。(村上春樹「鏡」)
否定と肯定を繰りかえしているのは、主人公自身の内面である。
現在の自分の生き方が正しいのか、間違っているのか。
彼自身の内面の葛藤が「プールの仕切り戸」に象徴されている。
おそらく、主人公は、そのまま何も考えることなく、平穏に生きていきたいと考えていたのだろう。
だから、彼は、決して自分自身の内面と(つまり、自分自身の本音と)向き合おうとはしなかった。
自分をごまかし続けることこそが、満足した人生を送るコツだったからだ(たとえ、それが自己満足の人生にすぎなくとも)。
以来、主人公は、鏡のない生活を送り続けている。
というわけで、僕は幽霊なんて見なかった。僕が見たのは──ただの僕自身さ。でも僕はあの夜味わった恐怖だけはいまだに忘れることができないでいるんだ。そしていつもこう思うんだ。人間にとって、自分自身以上に怖いものがこの世にあるだろうかってね。(村上春樹「鏡」)
本当に怖いもの、それは「自分自身を裏切った自分」のことだ。
人は誰も、自分自身を偽りながら生きていくことはできない。
できることは「自分は間違っていなかったんだ」と、信じているフリをしながら生きていくことだけだ。
もちろん、そんな人生は、きっと楽しくないだろう。
だからこそ、「信じた道を進んでいけ」と、この物語は教えてくれているのではないだろうか。
少なくとも、自分自身から憎まれ続けるような人生を送らないためにも。
村上春樹の小説のテーマは、自分自身の内面にあることが多い。
自分自身の内面を、どのように小説(物語)として書いていくのか。
そこに、村上春樹という小説家の面白さがある。
作品名:鏡
著者:村上春樹
書名:村上春樹全作品(1979-1989)第5巻
発行:1991/01/21
出版社:講談社