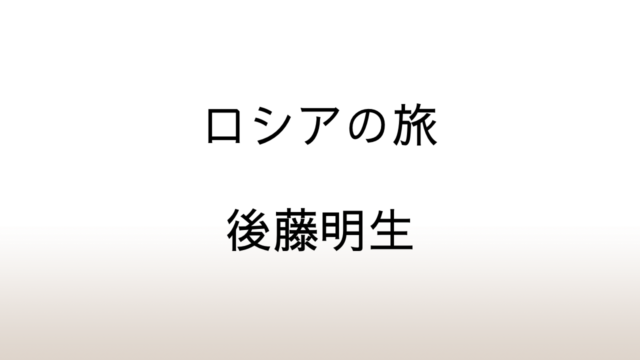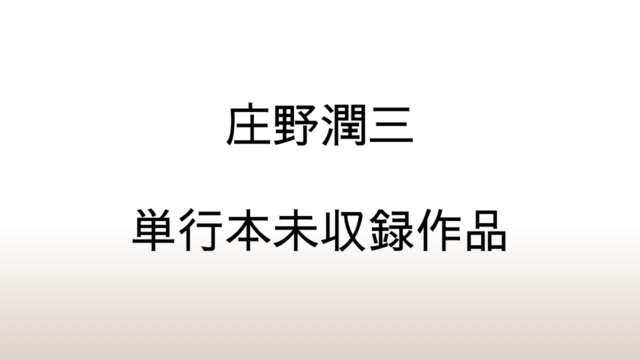夏目漱石「こころ」読了。
本作「こころ」は1914年(大正3年)4月から8月まで『朝日新聞』に連載された長編小説である。
この年、著者は47歳だった。
単行本は、1914年(大正3年)9月に岩波書店から刊行されている。
まるでミステリー小説「謎の男・先生」
本作「こころ」は漱石文学の最高峰と呼ばれる名作だが、意外と物語性が高く、読んで面白い小説となっている。
全3部構成のうち、「上 先生と私」は、鎌倉の海で<先生>と出会った私が、先生夫妻と仲良くなっていく様子が描かれているが、知れば知るほど、先生は謎の多い人物だった。
高学歴で教養がある割に、毎月一度友人の墓参りへ出かける以外は、特別の活動を行なっておらず、毎日家でブラブラしている。
子供ができないことを「天罰だ」と笑ったり、「恋は罪悪だ」と驚かせたり、財産の話になると突然興奮したり、「私は人類を憎んでいるんだから」と言ったり、とにかく先生には謎が多い。
<私>が先生の真実を知りたがったとき、先生は蒼い顔で<私>を問い詰める。
「あなたは本当に真面目なんですか」と先生が念を押した。「私は過去の因果で、人を疑りつけている。だから実はあなたも疑っている。しかしどうもあなただけは疑りたくない。あなたは疑るにはあまりに単純すぎるようだ。私は死ぬ前にたった一人でいいから、ひとを信用して死にたいと思っている。あなたはそのたった一人になれますか。なってくれますか。あなたは腹の底から真面目ですか」(夏目漱石「こころ」)
謎の男先生のキャラクターが、<私>の目によって少しずつ明らかにされていく。
それが、この上編の役割だ。
続く「中 両親と私」は、東京を離れて故郷へ帰った<私>が、父親の危篤に立ち会う話である。
一見、何の意味があるのかと思われる(本筋とは関係のないように見える)この中編には、先生の元を離れて、先生とはまるで対象的な実の両親と接することによって、<私>が先生の価値観を再認識するという役割が持たされている。
実際、<私>の両親と先生とは考え方や言動、そもそも生き方がまったく違っているので、この中編によって<私>は(あるいは読者は)、先生の生き方に対する理解を一層深めることになる。
「その先生は何をしているのかい」と父が聞いた。「何にもしていないんです」と私が答えた。私はとくの昔から先生の何もしていないという事を父にも母にも告げたつもりでいた。そうして父はたしかにそれを記憶しているはずであった。「何もしていないというのは、またどういう訳かね。お前がそれほど尊敬するくらいな人なら何かやっていそうなものだがね」(夏目漱石「こころ」)
上篇から下篇へといきなり繋がるよりも、ずっと良い構成である。
そして、いつまでも故郷へ残る私へ、先生からの長い遺書が届いて、物語はクライマックスの後編「下 先生と遺書」へと続く。
人の心の弱さというものを教えてくれる
学生時代に両親を亡くした先生は、後見人的な役割を果たしていた叔父に、両親の遺産をごまかされてしまう。
肉親に欺かれていたことを知った先生は、故郷と絶縁し、東京の下宿屋で暮らし始める。
下宿屋のお嬢さんに恋をした私は、窮地の親友Kを救うため、下宿にKを同居させるが、親友Kもお嬢さんを好きになってしまい、とうとう三角関係が発生する。
Kから恋の悩みを打ち明けられて焦った先生は、こっそりと親友を出し抜き、奥さんに直談判をして、お嬢さんを嫁にもらうことに成功する。
「精神的に向上心のないものは、馬鹿だ」私は二度同じ言葉を繰り返しました。そうして、その言葉がKの上にどう影響するかを見詰めていました。「馬鹿だ」とやがてKが答えました。「僕は馬鹿だ」(夏目漱石「こころ」)
こうして、先生とお嬢さんの結婚は無事に決まるが、予想外にも、奥さんから結婚の事実を聞かされたKが突然に自殺してしまう。
この「三角関係と親友Kの自殺」は、一般によく知られている『こころ』のエピソードだ。
以後、先生はKの自殺を背負いながら生きていくことになるのだが、目まぐるしく変化する先生の心理描写が、この後編の大きな柱となっている。
──というのが、本作「こころ」のざっくりとしたあらすじである(かなりざっくりだが)。
一般に、裏切りと人間不信とは対立の構図で理解されることが多い。
先生の裏切りによって人間不信に陥ったKが自殺へと追い込まれてしまったように。
ところが、先生には、身内たる叔父に裏切られたことで強い人間不信になったという経歴があり、裏切りと人間不信とは先生の中に共存する概念である。
つまり、人は「裏切る人」と「裏切られる人」に区分できるものではなく、その両方を内在する矛盾した存在だったのだ。
海援隊の『贈る言葉』という卒業ソングに「信じられぬと嘆くよりも、人を信じて傷つくほうがいい」というフレーズがある。
裏切る者と裏切られる者の対立構造が、そこにはあるが、おそらく、人間はそこまで単純ではない。
善人と悪人が同居しているからこそ、人間の心は複雑で難しいのである。
「君は今、君の親戚なぞのうちに、これといって、悪い人間はいないようだといいましたね。しかし悪い人間という一種の人間が世の中にあると君は思っているんですか。そんな鋳型に入れたような悪人は世の中にあるはずがありませんよ。平生はみんな善人なんです。少なくともみんな普通の人間なんです。それが、いざという間際に、急に悪人に変るんだから恐ろしいのです。だから油断ができないんです」(夏目漱石「こころ」)
本作「こころ」のテーマは、こうした人間心理の不思議な矛盾である。
そして、人間の心が豹変するきっかけとして「財産」と「恋愛」が大きな鍵となっていることも、この物語が与えている教訓の一つだろう。
お金は人間を変えるし、恋も人間を変える。
そこに、人間の心の弱さが象徴されているのではないだろうか。
何より、人間は罪の意識に弱い。
人の心の弱さというものを教えてくれているのが、この「こころ」という長篇小説なのである。
おすすめの出版社は文春文庫
夏目漱石「こころ」は、いろいろな出版社から文庫本が発売されている。
これまで、岩波文庫や新潮文庫、角川文庫で読んできて、それぞれの違いというか特徴を楽しんできたが、今回、初めて文春文庫を買って読んで、次の三つの点で非常に良かった。
まず、注釈がとても充実している。
「<私>のモデルは小宮豊隆と考えられる(森田草平)」というような作品背景まで注釈に書かれているから、作品理解を深めるのにすごくいい。
おまけに注釈は、見開き左ページの左端に掲載されているから、いちいち巻末をめくる手間が省けて効率的である。
もちろん、夏目漱石の年譜もちゃんと付いていて、至れり尽くせりだ。
二つめとして、漱石研究者として名高い江藤淳の「夏目漱石伝」と「作品解説」が収録されているのはありがたい。
これだけで充分に読み応えのある内容となっている。
三つ目として、文春文庫版「こころ」には、人気作「坊っちゃん」が併録されている。
一冊で「こころ」と「坊っちゃん」を楽しめるというのは、漱石ファンならずとも嬉しい配慮だろう。
文春文庫版「こころ」は、実にコスパが高いので、特に中学生や高校生の方々にはおすすめだと思った。
作品名:こころ
著者:夏目漱石
書名:こころ 坊っちゃん
発行:1996/03/10
出版社:文春文庫