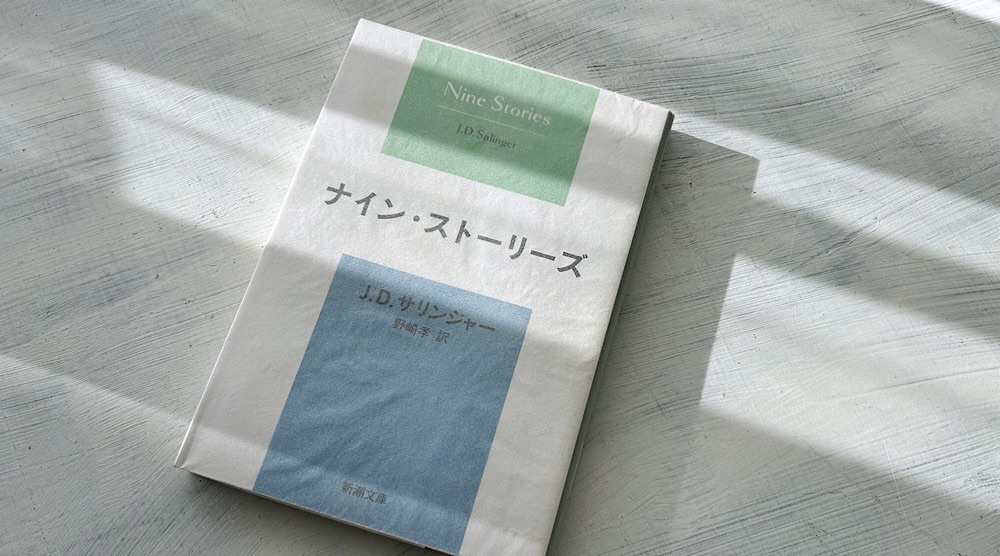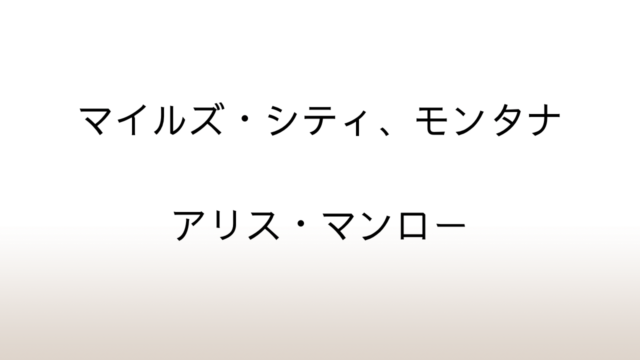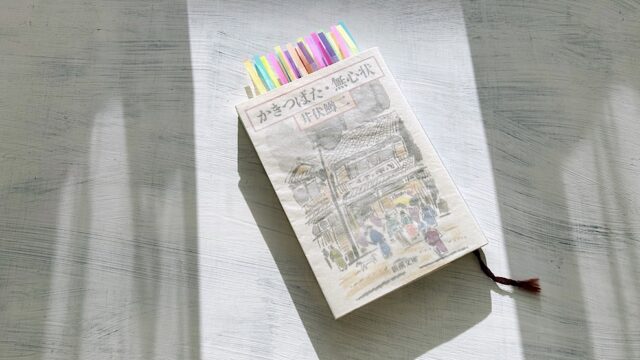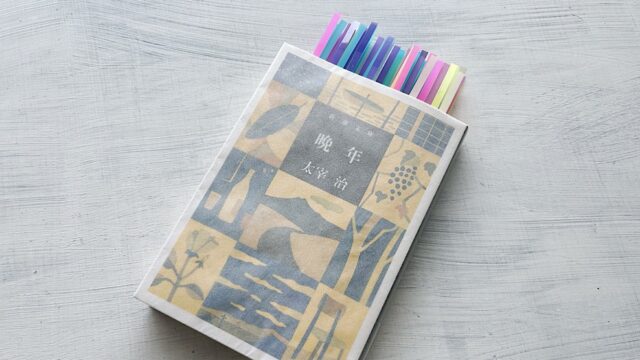サリンジャー『ナイン・ストーリーズ』読了。
本作『ナイン・ストーリーズ』は、1953年(昭和28年)4月にリトル・ブラウン社から刊行された短編小説集である。
この年、著者は34歳だった。
サリンジャーの短篇小説
生前、サリンジャーは、4冊の本を出版している(4冊の本しか出版していない)。
・『ライ麦畑でつかまえて』(1951)
・『ナイン・ストーリーズ』(1953)
・『フラニーとゾーイー』(1961)
・『大工よ、屋根の梁を高く上げよ シーモア-序章-』(1963)
このうち、いわゆる短編小説集は、本作『ナイン・ストーリーズ』のみで、全部で9篇の短篇小説が収録されている。
一方、サリンジャーが、雑誌等に発表した短篇小説は計30編あり、『ナイン・ストーリーズ』収録作品以外の21編は、本国アメリカでは書籍化されることがなかった(サリンジャーの死後に至るまで)。
ただし、なぜか、日本では、サリンジャーの全作品が翻訳・書籍化されており、『このサンドイッチ、マヨネーズ忘れてる/ハプワース16、1924年』『彼女の思い出/逆さまの森』などで読むことができる。


本書『ナイン・ストーリーズ』は、サリンジャーが公式に認めた唯一の短篇小説集だったということに、ひとつの意味があるかもしれない。
たった一冊の公認作品集ということもあって、『ナイン・ストーリーズ』の日本語版は、これまでに複数の翻訳で出版されている。
・ヴィレッジブックス『ナイン・ストーリーズ』柴田元幸・訳(2009)
・集英社文庫『九つの物語』中川敏・訳(1977)
・新潮文庫『ナイン・ストーリーズ』野崎孝・訳(1974)
・角川文庫『九つの物語』鈴木武樹・訳(1971)
・講談社『バナナ魚日和』沼澤洽治・訳(1973)
・荒地出版社『九つの物語』鷲尾久+武田勝彦・訳(1968)
・文建書房『J.D.サリンジャー作品集』鷲尾久+武田勝彦・訳(1964)
・思潮社『九つの物語』山田良成・訳(1963)
このうち、日本における『ナイン・ストーリーズ』のスタンダードと言えるのが、野崎孝・訳による新潮文庫版『ナイン・ストーリーズ』(1974)である。
特に、冒頭の作品「A Perfect Day for Bananafish」の日本語タイトル「バナナフィッシュにうってつけの日」は、野崎孝の訳で知られているものだ。
難解なサリンジャーを読み解く上で、複数の翻訳を読み比べてみることは、非常に大きな効果があるだろう。
本書収録作品(原題)及び初出は次のとおり。
「バナナフィッシュにうってつけの日」
・A Perfect Day for Bananafish
・1948年(昭和23年)1月『The New Yorker』
「コネティカットのひょこひょこおじさん」
・Uncle Wiggily in Connecticut
・1948年(昭和23年)3月『The New Yorker』
「対エスキモー戦争の前夜」
・Just Before the War with the Eskimos
・1948年(昭和23年)6月『The New Yorker』
「笑い男」
・The Laughing Man
・1949年(昭和24年)3月『The New Yorker』
「小舟のほとりで」
・Down at the Dinghy
・1949年(昭和24年)4月『Harper’s Magazine』
「エズミに捧ぐ──愛と汚辱のうちに」
・For Esme with Love and Squalor
・1950年(昭和25年)4月『The New Yorker』
「愛らしき口もと目は緑」
・Pretty Mouth and Green My Eyes
・1951年(昭和26年)7月『The New Yorker』
「ド・ドーミエ=スミスの時代」
・De Daumier-Smith’s Blue Period
・1952年(昭和27年)5月『World Review』
「テディ」
・Teddy
・1953年(昭和28年)1月『The New Yorker』
ほとんどの作品が『ニューヨーカー』に掲載されたものだったことが分かる。
また、『ナイン・ストーリーズ』は、いわゆる「最新作品集」でもあって、1953年(昭和28年)4月の単行本刊行から遡って、最新の作品ばかり9篇が収録された。
禅の公案「隻手音声」の意味
本作『ナイン・ストーリーズ』には、有名なエピグラムがある。
両手の鳴る音は知る。片手の鳴る音はいかに? ──禅の公案──(J.D.サリンジャー『ナイン・ストーリーズ』野崎孝・訳)
これは「隻手音声(せきしゅのおんじょう)」という禅の公案である。
両手の鳴らす音は知っているが、片手で鳴らす音は、どんな音か?
そんなの聴こえるわけがない。
しかし、聴こえないから、すなわち、音がない、ということでもない。
要は「理屈で考えるな」ということ、らしい。
『ナイン・ストーリーズ』を刊行するとき、サリンジャーは、鈴木大拙の『禅仏教入門』(1934)という英文著作を読んでいたという考察がある。
たしかに鈴木の諸著作が英米の出版社から再版されるようになったのは主に四八年以降ではある。しかし、サリンジャーが四〇年ごろに通ったコロンビア大学には東アジア図書館があり、当時から鈴木の英文著作に触れることは可能であっただろう。(竹内康浩・朴舜起「謎ときサリンジャー」)
「隻手音声」は、鈴木大拙『禅仏教入門』にも登場する、有名な禅の公案だ。
白隠禅師はよく片手を突き出して、弟子たちに隻手の音声を聞けと要求した。普通には両手を拍ったときに音響が生じるものであって、その意味からすれば、片手だけではどんな音も聞こえてこないはずである。しかしながら白隠は、いわゆる科学的・論理的と呼ばれる碁盤の上に建てられたわれらの日常生活を根本から撃滅せんとしたのである。(鈴木大拙「禅仏教入門」増原良彦・訳)
ポイントは「科学的・論理的と呼ばれる碁盤の上に建てられたわれらの日常生活を根本から撃滅せんとした」という部分で、本作『ナイン・ストーリーズ』でも、科学や論理では読み解くことのできない場面が登場する(特に、最後の「テディ」)。
「公案は一般に合理化へのあらゆる通路を断ち切るものである」と、鈴木大拙は説いたが、これは、テディ少年が「林檎という論理を吐き出してしまえ」という趣旨のことを言っているのと同じことだろう。
読者に求められているのは、論理を超えて、物語を受け入れることである。
『ナイン・ストーリーズ』を読む読者は、まず、このエピグラムを、しっかりと理解しておかなくてはならない。
バナナフィッシュにうってつけの日
本書収録作品中、最も古い作品であり、サリンジャーの全作品中『ライ麦畑でつかまえて』と並んで、最も有名な作品のひとつである。
心に深い傷跡を追った帰還兵が、現代社会に馴染むことができない様子が描かれている。
過去、サリンジャーは、同様のテーマの短篇小説をいくつも発表しており(「他人」「彼女の思い出」など)、戦場と日常社会との対比は、サリンジャーにとって、大きな文学的テーマとなっていた。
不幸なジャズシンガーを描いた「ブルー・メロディ」にさえも、同様の通奏低音は流れている。
ちょっとした単純な話で、母親のアップルパイと、きんきんに冷えたビールと、ブルックリン・ドジャーズと、ラックス化粧石鹸提供のラジオ劇といったもの──簡単にいえば、われわれがそのために戦っているものの話なのだ。(J.D.サリンジャー「ブルー・メロディ」金原瑞人・訳)
「われわれがそのために戦っているもの」は、黒人のジャズシンガーを見殺しにしたものであり、傷付いた帰還兵(シーモア)を自殺へと追い込んだものでもある。
そして、本作品において「われわれがそのために戦っているもの」は、「バナナフィッシュ」という幻の魚によって具現化された。
「バナナフィッシュ」は、醜悪な(憎悪すべき)現代社会を象徴する存在である。
浮袋がふたたび水平になると、シビルは濡れてぺったり目にかぶさった髪の毛を片手で払いのけ「いま一匹見えたわよ」と、言った。「見えたって、何が?」「バナナフィッシュ」(J.D.サリンジャー「バナナフィッシュにうってつけの日」野崎孝・訳)
俗物的な「バナナフィッシュ」にとって「最高の一日」は、俗社会に馴染むことのできない帰還兵にとって、それ以上、生きていくことができないくらい「最悪の日」だった。
主人公(シーモア)は自殺したのではない。
俗悪な現代社会に抹殺されたのだ(比喩ではない、現実的に「見殺し」にされたのだ)。
以降、作者(サリンジャー)は、主人公(シーモア・グラース)の伝説を書き続けることになり、それは、グラース・サーガ(グラース家の物語)という壮大な作品群へと発展することにもなった。
『ライ麦畑でつかまえて』と並ぶ、サリンジャー最高傑作のひとつである。
『ニューヨーカーの55短編:1940-1950』に再録された。

コネティカットのひょこひょこおじさん
本作「コネティカットのひょこひょこおじさん」は、郊外に住む中流家庭の主婦の、心の闇を描いた作品である。
エロイーズの闇は、彼女が人妻であり、母親であるが故に描かれるものである。
愛する男(ウォルト)を戦争で亡くし、それほど愛していない男と結婚したエロイーズは、妄想彼氏と一緒に暮らす幼い娘(ラモーナ)に、自分の孤独を発見する。
彼女はラモーナの眼鏡を手にとった。そして両手で握りしめて固く頬に押し当てた。涙があふれ出て、眼鏡のレンズを濡らした。「かわいそうなひょこひょこおじさん」何度も何度も繰り返して彼女はそう言った。(サリンジャー「コネティカットのひょこひょこおじさん」野崎孝・訳)
ラモーナの孤独は、エロイーナ自身の孤独でもあった。
エロイーズが足首を挫いたとき、元カレ(ウォルト)は「かわいそうなひょこひょこおじさんだな」と言って慰めてくれた。
「ひょこひょこおじさん」は、ハワード・ギャリスの連作童話に登場する主人公の名前である(親切な年寄り兎はリュウマチの脚を嘆いていた)。
傍目には満ち足りた生活を送っているように見えたエロイーズ(中流家庭の主婦の象徴)も、心のうちでは、満足できない生活の中で、大きな孤独を抱えていたのである。
ちなみに、コネティカット州は、ニューヨーク州に隣接しており、最も人口の多いブリッジポートからニュークまでは、約100キロメートル(「ニューヨーク大都市圏」とも呼ばれる)。
当時、サリンジャーは、コネティカット州スタンフォードに暮らしており、郊外に住む中流家庭という新興階級に大きな興味を持っていたらしい
エロイーナが愛した男(ウォルト)は、後にシーモア・グラース(「バナナフィッシュにうってつけの日」で自殺した主人公)の弟であることが明かされる。
グラース・サーガ(グラース家の物語)のひとつである。
1950年(昭和25年)公開のハリウッド映画『愚かなり我が心』原作小説だが、映画があまりにひどかったため、原作者サリンジャーは激怒したという。
以後、サリンジャー作品が映画化されることは、二度となかった。
対エスキモー戦争の前夜
本作「対エスキモー戦争の前夜」は、鬱屈した気持ちを抱える少女が、純真な若者との会話を通して、無垢だった頃の自分を取り戻すという、再生の物語である。
15歳の女子高生(ジニー・マノックス)は、ひどく心の狭い、意地悪な女の子だったが、セリーナの兄(フランクリン)との会話が、彼女を別人のように蘇らせてしまう。
この小説のポイントは、間違いなくジニーとフランクリンとの会話だ。
「うちの姉、どんな顔してるか言ってごらんなさいよ」ジニーは繰り返してそう言った。「自分で思ってるのの半分も美人だったら、まあ運がいいほうだな」と、セリーナの兄は言った。(サリンジャー「対エスキモー戦争の前夜」野崎孝・訳)
「男」なのか「男の子」なのか分からないような不思議な容姿のフランクリンは、ジニーの前でも平気で、ジニーの姉(ジョーン)の悪口を言ってみせる(彼はかつてジョーンにフラれていた)。
女の子に気にいられようなんて、これっぽっちも考えていない自然体の会話だ。
純真なフランクリンと話を続けていく中で、二人の心は少しずつ通い合っていく。
あるいは、ジニーにとってフランクリンとの会話は、カウンセリングのようなものであったのかもしれない。
この物語が「数年前、復活祭の贈物にもらったひよこが、屑籠の底に敷いた鋸屑の上で死んでいるのを見つけたときにも、捨てるのに三日もかかったジニーであった」という一文で終わっているのは、ジニーが優しい気持ちを持っていた「数年前」の頃のジニーに復活したことを暗に示しているからだ。
作品タイトル「対エスキモー戦争の前夜」は、フランクリンの言葉に由来している。
「こんだエスキモーと戦争するんだ。知ってるか、あんた?」「どことですって?」と、ジニー。「エスキモーだよ」(サリンジャー「対エスキモー戦争の前夜」野崎孝・訳)
この物語の底を流れているのは、現代社会に対する大きな不信感だろう。
「どうしてエスキモーと?」「知るもんか。このおれが知るわけないだろう? 今度の戦争にはな、年寄り連中がみんな行くんよ。六十ぐらいの奴らがな」(J.D.サリンジャー「対エスキモー戦争の前夜」野崎孝・訳)
非現実的な「エスキモーとの戦争」は、アメリカ社会に対する強烈なアイロニーであり、「今度の戦争にはな、年寄り連中がみんな行くんよ」という言葉には、若者たちを戦場へ送り込んだ現代社会に対する強い憎悪を感じる。
フランクリンも、また、戦争の傷痕を抱えた若者の一人だったのだ。
『1949年度受賞短篇集』(ダブルデー社)に再録された。
笑い男
短編小説「笑い男」には、二つのストーリーがある。
ひとつは、コマンチ団の団長(ジョン・ゲザツキー)が、絶世の美女(メアリ・ハドソン)に失恋する物語で、もうひとつは、その団長が子どもたちに話して聞かせる「笑い男」の物語だ。
団長の語る「笑い男」は、もちろん団長自身の話でもある。
「あたしにかまわないで」と、彼女は言った。「お願いだから、ほっといてちょうだい」私はまじまじと彼女を見つめたが、それからその場を離れてウォリアーズのベンチに向った。(J.D.サリンジャー「笑い男」野崎孝・訳)
一人の美しい女性が現れ、やがて姿を消してしまうというのが、この物語の本編の大筋だが、彼女と交際している男性(団長)の心理は、団長がバスの中で少年たちに話して聞かせる「笑い男」という創作物語の中に投影されていく。
彼はオンバに顔をそむけるように命じた。オンバは啜り泣きながらその命に従った。それから笑い男は自分の仮面を剥ぎ取った。それが彼の最期だった。そしてその顔が、血に染まった地面に向ってうつむいたのである。(サリンジャー「笑い男」野崎孝・訳)
「笑い男」の物語は、美しいメアリ・ハドソンに恋をする団長の心のメタファーであり、壮絶な死を遂げた笑い男の最後は、恋に破れた団長の絶望を巧妙に描き出している。
シャーウッド・アンダースンの影響が指摘されている作品(「わけが知りたい」)。
小舟のほとりで
社会からの疎外感を抱えて生きるニューファミリーの姿が、静かに描かれている。
主人公は、もちろん、25歳の母親(ブーブー・タンネンバウム)だが、彼女は、息子(ライオネル)との会話を通じて、タンネンバウム一家の孤独を浮かび上がらせている。
「残念だわ」しまいに彼女はそう言った。「きみの舟に乗りたくてたまんないんだけどなあ。きみがいないと淋しいんだもの。会いたくてたまんないの。一日じゅうおうちの中で一人ぽっちだったのよ、話相手もなくて」(J.D.サリンジャー「小舟のほとりで」野崎孝・訳)
嫌な女中たちが主人一家の陰口(ユダヤに対する人種差別)を叩いているが、それは、社会の闇をあぶり出すものでもあった。
本作の主人公ブーブー・タンネンバウムは、グラス家の一人である。
「あの眼鏡はウェッブ伯父さんのものよ。伯父さん、きっと喜ぶわよ」ブーブーは一口煙草を吸った。「昔はシーモア伯父さんのだったんだもん」(J.D.サリンジャー「小舟のほとりで」野崎孝・訳)
「旧姓グラース」「昔はシーモア伯父さんのだったんだもん」などというブーブーの台詞から、主人公(ブーブー)が「バナナフィッシュにうってつけの日」で自殺した青年(シーモア・グラース)の妹であったことが分かる。
この作品も、また、グラース・サーガ(グラース家の物語)のひとつだったのだ。
『ニューヨーカー』誌で不採用となったため、やむなく『ハーパーズ』誌に発表されたもの。
エズミに捧ぐ─愛と汚辱のうちに
本作「エズミに捧ぐ」は、戦争で精神を病んだ若者が、一人の少女からの手紙によって希望を取り戻すという、破滅と再生の物語である。
主人公の職業が短編作家だと知ったとき、少女(エズミ)は、「自分だけのための短編小説を書いてほしい」と、主人公に願う。
「どちらかといえば、汚辱のお話が好き」と、言った。「何の話ですって?」私は身を乗り出して言った。「汚辱。わたし、汚辱ってものすごく興味があるの」(J.D.サリンジャー「エズミに捧ぐ」野崎孝・訳)
貴族の流れを汲むという彼女は、毅然としてはいたけれど、戦争で両親を失ったダメージには、やはり計り知れないものがあったのだろう。
やがて、物語の主人公は「わたし」から「X」へと転換するが、神経衰弱の「わたし」に、一人称で物語を進めることは難しかったのかもしれない。
激しい戦闘で精神を病んだ主人公を救ったのは、ロンドンへ出発する直前に出会った13歳の少女(エズミ)からの手紙だった。
彼女は手紙に同封されていた「父の形見」だという腕時計は、ガラスのところが壊れていたが、その腕時計を手にしているうち、彼は陶然と引き込まれていくような快い眠気を覚える。
エズミ、本当の眠気を覚える人間はだね、いいか、元のような、あらゆる機──あらゆるキ─ノ─ウがだ、無傷のままの人間に戻る可能性を必ず持っているからね。(サリンジャー「エズミに捧ぐ」野崎孝・訳)
ガラスの壊れた腕時計は、戦争で病んだ主人公の象徴だ。
極度の不眠から解放された主人公には、回復へのわずかな希望を感じることができる。
つまり、彼の心は腕時計のガラスのように壊れているけれど、人間としての機能はまだ壊れてはいないということが、ここに暗示されているということだ。
作者(サリンジャー)のアメリカに対する感情は、イギリスの少女(エズミ)の言葉によって示唆されている。
「だって」と、彼女は言った。「わたしの見たアメリカ人って、やることがまるで動物みたいなんですもの、いっつもおたがいに撲り合いをしたり、みんなを侮辱したり、それから──一人はどんなことをしたか、ご存じ?」(サリンジャー「エズミに捧ぐ」野崎孝・訳)
傷付いたアメリカ兵の苦悩を描きつつ、本作「エズミに捧ぐ」は、戦地におけるアメリカ兵の恥ずべき姿をも同時に描いている。
アメリカ兵の神経衰弱も、アメリカ兵による乱暴な行為も、つまりは戦争に対する批判であり、戦争に参加した本国アメリカに対する批判なのだ。
「汚辱」とは、戦争に参加した故国アメリカの姿であり、戦争そのものの姿である。
汚辱を拭うことができるのは、人間による、人間同士の愛であり、どのような汚辱も、純粋な愛によって救われる可能性があるのだ。
無垢な少女からの手紙が、戦場で傷ついた青年の心を慰める構図は、「フランスにて」にも共通のものである。
やがて、『ライ麦畑でつかまえて』で、イノセントな少女(フィービー)が、兄(ホールデン・コールフィールド)の心を慰めるのも、「エズミ」や「フランスにて」と同様の構図と読んでいい。
愛らしき口もと目は緑
本作「愛らしき口もと目は緑」は、若き人妻と情事に耽る中年男性の心の動揺を描いた不倫小説である。
ある深夜、ベッドで若い女とイチャイチャしていた白髪まじりの男(リー)のところに、事務所の後輩(アーサー)からの電話がかかってくる。
どうやらアーサーの妻が帰っていないらしく、泥酔したアーサーは半狂乱になっている。
「俺にはどうも女房の野郎、台所でどっかの馬の骨にモーションかけたんじゃないかっていう気がするんだ。どうもそんな気がするよ。あいつ、酔っ払うと、きまって台所でどっかの野郎といちゃつきやがるんだ」(J.D.サリンジャー「愛らしき口もと目は緑」野崎孝・訳)
この物語のポイントは、アーサーの電話によって、人妻を寝取っている最中のリーの心境に、大きな変化が現れていくところだろう。
アーサーがジョーニーを罵倒するところでは、リーはそれとなくジョーニーの弁護をする。
アーサーが「ジョーニーはどんなに老いぼれた薄汚い不潔な男とも寝るんだ」と言ったときには、リーはそれが自分のことを指摘されたような気がして、大きな声で相手を制する。
さらに、アーサーが、「ジョニーとはもう離婚する」と言ったときには、自分が離婚原因となったような気がして動揺する。
このとき、アーサーは、夫と別れた人妻の面倒を自分が見ることになりはしないかと、ちょっと不安を覚えたに違いない。
ところが、アーサーが「ジョーニーから優しくされた」という思い出話を始めたところで、リーの性欲は急速に冷めてゆく。
結局のところ、人妻というのは、最後には家庭の中へ帰っていくものだ。
そのことが、アーサーに不倫の情事の虚しさを思い出させたのかもしれない。
一度切れた電話が再び鳴り、アーサーは「ジョーニーが帰ってきた」とリーに報告する。
アーサーとジョーニーの件は落着したが、リーには既に、隣で寝ている女とセックスを続ける気持ちにはなれない。
「あたしはなんだか犬にも劣る女みたい!」などと言っている女の向こう側に、リーは、アーサーと同じように、嫁の帰りを待っている哀れな男の姿を見たのだろうか。
ド・ドーミエ=スミスの青の時代
本作『ド・ドーミエ=スミスの青の時代』は、自己中心的な若者が、悟りを得て虚像から解き放たれるという、覚醒の物語である。
1939年(昭和14年)、フランス・パリの美術展で三つの金賞を得ていたこともあり、19歳の主人公には、自分以外の人間がすべて無価値に思えていた(彼が描く絵のほとんどが自画像だった)。
作品タイトル「ドーミエ・スミス」は彼の偽名で、年齢は29歳、彼の両親の親友はパブロ・ピカソという触れ込みだった。
ドーミエ・スミスは、自己顕示欲に満ちた主人公の作り出した虚像である。
ところが、彼の就職した美術学校は、モントリオールで最も貧しい地区にある下級アパートの二階の一部屋で、一階には整形外科の医療器具を売る店が入っていた。
きらびやかな彼の虚像に対して、現実の世界は、いかにも貧相で、虚像と現実との大きなギャップが早くも露呈しているが、それでも、彼の自己顕示欲が衰えるところはない。
ミス・クレーマーが封入してよこしたのは八インチに十インチの光沢のある印画紙を使った大型の照影で、ストラップレスの水着を着て白いズックの水兵帽をかぶり、片方の足首にアンクレットをはめている。(J.D.サリンジャー「ド・ドーミエ=スミスの青の時代」野崎孝・訳)
作品よりも自分の写真を強調して送ってきた23歳の主婦に、主人公はうんざりする。
さらに、もう一人の生徒(56歳の男性)の作品は、巨乳の女性が、教会で牧師から強姦されている場面を描いた風刺画で、これも主人公の気に入らないが、作品に署名があるところを含めて、その実、主人公と彼らとは、似た者同士の仲間だった。
主人公が興味を持ったのは、名前も年齢も不詳の修道女が描いた宗教画で、彼女と個人的につながりたいと考えた主人公は、修道院に宛てて私的な手紙を送るが、彼女の返信を待ちわびていたある日、主人公は不思議な体験をする。
いつの日にかおれは人生を心静かに、もしくは聡明に、もしくは優雅に生きるすべを悟るかもしれぬ。だがそれにしてもおれはしょせん一介の訪問客、琺瑯引きの溲瓶や便器の花が咲きほこり、目の見えぬ木製のマネキン人形の神が、値下げ札のついた脱腸帯をしめて立っている花園を訪れた一介の訪問客に過ぎぬではないか──(J.D.サリンジャー「ド・ドーミエ=スミスの青の時代」野崎孝・訳)
医療器具のショーウィンドウを前にして、彼は虚像と現実の乖離に気付く。
自分の虚像を認識した若者の成長が、この作品では描かれているのである。
彼の成長物語には、さらに大きなエピソードがある。
例のショーウィンドウで、三十歳位の女性が、マネキン人形の脱腸帯を交換している様子を目撃した<わたし>は、神秘主義的とも言える異常な経験をするのだ。
突然太陽が現われて(と、こういうことを言うに当って、わたしはそれ相当の自意識をもって言っているつもりだが)太陽が現われて、わたしの鼻柱めがけて、秒速九千三百万マイルの速度で飛んで来たのだ。わたしは目がくらみ、ひどくおびえて──ウィンドーのガラスに片手をついてようやく身体を支えたくらいである。続いたのはほんの数秒に過ぎなかった。そしてふたたび目が見えるようになったとき、ウィンドーの中にはすでに女性の姿はなく、後には二重の祝福を受けた世にも美しい琺瑯の花の花園が微かな光を放っていた。(J.D.サリンジャー「ド・ドーミエ=スミスの青の時代」野崎孝・訳)
尿瓶や便器が並ぶ医療器具店のショーウィンドウで、突然に悟りを得た主人公は、新しい主人公へと生まれ変わる。
間もなく、美術学校は閉校になってしまうが、主人公は、その夏を、ショートパンツのアメリカ娘たちを眺めながら楽しく過ごした。
自分以外のすべてが無価値に思えていた頃の彼は、もういない。
医療器具店のショーウィンドウで悟りを得た若者は、虚像を棄てて、現実の世界に生きることに決めたのである。
本作「ド・ドーミエ=スミスの青の時代」で描かれているのは、主人公の啓示体験である。
自意識過剰で傲慢な若者は、神秘的な啓示体験によって悟りを開き、すべてを受け入れることができるようになる(「シスター・アーマには自らの運命に従う自由を与えよう。すべての人が尼僧なのだ」)。
キリスト教をモチーフとしながら、主人公の啓示体験は、むしろ「禅」を匂わせるものだ。
ちなみに、サリンジャーが代表作となる『ライ麦畑でつかまえて』を発表するのは、「ド・ドーミエ=スミスの青の時代」発表の前年に当たる1951年(昭和26年)7月のこと。
『ライ麦畑』の発表を経て、サリンジャーの小説は、宗教的な要素を強めていく。
テディ
この作品は、『ナイン・ストーリーズ』で最も難解な作品であって、冒頭に掲げられたエピグラムと、最も密接な関わりを有する作品だと言える(つまり「隻手音声」を具現化した作品)。
この物語は、前世の記憶を持つ早熟の少年を主人公にした、輪廻転生の物語である。
テディは、「輪廻転生」を知る神秘的な少年だった。
「死んだら身体から跳び出せばいい。それだけのことだよ。誰しも何千回何万回とやってきたことじゃないか。覚えていないからといって、やったことがないことにはならないよ。全く馬鹿馬鹿しい」(J.D.サリンジャー「テディ」野崎孝・訳)
船上で出会った青年(ニコルソン)は、あくまで理屈で反論しようとするが(「しかし論理的事実としてはやはりだね、いくら理知的に──」)、テディ少年は、理屈そのものを受け入れようとはしない。
ニコルソンはデッキ・チェアの横から片脚を下ろし、身を乗り出して煙草の火を踏み消した。それからまた椅子に背を沈めながら「ぼくの理解するところでは」と、言いだした。「きみはヴェーダンタ哲学の輪廻説を固く信奉してるようだね」「輪廻説は説なんてもんじゃない、むしろそれは──」(サリンジャー「テディ」野崎孝・訳)
ヴェーダーンタ哲学は、インド哲学・ヒンドゥー教における学派の一つで、ウパニシャッドの「梵我一如思想」を主軸としているものだ。
松尾芭蕉の俳句が引用されていたりと、東洋思想の影響は、本作において大きなポイントとなっている。
「やがて死ぬけしきはみえず蝉の声」だしぬけにテディは言った。「この道や行く人なしに秋の暮」(J.D.サリンジャー「テディ」野崎孝・訳)
テディ少年が暗唱する松尾芭蕉の俳句は、少年が「無我の境地」を意識していることを示している(「感情的な要素がたっぷりという材料はほとんど使ってないでしょう」「感情的であるということをどうして人はそんなに大事なことだと思うのかなあ」)。
「ということは、きみには感情がないということ?」テディはしばらく考えてからおもむろに口を開いて「持ってるにしても、使った記憶はない」と、答えた。「感情って何の役に立つのか分かんないんだ」(J.D.サリンジャー「テディ」野崎孝・訳)
前世で、インドの聖者だったテディは、最終的悟達に達する直前、一人の女性に心を奪われたために瞑想を中断し、新たにアメリカ人として生まれ変わったのである。
「すべてが神だと知って、髪の毛が逆立ったりなんかしたのは六つのとき。今でも覚えてるけど、あれは日曜日だった。そのころ妹はまだ赤ん坊で、ミルクを飲んでたんだけど、全く突然に、妹は神だ、ミルクも神だってことが分かったんだな」(J.D.サリンジャー「テディ」野崎孝・訳)
「妹は神だ、ミルクも神だ」というテディの主張は、後に『フラニーとゾーイー』に登場する「誰もが太っちょのおばさんなんだ」という言葉にも対応するものだろう。
教育学者であるニコルソンは、テディの話を理解できないが、それは、ニコルソンが「論理的であろうとするからだ」と、テディは指摘する。
聖書に出てくる「エデンの園」で、アダムが食べたりんごの中に入っていたのは、論理とか知性とかいったもので、物事をありのままに見ようと思ったら、そいつを吐き出してしまわなくてはならない。
つまり、本作「テディ」では、こうした論理的思考からの解放こそが大きなテーマとなっているのだ(というか、むしろ、論理的解釈は無意味)。
ここに、エピグラム「片手の音を聴け」の意味がつながってくる。
両手の鳴る音は知る。片手の鳴る音はいかに? ──禅の公案──(J.D.サリンジャー『ナイン・ストーリーズ』野崎孝・訳)
本作「テディ」のテーマは、あらゆる論理からの解放である。
そして、以降、サリンジャーは、この「テディ」路線を強力に推し進めていくことになる。
そもそも、「テディ」という短篇小説自体、シーモア・グラースの弟(バディ・グラース)の作品だったということが、後に明かされる。
「テディ」のモデルは、おそらく、グラース家の長男(シーモア)だ(「バナナフィッシュにうってつけの日」で自殺した青年)。
自殺した長兄(シーモア)の伝説を残すために、サリンジャーは小説を書き続けた。
『フラニーとゾーイー』(1961)、『大工よ、屋根の梁を高く上げよ シーモア-序章-』(1963)、『ハプワース16、1924年』(1965)と、多くの作品で、サリンジャーは、シーモアを描いている。
「テディ」は、こうした一連の作品の、原点とも呼ぶべき重要作品だったのだ。
書名:ナイン・ストーリーズ
著者:J.D.サリンジャー
訳者:野崎孝
発行:1974/12/20(1988/1/30改版)
出版社:新潮文庫