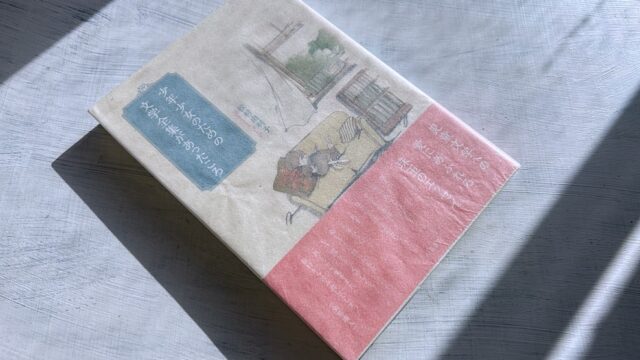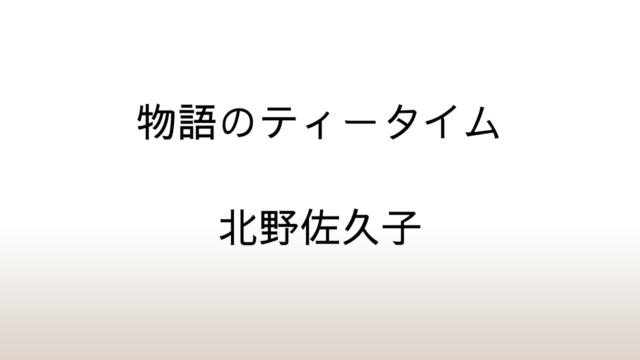石井桃子「ノンちゃん雲に乗る」読了。
本作「ノンちゃん雲に乗る」は、1947年(昭和22年)、大地書房から刊行された、石井桃子の処女長篇作品である。
なお、本作刊行時、著者の石井桃子は40歳だった。
それぞれの家族の思い出によって救われている大人たち
この長い児童文学作品のポイントを一つだけ抜き出してみる。
「昔」でなく「いま」自分はこうして、おかあさんのお話を聞いている……なんという不思議なことだろう。おじいちゃんのおとうさんにも、やはりその人のおかあさんから、このようにしてお話を聞いた「いま」があったはずです。でも、それは「昔」になってしまいました。けれど、「いま」ノンちゃんは、こうしておかあさんといます。「いま」は! 「いま」は!(石井桃子「ノンちゃん雲に乗る」)
この文章は、「いつのまにかノンちゃんは、しっかりおかあさんにつかまっていました。おかあさんが逃げだしてしまいそうな気がしたのです」という文章へと繋がっていく。
この物語は、8歳のノンちゃんが、自分の「生いたちの記」を語って聞かせるという構成になっているが、この「生いたちの記」は、大人になった「私」が、少女期を思い出して綴ったものと考えることができる。
そのとき、「私」の中に特に重要な要素として意識されていたものは、時間の流れではなかっただろうか。
「おかあさんが逃げだしてしまいそうな気がした」は、幼いノンちゃんの直感として描かれているが、語り手である「私」は、家族の穏やかな暮らしが永遠ではないことを知っている。
そう考えながら読んだせいか、文章を読み進めるうちに、やたらと自分自身の子ども時代のことが思い浮かばれて仕方なかった。
「ノンちゃん雲に乗る」は、少年少女には未来を感じさせ、大人には子供時代を思い起こさせる物語なのである。
作中、ノンちゃんは、目には見えない多くの大人たちを前にして、自分の「生い立ち」を話して聞かせている。
<おじいさん>の話によると、「ここにいる人たちはな、みんなおまえの同類さ。かなしゅうてかなしゅうて、泣いて泣いて、あまり心が重くなり、地下天国へおちてござった方々」である。
おそらく、全能の語り手たる「私」自身も、「かなしゅうてかなしゅうて、泣いて泣いて、あまり心が重くなり、地下天国へおちてござった方々」の一人だったのではないだろうか。
そして、そんな「私」を救ってくれるものが、懐かしい家族の思い出だったとしたら、「地下天国へおちてござった方々」も、それぞれの家族の思い出によって救われているかもしれないのである。
「そうです。ノンちゃんの帰るところは、世界じゅうにただひとつです。それは、おかあさんのふところでした」という最後の一文とともに。
昭和初期の日本の一般家庭における平穏な幸福
ところで、この物語は、東京都が、まだ東京府だった時代の物語である。
東京都制の施行は1943年(昭和18年)だから、戦前の東京郊外が舞台になっているのだが、物語全体に流れる柔らかいトーンが心地良い。
自分が最も気に入っているのは、ノンちゃんが目を覚ます朝の場面だ。
お勝手で、おかあさんが、おみおつけのダイコンを切っている音がしました。ノンちゃんの胸が、なんということもなく、うれしさでぷうとふくれました。まな板の上にもりあがる、水けをふくんだまっ白い、四かくい、細い棒の山を心にえがきながら、ノンちゃんはもう一度、目をつぶって、ぼうっと、朝寝のあと味をたのしんでいました。(石井桃子「ノンちゃん雲に乗る」)
母親が朝食の支度をしている音で目を覚ますというのは、日本の美しい朝の風景だったのではないだろうか。
「お勝手」や「おみおつけ」という言葉もきれいだ。
なにより、8歳のノンちゃんの大好物が「ダイコンのおみおつけ」だというところに、昭和初期の日本の一般家庭における平穏な幸福が象徴されているような気がしてならない。
人間の幸せなんて、そのくらいでちょうどよかったんだよな。
作品名:ノンちゃん雲に乗る
著者:石井桃子
書名:石井桃子集Ⅰ
発行:1998/9/4
出版社:岩波書店