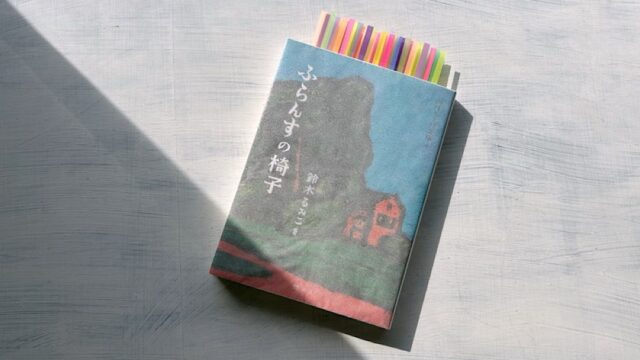トルーマン・カポーティ「遠い声、遠い部屋」読了。
本作「遠い声、遠い部屋」は、1948年(昭和23年)12月にランダムハウス社から刊行された長編小説である。
原題は『Other Voices, Other Rooms』。
この年、著者は24歳だった。
この作品が、カポーティにとって初めての長編小説であり、初めての著作(デビュー作)となった。
思春期の少年が自我を発見する過程を描いた物語
本作『遠い声、遠い部屋』は、思春期の少年が自我を発見する過程を描いた長編小説である。
特徴的なのは、彼の自我が、極めて特異な環境の中で目覚めつつあったということだ。
13歳の少年<ジョエル・ノックス>は、幼くしてシングルだった母親を病気で亡くし、叔母の家で暮らしていたところ、行方知れずだった父親からの手紙を受け取る。
父親との生活を始めるため、ジョエルは<スカリーズ・ランディング>を訪れるが、そこでの暮らしは、彼が想像していたものとは、全く異なる生活だった。
寝たきりの父親<サンソム>を介抱しているのは、女性的な心を持つ中年男性<ランドルフ>であり、精神的にかなり不安定なところのある中年女性<エイミー>である。
ランドルフやエイミーの暮らしを手伝う女中は、女性であるが故の不幸を背負った若き黒人女性の<ズー>。
そして、スカリーズ・ランディングを時折訪れる世捨て人<リトル・サンシャイン>や、隣人・トンプキンズ家の<アイダベル>と<フローラベル>という双子の姉妹、子どもの肉体を持ったフリーク(畸形)の成人女性<ミス・ウィステリア>など、実に個性的な登場人物に囲まれて、思春期の少年は、自身の成長と向きあっていく。
今まで長い間、彼はその「遥か遠くにある部屋」を見つけることができずにいた。それを見つけるのはいつだって簡単なことではなかったけれど、とくにこの一年ばかりはこれまでになく大変なことになっていた。(トルーマン・カポーティ「遠い声、遠い部屋」村上春樹・訳)
子どもと大人とのグレーゾーンの中で、少年は自分の進むべき道を探しあぐねていた。
彼を困惑させる大きなテーマのひとつは、彼自身の性的嗜好である。
ニューオーリンズで暮らしているとき、他人の家を覗き見して遊んでいたジョエルは、醜い小さな部屋の中で、二人の大人の男たちが立ったままキスをしている場面を見つけて、大きな衝撃を受ける。
この体験は、ジョエルに強い印象を残すが、ジョエルの性的な目覚めをより具体的に導くのは、死に損ないの父親を看病している中年男性ランドルフである。
「私が言いたいのはだね、マイ・ディア、ナルキッソスは決してエゴイストではなかったってことだ……彼はただ単に我々の同類であっただけさ。がんじがらめの孤立の中で、彼は自らの反映を目にして、そこに美しい仲間の姿を認めたのだ。分かちがたい無二の愛する人を……可哀想なナルキッソス」(トルーマン・カポーティ「遠い声、遠い部屋」村上春樹・訳)
ランドルフの孤独は、ジョエル自身の孤独でもある。
「ずっと昔にこう悟ったんだ。私の人生は今の時代に合ったものではないのだってね」と呟くランドルフの嘆きは、ジョエル自身の嘆きでもあっただろう。
自分の進むべき道を見つけて、女装したランドルフの元へと歩み寄っていくラストシーンは、まさに、ジョエルの(同性愛的傾向を有する)性的な目覚めを象徴している場面と言えるだろう。
もっとも、本作『遠い声、遠い部屋』は、極めて性的な内容を含みつつも、決して官能的な物語ではない。
ここで描かれているのは、ジョエルの精神的な成長であり、「新しい自分」「もう一人の自分」の発見だったからだ。
同性愛的傾向とイマジネーションの世界
それにしても、少年ジョエルの脳内妄想シミュレーションぶりは凄まじく徹底している。
イマジネーションとリアルとの狭間で、時折、読者は置いてけぼりにされる。
どこからが現実で、どこからが妄想なのか、その境界線が、非常に曖昧なのだ(と言うよりも、むしろ、境界線がない)。
もしも、この長篇小説を読む上でのハードルがあるとすれば、ひとつは、登場人物たちの持つ同性愛的傾向であり、もうひとつは、少年ジョエルの豊かなイマジネーションの世界だろう。
聞き覚えのない声が彼と言い争っていた。彼をからかい嘲り、彼自身でさえろくに知らない彼の秘密を暴き立てた。黙れと彼は叫んだ。それを黙らせようとして泣いた。でも言うまでもなく、その声は彼自身のものだった。(トルーマン・カポーティ「遠い声、遠い部屋」村上春樹・訳)
「現在進行形の中2病」と言ってしまえば、それまでだが、ジョエルの妄想癖はあまりに病的すぎる。
「子供なんてみんな病的なものなのさ。そしてそれが唯一の救いみたいになっている」と話すランドルフの言葉は、少年ジョエル(=著者カポーティ)の主張を代弁するものだったのかもしれない。
そして、ジョエルの豊かな(豊かすぎる)想像力が、この作品の大きな魅力となっていることも、また確かだ。
ゴシック的とも言える華美で装飾的な文章は、それ自体が、この作品の大きなチャーム・ポイントとなっているのだが、この難解なカポーティの文章を、見事な形で日本語に置き換えているのが、村上春樹の翻訳である。
年鑑を手にしたランドルフ、懐中電灯の光で捜し物をするミス・ウィステリア、ここにはない遠い声、遠い部屋を記憶しているリトル・サンシャイン。彼らはみんな記憶を持つか、さもなければ何も知らずに生きてきたのだ。(トルーマン・カポーティ「遠い声、遠い部屋」村上春樹・訳)
過去、村上春樹は数々の歴史的名作を翻訳してきた。
フィッツジェラルド『華麗なるギャツビー』、サリンジャー『ライ麦畑でつかまえて』、チャンドラー『長いお別れ』などだが、正直に言って、村上春樹の翻訳で読むこれらの名作は、決してしっくりと体に馴染むものではなかった。
作品の中に村上春樹が介入しすぎる気がしていたのかもしれない。
ところが、本作『遠い声、遠い部屋』では、作品と翻訳が美しく一体化している。
まるで、村上春樹自身が書いた作品のように、翻訳『遠い声、遠い部屋』は、すんなりと心の中に沁み込んでくる。
実は、この感覚は、カポーティの短編小説「おじいさんの思い出」「あるクリスマス」「クリスマスの思い出」でも感じたことがあるもので、今回の『遠い声、遠い部屋』も、こうしたイノセントな短編小説の延長線上にある作品として、自分の中で繋がっていたのかもしれない。
いずれにしても、「そろそろカポーティでも読もうかな」と考えていたところに、村上春樹の『遠い声、遠い部屋』が刊行されたことは、自分にとって非常に良いタイミングだった。
そして、この翻訳作品が、素晴らしい出来栄えだったということも、自分自身にとって大きな幸運だったと思う。
書名:遠い声、遠い部屋
著者:トルーマン・カポーティ
訳者:村上春樹
発行:2023/07/30
出版社:新潮社