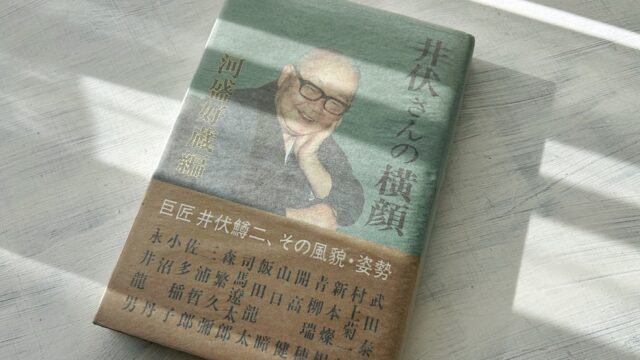永井龍男「皿皿皿と皿」読了。
本作「皿皿皿と皿」は、1962年(昭和37年)10月から1963年(昭和38年)9月まで『週刊朝日』に連載された長編小説である。
単行本は、1964年(昭和39年)1月に河出書房新社から刊行されている。
この年、著者は60歳だった。
季節感を盛った歳時記小説
まず、タイトルが変わっている。
次に、作中で作者が現れて、登場人物と会話をしている部分があるのも珍しい。
さらに、本作は一遍が原稿用紙四枚半という、かなり短い文章の積み重ねで構成された長編小説である。
いずれにしても、実験的要素の多い作品だったのではないだろうか。
主人公は、湘南地方で暮らす老夫婦で、年ごろの娘と三人暮らしをしている。
この三人家族が、隣近所の人たちと交流していく中で、季節が進行していく。
季節の移り変わりを敏感に反映させているという点で、著者は「歳時記小説」という言葉を使っている。
不思議なタイトルについては、作中に、こんな場面がある。
「そっちのことなら、おれの方で先に質問がある。いったい皿皿皿っていうのは、どういう意味なんだ」そう言って、杯をおいた。「困ったな、正面を切られると……。つまり、一皿ずつ独立した味を持っていて、全体としても一コースの調和のある物語、そういう物を書きたいと思った。一皿一皿に季節感を盛って、歳時記風な小説が出来れば、しめたもんだとね」(永井龍男「皿皿皿と皿」)
作中に著者が登場して、登場人物と酒を飲みながら、作品の意図について語っている。
かなり珍しい工夫だが、著者の意図は、この発言でおおよそ理解することができる。
全体にも一遍一遍にもドラマチックな展開はないが、俳句の持つ侘び寂びのような佇まいが、この小説にはある。
一篇ごとに、俳句を添えると、もっと楽しかったかもしれない。
新しい出会いと発見の日々
大きな流れとしては、年ごろの娘である<明子>が、隣家の<洋一>と仲良く遊んでいるが、就職した会社で見初められて縁談が決まってしまう、というストーリーが軸になっている。
そこに、明子の父親の仕事のことや、洋一の姉妹の結婚話、近所に住む画家志望の<湯田島>とのトラブルなどが絡んできて、ちょっとしたホームドラマを展開するといった仕組みになっている。
なにしろ、一回の掲載が四枚半で、その都度、完結するように構成されているから、新聞連載小説のように、壮大な物語は書けなかったのではないだろうか。
全体よりも細部を書き込むことによって、人の営みの不思議なところを感じさせる作品となっている。
「それがさ……」と、靴を履き終えた貞作は、「われながら、びっくりした。おれの咳が、親父そっくりなんだ」「親父って……」「死んだ、俺の親父の咳とだよ」(永井龍男「皿皿皿と皿」)
会話によって物語が構成されているところは、まさしく、テレビのホームドラマという感じがする。
日常生活の中の、ちょっとした発見が、そのまま物語になっている。
品川駅はなんとなく暗い。大きな都会の入口には、必ずこんな駅がある。電灯が暗いとか、ペンキの色がよどんでいるとかいうよりも、昼間から、誰か人間の表情にあるような暗さがただよっている。(永井龍男「皿皿皿と皿」)
考えてみると、我々の生活の中には、そんなちょっとした発見が、あちこちにある。
普通の人は、ただ、そんな発見を見過ごすか、忘れたりしてしまうだけだ。
隣家の庭から聞こえるブランコの静かな音に、貞作は「おれが死んだら、こういう日があるだろうか」と考える。
そして、「おれが死んでからも、こういう日があるに違いない。と、同時に、それはもうおれとは無関係だ」ということに気づく。
しかし、少なくとも自分が生きていくかぎり、毎日は新しい出会いと発見との連続である。
人間の生きる意味は、あるいは、そんなところにあるのではないだろうか。
書名:皿皿皿と皿
著者:永井龍男
発行:1964/1/30
出版社:河出書房新社