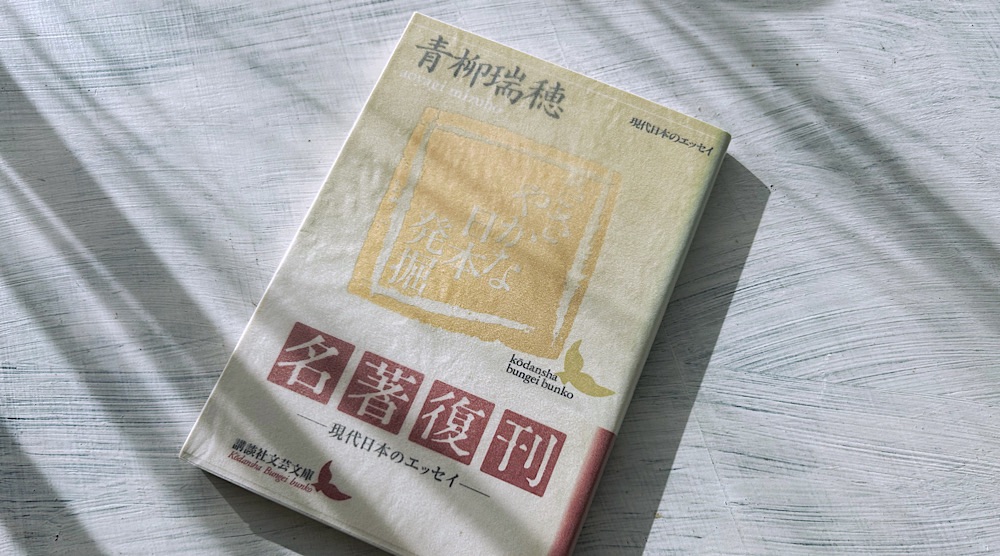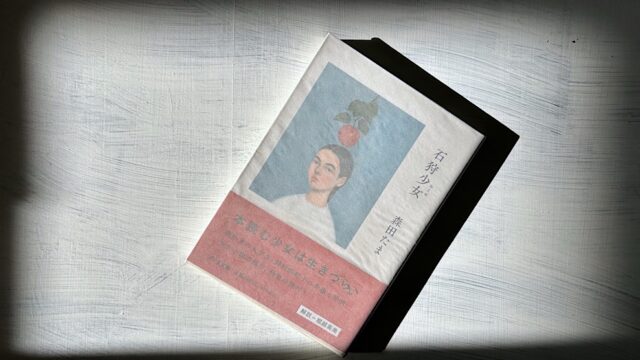青柳瑞穂「ささやかな日本発掘」読了。
本作「ささやかな日本発掘」は、1960年(昭和35年)に刊行された初めての随筆集である。
この年、著者は61歳だった。
なお、本作は、1961年(昭和36年)、第十二回読売文学賞を受賞している。
優れた文学は、全体の一部である破片でさえ美しい
「ささやかな日本発掘」を、僕は庄野潤三の作品で知った。
日本の美を極めた青柳瑞穂のエッセイを、庄野さんはこよなく愛していたらしい。
冒頭の「かけら」は、完備したものよりも破片の方が美しいと感じられる場合があるというテーマだが、美術品の鑑賞の話が文学の話へとつながっていくところがいい。
文学についても、これと同じことが言えそうである。「悪の華」は、一つ一つの詩としてではなしに、一つの環として全体に睨むべき詩集であることは言うまでもなかろうが、たまたま誰かによって引用されたその中の一一篇の詩の、さらにまたその一節は、時によると、私たちのかつて予期しなかったほどの美感を起させることがある。そして、このようにすぐれた一節の堆積から、「悪の華」は成っているのだと思い知る時、この一巻は私たちの想像を絶した存在であることに気づく。(青柳瑞穂「かけら」)
優れた文学は、全体の一部である破片でさえ美しい。
これは、美術品を愛した評論家らしい指摘ではないだろうか。
青柳瑞穂の美術的な哲学は、この冒頭の短いエッセイに、十分に集約されているような気がした。
「貧乏徳利の夢」は、旅に出たときは、その土地で二つ三つの掘出しをしないと、旅行したような気がしないという話。
ある田舎道を歩いていたら、きれいな小川の水に、鍋釜と一しょに、一枚の皿が浸してあった。見れば皿には藍で草の葉っぱらしいものが描かれていて、それが水でゆれてるように見えた。ほどなく、それを洗いに来た老婆にわけを話してゆずってもらったが、もしあのまま、川も水も鍋釜も、婆さん自身まで一しょに持ちかえることが出来たとしたら、掘出しの随一になったことだろう。今でもその皿を出すと、青い水草に、あのせせらぎの音を聞くような思いがする。(青柳瑞穂「貧乏徳利の夢」)
地方を旅して携え帰る器は、それぞれの小さな夢を宿している、と著者は言う。
その土地で生まれ、育ったものの背後には、土があり、森があり、川があり、家がある。
一つの古い器から、著者は、我々の古い祖先の存在にまで遡って、日本を思うことができるのだ。
こういう文章を読んでいると、庄野さんが、青柳瑞穂の随筆に心を奪われた理由が分かるような気がする。
骨董品の蒐集に託された祖国を愛する気持ち
全部で二十六篇ある随筆群の主役と言えるのが、表題作「ささやかな日本発掘」である。
この随筆には、青柳瑞穂の日本に対する様々な思いが収れんされている。
ここでは、様々な掘出物との出会いが具体的に綴られていて、骨董美術を愛する人にとっては必読の文章となっているが、何より感じるのは、著者の日本に対する深い愛情である。
だからといって、何時も流れのほとりにあるものでもあるまいから、私たちが都会の骨董屋で買い求めるのも是非ないことである。しかし、田舎で生れ、長い間、田舎で使われてものには、田舎の心が宿されている筈である。私たちはその心を感じとりたい。それは郷土の心であり、日本の心である。(青柳瑞穂「ささやかな日本発掘」)
著者にとって美術品は、単なるコレクションではない。
著者が蒐集しているものは、古い器を暮らしの中で愛用してきた人々の心であり、それは、つまり「日本の心」である。
あるいは、著者は、祖国を愛する自身の気持ちを、骨董品の蒐集に託したのかもしれない。
だからこそ、田舎で掘出物を発掘する作業は、著者にとって「日本を発掘する」作業だったのだ。
令和に生きる我々は、日本の心を、どこから求めてくればよいのだろうか。
書名:ささやかな日本発掘
著者:青柳瑞穂
発行:1990/8/10
出版社:講談社文芸文庫