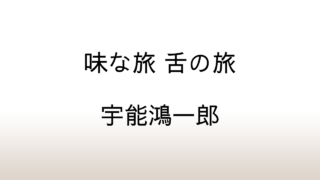富島健夫「青春劇場」読了。
本作「青春劇場」は、1971年(昭和46年)に集英社「コバルト・ブックス」から刊行された長編青春小説である。
高校生活は乗り換え列車のようなものだ
富島健夫の青春小説は、個性豊かな登場人物の群像ドラマを描いたものに、おもしろいものがあるような気がする(それほど、たくさんの作品を読んだわけじゃないけど)。
そういう意味において、『青春劇場』は最高におもしろい青春小説だった。
まず、この小説に、特定の主人公はいない。
とある高校の<三年三組>を舞台として、このクラスに在籍する生徒が、次から次へと登場する。
強いて言えば、三年三組の生徒みんなが主人公ということになる。
作品中で、クラス委員長<若月進>の、こんな言葉が紹介されている。
「英雄にだけ歴史があるのではない。どのような人間でも、歴史を持ち、そしてその歴史はすべて、地球よりも重いのだ。おれたちの日々の生活は、おれたちの歴史になる。堂々たる自分の歴史をつくらねばならぬ」(富島健夫「青春劇場」)
秀才・若月の言葉を借りれば、この作品に登場する高校生たちは、みな、自分だけの歴史を作りつつあるわけで、その一つの過程を切り取ったものが、本作『青春劇場』ということになるのだろう。
個性豊かなキャラクターが登場する代わり、一人一人について深く掘り下げられてはいない。
著者は、あくまでもストーリーを提示するだけで、登場人物たちの行動に対する評価は、読者に委ねられているということかもしれない。
鋭い考察はないが、刺激的な警句は随所に埋め込まれている(このあたりは、若干、太宰治を思い起こさせる)。
とりわけ、印象的なのは、宮原しのぶの呟いた「高校生活って、乗り換えのある列車のなかみたいなものね」という言葉である。
一人一人目的地は異なるが、とりあえず、高校卒業までの間、彼らは同じ車両に乗り合わせた乗客同士ということになる。
高校生活の何が大切なのかということは、物語の最後の場面で、若月進がクラスメートたちに呼びかける言葉で理解できる。
「しょせんぼくたちは一人一人で生きている。それはたしかだ。友情などということばを、ぼくはここでは使わない。けれども、ぼくたちには、やはり共通の思い出がある。その点でつながっているのは否定できない。ぼくたちは未来に生きるのだが、ときにはふっとうしろをふりかえってみるのも、心の安らぎのために必要であろう」(富島健夫「青春劇場」)
そして、若月進は、毎年一回はクラス会をもとうと提案する。
もちろん、彼らは、全員が仲良しグループというわけではなかった。
考え方の違いからトラブルが生じることも少なくなかった。
それでも、彼らは、三年三組の同窓生だという理由だけで、きっと年に一度のクラス会を楽しむだろう。
学生生活で育まれた共通の思い出というのは、それほどに尊いものなのだ(少なくとも、三年三組の彼らにとっては)。
スクール・カーストのない高校生活
『青春劇場』に登場する高校生は、みなそれぞれに自分だけの悩みを抱えている。
クラス委員長・若月進の苦悩は、できすぎ君な虚像と真の自分自身とのギャップであり、偽悪家・飯塚光雄の苦しみは、自分の中に潜む純情な恋心の存在だった。
活発な女子生徒・高木敏子の悩みは、男たちの注目を集める彼女自身の巨乳であり、人並み外れた巨根を持つ西郷竹虎は、女性と性的な関係を持つことができないのではないかと不安を抱いている。
いろいろな悩みがあるように、三年三組の生徒は、みなそれぞれに個性を持った、ユニークな集団だ。
彼らにスクール・カーストのようなヒエラルキーは存在しない。
互いを尊重し、互いに認め合う彼らは、自分自身を否定したりしないのと同じように、他者を否定したりしない。
そして、多くの群像を乗せた<三年三組号>は、間もなく卒業という終着駅に到着しようとしていた。
もちろん、これは本当の意味での終着駅ではない。
彼らの旅は、高校卒業を次のスタート地点として、また新しく始まっていくからだ。
考えてみると、僕の高校生活は、こんな小説みたいに美しくもなく、爽やかでもなかった。
もう一度、高校生活をやり直したいなんて思ったことは一度もない(むしろ、絶対にやり直したくない)。
だけど、ほとんど夢物語のような『青春劇場』の世界に憧れる僕自身も、また確かにいるらしい。
一瞬、高校生に戻れたような気がしただけでも、僕は満足するべきなんだろうか。
書名:青春劇場
著者:富島健夫
発行:1977/5/10
出版社:集英社文庫・コバルトシリーズ