進藤純孝「文壇私記」読了。
昭和28年早春、「文学界」編集部の肝入りで、新人の作家評論家の会合が開催された。
作家側の人選を任された安岡章太郎、三浦朱門、武田繁太郎の三人は、吉行淳之介に相談の上、編集部からリクエストされている、芥川賞作家になったばかりの五味康祐と島尾敏雄に加え、合計10人の作家を人選する。
さらに、編集部の人選により批評家5名が加えられ、集まった15名は、吉行淳之介、島尾敏雄、小島信夫、五味康祐、結城信一、近藤啓太郎、安岡章太郎、武田繁太郎、三浦朱門、庄野潤三、日野啓三、奥野健男、村松剛、浜田新一、進藤純孝(著者)というメンバー(ほとんどが初対面のようなものだった)。
「どうせ一、二回で終わりになるんだから」という理由で結成された「一二会」は、毎月12日に開催されることとなり、昭和35年頃までは続いていたという。
庄野潤三32歳の春で、当時、大阪の朝日放送の社員だった庄野の元には、島尾敏雄や安岡章太郎、石浜恒夫、吉行淳之介、三浦朱門などが出入りをしていた(ラジオ用の原稿を持ち込んでいた)。
「一二会」が結成された昭和28年の9月、庄野潤三は東京支社へ転勤となり、石神井公園の近く(練馬区南田中町)にある畠の中の木造新築住宅で暮らし始めた。
この頃、「一二会」メンバーの最大の関心ごとは芥川賞で、五味康祐(昭和27年下半期)、安岡章太郎(昭和28年上半期)、吉行淳之介(昭和29年上半期)、小島信夫・庄野潤三(昭和29年下半期)、近藤啓太郎(昭和31年上半期)と、一二会の仲間たちが競うようにして芥川賞を受賞した時代だった。
当時のことを、小島信夫は「吉行のアタマの中も庄野のアタマの中も、芥川賞のことでいっぱいだった」と書いているが、メンバーが次々に芥川賞候補になる中、順番待ちのような雰囲気が会の中にはあったらしい。
昭和28年12月、小島信夫『小銃』と庄野潤三『愛撫』という二人の処女作品集刊行に尽力したのが、新潮社編集部にいた著者(進藤純孝)で、仲間たちのこうした取組が、芥川賞受賞にも多少の影響があったかもしれない。
年が明けて昭和29年早春、「文学界」編集長交替を機に「一二会」は編集部から独立、新たに「構想の会」という名称の会が結成され、島尾敏雄、小島信夫、近藤啓太郎、安岡章太郎、吉行淳之介、庄野潤三、三浦朱門、服部達、進藤純孝(著者)が名を連ねた(「構想」というのは、当時、彼らが創刊を計画していた同人雑誌の名前だったが、結局、この同人雑誌の計画は立ち消えになった)。
山本健吉が初めて「第三の新人」という言葉を使ったのは、昭和28年1月号の「文学界」だったが、「第三の新人」の主要なメンバーが「構想の会」のメンバーになっていたと言えるだろう(ちなみに、山本健吉は「第三の新人」という名称の発案については否定している)。
昭和30年、日本経済新聞に「ザボンの花」を連載中の庄野潤三は、朝日放送を退社、文筆業一本で食べていくことを決意するが、「(芥川賞を)受賞してから半年後に、勤めをよすことになったが(略)、いくらもたたないうちに私は窮した」と綴っている。
大学時代からの盟友であった島尾敏雄が、妻の療養のために東京を去って奄美大島へ移住したばかりの頃であり、表面的な華やかさとは裏腹に「第三の新人」たちに、不安がまとわりつき始めていたのかもしれない。
昭和32年8月、苦境から逃れるようにして、庄野潤三はアメリカのケニオン・カレッジへ研究員として留学、33年8月に帰国後に「留学の日々に書いた部厚いアメリカの大学ノート八冊にのぼるメモを整理し、34年3月、書下ろし長編として『ガンビア滞在記』を上梓」しているが、「これが庄野再生の書であったと見ては間違いか」「それから二年して、庄野は、ガンビアに風光が似ているとかで気に入った多摩の横山の一つ、生田の丘に越した」「ここに住みつき、この地に根づいて、彼は実意の筆をつむぎはじめたのである」とは、著者(進藤純孝)の率直な感想だろう。
庄野潤三が渡米した昭和32年頃と言えば、「第三の新人」という名称には、「三等重役」とか「三等切符」に通じるような、何やら貶めるニュアンスが含まれていたし、安岡章太郎などは滞米中の庄野に宛てた手紙の中で「第三艦隊ハ沈没シカカッテイル」とさえ書いていた(小島信夫も同じくアメリカ留学中)。
実際、剣豪小説ブームや推理小説ブームで出版界は賑やかな時代、石原慎太郎『太陽の季節』、大江健三郎『死者の奢り』、開高健『裸の王様』と、新人の話題作が文壇の中心であったから、「第三の新人」などは黙殺されているかのような状況だったらしい(庄野や小島の渡米中、安岡や吉行にも原稿依頼のない時期が続いていた。「新潮」に至っては昭和31年から3年間一度もなかった)。
彼らが本当の活躍を見せるのは、昭和34年以降のことで、庄野潤三『静物』(講談社、昭和35年刊、新潮社文学賞)をはじめ、「第三の新人」の作品が、次々と文壇の注目を集めることになる(ちなみに、著者が新潮社を退社するのも昭和34年のことだった)。
その後の華やかな活躍を考えると、まるで嘘のような話だが、「第三の新人」と呼ばれた作家たちにも苦難の黎明期があったということなのだろう。
本書は、そんな「第三の新人」の若き日の姿を回想するもので、巻末には、安岡章太郎、吉行淳之介、近藤啓太郎、著者(進藤純孝)による対談も掲載されている。
戦後文学史を紐解く参考書の一冊としてお勧めしたい。
書名:文壇私記
著者:進藤純孝
発行:1977/11/30
出版社:集英社




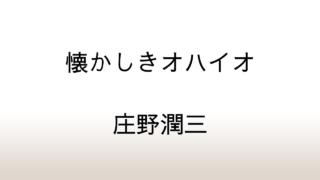

-150x150.jpg)









