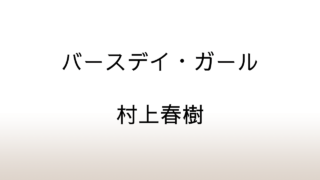庄野潤三の「雉子の羽」は、「文学界」昭和41年12月号から昭和42年12月号まで連載された長編小説である。
本作品最大の特徴は、171の断片的な物語が紡がれて、全体として長編小説という形になっているという部分にある。
すべての物語は、蓬田家の五人の家族の言葉によって語られる。
蓬田家は、父である蓬田と細君である「彼女」、大学生である長女「女の子」と高校生の長男「上の男の子」、小学生の次男「男の子」という、五人の家族だ。
夕飯の食卓で語られるような、日々の他愛ない出来事が、蓬田によって書き留められて、それが物語になる。
列車やバス、病院、商店、あるいは街角で偶然に聞えて来た人々の会話や、次男の小学校で起こった出来事など、些細な日常風景が、まるで散文詩のような美しい響きを持った文章で綴られていく。
登場人物は、米屋や美容室、魚屋、八百屋、バスの運転手、土方、黄色い小母さん、小学校の先生、次男のクラスメート、チンドン屋、かつぎ屋など、実に多様だが、どの人物もみな、昭和40年代初頭の日本を支えた人たちばかりである。
すべての物語は断片であって、始まりもなければ終わりもないが、断片が紡ぎ合わされていくことによって、高度経済成長期の中で発展を続けていた日本という国の、ひとつの姿が見えてくる。
これは、「昭和中期」というひとつの象徴的な時代を描いた、お伽噺のように温かい長編小説だ。
高度経済成長期を巡る昭和日本民俗誌
ぼくが今度、その土、どうするの、と聞いたら、お前んち、ぶっつぶすんだ、といった。堀った土でつぶすというつもりらしい。そして、最後にその土方が、姉ちゃんいるかと、聞いたの。だから、いる、といったら、東京から色男が来てるって、いっといてくれよな、といった。(「三十五」)
「雉子の羽」には、労務者たる「土方」が非常に頻繁に登場する。
この物語の主人公は「土方」であると言ってもおかしくないくらいに。
それは、「土方」という職業が、庶民を描く上で必要不可欠な存在だったということもあるかもしれないが、「土方」が頻繁に登場する社会的な背景を忘れてはいけない。
昭和40年代前半は高度経済成長期の真っ只中で、日本中の街並みが次々に移り変わっていった時代だ。
街の至るところに工事現場や飯場があり、日本列島改造を支えた主役が、まさしく「土方」の人々である。
「土方」の登場は、街の新陳代謝を意味しているのであり、その登場回数が多いほど、街の移り変わりは激しいということになる。
「雉子の羽」は変わりゆく日本を、まさにリアルタイムで、庶民目線によって克明に記録した物語であり、その意味では、高度経済成長期を巡る昭和日本民俗誌と呼べるほどに、充実したドキュメンタリーとも言えるだろう。
「失われていく自然」と「生まれ来る新興住宅街」とが同時に存在しえた一瞬の時代が、この物語の中にある。
街をスケッチしている詩人のように
夕方、蓬田が道を上って来ると、向うから女の土方が四、五人、かたまって帰って来た。道の横のもう出来上った建物をみて、「足場外すと、きれいに見えるね」と一人がいった。ほかの者は、ただ眺めただけで、何もいわずに歩いて行った。(「八十一」)
「雉子の羽」は、できるだけ余計な修飾語を省いた簡素な文章によって、見たことや聞いたことだけが、ただ写実的に、まるで映像のように描かれている。
それは、あたかもメモを取りながら、街をスケッチしている詩人のようだ。
引用は「第八十一話」の全文である。
道で「女の土方」とすれ違ったとき、彼女が「足場外すと、きれいに見えるね」と言った。
ただ、それだけの場面であって、その後の展開もなければ、著者の余計な感想も付け加えられたりしない。
日常風景の点描があるだけだ。
しかし、その日常風景の点描の中には、詩があり、庶民への愛があり、変わりゆく街並みに対する優しい眼差しがある。
「雉子の羽」は、紛れもなく庄野潤三の代表作の一つだ。
「雉子の羽」を読むことなく、庄野文学を語ることはできないだろう。
書名:雉子の羽
著者:庄野潤三
発行:1968/3/25
出版社:文藝春秋


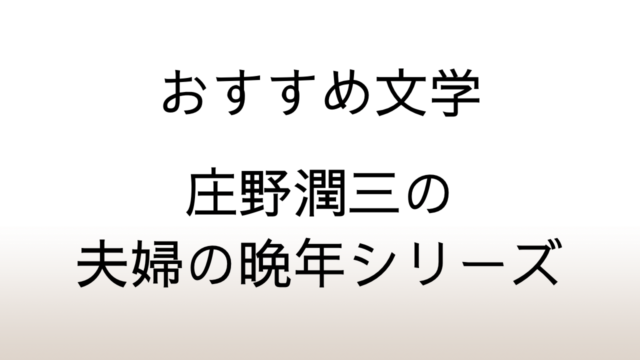



-150x150.jpg)