「流れ藻」は、小木近雄を主人公とした物語である。
近雄は25歳の若者で、2つ年下の妻・照代と生まれたばかりの長女・好子と3人家族で暮らしている。
近雄の仕事は、千葉県木更津にあるドライブインの店長で、この物語は、近雄の現在と過去を克明に記録した、いわゆる「評伝」ものと言えるだろう。
一般に「評伝」というのは、社会的に影響力のある人や、歴史的に功績のあった人について書かれることが多い。
いわゆる「偉人伝」だが、庄野潤三は無名の一般市民の評伝を好んで書いた。
言ってみれば「庶民伝」だが、本書「流れ藻」では、「小木近雄」の人生を描くことで、人間の真実に迫ろうとする著者(庄野潤三)の思いが貫かれている。
物語は、具体的で小さなエピソードをいくつも積み重ねる形で構築されていて、そのエピソードが現在のことだったり、過去の回想だったりして、作品に動きを与えている。
現在と過去がミルフィーユのように折り重なりあって、立体的な光と影を作り出している。
幼少時のことや東京大空襲で被災したときのこと、友達と一緒に家出をしたことやボクシングを習っていたこと、料理の修業をしたことや友人たちと女遊びを繰り返していたこと、殴り合いの喧嘩をしたことや勤め先のレストランで活躍したことなど、25歳の若者の人生は破天荒で生きる強さに漲っている。
一つ一つのエピソードは、あくまでも簡素であって、余分な装飾はひとつもない。
「魂は細部に宿る」と言うが、著者は、小さなエピソードをできるだけたくさん積み上げていくことで、小木近雄という一人の若者の姿を克明に描こうとしていたのかもしれない。
「流れ藻」は「新潮」昭和41年10月号に掲載された作品である。
戦争と戦後の動乱をたくましく生き抜き、高度経済成長の中で勝ち抜こうとした無名の若者は、文学作品という舞台の中で伝説になった。
生きる強さが魅力だった時代
会社をやめる時、近雄は、「どうしてこんないい地位に居りながら、やめるのか」と課長にいわれた。また、仲間から、「よく商売をやるふんぎりがついたな」といわれた。みんな不思議がる。その不思議がるのが近雄には分らない。(「五 姉ヶ崎」)
小木近雄は現状で満足しない男である。
常に前を向き続けて、何か新しいことに挑戦したいと考えている。
だから、ドライブ・インの店長から新社屋の地下に新しく開店する居酒屋の主任に抜擢されたときにも、迷うことなく会社を辞めて寿司屋を開いた。
寿司屋を始めてからも、庭で釣り堀を始めようとか、夏には海岸で「海の家」をやろうとか、常に新しいことを始めることばかり考えていて、周りの人間を驚かせている。
生きる強さが、そのまま、人間「小木近雄」の魅力になっているのだ。
そして、思い込んだら夢中で走り続ける近雄の生き方は、妻である照代の人生を、そのまま不安で覚束ないものにするものでもあった。
夫婦生活の不安を描く
「最近、あんなにいつまでもぐずぐずいうのか」というので、照代が、「いままではそうでもなかったけど、このごろは凄いんですよ」というと、「あっさりした男だと思ってたんだがなあ」といって、驚いていた。(「十一 うなぎ」)
「流れ藻」は、小木近雄の物語であると同時に、妻である照代の物語でもある。
野心家で鉄火な近雄の魅力に惹かれながらも、その夫婦生活は決して照代の思い望んでいたようなものではなかった。
「一緒にいながら、どうしてこんなにさびしいのだろう。照代は時々、そう思う」とあるのは、初期の庄野文学で頻繁に描かれた夫婦生活の不安の一面だ。
近雄の人間的な魅力が増すほどに、照代の気持ちがさいなまれていく様子は、夫婦生活の難しさを象徴的に描き出している。
自分の力で道を切り拓き続ける男の強さは、時に妻や子供を犠牲にすることさえためらわない。
「流れ藻」は、男の物語でもあり、女の物語でもある。
男と女の物語でもあり、生きる人間の物語である。
数々の小さなエピソードが、生きていくことの喜びや苦しみを教えてくれる。
書名:流れ藻
著者:庄野潤三
発行:1967/1/25
出版社:新潮社


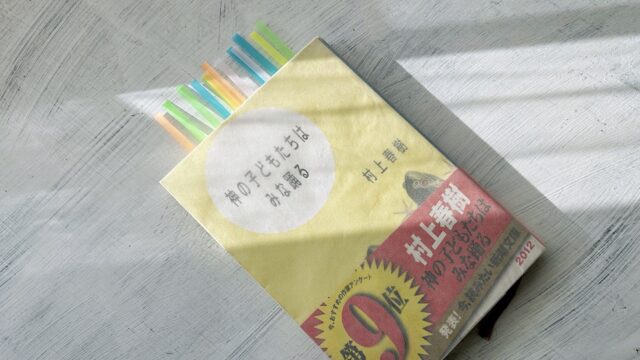
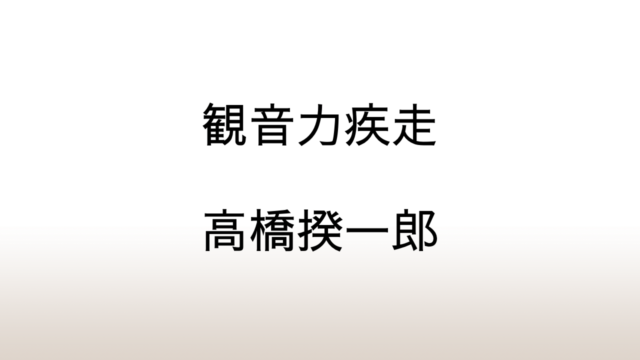


-150x150.jpg)









