庄野潤三の短編小説「日ざかり」読了。
「日ざかり」は、昭和37年「新潮」8月号に掲載され、作品集『鳥』(講談社、1964年)に収録された作品である。
作品は、全部で7篇の短い物語で構成されているが、ひとつひとつの物語には、関連性が見られない。
最初の物語は、近くの森の木陰の涼しいところで、尼僧に引率されてきた生徒が静かに遊んでいる話。
物語の語り手である「私」は、「上の女の子」と散歩に出かけていたのだが、女の子は「あの人たち、みんな尼さん?」「頭刈ってるの?」などと言って、「私」を慌てさせた。
次の物語は、「私」の家の横で屑屋が三人、話をしている風景で、彼らの仲間うちの一人が、女房子どもを置き去りにして、何処かの女のところへ行ってしまったらしい。
また、ある日、「私」は、オートバイに家族を乗せて走っている男を見た時、後ろに乗っている細君が思いがけなく美しい顔をした女なので、びっくりするということがあった。
次の物語は、遊びにやって来たTさんの長男の話で、Tさんの長男はいちばん難関と云われている官立のT大学を受験したが落ちたので、私立の大学の理工科に入り、今は大学院に残っている。
複雑な機械の故障を見つけるのがうまいと定評のあるTさんの息子さんは、とある会社のトラブルを一瞬で解決したことがあったが、それは機械に問題があるのではなく、機械を扱う環境に問題があったそうだ。
次の物語は、知人のBさんの家で会った、香水の会社を経営している人の話で、香水の商売をしている人の鼻はだんだん先がとがってきて、外国の童話に出てくる魔法使いのお婆さんの鼻のように、長く垂れさがってしまうというのは本当だと言う。
次の物語は、上の女の子が二年前の小学校三年生の時に書いた日記の話で、近くの農家へ卵を買いに行ったとき、おばあさんはおまけをしてくれるが、お嫁さんだとおまけをしてくれないと書かれている。
「私」は日記を読んで、子どもの本棚にある童話集に入っていたドイツの童話を思い出している。
庄野さんは、こんなふうに外国の昔話を、自分の作品の中で上手に応用することが珍しくないが、童話の持つ本質的な普遍性を知り抜いているからこそのテクニックだったのだろう。
次の物語は、「私」がバスを待っている時に見た、道路の修理をしている人夫たちの話で、彼らの一人が、背中がかゆいのか、背中を電信柱にあててこすっている。
「私」は、何年か前の記録映画で観た、ヒグマが森の大木に背中をこすりつけている場面を思い出した。
最後の物語は、新聞の海外トピックスの欄に、カトリックの尼さんが二人、服を着たままで海水浴をしている写真を見つけた話。
長い黒い服を着ているカトリックの女性が浜辺で水遊びをしている様子は、いかにも幻想的で文学的な関心をそそる。
この物語はどうやら、尼さんの海水浴の写真を見つけたことが、最初のきっかけだったのではないだろうか。
次に、著者は、森で出会ったカトリックの尼さんたちのことを思い出して、物語の冒頭に据える。
これで、最初と最後の2篇が整った。
後は、中間に一見脈絡のない、だけども、人間的な魅力を感じさせるエピソードを組み合わせていく。
写真で言えば組み写真で、俳句で言えば「取り合わせ」の技術を、庄野さんは小説の中で巧みに応用することのできる作家だった。
書名:『鳥』収録「日ざかり」
著者:庄野潤三
発行:1964/5/20
出版社:講談社



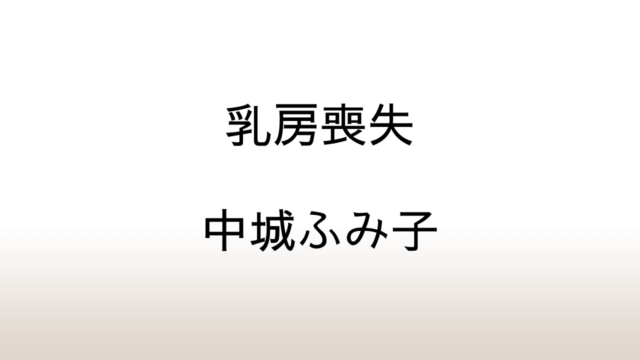



-150x150.jpg)









