庄野潤三の中編小説「雷鳴」読了。
「雷鳴」は、昭和37年「文学界」6月号に掲載され、作品集『鳥』(講談社、1964年)に収録された作品である。
この物語は、語り手の「私」が、仕事仲間の写真家である「松村さん」から聞いた話を、松村さんの話を再現する形で構成されたもので、作風としては、昭和40年代に庄野さんが積極的に取り組むことになる「聞き書き小説」に属するものと言えるだろう。
かつて、松村さんは、幼い女の子を亡くしたことがある。
幾度の空襲を受けたときには無事だったのに、終戦直後に、トウモロコシの粒が誤って気管に入ったことが原因で急死してしまった。
物語は、松村さんの、そんな昔話から始まる。
生きていれば、高校卒業くらいになっているだろう、近所の同じ年頃の子を見るたびに、松村さんは「ああ、もうこのくらいになったかなあ。ああ、もうこのくらいになったかなあ」と考えていたそうだ。
その下の女の子は八か月で生まれた未熟児で、生後一週間目に呼吸が止まってからというもの、何度も何度も息が止まった。
あんまり息が止めるので、まったく目が離せない状態がひと月も続いたが、この女の子は、今は元気で学校へ通っている。
それから、松村さんの話は父の思い出へと移り、昔の印刷屋の話へと広がっていく。
松村さんの親父さんが亡くなったのは、昭和11年の正月で、田舎のお祖母さんが危篤になったといって騒いでいたのが、何とか持ち直してホッとしたところに、親父さんが過労で倒れて、あっという間に亡くなった。
最後に親父さんは何か言っているんだけれども、何を言っているのか、もう聞き取れない。
何遍も聞いているうちに、どうやら「お前も二十過ぎたんだぞ」と言っているような気がしたという。
写真撮影の仕事をしている時、松村さんは電気のことを盛んに心配しているようなことがあった。
戦後のことだが、進駐軍のジープが電柱に衝突する事故を起こしたときに、垂れ下がった高圧線に触れた子どもを助けようとして、父親が亡くなる場面を目撃したことがあるからだという。
子どもは、頭が少し禿げたくらいで済んだのに、父親は即死だった。
それ以来、松村さんは極度に電気が怖くなってしまったらしい。
松村さんは、戦争中、空襲の混乱の中で、大きな怪我をしたことがある。
消火活動をしている際中に、建物の屋根から落下して足や腰の骨を折ってしまったのだ。
空襲で、街は松村さんの家がある一画だけを残して、全部焼けてしまったので、周りには何も残っていない。
そんな家で、不自由な体を抱えながら、松村さんは空襲の恐怖と戦っていた時の様子を話してくれた。
今、松村さんは元気になって、写真の仕事で、あちこちへ出かけている。
題名の「雷鳴」は、物語の冒頭、松村さんが、近所に落雷のあった時の様子を話したことに由来しているが、松村さんの話の中では、生と死とが文字どおり紙一重で隣り合っていることを意識させられてしまう。
雷の落ちたところが、たまたま我が家ではなく、近所の電柱だったこと。
空襲で生き延びた娘が、トウモロコシの誤飲で死んでしまったこと。
未熟児で何度も呼吸が止まった女の子が、今では元気に学校へ通っていること。
激しい空襲の中、松村さん宅の一角だけが被害に遭わなかったこと。
高圧線を握った男の子が助かって、息子をかばった父親だけが死んでしまったこと。
空襲で焼け残りながら、屋根から落ちて大けがをしてしまったこと。
危篤のお祖母さんが回復したと思ったら、親父さんが過労で死んでしまったこと。
松村さんの話の中には、偶然とか奇跡とかいう言葉で片付けてしまうには、どうにも納得のできない、人生の不思議なものがある。
果たして、庄野さんは、そこに運命とか神様とかいうことを考えていたのだろうか。
人生の不思議な出来事について、作家は余計な解釈を加えたりしない。
松村さんの話を上手に再構築しながら、人生の謎について、読者に投げかけているだけだ。
書名:『鳥』収録「雷鳴」
著者:庄野潤三
発行:1964/5/20
出版社:講談社



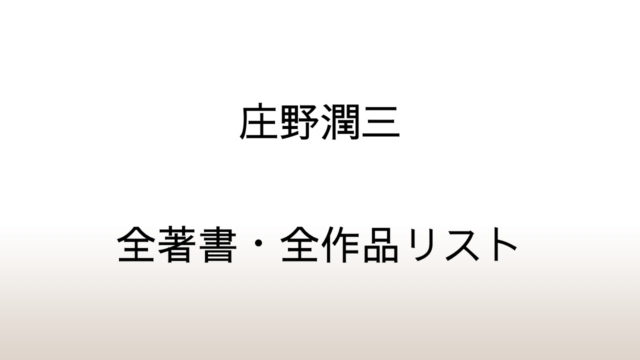



-150x150.jpg)









