庄野潤三「三つの葉」読了・
「三つの葉」は、昭和29年7月号の「小説新潮」で発表され、単行本『旅人の喜び』に収録された短篇小説である。
主人公の「加奈子」は「無口で寂しげな女の子」だった。
「父と母が突然死んでしまったり、自分一人だけ残されたら、その時わたしはどうするだろうということを考えたり、もし自分が或る時から不意に盲目になったとしたら、自分は服の色や人形の形をいつまでも忘れないでいられるだろうかということを心配したり」するような、まだ9歳の女の子だったのである。
加奈子の「母」は、家庭的な女性ではなかった。
男の子のような言葉で話したり、いったいに面倒臭がりで、家のなかの用事が全部嫌いであり、朝ごはんを食べているときに突然「ああ、ナイアガラへ行きたいな」などと突拍子もないことを言ったり、街の洋品店に小猿がいるのを見つけて「この小猿、譲って頂けません」などと言って、父を慌てさせたりしている。
「父」は、そんな母のことを、心の中でいつも不愉快に思っていたし、妻としての母に満足していないように思われた。
結婚するまで神戸で暮らしていた母は、父と結婚した後に大連へ渡ったのだけれど、大連へ来てからも、神戸へ帰りたくて泣いたりしたことは一度もなかったと、母は言う。
貿易商だった父が仕事の関係で旅行に出かけて不在になると、母は加奈子の通っている小学校の受持の男の先生を自宅に呼んで、いつもよりもあでやかな格好で、うきうきと相手をした。
ただでさえ美しくて男性を引き付ける魅力を持つ加奈子の母は、そんなとき一層美しく魅力的となり、加奈子を圧倒させたが、父の留守に他の男を自宅に招いて談笑している母のことを、加奈子はどうしても好きになれない。
「自分の家の玄関にきちんと揃えて脱いである男の靴を見た。その茶色の、河の表面にヒビが入っている、丹念に磨かれた靴を、わたしは好かなかった。それは、わたしにいやらしい感じを与えた」と、加奈子が考える場面は、夫婦関係の影の部分に着目した小説を書き続けた初期庄野文学らしい印象を与える。
実際、この作品は、9歳の少女の視点を通して描かれる微妙な夫婦関係であり、その意味で、やはり「夫婦小説」であった。
母は「四つ葉のクローバー」という唱歌を好んで歌った。
その唱歌は、歌詞がとても長くて一番だけしかなく、節は変化の多い、どこまでも続いてゆく面白い歌で、母がそれを歌っていると、いかにも女学校の唱歌らしいロマンチックに感じられる不思議な歌に聞こえた。
「麗らに照る日かげに百千の花ほほえむ」という言葉で始まる唱歌は、次に「三つの葉は希望、信仰、愛情のしるし」と続き、「残る一葉は幸、求めよとく其の葉、希望深く、信仰かたく、愛情あつくあれ、やがて汝も摘みて取らむ、四つ葉のクローバー」と、一度も同じ節の繰返しなしに続いてゆく。
母の歌う歌を加奈子も覚え、「三つの葉は希望、信仰、愛情のしるし」というフレーズを、加奈子も口ずさむようになる。
小説の題名である「三つの葉」は、もちろん、この唱歌の歌詞から来ているのだろう。
父の留守に男を連れ込む母が歌った「三つの葉は希望、信仰、愛情のしるし」という歌。
しかし、実際に裏切りを行っていたのは、母ではなくて父であった。
油断のならない夫婦関係を描くことにこだわった、庄野さんらしい作品だと思う。
書名:旅人の喜び
著者:庄野潤三
発行:1963/2/25
出版社:河出書房新書
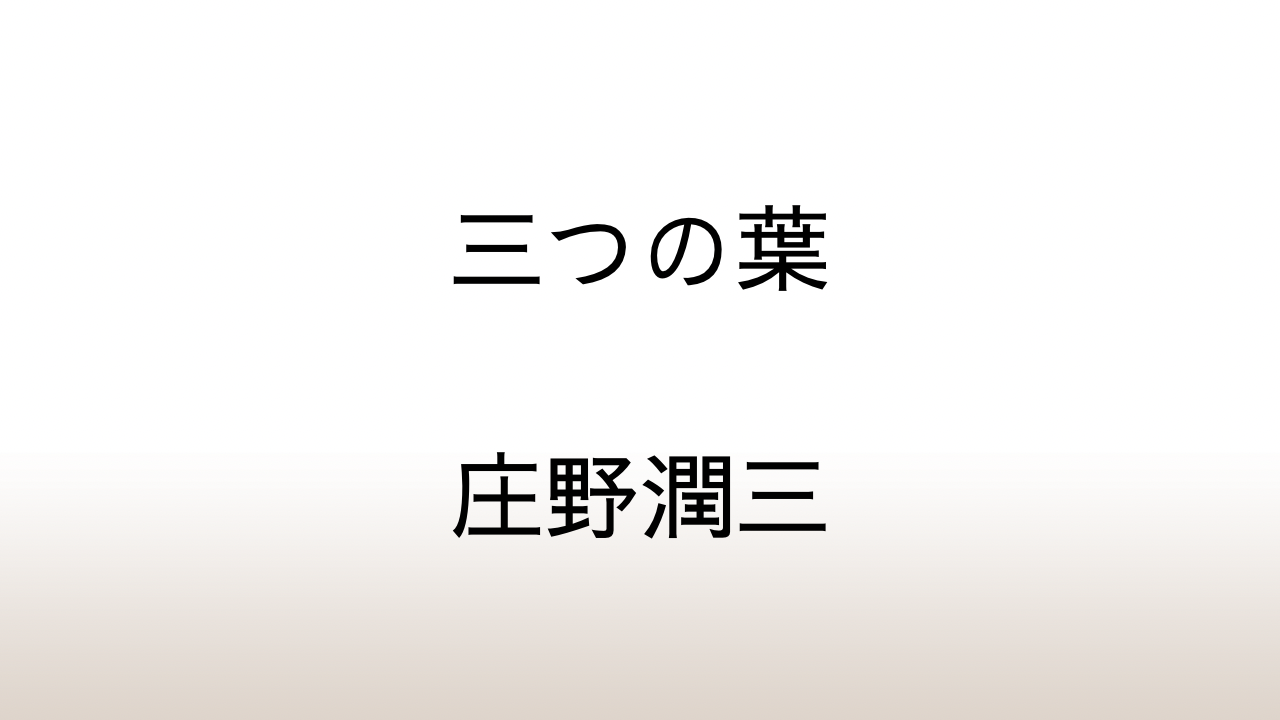




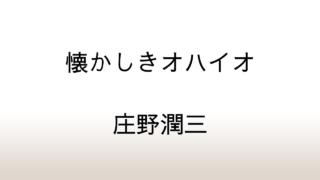
-150x150.jpg)









