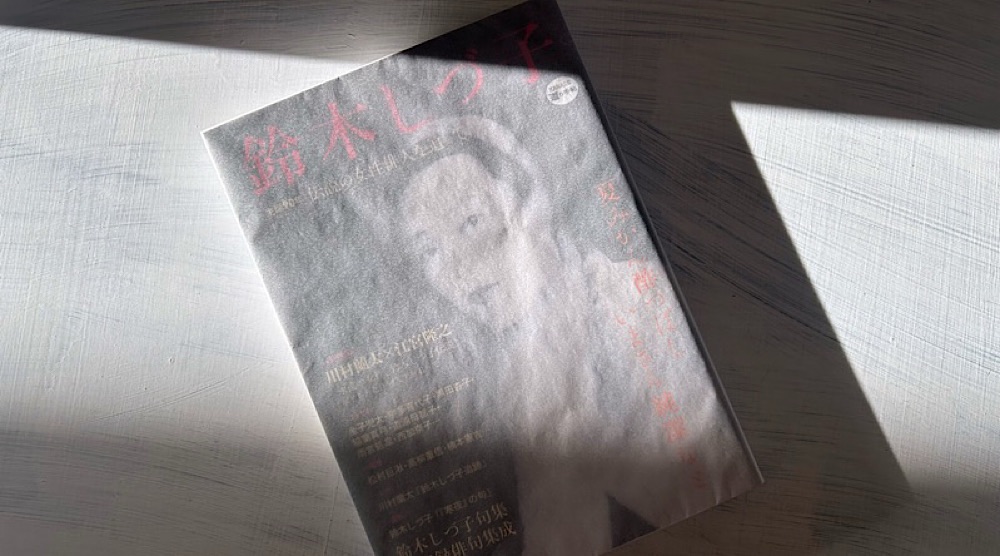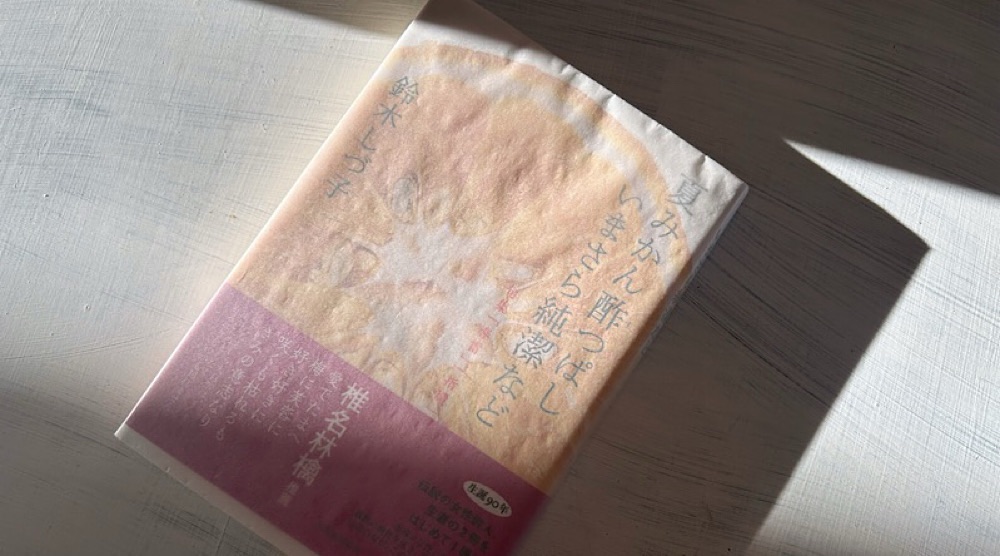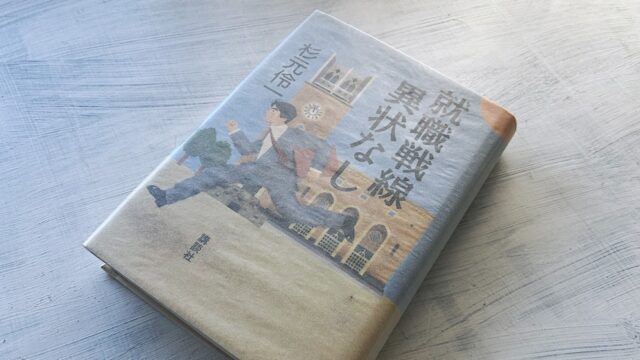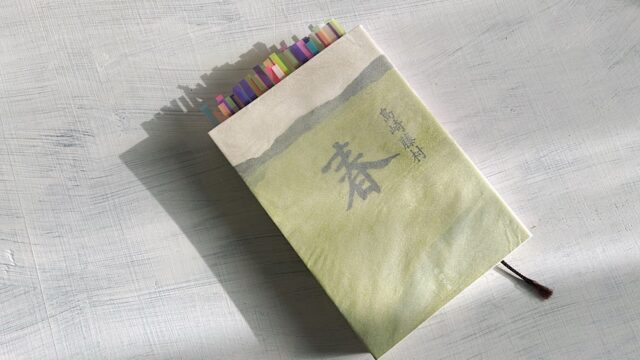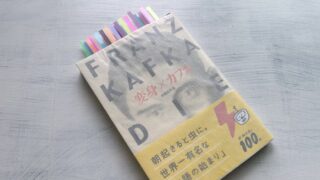KAWADE 道の手帖『鈴木しづ子──伝説の女性俳人を追って』読了。
本作『鈴木しづ子──伝説の女性俳人を追って』は、2009年(平成21年)8月に河出書房新社から刊行されたムック本である。
この年は、俳人(鈴木しづ子)の生誕90年の年だった。
美しすぎる娼婦俳人が伝説となるまで
鈴木しづ子は「謎の俳人」である。
なぜか?
戦後、颯爽と登場した若手の女性俳人が、たった2冊の句集を残して、忽然と姿を消したからだ。
鈴木しづ子の俳壇デビューは、1943年(昭和18年)10月『樹海』だった。
ゆかた着てならびゆく母の背をこゆ 鈴木しづ子
当時、24歳の鈴木しづ子は、主宰(松村巨湫)に師事して投句を続けていく。
1919年(大正8年)、東京・神田に生まれた鈴木鎮子(しづ子)は、東京淑徳高等女学校(現在の淑徳高等学校)を卒業した後、専修製図学校へ入学。
やがて、勤務先となった岡本工作機械製作所の社内俳句部に参加し、矢澤尾上と知り合った。
矢澤尾上は、1988年(昭和63年)8月『俳句研究』に、伝説の女性俳人(鈴木しづ子)の回想録「俳人・鈴木しづ子──その知られざる生涯と作品」を書いたことで知られている。
──1952年(昭和27年)に失踪して以降、鈴木しづ子は、常に「謎の俳人」だったわけだ。
矢澤尾上が所属する『樹海』の主宰だった松村巨湫が、社内俳句部の指導に当たっていたことから、鈴木しづ子も松村巨湫と知り合い、『樹海』に参加するようになる。
鈴木しづ子の作品が、本格的に注目を集めるのは、戦後になってからのことだ。
1946年(昭和21年)2月、処女句集『春雷』が羽生書房より刊行された。
初版1,500部、累計5,000部とも言われる『春雷』は、近年、古書市場にも姿を現すようになった(初版でなければ市場価格は20,000円前後)。
この混乱下に句集出版は、それだけでも ”事件” というものである。初版千五百部はまたたく間に売り切れ、鈴木しづ子は俳壇に知れ渡り、一種のアイドルのような存在になる。(齋藤愼爾「<戦後派>作家に列して」)
しづ子が、母と婚約者を相次いで亡くしたのは、この頃のことである。
母の死、ついで婚約者の戦死の報、病後の私には大きすぎる打撃だった。私はどうしたらよいのか。終戦直後の工場のひっそりした寮に戦災の身を横たえ、痴呆の如く思考力を失ってしまった。(鈴木しづ子「『寒夜の句』」/『樹海』1948/07)
母と婚約者を亡くした若い女性の生活は、あまりにも不安定なものだった。
1948年(昭和23年)に社内結婚する頃から、しづ子の生活環境も変わっていったらしい。
女流俳人の変化は、俳句にも投影されていく。
ダンサーになろか凍夜の駅間歩く 鈴木しづ子
男たちの(性的な)妄想をかきたてる作品が、鈴木しづ子を「伝説の俳人」と呼ばせることになったのかもしれない。
「美貌の娼婦俳人」は、戦後俳壇に小さくない話題を提供した。
娼婦またよきか熟れたる柿食うぶ 鈴木しづ子
1949年(昭和24年)、鈴木しづ子は妊娠したものの堕胎して夫とは離婚。
東京を離れて、岐阜県那珂(現在の各務原市)へ移り住む。
ダンサーとして働きながら、駐留米国黒人兵ケリー・クラッケ伍長と暮らし始めるのは、この頃のことだった。
黒人と踊る手さきやさくら散る 鈴木しづ子
それなりに幸せな生活だったかもしれないが、ケリー・クラッケは朝鮮戦争へ出兵中に麻薬中毒となり、1951年(昭和26年)、母国アメリカへ帰国後に死去した。
霧五千里ケリークラッケへだたり死す 鈴木しづ子
愛人(ケリー・クラッケ)の死は、孤独な女性(鈴木しづ子)に大きな影響を与えた。
「夏みかん酸つぱしいまさら純潔など」この句から、鈴木しづ子は大きく変貌した。昭和二十六年七月「樹海」に「夏みかん」二十一句が掲載され、仲間たちは驚愕した。(略)時代の風浪にもてあそばれ服毒自殺するまでには、一年足らずの歳月があれば十分であった。(石寒太「風流畸人・鈴木しづ子」/『俳句四季』1984/12)
1952年(昭和27年)1月、松村巨湫ら『樹海』関係者の編集により、第二句集『指環』が随筆社から刊行される。
本人の意思とは関係のないところで出版が進められていたともいう『指環』には、男たちが歓喜する「娼婦俳句」が多数並んだ(もちろん、女性陣はしづ子の作品を非難した)。
売春や鶏卵にある掌の温み 鈴木しづ子
世の中の関心は、鈴木しづ子という女性が「ダンサー」であるということだった。
句集『指環』は、勁さと弱さの狭間に揺れうごく女を描くことであったのに、世評のいくつかには(多くには)、彼女の生業に向ける好奇の目が、脂ぎって貼りついているのでした。(鳥海多佳男「鈴木しづ子句集『春雷』とその背景」/『俳句』1980/01)
丸木砂土『秘密の文学』(1955)で、鈴木しづ子は「肉体俳句」として紹介されている。
写真を見ると、長身秀麗の佳人である。戦時中は製図工として働いた。(丸木砂土「秘密の文学」)
現代風に言えば「美しすぎる娼婦俳人」というキャッチフレーズで、鈴木しづ子は、ジャーナリズムの餌食となった(「パンパン俳句、まかり通る」)。
作品に散りばめられた素材だけが抜き取られて、「美しすぎる娼婦俳人」鈴木しづ子は「伝説の俳人」となっていく。
敗戦国・日本の象徴だった「鈴木しづ子」
「鈴木しづ子」は、戦争に翻弄された「戦争未亡人」だった。
出征した婚約者が戦死したところから、彼女の人生は狂い始める。
しづ子が戦争に翻弄された人であることは、離婚後、東京から岐阜へと流れたあとの足跡を辿れば明らかだ。私はここに、戦争未亡人たちの戦後の暮らしを重ねてみずにはいられない。(稲葉真弓「堕ちていくことの美しさ」)
生きるために、誰もが必死の時代だった。
きれいごとを言って生き延びることができるほど、それは簡単な時代ではなかったのだ。
似たような人として、横浜で将校相手の娼婦をしていたヨコハマ・メリーさんを思い出す。街から忽然と姿を消したあたりも、しづ子に似ている。(稲葉真弓「堕ちていくことの美しさ」)
「しづ子」を翻弄したものは、戦争だけではなかったかもしれない。
死に物狂いで生きる女の暮らしに、好奇の目をぎらつかせる男たちが群がった。
破婚のあとはダンスを習い遂にダンサーとなり米兵相手に踊っているうちに、一黒人兵士と結ばれ愛隣の生活に満足していたようだ。(宮崎素洲「思い出と追憶と」/『俳壇』1989/08)
伝説として語られているのは、作品ではなく、私生活である。
「鈴木しづ子」のセクシュアルな俳句は、男たちの妄想を(いやが上にも)刺激した。
菊を活けた指で閨の燈を消す、とは。それ以上でもそれ以下でもない。瞬間のエロティシズム。(蜂飼耳「指は知る」)
性的な作品を抜きにして、「しづ子」の俳句が語られることはなかった。
ここに「鈴木しづ子」という俳人の、本当の悲劇がある。
そのことに早くから気付いていたのが、女性読者だった。
それは、俳人・鈴木しづ子への違和感ではない。彼女を語る「言葉」への違和感だ。何か、一言で言うとキモいのだ。鈴木しづ子を語る男たちの口ぶりが。(雨宮処凛「もっとも大きな不幸」)
雨宮処凛の指摘が、最も的確であったかもしれない。
「鈴木しづ子」を眺める男たちのエロい視線を、彼女は冷静に分析している(「興奮したんだろーな、昭和のオッサンたちは」)。
「娼婦」というフィルターを通してしか「しづ子」を見ることのできない男たちと違って、女性の目線は冷ややかだ。
しづ子さんはこの国のどこかで、いまも生きています。この国の女性俳人の中で彼女を特別視する必要はないのです。(黒田杏子「九十歳のしづ子おばあさん」)
(自分たちに都合の良い)伝説を創ってきたのは、いつでも男たちだった。
ある意味において、それはジェンダーバイアスとさえ言える。
ひとは物語をつくりたがる。女性作家などは、その格好の標的。俳人鈴木しづ子も、そうした象徴的人物の一人なのではないだろうか。(道浦母都子「物語のひと」)
本作 KAWADE 道の手帖『鈴木しづ子──伝説の女性俳人を追って』が成功しているのは、欲望を搔き立てられた男たちのバイアスに流されることなく、冷静な女性たちのコメントを掲載することによって、中庸のバランスを保っていることだろう。
あの頃の私、「女性の表現者」に憧憬と嫌悪の両方を抱いていた私、に、この作品を見せたら、何て言っただろうか。「何なんこれ、オナニーやないか。ゲージュツ家である自分に酔ってる!」(西加奈子「表現者」)
「傲然と雪降るケリーとなら死ねる」という句を、西加奈子は「何なんこれ、オナニーやないか」と切り捨てた(「どう? 私ってイケてる?」)。
「俳句」ではなく「私生活」に注目される俳人は、既に俳人ではない。
やはり、「鈴木しづ子」の(私生活ではなく)俳句は、もっと注目されるべきだったのだ。
好きなものは玻璃薔薇雨駅指春雷 鈴木しづ子
「玻璃」「薔薇」「雨」「駅」「指」「春雷」と名詞を積み重ねる手法は、「しづ子」の俳句の現代性を象徴している。
「鈴木しづ子」の本質とは、つまり、現代的であるということにあったのではないだろうか。
「ダンサー」も「売春婦」も、戦後を生きる「しづ子」にとっては、現代社会の世相を反映したリアルな現実でしかない。
彼女もまた、敗戦国・日本のツケを払わされている、一人の被害者にすぎなかったのだ。
そう考えてみると、鈴木しづ子の(特に戦後の)俳句は、実に凶暴だ。
東京と生死をちかふ盛夏かな 鈴木しづ子
命を賭した本土決戦すらなく、敗戦国となった日本社会の底辺で、「しづ子」は真実を見つめ続けていた。
彼女が見つめていたものは、我が人生を狂わせた世の中である。
堕ちてはいけない朽ち葉ばかりの鳳仙花 鈴木しづ子
「堕ちてはいけない朽ち葉」は、もちろん、「鈴木しづ子」である。
同時に、それは、敗戦国と成り果てた「大日本帝国」そのものでもあった。
鈴木しづ子の俳句が「娼婦俳句」ならば、敗戦国・日本は「娼婦」そのものだ。
黒人のアメリカ兵と踊っている「ダンサー」は、つまり、日本そのものだったと読むことができる。
しかるに、性欲に目のくらんだ男たちは、「鈴木しづ子」に「ダンサー」や「売春婦」として以上の価値観を与えなかった。
「鈴木しづ子」の再評価が進んだのは、1980年代のことである。
鈴木しづ子が、終戦直後の物心両面の荒廃と飢餓を、俳人として生き抜いたそのことは、鈴木しづ子一人の嗚咽と哀愁、抵抗と情炎の単なる自分史ではない。誰が、真実の戦後の女性史の一頁を、俳句という短詩のなかで、かくまで虚飾なく詠いあげたであろうか。(上田都史「鈴木しづ子のこと」/『俳句』1985/11)
当時、第二句集『指環』の出版記念会を最後に姿を消した「鈴木しづ子」は、晩年を北海道の小樽市で暮らしているという謎の噂が、半ば定着していた。
俳句雑誌『餐燈』に投句していた女流俳人「群木鮎子」が「鈴木しづ子」その人である、という説である。
男の体臭かがねばさみしい私になった 群木鮎子
そもそも、「鈴木しづ子」にも(未発表ながら)北海道を題材とする作品が、いくつもあった。
梅雨降りや札幌過ぎの小一時間 鈴木しづ子
北海道に縁のある「鈴木しづ子」だったから、消息不明となった後に、小樽へ移住していたとしても不思議はない。
「群木鮎子」が俳壇に登場するのは、「鈴木しづ子」の失踪後、一年後のことだったから、この仮説は実にロマンチックである(男心をくすぐる都市伝説という意味で)。
しかし、「群木鮎子」と「鈴木しづ子」が同一人物であるという確証は何ひとつなく、100パーセントの憶測にすぎない。
まして、俳句鑑賞の観点から見ると、「群木鮎子」と「鈴木しづ子」との作風に類似性を探すことは困難とさえ言われる。
実際、「群木鮎子」なる俳人の作品は、かなり稚拙で、「鈴木しづ子」のキャリアを考えると、到底、同一人物と考えることは難しい。
ただ単に、性的な素材を扱っているというだけで、「群木鮎子=鈴木しづ子」説を証明するには、やはり、無理があるということだったのだろうか。
毎年、終戦記念日が近づくと、敗戦に翻弄された女流俳人(鈴木しづ子)のことが思い出される。
鈴木しづ子の戦後は、敗戦国・日本の戦後である。
コスモスなどやさしく吹けば死ねないよ 鈴木しづ子
風に吹かれて頼りなく揺れるコスモスの花は「鈴木しづ子」であり、敗戦国・日本の姿でもある。
彼女は、まだ死んでいなかった。
敗戦国・日本が死んでいないのと同じように。
ダンサーだろうが娼婦俳句だろうが、彼女は戦後を(歯を食いしばって必死で)生き続けていたのだ。
書名:鈴木しづ子──伝説の女性俳人を追って
著者:KAWADE 道の手帖
発行:2009/08/20
出版社:河出書房新社