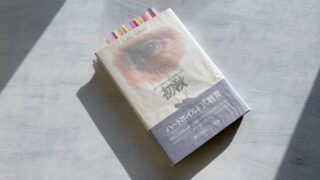1907年(明治40年)9月、札幌駅裏(現在の札幌駅北口)に、田中サト(39歳)という未亡人が暮らしていた。
田中サトは、北海道職員などが暮らす素人下宿屋の女主人で、二人の娘が一緒に生活していた。
姉の名を田中久子(19歳)といい、妹の名を田中英子(12歳)という。
しめやかなる恋の多くありそうな街・札幌
この秋、道庁へ通う下宿生(向井永太郎、26歳)が、一人の若者を連れてきた。
函館市内の弥生尋常小学校を退職したばかりの歌人(石川啄木、21歳)である。
函館の文芸結社(苜蓿社)の同人(向井永太郎)は、函館大火で被災した石川啄木の札幌での職探しを援助する友人だった。
歌人・石川啄木が、札幌停車場に降り立ったのは、1907年(明治40年)9月14日午後1時過ぎのことである。
乗客の大半はここで降りた。私も小形の鞄一つを下げてプラットフォームに立つと、二歳になる女の子を抱いた、背の高い立見君の姿がすぐ目についた。も一人の友人も迎えに来てくれた。
「君の家は近いね」
「近い。どうして知ってる?」
「子供を抱いて来てるじゃないか」
(石川啄木「小説・札幌」)
札幌駅には、向井永太郎のほかに、道庁農務課に勤務する松岡蕗堂(同じく「苜蓿社」の歌人)も来ていた。
啄木の札幌に対する印象は『小説・札幌』(未発表)で知ることができる。
道幅にばかに広い停車場通りの、両側のアカシヤの並木は、蕭条たる秋の雨に遠く遠く煙っている。その下を往来する人の歩みは皆静かだ。男も女もしめやかな恋を抱いて歩いているように見える。蛇目の傘をさした若い女の紫の袴が、そのあたりの風物としっくり調和していた。(石川啄木「小説・札幌」)
当時、札幌停車場通り(現在の「札幌駅前通り」)は、既にアカシヤ並木がひとつの名物となっていた。

アカシヤ並木の駅前通りを、啄木は「アカシヤ街」と呼んでいる。
「この通りは僕らがアカシヤ街と呼ぶのだ。あそこに大きい煉瓦造りが見える。あれは五号館というのだ。どうだ、気に入らないかね?」「いい! いつまでも住んでいたい──」実際私はそう思った。(石川啄木「小説・札幌」)
札幌駅前の煉瓦造りの建物は、地元の百貨店「五番館」である。
札幌はまことに美しき北の都なり。初めて見たる我が喜びは何にか例えむ。アカシヤの並木を騒がせ、ポプラの葉を裏返して吹く風の冷たさ。札幌は秋風の国なり、木立のまちなり。おおらかに静かにして、人の香よりは樹の香こそ勝りたれ。大いなる田舎町なり。しめやかなる恋の多くありそうなる郷なり。詩人の住むべき都会なり。(石川啄木「随筆・秋風記」)
1907年(明治40年)9月18日付『北門新報』に発表した『随筆・秋風記』で、啄木は「札幌はまことに美しき北の都なり」と、初めて訪れた札幌を絶賛している。
啄木の札幌滞在は、結果としてわずか二週間に過ぎないが、その影響は大きかった(札幌にとっても、石川啄木という歌人にとっても)。
満二十一歳七ヶ月、詩集『あこがれ』一冊を持つ青年啄木が、わずか二週間滞在したに過ぎないのに、「札幌の二週間ほど、慌ただしいような懐かしい記憶を私の心に残した土地は他にない」というのはなぜだろう。そして、そういう啄木を札幌人もまた懐かしみ親しんで記念しようとするのはなぜだろう。その啄木と札幌との結び目に、文学の秘密があるように思う。(和田謹吾「石川啄木と札幌」/『啄木と札幌(石川啄木記念像建立記念)』
札幌市の中央部・大通公園の札幌駅前通り寄りに、石川啄木の歌碑が建立されたのは、1981年(昭和56年)9月14日のことである。
それは、啄木没後「七十回忌」の年だった。
大通公園の中央部に位置することもあり、石川啄木の歌碑は今も、札幌市内観光ルートのひとつとなっている(最近は外国人観光客が多いが)。
歌碑には、啄木の代表歌集『一握の砂』収録の作品が採用された。
しんとして幅廣き街の
秋の夜の
玉蜀黍の焼くるにおひよ
(石川啄木『一握の砂』)
かつて、札幌の名物だったトウキビの路上販売は、現在も大通公園のワゴン売りとして、札幌名物のひとつとなっている。
スイートピーの女・田中久子
向井永太郎の紹介で入居した下宿屋は、札幌駅裏にあった。
立見君の宿は北七条の西○丁目かにあった。古い洋風擬いの建物の、素人下宿を営んでいる林という寡婦の家に室借りをしていた。立見君はその室を「猫箱」と呼んでいた。(石川啄木「小説・札幌」)
『小説・札幌』では「林という寡婦」として登場する女主人が、田中サトである。
田中サトの営む下宿屋は、北7条西4丁目にあった。
九月十四日(土)午后一時数分札幌停車場に着、向井松岡両君に迎えられて向井君の宿(北七条西四ノ四田中方)にいたる。(略)今札幌に貸家ほとんどなく一軒もなく、下宿屋も満員なりという。(石川啄木『明治四十丁未歳日誌』)
函館大火の被災者の受け入れで、札幌市内の賃貸住宅には、ほとんど空きがなかったらしい。
札幌駅から啄木は、向井永太郎で案内で田中サトの下宿へ向かった(「札幌は大なる田舎なり」の感想をもたらした札幌散策は、翌日の9月15日(日)午後のもの)。
下宿先は田中サトという女性の営む素人下宿屋で、札幌区北七条西四丁目四番地にあった。今の地番表示でいうと、札幌市北区北七条西四丁目四番地である。(好川之範「啄木の札幌放浪こぼれ草」/『啄木と札幌(石川啄木記念像建立記念))
この下宿屋で、啄木は「スイートピーの女」田中久子と出会う。
田中久子は、下宿屋の女主人(田中サト)の長女だった。
姉は真佐子と言った。その年の春、さる外国人の建てている女学校を卒業したとかで、体はまだ充分発育していないように見えた。妹とは似ても肖つかぬ丸顔の、色の白い、どこと言って美しい点はないが、少し藪睨みの気味なのと片えくぼのあるのとに人好きのする表情があった。女学校出とは思われぬようなしとやかな娘で、絶えだえな声を出して讃美歌を歌っていることなどがあった。学校ではだいぶ宗教的な教育を受けたらしい。(石川啄木『小説・札幌』)
『小説・札幌』では「真佐子」として登場する「田中久子」は、サラ・クララ・スミスの「北星女学校」(現在の北星女子高校)を卒業したばかりだった。
札幌の下宿生活で、青年・石川啄木は、田中久子に特別の感情を寄せることがあったかもしれない。
その頃、啄木の嫁(節子)は娘と一緒に、小樽にいる啄木の姉の家で暮らしていた。
それから飯を済まして便所に行って来ると、真佐子は例の場所に座って(そこは私の室の前、玄関から続きの八畳間で、家中の人の始終通る室だが、真佐子は外に室がないので、そこの隅ッコに机や本箱を置いていた)編物に倦きたという態で、肩肘を机に突き、編物の針で小さな硝子の罎に挿した花を突ついていた。豌豆の花の少し大きい様な花であった。
「何です、その花?」と私は何気なく言った。
「スヰイトビインです」
よく聞えなかったので聞直すと、
「あの、遊蝶花とか言うそうでございます」
「そうですか。これですかスヰイトビインと言うのは」
「お好きでいらっしゃいますか?」
「そう! 可愛らしい花ですね」
見ると、耳の根をほんのり紅くしている。
(石川啄木『小説・札幌』)
この一瞬の会話によって、田中久子は「スイートピーの女」として、長く石川啄木の記憶に留められることになる。
妻(節子)が小樽からやってきたとき、「真佐子」は、啄木の娘を愛しそうに抱いた。
二人限になった時、妻は何かの序にこんな事を言った。
「真佐子さんは少し藪睨みですね。穏しい方でしょう」
やがて出社の時刻になった。玄関を出ると、そこからは見えない生垣の内側に、私の子を抱いた真佐子が立っていた。
私を見ると、「あれ、父様ですよ、父様ですよ」と言って子供に教える。
「重くありませんか、そんなに抱いていて?」
「いいえ。嬢ちゃん、サァ、お土産を買って来て下さいって。マァ何とも仰しゃらない!」
と言いながら、たまらないと言った態に頬擦りをする。
赤児を可愛がる処女には男の心を擽るような点がある。
私は二三歩真佐子に近づいたが、気がつくと玄関にはまだ妻が立っていたので、そのまま外へ出てしまった。
(石川啄木『小説・札幌』)
生前未発表の『小説・札幌』は、ある意味で、主人公と真佐子との不倫を匂わせる物語として読むことができる。
結局、二週間後に、啄木は小樽市内に仕事を見つけて引越してしまうから、田中久子との関係が、男女の恋愛関係へと進むことはなかった。
北星女学校を卒業した田中久子は、教員の職を希望していて、母親(田中サト)は啄木にも就職先の斡旋を依頼していたらしい。
尚田中の久子様の事母堂に御約束の学校の方目下区内に一人もアキなし、何れ出札の上ゆるゆる御世話致すべしと御伝へ被下度候(略)十二月九日夜 小樽花園町十四 石川啄木拝(向井永太郎宛ての書簡より)
小樽を追われて移住した釧路からの手紙にも、久子の就職についての件を見つけることができる。
田中様の久子氏学校教員希望の件、小樽では小生自身の態度不明なりしと、且つ空席なかりしためその儘に致し置き候ひしが、若し今猶其希望ならば(而して釧路でもよければ)空席もある模様にて且つ小生は有力なるツテも作り候間、履歴書御送付方御勧誘被下度候、本月末か来月初めには小生の家族共も来る筈故拙宅に御同居、先方で異議なくば遠慮無用に候、給料もあまり悪くない様子に候。二月四日夜 啄木生(向井永太郎宛ての書簡より)
釧路に教職の空きを見つける啄木だったが、田中久子は1908年(明治41年)1月、札幌近郊の新琴似尋常高等小学校(現在の新琴似小学校)へ、既に教員として就職済みだった。
遠い釧路へ教員として赴任していたら、田中久子と石川啄木の仲は、果たしてどうなっていただろうか。
1909年(明治42年)の『きれぎれに心に浮んだ感じと回想』で啄木は、久し振りに田中久子を思い出している。
やはりその友人と、ある日、札幌の話をしたとき、話の中の女の名をふと忘れてしまって、どうしても思い出せなかった。それから二三日の間、機会があると考えてみたが、やはり思い出すことができなかった。その女というのは、私が一昨年の秋、二週間札幌にいて泊まっていた家の娘であった。スヰトピイとかいう花を机の上の瓶にさして、その前で小声に讃美歌を歌いながら、針仕事をしているおとなしい娘であった。(石川啄木「きれぎれに心に浮んだ感じと回想」)
「その友人」とあるのは、東京での親友(金田一京助)のことである。
金田一京助に啄木は(田中久子の名を告げず)、ただ「スイートピーの女」とだけ伝えたらしい。
突然、その女の名を思い出したとき、「大切な落とし物を拾ったよりもなお嬉しかった」と、啄木は綴っている。
ドイツ語で記された謎のメモ『忘れな草』には、啄木と関わりのあった女性19人の名前が、土地ごとに綴られているが、札幌のところには「田中久子」の名前だけがあった。
サッポロ:──ヒサ、タナカ(石川啄木「忘れな草」)
女性教師となった田中久子は、1909年(明治42年)4月、2回目の卒業生を送り出して新琴似尋常高等小学校を退職。
6月には家族と一緒に朝鮮へ渡り、1913年(大正2年)、滝川出身の有川藤次郎と結婚するが、長女(通子)を出産後、1920年(大正9年)に32歳で他界した。
1910年(明治43年)に出版された歌集『一握の砂』には、田中久子を詠んだ作品が収録されている。
わが宿の姉と妹のいさかひに
初夜過ぎゆきし
札幌の雨
(石川啄木『一握の砂』)
札幌の初夜を過ごした「わが宿」とは、もちろん、田中サトの下宿屋であり、「姉と妹のいさかい」は、姉(久子)と妹(英子)との姉妹喧嘩のことである。
下宿屋田中の建物は以前、税務署の官舎であったらしく、玄関前の庭先は五加(うこぎ)の生け垣を回した木造マサブキの平屋だったという。啄木は田中方の母屋の六畳間に松岡蕗堂と同室し、離れに向井永太郎の一家三人が住んだ。(好川之範「啄木の札幌放浪こぼれ草」/『啄木と札幌(石川啄木記念像建立記念))
下宿屋を廃業した田中一家が朝鮮へ渡った後、この建物は「北七条郵便局」へと変わり、啄木が暮らした元下宿屋も、1932年(昭和7年)に取り壊されてしまった。
大通公園に石川啄木の歌碑が建立された1981年(昭和56年)当時も、下宿跡には「北7条郵便局」が建っていた。
昭和五十一年二月二十日、地元町内会が主催した啄木生誕九十年祭時に札幌市北区役所が「石川啄木の下宿跡」と記した高札式の史跡案内板を建てている。また、このとき、市内アマチュア彫刻家の葛西茂雄氏が札幌初の啄木胸像の秀作をつくり、北区役所ロビーに掲出されることになった。技術指導は坂担道氏である。(好川之範「啄木の札幌放浪こぼれ草」/『啄木と札幌(石川啄木記念像建立記念))
バブル崩壊直後の1992年(平成4年)、北7条郵便局は現在地(西6丁目)へと移転し、啄木の下宿跡には、現代的なオフィスビル「札幌クレストビル」が建てられた。
現在、札幌クレストビルの入り口には、葛西茂雄作の啄木胸像と北区役所による説明版が設置されている(「北区歴史と文化の八十八選」)。
1908年(明治41年)の日記に、啄木は札幌で出会った人々の名前を並べた。
八月二日 昨年の日誌と、北門時代の旧稿を読み、そぞろに函館と札幌を忍ぶ。”その人々” 稿を起して書くこと僅かに二枚。札幌二週日の間に逢いたる人々──久ちゃん、向井君、松岡、小国君、伊藤和光子、加地燧洋等を書かむとするなり。(石川啄木「明治四十一年日誌」)
「久ちゃん」こと「スイートピーの女・田中久子」は、啄木伝説とともに、札幌の文学史に今も刻みこまれている。
札幌クレストビルに残る「石川啄木の下宿跡」は、田中久子という女性が生きた歴史を物語る、ひとつの証だったのかもしれない。
書名:啄木と札幌──石川啄木記念像建立記念誌──
編集:木原直彦(石川啄木記念像設立期成会)
発行:1981/09/14