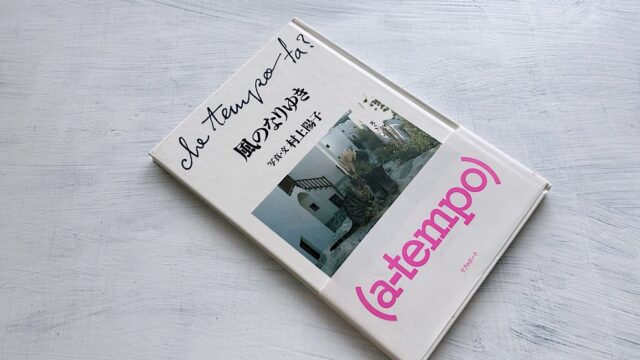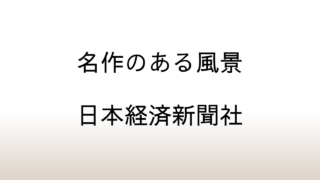トマス・ウルフ「天使よ故郷を見よ」読了。
本作「天使よ故郷を見よ」は、アメリカの作家トマス・ウルフのデビュー作である(1929年)。
フィッツジェラルドやヘミングウェイと同時代の作家であるトマス・ウルフについては、これまで未読だったが、映画『ベストセラー 編集者パーキンズに捧ぐ』(2016)がおもしろかったので、映画に登場している作品を読んでみることにした。
ちなみに、この映画には、フィッツジェラルドやヘミングウェイも登場しているので、文学好きの方にはおすすめ。
さて、トマス・ウルフの『天使よ故郷を見よ』を探してみると、思いがけず講談社文芸文庫の近刊で見つかった。
どうやら、これは、映画『ベストセラー 編集者パーキンズに捧ぐ』の影響だったらしい。
映画を観て覚悟していたものの、講談社文芸文庫で上下巻の2冊仕様、なかなかのボリュームだが、読み終わってみると、意外にもあっという間だった。
一言でいえば、この小説は、主人公ユウジーン・ガントが大学を卒業するまでの軌跡を描いた青春の物語である。
ただし、その青春を語るために、著者は祖父母の代にまで遡って、ユウジーンが生まれた環境を語ろうとしている。
主人公ユウジーンは、もちろん著者トマス・ウルフ自身の投影であり、ユウジーンの波乱に満ちた青春は、トマス・ウルフ本人の体験によるところが大きいだろう。
さらに、著者は、家庭環境のみならず、地域や学校の人々、さらには世界情勢まで巻き込んで、ユウジーンの成長過程に影響を与えたと考えられる非常に多くの事象を配置して、ユウジーンの人間性を表そうとしている。
人はみな、青春時代にたどりつくまでに、実に様々な経験を積み重ねているのだということに、改めて気付かされた。
ジーン、奴らは地獄へ堕ちろだ。奴らのためにくよくよするのはよせ。手に入るものは手に入れよだ。どんな奴にも鐚一文出すな。鐚一文貰うな。いとしいとしは地獄へ堕ちろ。間の悪い日もたんとあろうが、運のいい日もしこたまあるんだ。忘れるさ。おさらばする奴はおさらばだ」(トマス・ウルフ「天使よ故郷を見よ」)
幼少期のエピソードも面白いが、この物語の大きなポイントは、やはり、ユウジーンの青春期に据えられている。
その中でも、特に大きな山場と言えるのが、年上の恋人ローラ・ジェイムズとの失恋と、最愛の兄ベンジャミンの死だろう。
とりわけ、家族の中で誰よりもユウジーンに理解を示してくれていたベンジャミンの死は、この長い物語の大きなクライマックスとなっている。
ベンジャミンの死と大学卒業によって、ユウジーンの青春は明確な区切りを見せる。
ラスト場面を読んだとき、そこに至るまでの長い長い積み重ねの意味が分かるような気がした。
亡き兄の亡霊と石造の天使が導いてくれた新たな道
作品名「天使よ故郷を見よ」に使われている<天使>の持つ意味は、作品を最後まで読み通したときに分かるだろう。
主人公ユウジーンの父親ガントは、墓石を刻む職人なのだが、彼の工房には、ガントの作品である天使の石像があった。
作品中でほとんど登場することはないが、ユウジーンの成長を見守り続けたのは、紛れもなく、この天使の石造である。
ユウジーンは、月あかりに照らされた古煉瓦に父の名がはげかかっているのを見た。店の石造ポーチには、天使たちが大理石のしなを作っている。それらは月光のなかに凍てついたかと見えた。(トマス・ウルフ「天使よ故郷を見よ」)
死んだベンジャミンの亡霊が出現したとき、ユウジーンは石造の天使が動いている姿に驚く。
実は、すべてが幻なのだが、ベンジャミンの亡霊と天使の石像が、ユウジーンを新しい道へと導いていると考えることもできるかもしれない。
「都なんかちっともありゃしないんだ。あるのは一つの航海、初めであると同時に終りであるただひとつの航海ばかりだ」(トマス・ウルフ「天使よ故郷を見よ」)
おそらく初読では見えていないものも多いだろう。
少し時間を空けて、いずれまた再読に挑戦してみたい。
書名:天使よ故郷を見よ
著者:トマス・ウルフ
訳者:大沢衛
発行:2017/7/10
出版社:講談社文芸文庫