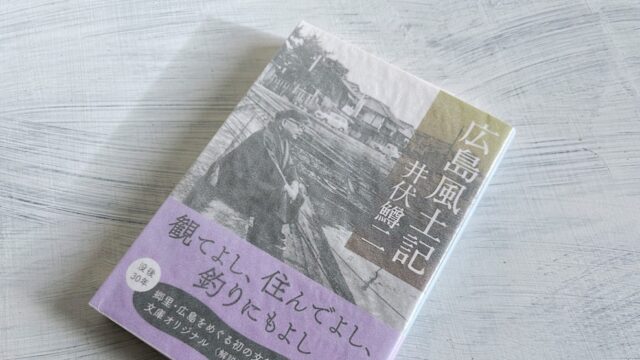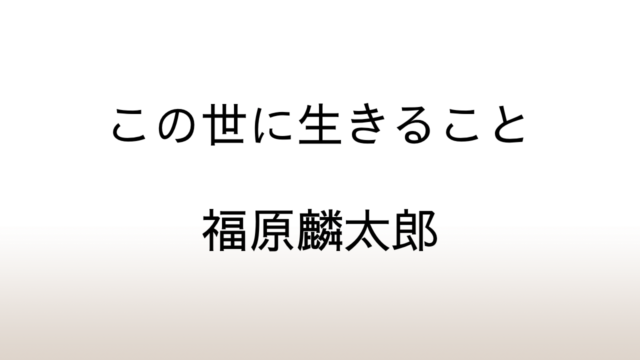村上春樹「街とその不確かな壁」読了。
本作「街とその不確かな壁」は、2023年(令和5年)4月に刊行された長編小説である。
この年、著者は74歳だった。
「世界の終り」のシークエル(後日譚)
村上春樹の新作『街とその不確かな壁』は、1985年(昭和60年)に刊行された長編小説『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』のシークエル(後日譚)である。
正確に言うと、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』のうちの「世界の終り」に相当する部分の後日譚ということになるだろうか。
事前の印象として、本作は、1980年(昭和55年)9月『文学界』に発表された(幻の)中篇小説「街と、その不確かな壁」を再構築した作品だろうと思っていたのだけれど、実際の作品は、予想以上に踏み込んだ物語になっていた。
考えてみると、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』自体、「街と、その不確かな壁」を再構築して完成された作品だったから、今さら「街と、その不確かな壁」をリライトする必要性は、あまりなかったのかもしれない。
そういう意味で、僕は本作を「世界の終り」のシークエルとして読んだ。
もちろん、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』を読んだことがない人にもストーリーが理解できるように、本作の「第一部」として「世界の終り」をコンパクトにまとめたものが置かれている。
あるいは、この「第一部」こそが、1980年版「街と、その不確かな壁」のリライトなのかもしれないけれど、基本的なプロットやディテールは、ほぼ忠実に「世界の終り」をなぞる形で描かれている。
「わたしの実体は──本物のわたしは──ずっと遠くの街で、まったく別の生活を送っている。街は高い壁に周囲をかこまれていて、名前を持たない。壁には門がひとつしかなく、頑丈な門衛に護られている。そこにいるわたしは夢も見ないし、涙も流さない」それが、きみがその街のことを口にした最初だった。(村上春樹「街とその不確かな壁」)
「第一部」は、ダイジェスト版「世界の終り」で、本作においてはプロローグとしての位置付けを有するものだろう。
ただし、「第一部」において、「世界の終り」で明かされていなかった新事実が、いくつも含まれていることには注意を要する。
高い壁に囲まれた街が、十六歳の少女の空想の産物であることや、「古い夢」は街を追放された本体が残していった「心の残響」であることなど(もっとも、これは「世界の終り」を読んでいない読者にとっては、ほとんど意味を持たないかもしれないが)。
もし仮に(「あとがき」で著者が述べているように)、本作が「第一部」のみで完了していたとしたら、きっと僕は失望しただろうと思う。
「第一部」は、「街と、その不確かな壁」よりは完成されているけれど、「世界の終り」より優れているとは思われなかったから。
夢と現実、外面と内面、意識と下意識(潜在意識)
本作『街とその不確かな壁』の本編は「第二部」である。
ここでは、かつて<影>と別れて街に留まったはずの<僕>(=私)が現実世界へと戻り、福島県にある図書館の館長として働き始めるところから、物語が始まる。
<私>は四十歳を過ぎた中年男性で、かつて空想の中で「街」を生み出した十六歳の少女を忘れられないでいる。
そして、この「第二部」においても、「世界の終り」の中で明かされなかった謎を解くヒントが、いくつも登場する。
これは、「あとがき」の中で著者が述べているように、「世界の終り」を補完する役割を意識したものなのだろう。
気になるのは、随所に登場する断片的なエピソードが、過去の村上作品に登場する「どこかで聞いたことのあるような話」ばかりだということだ。
ホルヘ・ルイス・ボルヘスが言ったように、一人の作家が一生のうちに真摯に語ることができる物語は、基本的に数が限られている。我々はその限られた数のモチーフを、手を変え品を変え、様々な形に書き換えていくだけなのだ──と言ってしまっていいのかもしれない。(村上春樹「街とその不確かな壁」あとがき)
デジャヴのようなエピソードの断片は、どうやら巧みに計算されて配置されたものらしい(ただし、過去の村上作品を読んだことのない人には関係ない話だが)。
エピグラムとして、コールリッジの『クブラ・カーン』が引用されているように、本作のテーマは、夢と現実との共存である。
言い換えると、それは、人間の外面と内面、意識と下意識(潜在意識)との共存ということになる。
「僕は思うのですが、街を囲む壁とはおそらく、あなたという人間を作り上げている意識のことです。だからこそその壁はあなたの意志とは無縁に、自由にその姿かたちを変化させることができるのです」(村上春樹「街とその不確かな壁」)
人は、誰も自分の中に、自分だけの「高い壁に囲まれた街」を持っている。
あるいは、それは、遠い昔に置き去りにされた、夢や理想のようなものだったかもしれない。
ちなみに、コールリッジの「クーブラ・カーン」は、サリンジャーの初期の中編小説「倒錯の森」でも引用されていて、村上作品との類似性を探る上で興味深い内容となっている。
心の中に古い夢を抱えながら、人間は時間という流れの中で生き続けていくのだということを、この物語は訴えかけているようだ。
マジック・リアリズムで知られるガルシア=マルケスの『コレラの時代の愛』が引用されているところからも、本作で著者が伝えようとしていることが感じられるのではないだろうか。
セックス描写の登場しないイノセントな世界観
本作を読みながら、僕はトルーマン・カポーティの小説を思い出していた。
理由は分からない。
全般に漂うイノセントな世界観が、カポーティの作品群を連想させたのだろうか。
作中で『ハーメルンの笛吹き男』の話が登場するが、笛を吹いて子どもたちを連れ去っていくパイドパイパーは、「世界の終り」に出てくる角笛(単角獣を呼び寄せる)を連想させる。
もしかすると、単角獣は「心の中のイノセンス」のメタファーだった、という解釈も成り立つのかもしれない。
なにしろ、本作では、村上春樹の小説には珍しく、過剰なセックス描写(性的描写)が登場しない。
それから彼女は私の前につかつかとやって来て、首を伸ばし、すばやく私の頬にキスをした。とても自然に、どこまでも当たり前のことのように。(略)「うちまで送ってきてくれてありがとう。こういうの、久しぶりで楽しかったわ。なんだか高校生のデートみたいで」(村上春樹「街とその不確かな壁」)
まるで傷付きやすい思春期の少年のように、この小説はピュアでセンシティブな世界観を構築している(そして、思春期の少年少女の持つ「両価性(アンビバレンツ)」のようなものが、この小説からは感じられる)。
とは言え、この作品は、明らかに大人の目線によって(しかも、かなり年齢を重ねた大人の目線によって)描かれていることは明らかだ。
かつて思春期を失った老人が、遠い昔を慈しむような懐かしさが、この小説にはある。
「第一部」がプロローグで、「第二部」を本編とするなら、「第三部」はエピローグということになるだろう。
ここではストーリー上の大きな展開はない。
長かった物語をソフトランディングさせようとするかのように、物語は余韻を残しながら静かにゆっくりと幕を引いていく。
「さよなら」ともう一度私は彼女に向かって言った。「さよなら」と彼女も言った。まるでこれまで見たこともない食物を初めて口に入れる人のように、ゆっくり注意深く、そして用心深く。そのあと、いつもの小さな微笑みが口元に浮かんだが、その微笑みも今までと同じものではなかった。(村上春樹「街とその不確かな壁」)
かつて失敗した作品のタイトルを冠した長編小説として、この「第三部」には入念の注意が払われているはずだが、言いたいことは「第二部」で全部言ってしまったという印象がないでもない。
そうすると、「第三部」そのものが、この作品の余韻ということになるのだろうか。
全体の感想として、本作『街とその不確かな壁』は、非常に優れた作品だと思う。
何より、奥が深い割には、読みやすくて分かりやすい。
ある意味で『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』よりも取っつきやすい作品と言えるだろう(登場人物はセックスもしない)。
冷静に世界を見つめる主人公の穏やかな語りは、悟りを開きつつある古老の持つ静けさだ。
その昔「ポップでアクションのある作品」を書いていた頃を思うと、村上さんも年を取ったなあと思う(そして、僕自分自身も)。
「若い時は、ポップでアクションのあるものにひかれる。でも、もう僕も高齢者の部類。この話は、3世代が立体的に絡み合う。色んな世代の目で見て、腰を落ち着けて人の内面をしっかりと描きたかった」(読売新聞2023/04/14)
そして、年老いたからこそ生まれた課題こそが、今回の作品の中にも含まれる「継承」だったのではないだろうか。
本作『街とその不確かな壁』は、村上春樹が、作家として一つの極みに到達したことを告げる作品になっているのかもしれない。
それが、彼の代表作になるかどうかは別として。
あと、極めて個人的に言うと、僕はやっぱり『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』の方が好きです。
書名:街とその不確かな壁
著者:村上春樹
発行:2023/04/10
出版社:新潮社