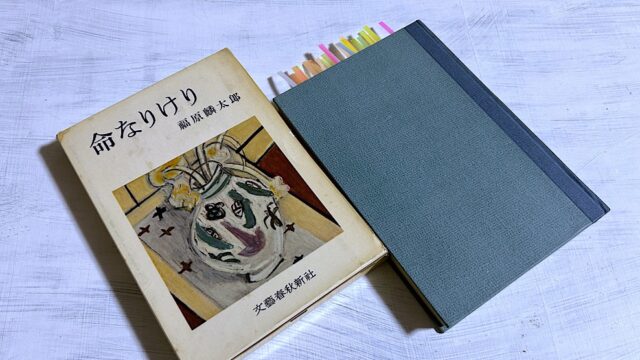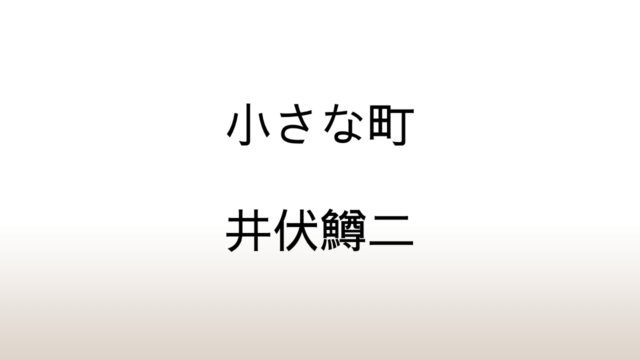エーリッヒ・ケストナー「飛ぶ教室」読了。
本作「飛ぶ教室」は、1933年(昭和8年)に刊行された長篇小説である。
この年、著者は34歳だった。
少年たちと大人との絆
小説を読み終えて、解説を読んでいると、忌野清志郎の名前が出てきたので驚いた。
大人だろ、勇気出せよ。子どものころのように──といった内容の歌を忌野清志郎が歌っているが、ケストナーもまた、児童物を書きながら、ひそかに大人にも訴えていたのではないか。──大人だろ、考えろよ。子どものころのように。(丘沢静也「飛ぶ教室」解説)
「♪おとなだろ、勇気を出せよ~」で始まるのは、RCサクセション最後のオリジナル・アルバムとなった『Baby A Go Go』(1990)収録の「空がまた暗くなる」。
不安な社会情勢を歌ったメッセージ・ソングだったが、それにしても、解説に清志郎が引用されるなんて、ドイツ文学の世界も変わったなあと思う。
実際、ケストナーの『飛ぶ教室』は、いずれ大人になる子どもたちに向けたメッセージでありつつ、現在の大人たちに対するメッセージとして読むこともできる。
どうして大人は自分の若いときのことをすっかり忘れてしまうのだろうか。子どもだって悲しくて不幸になることがあるのに、大人になると、さっぱり忘れてしまっている。(この機会に心からお願いしたい。子ども時代をけっして忘れないでもらいたい。どうか約束してもらいたい)(エーリッヒ・ケストナー「飛ぶ教室」丘沢静也・訳)
「まえがき」に書かれた作者からのメッセージは、本編に登場する大人(禁煙さん)からのメッセージに対応するものだ。
「大切なことを忘れないために」と、禁煙さんが言った。「できることなら消えてほしくないこの時に、お願いしておく。若いときのことを忘れるな、と。きみたちはまだ子どもだから、お節介に思えるだろう。だがお節介じゃないんだよ。信じてほしい。私たちは年齢を重ねたが、若いままだ。私たちには、わかってるんだ。ふたりとも」(エーリッヒ・ケストナー「飛ぶ教室」丘沢静也・訳)
「若いときのことを忘れるな」という言葉は、このクリスマス物語の重要なテーマだ。
もしかすると、作者(ケストナー)は、この一言を伝えるためだけに、『飛ぶ教室』という物語を生み出したのかもしれない。
きびしい人生は、お金を稼ぐようになってから始まるわけではない。そこで始まるわけでも、そこで終わるわけでもない。(エーリッヒ・ケストナー「飛ぶ教室」丘沢静也・訳)
こうした子どもたちへのメッセージは、そのまま、大人に対するメッセージとしても読むことができる。
きびしい人生は、お金を稼ぐようになったところで終わるわけではない──。
つまり、どんな人生であっても、勝負はまだまだこれからなんだ、というメッセージとして。
ケストナーの小説には、訓示めいた言葉が多くて、いささか説教くさい部分もあるが、その説教くささが、ケストナーの魅力でもある(禁煙さんが言うように、お節介のようにも思えるが)。
賢さのない勇気は、乱暴にすぎない。勇気のない賢さは、冗談にすぎない。世界の歴史には、勇気はあるけれど馬鹿な人間や、賢いけれど臆病な人間がたくさんいた。(エーリッヒ・ケストナー「飛ぶ教室」丘沢静也・訳)
本作『飛ぶ教室』は、ナチス政権の誕生した1933年(昭和8年)に出版された作品だが、必要以上に社会情勢を意識する必要はない。
なぜなら、この物語に含まれているメッセージは、いつの時代の子どもたちにも伝えるべきメッセージとなっているからだ。
主人公は、もちろん、キルヒベルクのヨハン・ジギスムント・ギムナジウムに通う子どもたちで、彼らは寄宿舎で生活している(ギムナジウム5年生の彼らは14歳だ)。
作品タイトルの「飛ぶ教室」は、ジョニー・トロッツの書いたクリスマス劇のタイトルのことで、この物語は、クリスマス直前の寄宿学校が舞台となっている。
ジョニーが書いた芝居は、クリスマス祭に体育館で上演される。前にも紹介したが、「飛ぶ教室」というタイトルだ。5幕物で、ある意味では予言劇である。未来の学校が、実際どんなふうに運営されるだろうかが描かれていた。(エーリッヒ・ケストナー「飛ぶ教室」丘沢静也・訳)
ジョニーの『飛ぶ教室』は、あるいは、不安な社会情勢を反映したものだったかもしれない(実際、彼らは不安定な社会を生きていたのだ)。
上級生や他校生との関わりの中で、少年たちは様々なトラブルに巻き込まれるが、彼らをいつも支える大人たちがいた。
「どうして私にたずねてくれなかったのかな? あんまり信頼されてないのかな?」こちらに顔を向けた。「だったら私自身、罰せられるべきだ。きみたちの違反には私も責任があるわけだから」(エーリッヒ・ケストナー「飛ぶ教室」丘沢静也・訳)
実業学校生につかまった仲間(ルーディ・クロイツカム)を救出するため、少年たちが(舎則に違反して)寄宿学校を抜け出したときに助けてくれたのも、禁煙さんとベーク先生(正義さん)だった。
「なぜ、いけないんだ」と、フリッチェが声をあげた。「教師には、とんでもない義務と責任がある。自分が変えていく能力をなくしちゃダメなんだ。でないと生徒は、朝ベッドから起きださず、授業はレコードで聞けばいいってことになるだろ。だがね、ぼくらに必要なのは人間の教師であって、2本足の缶詰めじゃないんだ。ぼくらを成長させようと思うんだったら、教師のほうだって成長してもらわなきゃ」(エーリッヒ・ケストナー「飛ぶ教室」丘沢静也・訳)
昨今、AIの進化と普及によって、多くの職業が消えてしまうのではないかと言われている。
「学校の先生」も、その候補に挙がっていたらしいが、「ぼくらに必要なのは人間の教師であって、2本足の缶詰めじゃないんだ」という少年(フリッチェ)の言葉は、1931年(昭和6年)のドイツで発せられたものだ(あとがきに作者が登場して、2年前のクリスマスの物語と説明している)。
教師と生徒とが、いかに人間的な絆によって結ばれた関係かということを、再認識させてくれる場面だ。
「正義さんをお手本にしてるんじゃないかな」と、大きな秘密でもうち明けるかのように、ウーリが言った。「正義さんとおんなじように正義が大好きなんだ。たぶん正義さんみたいな大人になるんだろうな」(エーリッヒ・ケストナー「飛ぶ教室」丘沢静也・訳)
作者(ケストナー)が理想的と考える「大人と子どもとの関係」が、この物語には描かれているのだろう。
「友情・努力・勝利」のクリスマス物語
本作『飛ぶ教室』は、まるで『週刊少年ジャンプ』のような物語だ。
「友情・努力・勝利」が、基本コンセプトになっている。
例えば、ボクサー志望の巨漢(マティアス・ゼルプマン)は、臆病で弱虫のチビ(ウールー・フォン・ジルメン)と親友だ。
「だがな、チビ。そんなつもりで、おれ、きのう言ったんじゃないぞ」と、マティアスが言った。「もっとひどいことになってたかもしれないんだぜ。おれは弱虫じゃない。でも、百万くれるって言われても、──はしごから飛び降りたりはしないぞ」(エーリッヒ・ケストナー「飛ぶ教室」丘沢静也・訳)
弱虫を克服するため、はしごから飛び降りて大怪我(全治4週間)をしたウーリの勇気を、マティアスは讃える。
ウーリの勇気は、危険な行為に挑戦するという勇気ではなく、弱虫な自分自身と正面から向き合うことの勇気だった(「ウーリのほうが恥を知ってるってことなんだよ」)。
「あのときウーリは自分で自分に勝ったわけだ」と、船長は考えながら言った。「だからほかのことは、大したことじゃなくなった」(エーリッヒ・ケストナー「飛ぶ教室」丘沢静也・訳)
「船長」とあるのは、父親に見捨てられたジョニー(ジョナサン・トロッツ)の育ての親となった人だ。
ジョニーはマルティンにうなずいた。「心配するなよ。すごく幸せってわけじゃない。幸せだなんて言ったら、ウソになる。けどさ、すごく不幸でもないんだから」(エーリッヒ・ケストナー「飛ぶ教室」丘沢静也・訳)
成績がクラス1番で、絵が上手なマルティン・ターラーも、また、貧しい家庭で育ち、奨学金を受けながら寄宿学校へ通っている苦学生の一人だった。
少年は窓のかんぬきをにぎりしめ、くたびれた灰色の12月の空を見あげて、つぶやいた。「お母さん、ぼくのお母さん」そして泣いてしまった。絶対に泣いてはならなかったはずなのに。(エーリッヒ・ケストナー「飛ぶ教室」丘沢静也・訳)
帰省する交通費を工面できずに泣いていたマルティンを救ってくれたのも、やはり、ベーク先生(正義さん)だった。
「もういいだろ」と、ベーク先生が言った。「きみたちは私に禁煙さんをプレゼントしてくれたんだよ。あいつと今晩、クリスマスを祝うんだ。あのりっぱな禁煙車でね」(エーリッヒ・ケストナー「飛ぶ教室」丘沢静也・訳)
本作『飛ぶ教室』は、二人の優しい大人たち(禁煙さんと正義さん)の友情の物語でもある。
「ヨハン・ベーク、つまり正義さんと、私は、いろんなことを学んだ。この学校で、それから卒業してからも。だが私たちはなにひとつ忘れちゃいない。若かったときのことはしっかり覚えてるんだ。それが大切なんだよ」(エーリッヒ・ケストナー「飛ぶ教室」丘沢静也・訳)
かつて、寄宿学校で親友同士だった二人だが、妻と子どもを病気で失ったとき、ベーク先生の親友(つまり、当時は有能な医者だった禁煙さん)は、何ひとつ告げることなく失踪した(「でも運命には、どんなに勉強しても逆らえないことがある」)。
市民菜園に置かれた禁煙席車両で暮らしている禁煙さんと正義さんを引き合わせたのも、やはり、少年たちだった。
つまり、大人と子どもたちが、互いに信頼関係を築きながら支え合っているのが、この物語の基本的な構図と言っていい。
チビで弱虫のウーリが紙くずかごに入れられて、教室の天井から吊るされているのを見つけたとき、クロイツカム先生は、ウーリの親友で腕自慢のマティアスに話しかける。
「どうして止めなかった?」「多すぎたんです、相手が」と、ウーリが天井から説明した。「どんな迷惑行為にも、それをやった者にだけ責任があるのではなく、それを止めなかった者にも責任がある」と、先生が宣告した。(エーリッヒ・ケストナー「飛ぶ教室」丘沢静也・訳)
少年たちと正面から向き合う大人は、彼らの信頼を得ることができるということを、作者(ケストナー)は伝えたかったのかもしれない。
『飛ぶ教室』は、作者(ケストナー)からのメッセージに溢れた物語だったのだ。
それにしても、ケストナー作品では、作者自身が、物語の中に登場することが珍しくない(いわゆる「メタ構造」)。
物語の終わりで、作者は、登場人物の一人(ジョニー)と偶然に遭遇する(クリスマス劇『飛ぶ教室』の脚本を書いた少年だ)。
小説家志望のジョニーは、自分の書いた作品を送ってもいいかと、作者に訊ねる。
「いいですよ」と、私は言った。「でもね、ジョニー、書いたものを見せてもらうだけで、才能のことはわからないよ。書けてるかどうかはチェックできるけど、作家になれるかどうかはチェックできないからね。それは後になって決まることだ」(エーリッヒ・ケストナー「飛ぶ教室」丘沢静也・訳)
作者自身も、また、少年たちを支える大人の一人としての役割を果たしているのだ。
作品上、こうした構造は、物語にリアリティを与える効果を発揮している(「きみたちのこと、本に書いたんだよ」「それも、きみたちが2年前のクリスマスにやった貴重な経験について」)。
ケストナー作品の魅力のひとつが、こうした「遊び」にあるのではないだろうか。
大切なことは、作者(ケストナー)が、子どもたちの心に真正面から向き合っている、ということだろう(禁煙さんや正義さんと同じように)。
相手が子どもだからと言って、ごまかすようなことはしない。
ボクシングで言うように、ガードを固めることだ。パンチを食らっても、耐えられるようになっておこう。でないと、人生最初の一発でふらふらになる。人生は、とんでもなく大きなグローブをはめているものだ。(エーリッヒ・ケストナー「飛ぶ教室」丘沢静也・訳)
過酷な時代を生きなければいけない子どもたちに向けられたメッセージ。
それは、未来の大人たちへと贈られた、作者(ケストナー)からのクリスマス・プレゼントだったのかもしれない。
書名:飛ぶ教室
著者:エーリッヒ・ケストナー
訳者:丘沢静也
発行:2006/09/20
出版社:光文社古典新訳文庫
[itemlink post_id=”18790″