レイモンド・チャンドラー「高い窓」読了。
本作「高い窓」は、私立探偵フィリップ・マーロウが登場する長編ミステリーの第3作目の作品で、アメリカでは1942年(昭和17年)に刊行された。
日本では、1959年(昭和34年)に<ハヤカワ・ポケット・ミステリ>から、田中小実昌の翻訳で刊行されたのが最初だが、現在は、1988年(昭和63年)に清水俊二が翻訳した<ハヤカワ・ミステリ文庫>版が定番となっている。
なお、最新の翻訳としては、2014年の村上春樹<ハヤカワ・ミステリ文庫>版がある。
今回は、1988年から親しまれている清水俊二訳によるものだが、村上春樹ファンの管理人としても、フィリップ・マーロウ・シリーズは、清水俊二の訳でなければしっくりこないような気がする。
そもそも、管理人がレイモンド・チャンドラーを読むようになったのは、村上春樹の影響で、『羊をめぐる冒険』が、チャンドラーの『長いお別れ』に対するオマージュであったことなど、僕にとっては、村上作品こそが、チャンドラーの原体験となっている部分があるほどだ。
マーロウ・シリーズの最大の魅力は、ストーリー展開よりも、キャラクター設定にある。
例えば、登場人物の一人一人に対する描写説明が非常に子細で、いわゆる「キャラ立ち」の素晴らしさが、長いフィクションにリアリティを与えている。
彼女は私たちが芝生を踏んで近づいて行くのをものうげに見つめていた。三十フィート離れたところからはなかなかの女に見えた。十フィート離れたところでは、三十フィート離れて見るべき女だった。口が大きすぎ、目が青すぎ、化粧が派手すぎ、細く描かれた眉毛が長すぎる上にいかにも奇妙なかたちで、睫毛の上のマスカラが濃すぎて、鉄柵のミニチュアのように見えた。
白い帆布のスラックス、はだしの足にブルーと白のサンダル、真紅のペディキュア、白い網のブラウスに本物のエメラルドではない緑色の宝石の頸飾り。頭髪はナイトクラブのロビーのように手がこんでいた。(レイモンド・チャンドラー「高い窓」)
これは、人間だけではなく、舞台設定についても同様で、マーロウが出現する部屋の描写は、小物ひとつひとつの様子まで、きめ細かく書き込まれている。
現代風に言えば、ゲームの舞台設定における世界観が完璧に構築されている、というようなことになるだろうか。
そもそも、こうした描写のすべては、マーロウの観察眼の鋭さを、そのまま表現しているということでもある。
全体のストーリー展開とは関係のない部分かもしれないが、フィリップ・マーロウの世界を楽しむ上では欠くことのできないマテリアルになっていると思う。
筋書だけ抜き出してしまっては、面白くも何ともない。
それが、フィリップ・マーロウという物語の世界なのだ。
失われた金貨を探し求めて
ある金持ちの女性から依頼を受ける。
女性の息子の嫁が失踪し、同時に、女性の亡き夫がコレクションしていた貴重な金貨が一枚紛失していたのだ。
女性は、事件を公にすることなく硬貨を取り戻すよう、マーロウに依頼するが、マーロウの行く先々で人が殺されていく。
この物語の難しいところは、マーロウの本当の敵がどこにいるのかが、まったく分からないことだ。
一方で、それは、マーロウが本当に味方すべき人物が誰なのかということが、まったく分からないということでもある。
読者は著しく不安定な物語の中に放り出されたまま、このミステリーを読み進めることになるだろう。
謎解きとしての醍醐味はあるが、小説として感情移入しにくい作品だという気はする。
マーロウの味方すべき人間が明らかになった時点で、物語は終わってしまうからだ。
これは、難解なミステリー作品としては有効な成果をもたらす一方で、ひとつの文学作品としては『長いお別れ』や『さらば愛しき女よ』のような名作にまでは至らなかった、大きな要因になっているとも思われる。
もちろん、本作『高い窓』においても、男女間の複雑な恋愛感情のもつれなど、微細な人間関係が描かれているが、これはマーロウ・シリーズにとって、最大の魅力であるからして省くことはできないものである。
「人って、いつもいやなことは忘れろっていうのね。でも決して忘れられない。なのにそういうなんて、愚かなことだと思いますわ」「わかったよ」と、私は傷ついたふりをしていった。「私は愚か者だ。もうすこし眠ったらどうだね」(レイモンド・チャンドラー「高い窓」)
マーロウ・シリーズには人生訓が多い。
だからこそ、大人が読むべき文学作品なのだ。
ただし、マーロウと女性登場人物との色っぽい関係は、本作では登場しない。
<セックスとバイオレンス>が売り物の安っぽいハードボイルドとは、そもそも次元が異なっているのかもしれない。
書名:高い窓
著者:レイモンド・チャンドラー
訳者:清水俊二
発行:1988/9/15
出版社:ハヤカワ・ミステリ文庫
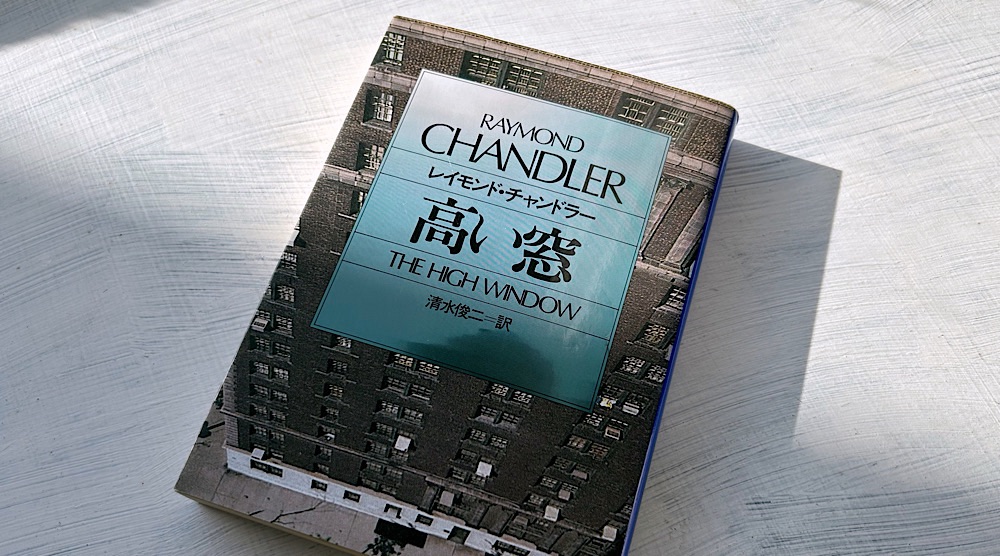


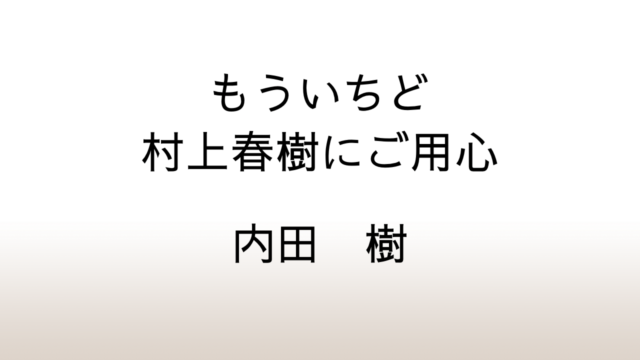



-150x150.jpg)








