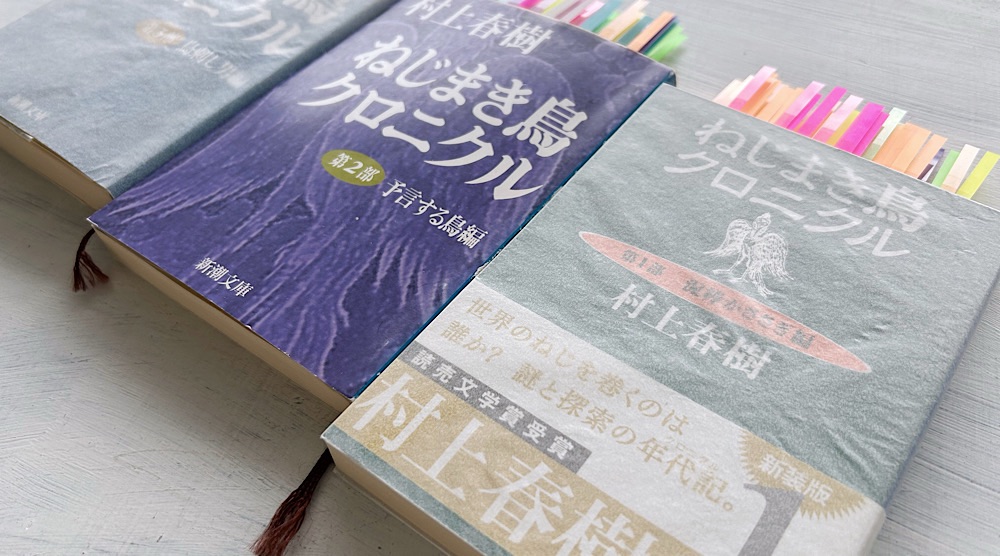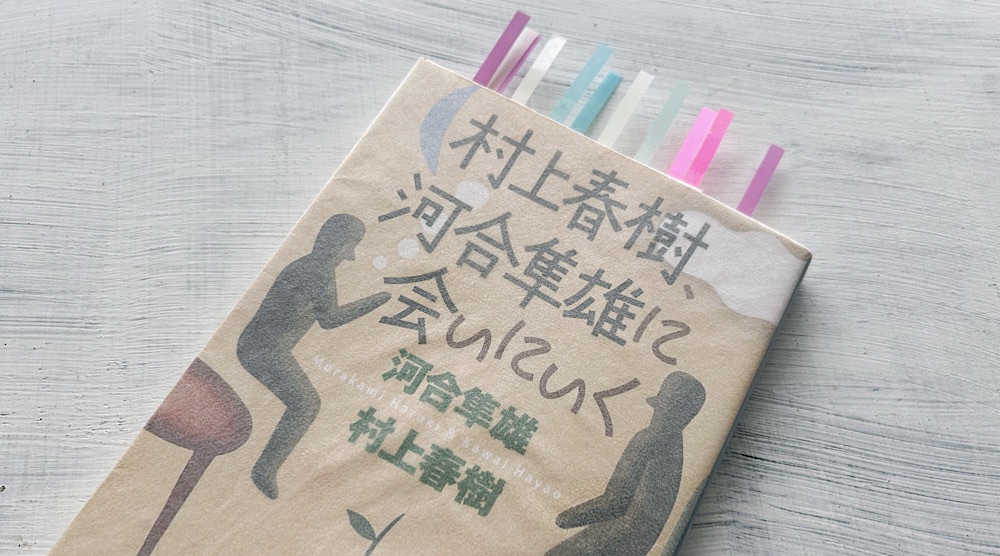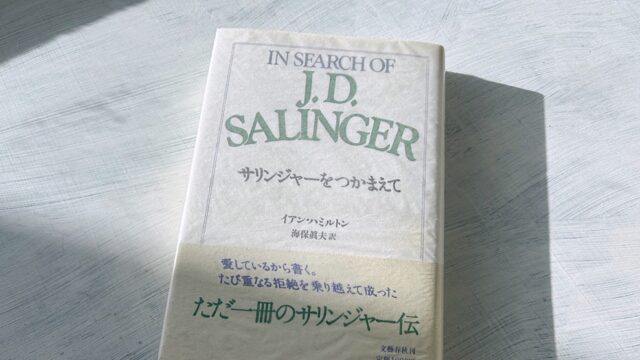村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』読了。
本作『ねじまき鳥クロニクル』は、1994年(平成6年)4月及び1995年(平成7年)8月に刊行された長篇小説である。
「第1部 泥棒かささぎ編」の初出は、1992年(平成4年)10月~1993年(平成5年)8月『新潮』で、連載開始の年、著者は43歳だった。
単行本は、1994年(平成6年)4月12日(火曜日)に、新潮社から刊行されている。
「第2部 予言する鳥編」も、同じく1994年(平成6年)4月12日(火曜日)の刊行だが、「第3部 鳥刺し男編」は、「第1部」「第2部」に遅れて、1995年(平成7年)8月25日に刊行された(いずれも単行本書き下ろし)。
1996年(平成8年)2月、第47回「読売文学賞」受賞。
『ねじまき鳥クロニクル』の文学的テーマ
『クーリエ・ジャポン』(Vol.036/2007年10月号)に、『タイム』誌・東京支局長の寄稿が掲載されている(もちろん、村上春樹に関する記事だ)。
彼の作品の背後にはつねに日本の歴史があり、彼の最も優れた小説とされる1994年の『ねじまき鳥クロニクル』は、日本を悲惨な戦争に巻き込んだ集団志向を分析している。(『クーリエ・ジャポン』(Vol.036/2007年10月号))
2007年(平成19年)時点において、『ねじまき鳥クロニクル』は、「彼の最も優れた小説」として、『タイム』誌の評価を受けていたらしい。(『海辺のカフカ』は2002年、『1Q84』は2009年の刊行)。
『ねじまき鳥クロニクル』は、なぜ、「彼の最も優れた小説」として評価されていたのだろうか?
本作『ねじまき鳥クロニクル』は、結婚6年目となるアラサー夫婦の危機を描いた物語である(端的に言えば夫婦喧嘩の話)。
主人公(岡田亨、30歳)は、法律事務所の仕事を辞める。
妻(岡田久美子)が大切にしていた猫(ワタヤノボル)がいなくなる。
「わかってほしいんだけど、あの猫は私にとっては本当に大事な存在なのよ」と妻は言った。「というか、あの猫は私たちにとって大事な存在だと思うの」(村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』第1部 泥棒かささぎ編4│高い塔と深い井戸、あるいはノモンハンを遠く離れて)
猫は見つからず、夫婦は喧嘩する。
「あなたは私と一緒に暮らしていても、本当は私のことなんかほとんど気にとめてもいなかったんじゃないの? あなたは自分のことだけを考えて生きていたのよ、きっと」と彼女は言った。(村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』第1部 泥棒かささぎ編2│満月と日蝕、納屋の中で死んでいく馬たちについて)
そして、ある日、妻が突然に失踪した。
主人公は、妻が失踪した理由について考える。
ひとりの人間が、他のひとりの人間について十全に理解するというのは果して可能なことなのだろうか。(略)我々は我々がよく知っていると思い込んでいる相手について、本当の何か大事なことを知っているのだろうか。(村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』第1部 泥棒かささぎ2編│満月と日蝕、納屋の中で死んでいく馬たちについて)
主人公は「青いティッシュペーパー」と「柄のついたトイレットペーパー」を、妻が嫌っていることに気がついていなかった。
妻が「牛肉とピーマンを一緒に炒めるのが大嫌い」だということも知らなかった。
6年間も一緒に生活していながら、どうやら自分たちには、まだまだ互いに理解できていない部分があるらしい。
その夜、僕は明かりを消した寝室の中で、クミコの隣に横になって天井を見ながら、自分はこの女についていったい何を知っているのだろうと自問した。(村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』第1部 泥棒かささぎ編2│満月と日蝕、納屋の中で死んでいく馬たちについて)
夫婦関係や妻への疑問は、やがて、自分自身に対する疑問へとつながっていく。
あるいは僕は彼女のことを最後までよく知らないまま年老いて、そして死んでいくのだろうか? もしそうだとしたら、僕がこうして送っている結婚生活というのはいったい何なんだろう? そしてそのような未知の相手と共に生活し、同じベッドの中で寝ている僕の人生というのはいったい何なんだろう?(村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』第1部 泥棒かささぎ編2│満月と日蝕、納屋の中で死んでいく馬たちについて)
突き詰めると、「僕の人生というのはいったい何なんだろう?」というところに、『ねじまき鳥クロニクル』という長編小説のテーマがある(わかりやすい言葉で言えば「自分探し」)。
本作『ねじまき鳥クロニクル』は、夫婦喧嘩を通して(妻の失踪を通して)、自分自身の核心へと迫っていく、内面の物語である。
女たちの「心の闇」にコミットする
本作『ねじまき鳥クロニクル』について、著者(村上春樹)は、心理学者(河合隼雄)との対談で、自分なりの解釈を披露している(『村上春樹、河合隼雄に会いにいく』1996年)。
【村上】物語のはじめでは、彼にはまだクミコにコミットする資格がないんですよ。井戸をくぐって行くことは、その資格を得るための、『魔笛』で言う試練みたいなものじゃないかとぼくは思ったんです。(河合隼雄・村上春樹『村上春樹、河合隼雄に会いにいく』)
『村上春樹、河合隼雄に会いにいく』では、『ねじまき鳥クロニクル』にフォーカスした議論が展開されているので、『ねじまき鳥クロニクル』をもっと深く理解したいと思う人には読む価値あり(おかしな解説本より、ずっと意味があるし、おもしろい)。
妻(クミコ)の気持ちを理解できない主人公は、猫探しの過程の中で出会った人々との対話を通して、少しずつ、妻の心へと近づいていく。
例えば、妻から紹介された謎の占い師(加納マルタ)の妹(加納クレタ、26歳)は、孤独な十代を過ごした女性である。
私は家族の中でひとりぼっちでした。私の人生は孤独でした。私は苦痛に満ちた──その苦痛についてはあとでまたくわしくお話いたしますが──十代を送りました。(村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』第1部 泥棒かささぎ編8│加納クレタの長い話、苦痛についての考察)
失踪した妻(クミコ)の化身とも言うべき加納クレタは、クミコの兄(綿谷昇)に汚された過去を持つという点においても、クミコと一致している(「考えてみれば、加納クレタの体つきはおどろくくらいクミコに似ていた」)。
加納クレタは言った。「もちろん私たちは現実に交わっているわけではありません。岡田様が射精なさるとき、それは私の体内にではなく、岡田様自身の意識の中に射精なさるわけです。おわかりですか?」(村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』第2部 予言する鳥編4│失われた恩寵、意識の娼婦)
多額の借金を返済するために売春で金を稼ぐ加納クレタの姿は、偏執的な性的欲望を満たすために不特定多数の男たちとセックスを繰り返す妻(クミコ)の本質へとつながっていく。
そして、二人の女性に共通しているのは、クミコの兄(綿谷ノボル)によって汚されてしまった、ということだった(「何故ならその男は私の体の中の何かをこじあけたからです」)。
それから奇妙なことが起こりました。そのぱっくりとふたつに裂けた自分の肉の中から、私がこれまでに見たことも触れたこともなかった何かが、かきわけるようにして抜け出してくるのを私は感じたのです。(村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』第2部 予言する鳥編13│加納クレタの話の続き)
本来、見てはいけない「自分の中の何か」を引き出したのは、綿谷ノボルだった(「私は綿谷ノボル様によって肉体を犯され、意識をこじあけられることで、第三の私を獲得しました」)。
もう一人、妻(クミコ)の化身と考えられる女性が登場する。
物語の冒頭で、心の奥底深くに潜む性的欲望を剝き出しにしたような卑猥な電話をかけてきた、謎の女である(「これじゃまるでポルノ・テープじゃないか」)。
「オカダトオルさん、私の名前をみつけてちょうだい。いいえ、わざわざみつける必要もないのよ。あなたは私の名前を既にちゃんと知っているの。あなたはそれを思いだすだけでいいのよ。あなたが私の名前をみつけることさえできれば、私はここを出ていくことができる」(村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』第2部 予言する鳥編8│欲望の根、208号室の中、壁を通り抜ける)
井戸に潜り、壁を抜けたことで主人公は、謎の女(つまり「妻の心」)にコミットすることができた。
僕は短く息をのみ、ゆっくりとそれを吐き出す。吐き出す息はまるで焼けた石のように固く、熱い。間違いない。あの女はクミコだったのだ。(村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』第2部 予言する鳥編18│クレタ島からの便り、世界の縁から落ちてしまったもの、良いニュースは小さな声で語られる)
言い換えれば、主人公は、加納クレタという妻の分身を通して、妻の潜在意識にまで降りていくことが可能となったのである(「岡田様、私は娼婦なのです。かつては肉体の娼婦であり、今では意識の娼婦なのです」)。
加納クレタが「ぱっくりとふたつに裂けた自分の肉の中から、私がこれまでに見たことも触れたこともなかった何かが、かきわけるようにして抜け出してくるのを私は感じた」と語っているものは、井戸への案内人(笠原メイ、16歳)が語っているものでもある。
「私という人間は私の中にあったあの白いぐしゃぐしゃとした脂肪のかたまりみたいなものに乗っ取られていこうとしているのよ」(村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』第2部 予言する鳥編16│笠原メイの家に起こった唯一の悪いこと、笠原メイのぐしゃぐしゃとした熱源についての考察)
オートバイ事故で、彼女(笠原メイ)のボーイフレンドを殺したものは、彼女自身の中に潜む「ぐしゃぐしゃ」だった。
「ねえ、ねじまき鳥さん、私には世界がみんな空っぽに見えるの。私のまわりにある何もかもがインチキみたいに見えるの。インチキじゃないのは私の中にあるそのぐしゃぐしゃだけなの」(村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』第2部 予言する鳥編16│笠原メイの家に起こった唯一の悪いこと、笠原メイのぐしゃぐしゃとした熱源についての考察)
空地の井戸へと導いてくれた笠原メイは、主人公(岡田亨)の意識下の管理人としての機能を果たしている(双子の女の子や羊牧場の管理人と同じように)。
後に、主人公の雇い主となるセレブ(赤坂ナツメグ)が治療していたものも、やはり「自分の中に潜む何か」だった(「世の中の女たちのすべてがこのような何かを抱えているのだろうか?」)。
彼女は意識を集中してそのかたちをもっと具体的に探ってみようとした。しかし彼女が意識を集中すると、その何かは身をよじるようにするりとかたちを変えた。これは生きているのだ。(村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』第3部 鳥刺し男編21│ナツメグの話)
「自分の肉の中から出てくる何か」や「白いぐしゃぐしゃ」は、綿谷ノボルが主張する「欲望の根」に通じるものではなかったか。
「動機というものはいうなれば欲望の根です。大事なのは、その根をたどることです。現実という複雑さの地面を掘るのです。それをどこまでも掘っていくのです。その根のいちばん先のところまでどこまでも掘っていくのです」(村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』第2部 予言する鳥編8│欲望の根、208号室の中、壁を通り抜ける)
妻(クミコ)や加納クレタは、綿谷ノボルによって「欲望の根」のいちばん先のところまで掘られてしまったために、自分自身を損なってしまった(非常に濃密な性行為によって)。
こうした「欲望の根」は、妻(クミコ)の好きな「クラゲ」に象徴されているものとして読むことができる。
「私たちは習慣的にこれが世界だと思っているわけだけれど、本当はそうじゃないの。本当の世界はもっと暗くて、深いところにあるし、その大半がクラゲみたいなもので占められているのよ」(村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』第2部 予言する鳥編6│遺産相続、クラゲについての考察、乖離の感覚のようなもの)
『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』(1985)で「カタツムリ」が物語の世界観を象徴していたように、本作『ねじまき鳥クロニクル』では、「クラゲ」が物語の世界観を象徴していると言っていい。
「だからその家の中で君はいつも孤独であり、いつも緊張していた。得体の知れない潜在的な不安の中にひっそりと暮らしていた。まるであの水族館のクラゲみたいにね」(村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』第3部 鳥刺し男編36│蛍の光、魔法のとき方、朝に目覚まし時計の鳴る世界)
クラゲの、もっと奥深いところまでコミットするには、井戸へ潜り、壁を抜けることが必要だった。
ヒントを与えてくれたのは、間宮中尉の「ノモンハン戦争体験」である。
「暗闇」はノモンハン戦争にまでつながっていく
本作『ねじまき鳥クロニクル』において、「ノモンハン戦争」は、非常に重要なキーワードとなっている。
失踪した妻を探すのに、どうして「ノモンハン戦争」が出てくるのか?
それは、「現代を生きている我々とは何か?」を考えるとき、近代の戦争体験は、大きな鍵となり得るからだ。
【村上】たとえば、ノモンハンでの間宮中尉の強烈な体験も、ただの老人の思い出話ではなく、僕の中にも引き継がれている生の記憶であり、僕の血肉となっているものであり、現在に直接の作用を及ぼしているものです。そこが大事なんです。(『考える人』2010年夏号「村上春樹ロングインタビュー」)
同様の主張は、他にもある。
【村上】それと同時に、いまの日本の社会が、戦争が終わって、いろいろつくり直されても、本質的に何も変わっていない、ということに気がついてくる。それがぼくが『ねじまき鳥クロニクル』のなかで、ノモンハンを書きたかったひとつの理由でもあるのです。(河合隼雄・村上春樹『村上春樹、河合隼雄に会いにいく』)
妻(クミコ)の家族と親密な交際のあった占い師(本田さん)は、亡くなる際に、主人公への形見分けを、戦友(間宮徳太郎)に託した。
間宮中尉との出会いにより、主人公は、ノモンハン事件を通して、井戸の底へ潜ることの啓示を受ける。
つまり、本田さんは、間宮中尉を通して、井戸の底へ潜ることの意味を教えてくれたのだ(「下に下りたいときには、いちばん深い井戸の底に下りればいい」)。
ロシア人将校(皮剥ぎボリス)の残酷な拷問を見せつけられた間宮中尉は、外蒙古の砂漠にある深い井戸で、不思議な体験をする。
そのような特殊な状況下にあって、私の意識はきわめて濃密に凝縮されており、そしてそこに一瞬強烈な光が射し込むことによって、私は自らの意識の中核のような場所にまっすぐに下りていけたのではないでしょうか。とにかく、私はそこにあるものの姿を見たのです。(村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』第2部 予言する鳥編4│失われた恩寵、意識の娼婦)
間宮中尉の「井戸体験」は、やがて、主人公自身の「井戸体験」へとつながっていく。
それは、自分自身の中にある「何か」と向き合うことにより、妻(クミコ)の中にある「何か」へとコミットすることでもあった。
井戸の底で、主人公は、妻(クミコ)が妊娠したときの(そして堕胎したときの)ことを思い出す。
たぶんあの時から何かが変わり始めたんだ、僕はふと思った。間違いない。あの時を境として僕のまわりで流れが確かな変化を見せ始めたのだ。今になって考えてみれば、あの堕胎手術は僕ら二人にとって、非常に重要な意味を持つ出来事だったのだ。(村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』第2部 予言する鳥編17│いちばん簡単なこと、洗練されたかたちでの復讐、ギターケースの中にあったもの)
警告(サイン)は、既に札幌の夜にあった。
「自分の痛みは自分にしかわからない、と人は言います。しかし本当にそうでしょうか? 私はそうは思いません。たとえば誰かが本当に苦しんでいる光景を目の前にすれば、私たちもその苦しみや痛みを自分自身のものとして感じることがあります。それが共感する力です」(村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』第2部 予言する鳥編7│妊娠についての回想と対話、苦痛についての実験的考察)
謎のギター弾きは「自分という殻を離れ、多くの人々と痛みや喜びを共有したい」と言った。
そして、「自分の殻」を壊すための道具として、主人公に「野球バット」を引き継いだのだ。
多くのエピソードが、まるでパズルのように散りばめられているが、一つ一つのピースをつなぎ合わせていくと、大きな物語の全体像が見えてくる。
いずれ、シナモンの『ねじまき鳥クロニクル』で綴られることになる動物園での虐殺エピソードは、札幌のギター弾きのエピソードと共鳴するものだ。
銃剣を突き刺し、かき回し、突きあげ、抜いた。獣医は無感動にそれを眺めていた。彼は自分が分裂を始めているような錯覚に襲われた。自分は相手を刺すものであり、同時に相手に刺されるものだった。彼は突き出した銃剣の手ごたえと、切り刻まれる内臓の痛みを同時に感じることができた。(村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』第3部 鳥刺し男編28│あるいは二度目の要領の悪い虐殺)
主人公に必要だったのは、妻(クミコ)に潜む「心の痛み」に共感することだったのかもしれない。
「ねじまき鳥」が紡いだ物語
すべてのエピソードで通奏低音となっているのが、作品タイトルでもある「ねじまき鳥」である。
近所の木立からまるでねじでも巻くようなギイイイッという規則的な鳥の声が聞こえた。我々はその鳥を「ねじまき鳥」と呼んでいた。クミコがそう名づけたのだ。(村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』第1部 泥棒かささぎ1編│火曜日のねじまき鳥、六本の指と四つの乳房について)
ねじまき鳥の姿を見た者はいないし、その鳴き声も、誰にでも聴くことのできるものではなかった。
「ねじを巻く鳥だよ」と僕は言った。「毎朝木の上で世界のねじを巻くんだ。ギイイイイイって」(村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』第1部 泥棒かささぎ編5│レモンドロップ中毒、飛べない鳥と涸れた井戸)
ねじまき鳥は、「運命」や「宿命」といった言葉を具現する象徴ととらえていい(「運命は獣医の宿業の病だった」)。
「世の中の人々はみんなもっと立派で複雑で巨大な装置がしっかりと世界を動かしていると思っている。でもそんなことはない。本当はねじまき鳥がいろんな場所に行って、行く先々でちょっとずつ小さなねじを巻いて世界を動かしているんだよ」(村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』第2部 予言する鳥編15│正しい名前、夏の朝にサラダオイルをかけて焼かれたもの、不正確なメタファー)
しかし、ねじまき鳥が本当に力を発揮するのは、バラバラになった複数のパズルをつなぎ合わせる効果を発揮したときだろう。
例えば、赤坂ナツメグの息子(赤坂シナモン)が言葉を失った夜も、ねじまき鳥が鳴いた。
それからもう一度同じ音が聞こえた。音は間違いなく窓の外から聞こえてきた。誰かがどこかで大きなねじを巻いている音だった。(村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』第3部 鳥刺し男編5│真夜中の出来事)
謎の男たちが埋めた「心臓」を掘り起こしたことで、シナモンは、永遠に言葉を失ってしまう。
「今では私にもわかっている。彼の言葉はその物語のある世界の迷路の中に吞み込まれて消えてしまったのよ。その物語から出てきたものが彼の舌を奪って持っていってしまったのよ。そしてそれは、その数年後に私の夫を殺すことになった」(村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』第3部 鳥刺し男編15│シナモンの不思議な手話、音楽の捧げもの)
「その物語」とは、ナツメグが幼いシナモンと造り上げた、かつての新京(満州国の首都)における「動物園の物語」である(シナモンのパソコンのパスワードは「Zoo」)。
動物園で獣医として働いていたのは、幼きナツメグの父親だった。
彼らはおそろしく腕がよく、作業の要領もいい。動物たちはあっというまもなく皮と肉と内臓と骨とに分けられてしまう。(村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』第3部 鳥刺し男編10│動物園襲撃(あるいは要領の悪い虐殺))
後年、ナツメグの夫(シナモンの父)は、あたかも、中国人が動物たちを切り分けてしまったかのように、惨殺された死体となって発見される。
身体じゅうの血という血が、ほとんど一滴残らず外に流れ出てしまっていた。そして心臓と、胃と、肝臓と、ふたつの腎臓と、膵臓が身体からなくなっていた。(村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』第3部 鳥刺し男編21│ナツメグの話)
少年時代のシナモンが見た「心臓」は、あるいは、父親の将来に対する呪いだったのかもしれない。
そして、その呪いは、終戦直前に新京の動物園で起こった虐殺事件が由来していたかもしれないのだ。
シナモン少年と獣医だった祖父をつないでいるのも、ねじまき鳥だった。
彼はただねじまき鳥の声に耳を澄ましていた。鳥は昨日の午後と同じように木立のどこかから、やはりネジを巻くようにギイイ、ギイイイと鳴いていた。(村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』第3部 鳥刺し男編28│あるいは二度目の要領の悪い虐殺)
『ねじまき鳥クロニクル』は、赤坂シナモンによって綴られた物語である。
おそらくシナモンは自分という人間の存在理由を真剣に探しているのだ。彼はそれを自分がまだ生まれる以前に遡って探索していたに違いない。(村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』第3部 鳥刺し男編29│シナモンのミッシング・リンク)
シナモンの作りあげた物語群に「クロニクル(年代記)」というタイトルが与えられている理由は、シナモンの歴史は、シナモン一人の人生によってのみ語られるべきものではないからだ。
シナモンは、自分という人間を語るために、祖父の生きた満州国にまで遡らなければならなかったのである。
すべては輪のように繋がり、その輪の中心にあるのは戦前の満州であり、中国大陸であり、昭和十四年のノモンハンでの戦争だった。(村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』第3部 鳥刺し男編24│羊を数える、輪の中心にあるもの)
「ねじまき鳥」は、複数の時代と複数の人々とをつなぎ合わせるパスワードとして機能している。
しかしそれが偶然の一致であるにせよないにせよ、シナモンの物語では「ねじまき鳥」という存在が、大きな力を持っていた。人々はとくべつな人間にしか聞こえないその鳥の声によって導かれ、避けがたい破滅へと向かった。(村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』第3部 鳥刺し男編29│シナモンのミッシング・リンク)
獣医(シナモンの祖父)は、小さな子どもの頃から「自分という人間は結局のところ何かの外部の力によって定められて生きているのだ」という思いを抱いて生きてきた(「あるいはそれは、彼の右の頬についている鮮やかな青いあざのせいかもしれない」)。
彼らは人形が背中のねじを巻かれてテーブルの上に置かれたみたいに選択の余地のない行為に従事し、選択の余地のない方向に進まされた。その鳥の声の聞こえる範囲にいたほとんどの人々が激しく損なわれ、失われた。多くの人々が死んでいった。彼らはそのままテーブルの縁から下にこぼれ落ちていった。(村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』第3部 鳥刺し男編29│シナモンのミッシング・リンク)
『ねじまき鳥クロニクル』という作品の素晴らしさは、「ねじまき鳥」というメタファーに象徴されていると言っていい。
「ねじまき鳥」という概念こそが、やがて「彼の最も優れた小説」という評価を受けることになる、最大のポイントだったのだ。
結論から言えば、『ねじまき鳥クロニクル』は、やはり、村上春樹にとっての最高傑作である。
最も売れたのは『ノルウェイの森』で、最も長いのは『1Q84』、最も根強い人気があるのは『羊をめぐる冒険』で、最もおもしろいのは『ダンス・ダンス・ダンス』だけれど、「最も素晴らしい作品」となると、やはり『ねじまき鳥クロニクル』を置いて、他にはないだろう。
できれば映画で観てみたい迫力が、この物語にはある(一歩間違うと、これ以上ないくらいに陳腐な作品になってしまうかもしれないが)。
ノモンハン戦争と現代をつなぐもの
夫婦喧嘩の要因を「ノモンハン事件」にまで遡って紐解いた、ダイナミックなストーリー展開も、『ねじまき鳥クロニクル』という作品の、大きな見どころとなっている。
【村上】僕にとって『ねじまき鳥クロニクル』のなかでいちばん大事な部分は、「壁抜け」の話です。堅い石の壁を抜けて、いまいる場所から別の空間に行ってしまえること、また逆にノモンハンの暴力の風さえ、その壁を抜けてこちらに吹き込んでくるということ、隔てられているように見える世界も、実は隔てられてないんだということ、それがいちばん書きたかったことです(『考える人』2010年夏号「村上春樹ロングインタビュー」)
「壁抜け」は、かつて『ダンス・ダンス・ダンス』(1988)にも登場した、潜在意識下におけるワープ現象だ。
部屋の暗闇の中に廊下の光がさっと差し込むのとほとんど同時に、僕らは壁の中に滑り込んだ。(略)僕は壁を通り抜けているんだ。(村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』第2部 予言する鳥編8│欲望の根、208号室の中、壁を通り抜ける)
主人公に壁抜けを促したのは、偏執的な性的欲望を剥き出しにした謎の女(妻の本当の姿)である。
性欲にまみれた妻の姿は、かつて、満州国で非道な虐殺を行った日本兵たちの姿でもある(そこは、闇が支配する世界だった)。
「そして彼は今その力を使って、不特定多数の人々が暗闇の中に無意識に隠しているものを、外に引き出そうとしている。それを政治家としての自分のために利用しようとしている。それは本当に危険なことだ」(村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』第3部 鳥刺し男編29│シナモンのミッシング・リンク)
構造的に『ねじまき鳥クロニクル』は、「主人公」VS「綿谷ノボル」という二者間の対立を描いた物語である(両者は「クミコ」を求めて争い合う)。
それは、「光の世界」と「闇の世界」との争いでもあった(「それは君が僕の側の世界から、綿谷ノボルの側の世界に移ったということだ。大事なのはそのシフトなんだ」)。
【村上】『ねじまき鳥クロニクル』の中においては、クミコという存在を取り戻すことがひとつのモチーフになっているのですね。彼女は闇の世界の中に引きずり込まれているのです。彼女を闇の世界から取り戻すためには暴力を揮わざるをえない。そうしないことには、闇の世界から取り戻すことについての、カタルシス、説得力がないのです。(河合隼雄・村上春樹『村上春樹、河合隼雄に会いにいく』)
『ねじまき鳥クロニクル』の世界において、暴力は「野球バット」に象徴される(新京で中国人を撲殺した野球バットを使って、主人公は綿谷ノボルを撲殺する)。
「彼の引きずりだすものは、暴力と血に宿命的にまみれている。そしてそれは歴史の奥にあるいちばん深い暗闇にまでまっすぐ結びついている。それは多くの人々を結果的に損ない、失わせるものだ」(村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』第3部 鳥刺し男編29│シナモンのミッシング・リンク)
「闇の世界」の支配者である「綿谷ノボル」は、「歴史の奥にあるいちばん深い暗闇」の象徴であり、だからこそ、主人公は「野球バット」を手にして、綿谷ノボルを叩き潰さなければならない(それは、自分の中の「戦争の記憶」との戦いだった)。
「それを見ちゃいけない」誰かが大声で僕を押しとどめた。奥の部屋の闇の中からクミコの声がそう叫んでいた。(村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』第3部 鳥刺し男編37│ただの現実のナイフ、前もって予言されたこと)
暗闇の中で「自分が殴り殺したもの」の正体を、主人公は見ることができない。
しかし、現実世界の綿谷ノボルは、間違いなく昏倒していた。
僕は彼の中の何かを、あるいは彼と強い繋がりのある何かをあそこでしっかりと殴り殺した。おそらく綿谷ノボルはそれを前もって予感し、悪い夢を見続けていたのだ。(村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』第3部 鳥刺し男編39│二種類の異なったニュース、どこかに消え去ったもの)
主人公が殴り殺したものは「不特定多数の人々が暗闇の中に無意識に隠しているもの」だ。
ある意味で、それは、自分自身との戦いでもあった。
物語の最終場面では、涸れ井戸に水が湧いていることが確認される。
僕のまわりには水があった。それはもう涸れた井戸ではなかった。僕は水の中に腰をおろしているのだ。(村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』第3部 鳥刺し男編37│ただの現実のナイフ、前もって予言されたこと)
涸れた井戸に湧き出る水は、主人公の再生を暗示している。
【村上】これまでのぼくの小説は、何かを求めるけれども、最後に求めるものが消えてしまうという一種の聖杯伝説という形をとることが多かったのです。ところが『ねじまき鳥クロニクル』では「取り戻す」ということが、すごく大事なことになっていくのですね。(河合隼雄・村上春樹『村上春樹、河合隼雄に会いにいく』)
少なくとも、壁を抜け、暗闇の世界で謎の女(本当のクミコ)と愛し合い、野球バットで綿谷ノボルを撲殺した主人公は、物語の冒頭部分に比べて、多くの成長を成し遂げていた。
主人公の成長を支えたものは、多くの登場人物が語った「心の闇」である。
ほとんど「トラウマ」と言っていい「心の闇」は、人々の暗闇の中で、ひっそりと隠しこまれてきたものだ。
主人公は、人々の「心の闇」に触れることで「歴史の闇」に触れ、妻(クミコ)の「心の闇」へと入り込むことができたのである。
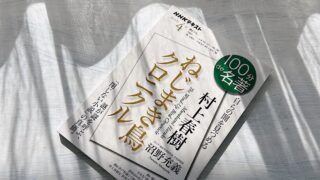
夫婦のイメージは夏目漱石の『門』にあった
『ねじまき鳥クロニクル』の執筆にあたり、著者(村上春樹)は、夏目漱石『門』を意識していたらしい。
【村上】ぼくが『ねじまき鳥クロニクル』を書くときにふとイメージがあったのは、やはり漱石の『門』の夫婦ですね。ぼくが書いたのとはまったく違うタイプの夫婦ですが、イメージとしては頭の隅にあった。(河合隼雄・村上春樹『村上春樹、河合隼雄に会いにいく』)
「宗助」と「御米(およね)」は、社会から隔絶された世界で生きる夫婦として描かれている(なにしろ、世の中の常識に逆らって結婚した二人だった)。
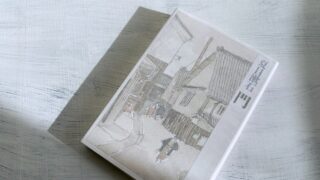
つまり、「夫婦の小説」を書くというイメージが、著者の中には最初からあったのだろう。
結婚してから六年間、我々は仕事場の同僚たちとの便宜的なつきあいを別にすれば、ほとんど誰とも関わりあいを持たずに、ふたりだけで奥に引っ込んで暮らしていたようなものだった。(村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』第2部 予言する鳥編1│できるだけ具体的なこと、文学における食欲)
漱石の『門』で、主人公(宗助)は禅門を叩くが、何一つ得ることができないまま、禅門から帰ってくる。
一方、本作『ねじまき鳥クロニクル』の主人公は、井戸に潜り、壁を抜け、暗闇の世界に潜む「心の闇」を殴り殺して、現実世界へと生還する(一種の「勇者伝説」)。
少なくとも、『ねじまき鳥クロニクル』の方が、「妻の心」にコミットしようとする姿勢が明確である(時代が違うと言えば、それまでだが)。
本作『ねじまき鳥クロニクル』は、妻の「心の闇」にコミットしようと努力する夫の物語だ。
あるいは、妻の「失踪」は、象徴としての「失踪」であったかもしれない。
自分の心の中に引きこもってしまえば、それも、ひとつの「失踪」である。
大切なことは、「心の中の見えない部分」に、どのようにしてコミットしていくかということなのだ。
心理学者(河合隼雄)は、「夫婦が相手を理解しようと思ったら、理性で話し合うのではなくて、『井戸』を掘らないとだめなのです」と指摘している(『村上春樹、河合隼雄に会いにいく』)。
「井戸」は、フロイト心理学における「イド(エス)」を意味しているとの考察もあるが(久居つばき『ねじまき鳥の探し方』1994年)、「心の中の見えない部分」まで掘り下げていくことは、現代社会におけるコミットメントを考えるときに、もっと重視されるべきことなのではないだろうか。
ちなみに、主人公の宿敵(綿谷ノボル)には、著者(村上春樹)自身の姿が、逆説的に投影されていて楽しい。
彼のその本を解釈する本まで何冊か現れた。彼が本の中で使った「性的経済と排泄的経済」という言葉はその年の流行語までになった。雑誌や新聞が、彼のことを新しい時代のインタレクチュアルの一人として取り上げ、特集した。(村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』第1部 泥棒かささぎ編6│岡田久美子はどのようにして生まれ、綿谷ノボルはどのようにして生まれたか)
「彼の本を解釈する本」は、村上春樹の小説を解釈する本が幾冊も登場したことを示しているし、「性的経済と排泄的経済」という流行語は、『ダンス・ダンス・ダンス』(1988)の「文化的雪かき」という言葉を思い出させる。
そして、1980年代後半のインタレクチュアルの一人として取り上げられ、特集されたのが、まさしく、村上春樹その人だった。
それは、『ノルウェイの森』(1987)の大ヒットにより、「村上春樹現象」という言葉までが生まれた社会を揶揄しているものと考えていい。
さりげないブラックジョークも、また、村上春樹という作家の得意とするところだったが、綿谷ノボルなる存在に、簡単に手玉にとられてしまう社会こそが、『ねじまき鳥クロニクル』という物語を生み出した土壌だったのではないか。
ノモンハン戦争を生み出したものと、綿谷ノボルを生み出したものと、『ねじまき鳥クロニクル』を生み出したものは、みな同じ土壌の下で根深くつながっている。
その根っこを、どこまでも掘り下げていく作業こそが、つまり、『ねじまき鳥クロニクル』そのものである。
このくらい濃厚な小説になると、一度や二度読んだくらいで細部まで把握することは、ほとんど不可能だろう。
何度でも何度でも「繰り返し読むことができる」というのは、素晴らしい文学作品の、最高の楽しみ方の一つなのだ。
書名:ねじまき鳥クロニクル
著者:村上春樹
発行:1997/10/01
出版社:新潮文庫